■
『沖縄文化論―忘れられた日本』(中公文庫)
岡本太郎/著
願わくば初版で、書いた当時(1961年)、売り出された当時の空気感で味わいたかったが叶わず、読んだのは1996年版。
でも、それすら気にならなくなるくらいの文章の濃さ!

久々手元に置いて、ことあるごとに読み返したいと思わせる本に出会えた。
どんな旅行本にもない沖縄の本来の姿。
どんな歴史書にもない生々しい記録の数々。
あらゆる迷いに対してズバッと明解な答えが書いてあり、
ここ最近のモヤモヤした疑問が吹っ飛んで明らかになった思いがした。
1人でも多くの人にこの本を読んで欲しい。
沖縄の原初にこそ、日本の本来あるべき姿がある。
本書の前に『縄文土器論』や『日本再発見』などが書かれて、沖縄への旅はむしろ息抜きのはずだったとのこと。
それが実は、こちらこそ本家本元だったと気づかされることになるとは、運命の導きの面白さ。
まだまだ戦争の爪痕が生々しい頃の沖縄。許可証がなければ入ることも許されなかった。
マラリアで何度も村民が全滅したり、究極的な貧しさ故に、妊婦が絶壁の割れ目を跨ぐ儀式などが行われていたという事実に唖然とした。
本書の中で、太郎はどんなに些細なことも、無意識に受け流されていることにも、根源的意味をズパッと提示している。
あらゆることの
「初源的な感動」を示している。
だから、世間的に素晴らしいとされていることに対する批評もハンパない切れ味!

p.131の日本舞踊など痛烈!p.169では、神社を酷くこき下ろしている/驚
画家の冷静で鋭い視線、学んだ民俗学の知識、そして持ち前のがっぷりよつの情熱と好奇心、正直な感動をもって、
沖縄および日本を表も裏もひっぺがして体験し、分析し、消化した上で紹介している。
ゆったりした悠久の
「沖縄時間」に対しては、自分のことを「超せっかち」と自覚しているのが面白いw
正直で可愛い人なんだな

でも、これほど本質的なことをわかりやすく著して、著作もかなり売れたにも関わらず、
世の中が当時の価値観からまったく変わっていないのはどうゆうわけなんだろう???
ラストはとても詩的。浜辺で遊んでいた子猫2匹は太郎と敏子の比喩だろうか?
▼
本文抜粋メモ
ほぼ毎ページにココロに響く文章があったので、今後もちょっとずつ書いていきたい。
今回は、ここ最近のこととのリンクについて。
p.70
この世界では物として残ることが永遠ではない。その日その日、その時その時を、平気で、そのまま生きている。風にたえ、飢えにたえ、滅びるときは滅びるままに。生きつぎ生きながらえる、その生命の流れのようなものが永劫なのだ。
p.72
俗にマスコミ禍なんてことがいわれているが、どんなに矛盾を感じても、現代人はこの巨大な雑音なしには生きられない。私のように、好きなこと以外は絶対にやらず、気ままに生きているものだって、それに無関心ではいられないし、時にやりきれなくなる。
この目まぐるしさはどうしたものだろう。文明開化以来、西欧から入ってきて頭からすっぽりはめ込まれた近代、その時計の針に一生けんめい追いつこうとした後進国意識、その焦りが身についてしまったのではないか。どうも本当の生き方ではない。
しかし勿論日本にかぎらない。世界じゅうのオーガニゼーション・マンが、自覚するしないにかかわらず落ち込んでいる絶望的なシチュエーションである。生命のリズムと時計との違和感。というよりも生命自体が画一化しているということだ。ただ空しく一方的時間にのまれてしまっては、生きてる甲斐がない。
p.73
考えてみれば、あまり栄養にもならないこの紙束(新聞、週刊誌、雑誌など)をよくまあ、せっせと、毎日のみ下していたものだと、われながら奇妙な気がした。
p.74
強いものは無限にずれてゆく時代にたえ、その虚無をのりこえるべきである。
つまり悠久の時間に生きようなんて、とぼけた決心をしたって、現代社会では許されない。
どうしたら二つの矛盾する時間をそのまま捉え、生命の充実をとりもどすことができるか。問題は組織された社会の、組織された時間の中に、この初源的な感動の持続をいかにもり込み、生かすかということだ。
p.184
狭さ、ひろさということからいえば、今日、日本も沖縄もともに、素直に外に向かってひらかれている。むしろ大国といわれるアメリカやソ連、広大な大陸を占取する人々の考え方の方がはるかに狭量のようだ。われわれの負い目はむしろそれに対するコンプレックスではないか。頑なに己れの基準だけで他を律する閉ざされた精神、ああいう無神経なほどの自己主張、自足は、とうていもちえない。いったい、われわれは立場を忘れて引きずり廻されるお人好しなのだろうか。
p.186
多くの沖縄人の、あのやわらかい表情、運命的力に対して恭順に、無抵抗に見える態度の底には、チュラカサの伝統、災いをいんぎんに扱って送り出してしまうという、辛抱強い護身術が働いているのではないか。
p.196
われわれは自己主張、自己発見のポイントとして、あまりにも「東洋」という観念、そしてそれを土台とした「日本文化」というレッテル、お体裁にこだわりすぎたようだ。東洋文化圏をかざしたり、「アジアは一つなり」なんて根拠のない迷文句が、われわれの根源にあるエネルギーを見誤らせてしまった。それをまた裏返しにした、近頃の欧米式民主主義、ヒューマニズム一辺倒にもその危険はある。(中略)私は極論したい。沖縄・日本をひっくるめて、この文化は東洋文化ではないということだ。地理的にはアジアだが、アジア大陸の運命はしょっていない。
p.197
この自然の中で、生活感情もまったく同質である。雨につけ風につけ、人々の顔も心も、同じように曇り、また晴れる。そこに致命的な喰いちがい、理解をこえる影はない。だからお互いにひどく解りがいい。声荒々しく説得したり、矛盾をのりこえるためのシチメンドクサイ思想が生まれる余地はない。
p.199
このような生活感情を土台にした文化は、逆にひどく無邪気である。悔いとか恨みの、しめっぽい影はない。素朴のようだが、鋭くたくましい。切実な生命力を端的に伝えている。物に対する執念、物として永らえようなんて考えはない。考えようがなかったのだ。サバサバした人生観である。
p.200
この間にあわせのやり方を他人事のように慨嘆する。日本人の非論理性、無計画性、非近代性だ、などと解ったようなコウシャクをする人もいあるが、そんなのをひっくるめてその中で住んでいる。何という平気さ。およそオウヨウではないのに、不思議に物にこだわらない。これは伝統である。別な言い方をすれば、物の重さに耐える粘り強さがない。物を土台とした文明に対して、何か違和感がある。
p.202
もしこれから逞しい日本文化を押し出して行くのに、体系が必要だというなら、もう一ぺんバラバラにもどしてしまって、こちらの生き方の土台、その実体の上から、再構築すべきである。
p.206
(わびさびの)湿っぽさはピープルのものではない。中間層の優越と劣等のコンプレックスのからみあった暗さだ。民衆はどんなに苦しくとも、その本質において明朗であり、透明なのだ。(中略)今日、歴史は急速に前進だけだ。世界はますます合理的に組織され、近代的にステレオタイプ化されるだろう。そいう拡大にともなって、一方にパティキュラーな条件、われわれのうちにある生活の初源的な感動は抑圧されてしまう。しかしそれは一種の孤独感として、われわれの内部に逆に深まり強まって行くにちがいない。
▼
分からなかった単語の意味メモ
ユンタ=沖縄県八重山地方に伝承される歌謡の一群。多くは長編の叙事詩で、労働の際に男女掛け合いで歌われる。
ユングトゥ=沖縄県八重山列島の歌謡。種子取祭(たにどうりい)や結願祭(きついがん)などの祭祀で,あるいは新築や婚礼など各家々での祝席で,個人によって演じられる。唱えるものと歌うものがあり,歌うものも旋律が比較的単純で歌詞の1音節を装飾をつけずに1音で歌うものが多い。
アヨウ=三線を用いない古い歌謡
メタフィジック=形而上学
人頭税=担税能力の差に関係なく、各個人に対して一律に同額を課する租税。
ヴァニティ=虚栄。虚栄心。虚飾。
生後生(いきぐしょう)
スポンテニエティー=自発性。自発的行動。
イコノグラフィ(iconography)=図像(体系);肖像画集
ミディアム=媒介するもの。媒体。また、仲介者。
アドミレーション(admiration)= (…に対する)賞賛(の気持ち),感嘆,感服,感心
モノトニー(monotony)=単調さ,変化のなさ;(話し方などの)一本調子
デスポティズム(despotism)=専制政治。また、独裁政治。
♪
谷茶前節
親の新婚旅行は沖縄で、ウチにこのSPがある。小さい頃から聴いていてふしぎに感動したのを覚えている。
















 なF氏(有給をとったv)と一緒に訪ねてみた。
なF氏(有給をとったv)と一緒に訪ねてみた。

 を注文。
を注文。
 が寄ってきて人懐こくご挨拶をしてくれた
が寄ってきて人懐こくご挨拶をしてくれた



 も飾ってある。
も飾ってある。 だったらしく、寝室(にしては、やたら書棚やテーブルが置いてあったけど)にも、
だったらしく、寝室(にしては、やたら書棚やテーブルが置いてあったけど)にも、
 になってた。残念。
になってた。残念。






 、造りが良いと煙たくもならないし、周りは緑が多いから毎日が森林浴みたいなものだ」とも。うらやま~!
、造りが良いと煙たくもならないし、周りは緑が多いから毎日が森林浴みたいなものだ」とも。うらやま~!

 」みたいなドキドキ&ワクワク感たっぷりなエンターテイメント要素が強く、
」みたいなドキドキ&ワクワク感たっぷりなエンターテイメント要素が強く、 の刮目とは、目をこすって、よく見ること。だそうな。
の刮目とは、目をこすって、よく見ること。だそうな。
 驚
驚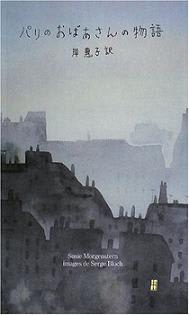
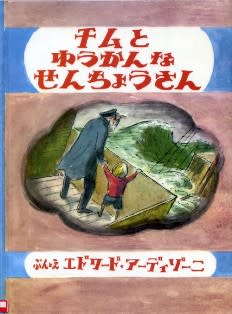
 に憧れる少年チムは、ある日、友だちの船乗りのおじさんにボートに乗っけてもらい、汽船に乗り込む。
に憧れる少年チムは、ある日、友だちの船乗りのおじさんにボートに乗っけてもらい、汽船に乗り込む。 が来て、船は転覆。救命ボートに助けられ、無事に家族のもとに帰る。というお話。
が来て、船は転覆。救命ボートに助けられ、無事に家族のもとに帰る。というお話。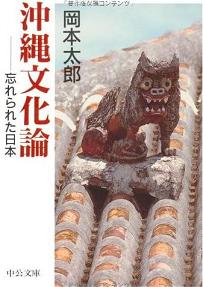

 が多いけど、下戸も多いんだ」ってホント角田さん鋭いっ!ノンサケロックw
が多いけど、下戸も多いんだ」ってホント角田さん鋭いっ!ノンサケロックw



 が生まれ、単細胞生物が生まれる。
が生まれ、単細胞生物が生まれる。 に這い上がった生物が、あらゆるバリエーションに変化してゆく。
に這い上がった生物が、あらゆるバリエーションに変化してゆく。 が出てきたなあ!
が出てきたなあ! の卵丸飲み芸はスゴイ!!!
の卵丸飲み芸はスゴイ!!!
 をする。
をする。
 で日本中を旅してみたい。理想ですv
で日本中を旅してみたい。理想ですv




