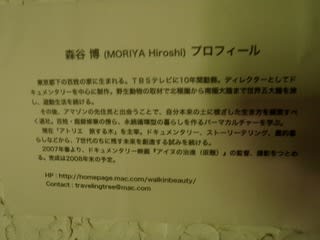本日、 。
。

今日明日は、シャロムヒュッテで『あずみの自然農塾』http://www.ultraman.gr.jp/sizennou/2010azuminosizennoubosyuyoukou.htm
です。
昨日は、蕎麦刈りの続きと、稲刈りとタカキビの脱穀をしました。

タカキビは、脱粒しにくい雑穀です。
荒縄を巻き付けた板(洗濯板のような)に、タカキビを擦りつけます。

脱穀されたタカキビは、殻を残したまま粒のみ脱穀出来ていいですよ。

その後、大小のフルイでフルって粒のみにしていきます。

脱穀途中のタカキビです。
この後、唐箕などで殻を飛ばして殻を除いたものが、種子。
さらに籾すりしたものが、食用のタカキビになります。
お知らせ
(財)自然農法国際研究開発センターが主催する
環境にやさしい菜園講座シリーズ④
「自然農法で野菜作りはじめませんか」
日時:10月23日(土)13:30~15:00
会場:松本市波田公民館 講堂
参加費:無料(申し込み不要)
お問い合わせ先)自然と健康の会事務局 0263-92-6800(担当:佐藤)
 。
。
今日明日は、シャロムヒュッテで『あずみの自然農塾』http://www.ultraman.gr.jp/sizennou/2010azuminosizennoubosyuyoukou.htm
です。
昨日は、蕎麦刈りの続きと、稲刈りとタカキビの脱穀をしました。

タカキビは、脱粒しにくい雑穀です。
荒縄を巻き付けた板(洗濯板のような)に、タカキビを擦りつけます。

脱穀されたタカキビは、殻を残したまま粒のみ脱穀出来ていいですよ。

その後、大小のフルイでフルって粒のみにしていきます。

脱穀途中のタカキビです。
この後、唐箕などで殻を飛ばして殻を除いたものが、種子。
さらに籾すりしたものが、食用のタカキビになります。
お知らせ

(財)自然農法国際研究開発センターが主催する
環境にやさしい菜園講座シリーズ④
「自然農法で野菜作りはじめませんか」
日時:10月23日(土)13:30~15:00
会場:松本市波田公民館 講堂
参加費:無料(申し込み不要)
お問い合わせ先)自然と健康の会事務局 0263-92-6800(担当:佐藤)
























 で田んぼが水浸しになり、まだどろどろなので稲刈りをお休みにしました。
で田んぼが水浸しになり、まだどろどろなので稲刈りをお休みにしました。