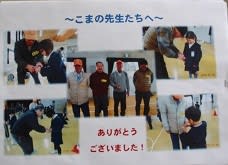
地元に二つある小学校で、1年生児童を対象とした「むかし遊び指導」を依頼された。
これは、学校と地域住民が協働することで、地域の子どもは地域と学校と保護者が一体となって育てようという「協育ネット協議会」、あるいは「コミニュティスクール」の一環事業である。それを、社会福祉協議会など地域活動団体の、青少年健全育成の柱となる活動の一つとして積極的に取り組んでいる。
読んで字の如く「きょういく」のきょうの字は、協働する、協力するの「協」であり、おしえるの「教育」ではない。
つまり、学習指導などの「教育」は、やはり学校や教師が中心となるべきで、我々は教師が教育に集中しやすい環境づくりに協力することが求められる。そんな地域活動の担い手が、我々高齢者の集まりなのである。
そんなややこしい前置きはともかくとして、地元に有り余る高齢者パワーを活用しよう。高齢者パワーを機能させようという取り組みである。
「むかし遊び」といえば、おおよそ見当はつくだろうと思いながら、話を進めて行きたいところだが。
実際に子どもたちと向き合ってみると、お父さんお母さんが忙しすぎるのか、お父さんお母さんさえこういった遊びはしてこなかったのではないか、という子どもの多さにびっくりである。
たとえばコマ回し。コマにひもを巻き付ける方法を知らない。投げ方も全く分からない。親子でこのような遊びは全くしたことがない様子がうかがえる。お手玉、あやとり、竹馬、竹ぼっくり、竹トンボの飛ばし方、などなど。みんな似たようなもので、初めて触れる子がほとんど。しかし、テレビゲームやスリーDSなどといった最新ゲーム機の扱いは、こちらがちんぷんかんぷん。言って見ればお互いさまというところか。
兎に角、懇切丁寧にすべての遊びをこなせるよう、短い時間で指導する。「これどうやるん?」などと聞いてくる子はホンのわずか。「こうやるといいよ」と、聞いて来ない子に教えようとすると逃げられそうになる。そこで思い起こすのは「やってみせ、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動かじ」という言葉。そうあだよねーと思い直すのだが。
60人の児童に30人を動員して指導に当たる。結果はこちらも汗だくになりながらではあるが面白かった。
その挙句「コマ回しのせんせい」や「竹馬のせんせい」になってしまった。ちょっとくすぐったいが、こんなことが役に立つのなら、いつでもお手伝いするよ。と思いながら、我が孫には教えてやっていないんだな~これが。

















