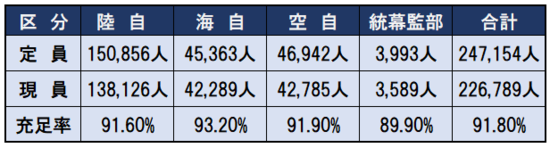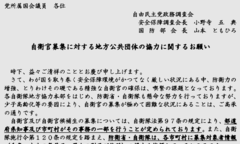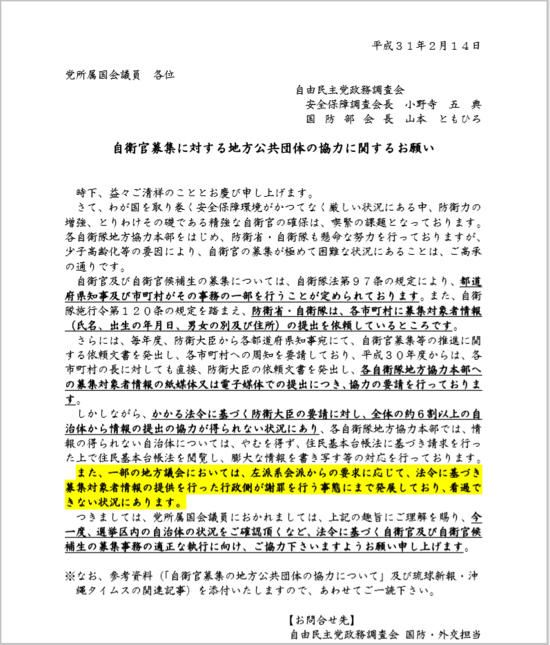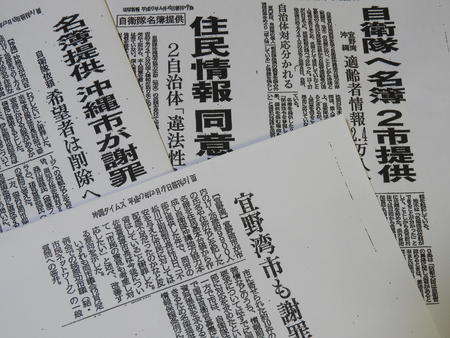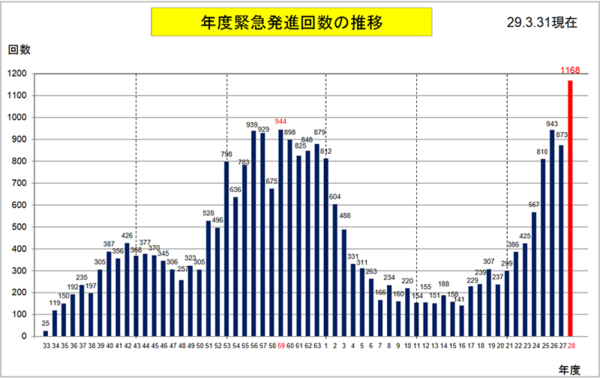【社説】:福岡沖地震14年 語り継ぎ「命」守る社会を
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説】:福岡沖地震14年 語り継ぎ「命」守る社会を
都市のにぎわいの陰で「震災遺構」の一つが姿を消す。福岡市・天神の福岡ビル(通称・福ビル)である。市の再開発事業に合わせ、解体工事が来月にも始まる。
天神の顔でもある福ビルは、2005年3月20日午前10時53分に起きた福岡沖地震で、外観を彩る窓ガラスが砕け散った。本紙記録集によると444枚が割れ、290枚が落下した。
日曜の午前中だったこともあってか、ビル直下で負傷者が出なかったことが奇跡的だった。
ガラスが飛び散る映像はテレビニュースで何度も流された。マグニチュード(M)7、最大震度6弱を記録した地震被害を象徴する建物だった。5年後に建て替わるという。
あの日から14年が過ぎる。その年に生まれた子どもの多くは、来年には高校に進学する年齢だ。地震の恐ろしさはきちんと伝承されているだろうか。
その後、東日本大震災や熊本地震、北海道地震が発生した。今年初めには熊本県和水(なごみ)町で、「福岡沖」と同じ震度6弱の揺れを観測する地震が起きた。
今や各地の学校では、避難の経路づくりや訓練が行われている。同時に求められるのは、子どもたちに災害の記憶を次代に語り継いでもらう教育である。
福岡市では当時、高速道や地下鉄が止まった。死者1人、負傷者は約1200人に上った。震度7だったとの推定もある玄界島の住民約700人の大半が島外で避難生活を強いられた。
島に、07年に現地入りされた天皇、皇后両陛下の歌碑が立つ。〈洋中(わたなか)の小さき陸(くが)よ 四(し)百余の人いま住むを思ひつつ去る〉
皇后さまは島を離れる際、避難民のうち最後の約400人が帰島を果たしたことへの安堵(あんど)の思いを詠まれた。幾世代後の心にも刻まれる歌碑となろう。
東日本大震災では「命てんでんこ」という地元の言葉が生きた。「命はめいめい(各自)が守る」の意味で、明治、昭和の大津波の経験から人に構わず高台へ逃げれば結果的にみんな助かる-との言い伝えだ。岩手県釜石市では小中学生約2900人が迷わず逃げて助かった。
福岡沖地震を起こした警固(けご)断層帯北西部(海側)が再び動き、大地震となる恐れがどれほどかは、記録が乏しく不明だ。ただ、15年末から16年春にかけて博多湾を震源に有感地震が続発した。断層帯南東部(陸側)で30年内に大地震が起きる確率は最大6%とされる。約260万人が住む福岡都市圏を襲う地震は決して過去の話ではない。
災害対策基本法は、地域住民の責務として災害の教訓の「伝承」を挙げる。教育・啓発などあらゆる手段で語り継ぎたい。
=2019/03/19付 西日本新聞朝刊=
元稿:西日本新聞社 朝刊 主要ニュース オピニオン 【社説】 2019年03月19日 11:08:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。