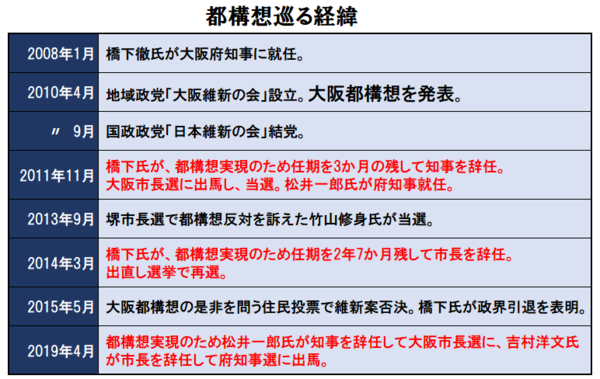【社説①】:佐久の死亡事故 わりきれなさ募る判決
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:佐久の死亡事故 わりきれなさ募る判決
なぜ息子は命を落とさなくてはならなかったのか―。両親が独自に手がかりを得て実現させた2度目の刑事裁判でも事実が解明されたとは言いがたい。わりきれなさが募る判決である。
2015年3月に佐久市で起きた事故だ。高校入学を目前にしていた和田樹生(みきお)さんが自宅前の横断歩道で車にはねられて亡くなった。23日で4年になる。
車を運転していた男性が道交法違反(速度超過)に問われた裁判で、地裁佐久支部が公訴棄却を言い渡した。男性は既に自動車運転処罰法違反(過失致死)で、禁錮3年、執行猶予5年の判決が確定している。その後、両親の告発を受けて地検が捜査し、あらためて起訴していた。
前回の裁判は、道交法違反では起訴されていなかった。判決は、事故の主因を「前方左右の不注視」と認定している。男性が酒を飲んでいたことも分かっているが、呼気検査で基準を下回り、酒気帯び運転にも問われなかった。
樹生さんは40メートル以上もはね飛ばされて亡くなっている。判決は車の時速を70〜80キロと認定したが、本当にそうなのか。防犯カメラの映像を入手した両親が専門家に調べてもらうと、110キロに達していたとの解析結果が出た。それが2度目の裁判につながった。
争われたのは、「一事不再理」の原則に反しないかだ。同一の犯罪について、重ねて刑事責任を問われないことを憲法は定めている。国家の刑罰権の乱用を防ぐため、ゆるがせにはできない刑事司法の原則である。
判決は、過失運転致死と速度超過は別個のものと評価できるとし、一事不再理には当たらないと述べている。一人の命が奪われた事故の重大さを踏まえれば、裁判所としてのぎりぎりの判断と受けとめるべきだろう。
それでいながら、形式上の不備を理由に公訴を棄却している。検察側が主張する速度に達していたと認定するには合理的な疑いが残ると指摘。裁判の前に、道交法に基づく通告や反則金納付の手続きを踏んでいないとした。
「誰のためにもならない判決だと思う」。母親の真理さんが語った言葉に無念さがにじむ。真相を知りたいという両親の願いは届かなかった。
事故現場の状況に疑問を抱いた両親が行動を起こさなければ、再度の裁判はなかった。そもそも警察、検察の当初からの捜査は十分だったのか。捜査機関のあり方と裁判所の姿勢が問われる。 (3月20日)
元稿:信濃毎日新聞社 朝刊 ニュースセレクト 社説・解説・コラム 【社説】 2019年03月20日 09:07:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。