【森友改ざん報告書③ー②】:これが全文だ。「妻関係していたら総理辞める」答弁後に記録破棄していた
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【森友改ざん報告書③ー②:これが全文だ。「妻関係していたら総理辞める」答弁後に記録破棄していた
森友学園への国有地払い下げをめぐる決裁文書の改ざん問題で、財務省は6月4日に調査報告書を公開した。

時事通信社/HuffPost Japan
報告書では、以下のようなことが記された。
- 2017年2月に安倍晋三首相が国会で「私や妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞める」と答弁して以降、安倍昭恵氏(総理夫人)の名前が入った書類の存否の確認をしたり、政治家の問い合わせに関する記録などを廃棄した。
- 国会議員団の国有地視察(2017年2月21日)の際、財務省側が森友学園側の弁護士に「(森友学園の籠池泰典)理事長らの発言次第では国会審議がさらに混乱しかねない」「理事長は出張で不在」「撤去費用は相当かかった気がする、トラック何千台も走った気もする」など、説明ぶりを提案した。
- 近畿財務局の統括国有財産管理官の配下職員は、「改ざんを行うことへの強い抵抗感があった」「本省理財局からの度重なる指示に強く反発」していた。
- 会計検査院による検査開始後の2017年4月、財務省理財局の職員が国交省に出向き、国交省が保管していた森友学園に関する決裁文書を「改ざん後」の文書に差し替える作業をおこなっていた。会計検査院の検査に対し、国交省側はもともと保管していた「原本」を提出。一方、財務省側は「改ざん後」の文書を提出した。
- 佐川氏を停職3カ月相当にするなど、20人を懲戒や厳重注意などで処分する。
ハフポスト日本版では、財務省が発表した報告書の全文を掲載する。
IV.応接録の廃棄等の経緯
(1)応接録の元々の保存状況(*13)
(*13)一般に、応接録については、作成するかどうか、実際のやりとりをどの程度詳細に記録するか、記録する際の表現ぶりをどうするかといった点は担当者の裁量に委ねられる面が大きいことや、相手方に対して、実際のやりとりが正確に反映されていることを逐一確認しているわけでもないことに、留意が必要と考えられる。
1 森友学園案件に係る決裁文書が作成され、その後改ざんが行われた期間にかけて、「財務省行政文書管理規則(*14)」においては、一定の行政文書についてのみ1年以上の保存期間を列記していた。森友学園案件に係る決裁文書についても、当該規則に則って、たとえば「文書1(貸付決議1)」であれば「運用終了日以後10年」、「文書3(売払決議)」であれば「30年」の保存期間が定められている。他方、応接録など、当該規則に列記されていない文書については、「財務省行政文書管理規則細則(*15)」に基づき、保存期間は「1年未満」とされ、具体的な終期は「年度末まで」や「事案終了まで」等と定めることとされていた(*16)。
(*14)平成23年財務省訓令第10号
(*15)「財務省行政文書管理規則」に基づき、総括文書管理者(大臣官房長)が施行に関し必要な事項を定める細則
(*16)「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号)や「財務省行政文書管理規則」等において、保存期間が終了した文書は、独立行政法人国立公文書館に移管するか、廃棄しなければならないこととされている。
2 森友学園案件に関する応接録は、作成時点で「1年未満保存(事案終了まで)」と定められていた。この保存期間の具体的な終期について、森友学園との間で売買契約が締結された平成28年6月20日(月)をもって事案が終了したと考えていた職員もある一方で、当面は保存し続けるのだろうと考えていた職員もあり、関係者間の認識は必ずしも統一されていなかった。
3 他方で、個別の国有財産の管理処分に従事する職員は、一般に、当該国有地について外部から照会等を受ける場合に備えて、過去に照会等があった際の応接録のうち後日必要になるかもしれないと考えたものを手元に保存しておくことが多い。森友学園案件を担当する近畿財務局の職員も、一連の応接録を保存していたほか、その電子ファイルをサーバ上に保存していた。
4 また、近畿財務局において作成された応接録の一部は、随時、本省理財局の国有財産審理室にも共有されていた。同室の職員は、そうした応接録を紙媒体の形で保存したり、サーバ上の共有フォルダ(*17)や各職員が使用するコンピュータ上に電子ファイルの形で保存していた。
(*17)同一部局の複数職員がアクセス権限を有するフォルダ。
(2)政治家関係者との応接録の廃棄等の経緯
1 森友学園案件に関する応接録で「1年未満保存(事案終了まで)」と定められていたものについては、平成29年2月以降、本省理財局において、森友学園との間で売買契約が締結された平成28年6月20日(月)をもって「事案終了」に当たるものと整理し、国有財産審理室長から理財局長まで報告した上で、近畿財務局にも伝達された。
2 平成29年2月17日(金)の衆議院予算委員会における内閣総理大臣の上記答弁以降、本省理財局の総務課長から国有財産審理室長及び近畿財務局の管財部長に対し、総理夫人の名前が入った書類の存否について確認がなされた。これに対して、総理夫人本人からの照会は無いことや、総理夫人付から本省理財局に照会があった際の記録は作成し、共有しているが、内容は特段問題となるものではないことを確認したほか、近畿財務局の管財部長からは、その他の政治家関係者からの照会状況に関する記録の取扱いについて相談がなされた。さらに、上記の同年2月21日(火)の国会議員団との面会の状況も踏まえ、本省理財局の総務課長から近畿財務局の管財部長に対して政治家関係者をはじめとする各種照会状況のリストの作成を依頼し、本省理財局の国有財産審理室長に当該リストが送付された。
3 本省理財局の総務課長は、その後速やかに、国有財産審理室長に対して政治家関係者からの照会状況に絞り込んだリストを作成するよう指示をした上で、当該リストにより理財局長に報告した。その際、理財局長は、応接録の取扱いは文書管理のルールに従って適切に行われるものであるとの考えであったことから、総務課長は、政治家関係者との応接録を廃棄するよう指示されたものと受け止め、その旨を国有財産審理室長、さらに近畿財務局の管財部長に伝達した。こうした状況は、理財局次長や国有財産企画課長にも共有された(*18)。
(*18)この際、あわせて、当該リスト自体も廃棄された。
4 近畿財務局においては、本省理財局からの指示を受けて、政治家関係者との応接録として存在が確認されたものを紙媒体及び電子ファイルともに廃棄した。本省理財局内においても、保存されていた政治家関係者との応接録の廃棄を進めたが、サーバ上の共有フォルダに保存されていた電子ファイルについては、廃棄されず残されたものも存在した(*19)。
(*19)今回の調査においては、平成29年5月のシステム更改前に使用されていたコンピュータからも、可能な限りの電子ファイルの復元作業を行い、後述する「廃棄されなかった応接録」とともに公表を行っている。
(3)森友学園側との応接録の廃棄等の経緯
1 平成29年2月22日(水)、国会議員より、森友学園案件における森友学園側との応接録の存否についての確認があった。また、翌日23日(木)には、一部政党より、平成25年から平成26年にかけての財務省本省及び近畿財務局職員と森友学園関係者との接触記録の存否について、無いならば無い旨を書面で提出するよう要求があった。本省理財局内では、森友学園案件に関する応接録に関して、上記の通り売買契約が締結された平成28年6月20日(月)をもって「事案終了」に当たるものと整理していたことから、そうした記録は無いものと整理し、後者の要求に対して、平成29年2月24日(金)、その旨を記載した書面を提出した。
2 平成29年2月24日(金)の衆議院予算委員会において、本省理財局長は、「昨年6月の売買契約に至るまでの財務局と学園側の交渉記録につきまして、委員からのご依頼を受けまして確認しましたところ、近畿財務局と森友学園との交渉記録というのはございませんでした」「面会等の記録につきましては、財務省の行政文書管理規則に基づきまして保存期間1年未満とされておりまして、具体的な廃棄時期につきましては、事案の終了ということで取り扱いをさせていただいております。したがいまして、本件につきましては、平成28年6月の売買契約締結をもちまして既に事案が終了してございますので、記録が残っていないということでございます」等と答弁した。
3 平成29年2月24日(金)の衆議院予算委員会において上記の理財局長の答弁があるまでに、本省理財局の総務課長及び国有財産審理室長は、森友学園案件関係の各種応接録が実際には残っていることを認識していたものと認められる。他方、理財局長は、各種応接録の実際の存否を確認しないまま、「財務省行政文書管理規則」等に定められている以上、保存期間が終了した応接録は廃棄されているはずであると認識していたものと認められる。
4 さらに、上記の本省理財局長の答弁の後には、同局長から総務課長に対して、国会において「財務省行政文書管理規則」どおり対応している旨を答弁したことを踏まえ、文書管理の徹底について念押しがあり、総務課長は、残っている応接録があるならば適切に廃棄するよう指示されたものと受け止めた。
5 文書管理を徹底すべきとの趣旨は、速やかに、本省理財局の総務課長から近畿財務局の管財部長に伝達された。管財部長は、部内の職員に対して、森友学園案件に係る応接録を廃棄せよ、といった具体的な指示までは行わなかったが、適切な文書管理を行うべき旨を繰り返し周知した。これを受け、保存期間が終了した応接録について、紙媒体で保存されていたもののほか、サーバ上に電子ファイルの形で保存されていたものについても廃棄が進められた。他方、個々の職員の判断により、廃棄せずに当該職員の手控えとして手元に残された応接録も引き続き存在した。
6 本省理財局においては、総務課長から国有財産審理室長に対して、文書管理はルールに従って適正に行うよう話があり、国有財産審理室長から配下の一部の職員にも、この趣旨が伝えられた。国有財産審理室の職員は、文書管理を適切に行うべき旨が周知されたという認識はあっても、応接録を速やかに一斉に廃棄すべき旨の指示を受けたとは認識していない職員もいる状況であった。こうした中、国有財産審理室においては、紙媒体で保存されていた応接録を含め、保存期間が終了した関連文書について廃棄を進めたが、他方、サーバ上の共有フォルダに保存されていた電子ファイルは、多忙であったこともあり、保存されたままとなった。
(4)廃棄されなかった応接録の取扱い
1 上記の経緯により、本省理財局及び近畿財務局の一部職員は、保存期間が終了した応接録が必ずしもすべて廃棄されず、保存されたままとなっている状況を認識していた。ただし、廃棄を徹底すべきとの認識が必ずしも共有されていなかったことに加え、平成29年3月以降には財務省職員を刑事告発する動きが報道され、さらに同年5月には東京地方裁判所に対して証拠保全の申立てが行われるに至り、それ以上の廃棄は行われなかった。
2 平成29年3月以降、森友学園案件に関する会計検査院の会計検査が実施に移され、会計検査院から、廃棄していない応接録等を提示するよう繰り返し求めがあったが、本省理財局においては、国会審議等において存在を認めていない文書の提出に応じることは妥当ではないと考え、存在しない旨の回答を続けた。さらに会計検査院からは、行政文書と位置付けているかどうかにかかわらず、個々の職員が手控えとして残している資料や、サーバ及び職員のコンピュータ上に電子ファイルとして残されている資料を提出するよう重ねて求めがあり、同年10月から11月にかけて、本省理財局の総務課長の判断により、近畿財務局のサーバ上の電子ファイルの構成に関する資料を提示することとした。ただし、当該資料では、廃棄されず残されていた応接録等の電子ファイルの存在には触れなかった(*20)。
(*20)近畿財務局においては、情報公開請求への対応のため、平成29年10月から11月にかけて、管財部にとどまらず他の部門も含めて、森友学園案件の関連文書の探索が行われた。その結果、統括法務監査官部門等において法律相談に関する文書が保存されていることが確認されたことから、同年11月21日(火)に会計検査院に連絡し、また、情報公開請求に対しては、平成30年1月4日(木)に開示決定をした。
3 情報公開請求により、森友学園案件に関する一連の応接録の開示を求められるケースも相次いだが、その都度、「文書不存在」を理由に不開示の決定を行ってきている。
4 本省理財局では、平成29年7月、理財局長が交代するなどの定期人事異動があったが、新たに転入してきた幹部職員に対しては、応接録が廃棄されず残っている実態は説明されなかった。
5 今般、決裁文書の改ざんに関する調査を進める過程において、廃棄されず残されていることが確認された応接録や、サーバ及び職員のコンピュータ上に残された電子ファイルの探索等により確認できた応接録については、平成30年5月23日(水)に公表したとおりである(*21)。
(*21)財務省ホームページ参照。https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/search_kessaibunsho.htm
(5)売買契約締結後に作成された応接録の取扱い
1 平成28年6月20日(月)に森友学園との間で売買契約を締結した後も、近畿財務局と森友学園側とのやりとりについて応接録を作成する場合があった。たとえば、平成29年2月9日(木)に森友学園案件に関する報道があって以降、同年2月13日(月)から14日(火)にかけて近畿財務局と森友学園側の間で報道機関への対応を相談した際にも、詳細な応接録が作成されていた。こうした応接録も「1年未満保存」の文書であり、具体的な終期は「平成28年度末」とされていた。
2 平成29年3月15日(水)の衆議院財務金融委員会において、国会議員から、同年2月8日(水)以降数日間の森友学園側との接触記録を同委員会に提出するよう要求があった。これを受け、本省理財局の総務課長から近畿財務局の管財部長に対して、そうした記録については位置づけをよく整理しなければならない旨の相談を行った。近畿財務局側では、進行年度中の応接録を全く作成していない、あるいは全て廃棄済みであると整理することは無理があると考え、近畿財務局長まで相談の上で、売却価格の公表に関する同年2月9日(木)付の同意書とともに、報道対応に関する同年2月13日(月)・14日(火)付の応接録については存在するものとして、提出に応じることとした。ただし、既に作成済みであった応接録は中身が詳細過ぎることから、要旨のみに圧縮した応接録を作成し直すこととし、統括国有財産管理官以下で作業を行った上で、本省理財局経由で提出した。
3 作成し直す前の上記応接録を含め、平成28年6月20日(月)に森友学園との間で売買契約を締結した後に作成された応接録については、平成30年6月4日(月)に公表したとおりである(*22)。
(*22)財務省ホームページ参照。https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/search_kessaibunsho.htm
V.決裁文書の改ざん等の経緯
(1)決裁文書の元々の作成・管理状況
1 森友学園案件に係る決裁文書のうち、本省理財局が作成したのは「文書5(特例承認)」の1件のみであり、平成27年4月30日(木)、「一元的な文書管理システム(*23)」上で電子決裁が完了している。残る決裁文書は、近畿財務局において作成されたものであり、紙媒体で決裁が行われ、保存されている。
(*23)行政文書の起案・登録から廃棄・移管までのライフサイクルを電子的に管理するためのシステムであり、「公文書等の管理に関する法律」が求める文書管理業務を厳格かつ効率的に実施するために活用されている。総務省行政管理局が整備・管理し、全府省庁で導入済み。
2 近畿財務局が作成した決裁文書の中には、各種経緯等をかなり詳細に記載しているものがあった。また、本省理財局が作成した「文書5(特例承認)」にも各種経緯が詳細に記載されていたが、これは、国有財産審理室の担当者が、近畿財務局において既に決裁済みだった「文書4(特例申請)」と平仄を合わせる形で記載したことによるものであった。
3 「一元的な文書管理システム」上で電子決裁を行う場合、まず担当者が、決裁文書本文のほか各種参考書類等の電子ファイルを当該システムにアップロードし、決裁権者もそれぞれのアカウントで当該システムにログインした上で決裁文書の内容を確認し、コンピュータ上で決裁を行っている。ただし、重要な案件については、担当者からその上司である決裁権者に対して、案件の概要をまとめた紙媒体の資料によってあらかじめ説明を済ませた上で、電子決裁を回すことが一般的であり、そうした場合、決裁権者は、システム上アップロードされている各種添付書類まで逐一目を通さないことも多い。「文書5(特例承認)」の電子決裁に際しても、本省理財局の国有財産審理室の当時の担当者は、別の資料により上司である決裁権者への説明を済ませた上で電子決裁を回しており、決裁権者の側は、各種添付書類に目を通さぬまま、決裁を行っていたのが実態であった。
4 「一元的な文書管理システム」上で電子決裁が行われた「文書5(特例承認)」については、改ざんが行われた後も当該システム上に元々の文書が保存されており、その内容は、平成30年3月26日(月)に公表したとおりである(*24)。
(*24)財務省ホームページ参照。https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/search_kessaibunsho.htm
5 他方、近畿財務局において紙媒体で決裁が行われた文書については、通常の決裁文書には添付しないような資料・メモ等が編綴された状態で管理・保存されていたものがあるなど、必ずしも整然と管理されていない実態であった。改ざん前の管理・保存状況をできる限り復元した内容は、平成30年5月23日(水)に公表したとおりである(*25)。
(*25)同上(財務省ホームページ参照。https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/search_kessaibunsho.htm)
(2)「文書4(特例申請)」「文書5(特例承認)」の改ざんの経緯
1 近畿財務局及び本省理財局の国有財産審理室長が対応した平成29年2月21日(火)の国会議員団との面会を受けて、対応者の間では、「文書4(特例申請)」「文書5(特例承認)」等における政治家関係者に関する記載の取扱いが問題となり得ることが認識された。
2 その後、本省理財局の国有財産審理室長から総務課長に対して、本省理財局が作成した「文書5(特例承認)」の中にも政治家関係者からの照会状況に関する記載がある旨の問題提起があり、両者から理財局長に対して速やかに報告された。理財局長は、当該文書の位置づけ等を十分に把握しないまま、そうした記載のある文書を外に出すべきではなく、最低限の記載とすべきであると反応した。理財局長からはそれ以上具体的な指示はなかったものの、総務課長及び国有財産審理室長としては、理財局長の上記反応を受けて、将来的に当該決裁文書の公表を求められる場合に備えて、記載を直す必要があると認識した。こうした認識は、国有財産企画課長にも共有された。
3 その上で、「文書5(特例承認)」については、平成29年2月26日(日)に、本省理財局の国有財産審理室長及び配下の国有財産審理室の職員が、国有財産企画課長にも報告の上で、政治家関係者からの照会状況等が記載された経緯部分を削除するなどの具体的な作業を行った。
4 近畿財務局が作成した「文書4(特例申請)」については、後述するとおり、近畿財務局において若干の書き換え作業に着手していたが、平成29年2月26日(日)、本省理財局から近畿財務局の管財部職員に出勤を要請した上で、国有財産審理室の職員から、上記「文書5(特例承認)」と同様の書き換えを行うよう具体的に指示をした。近畿財務局においては、管財部次長及び統括国有財産管理官以下の職員が、指示通りの作業を行った。
5 本省理財局が作成した「文書5(特例承認)」は、上記のとおり「一元的な文書管理システム」上で電子決裁が完了した文書であり、当該システム上で決裁文書の更新を行う権限は、一部職員にしか付与されていなかった。国有財産審理室長らは、上記の書き換え作業を行った平成29年2月26日(日)の時点では、当該システム上の更新処理をどのように行えばよいかが分からなかったため、同日中はそれ以上の処理は行わなかった。
6 その後、本省理財局の国有財産審理室長は、起案部局の課室長級職員が務める文書管理責任者(*26)又はその配下で文書管理担当者権限を設定された職員のアカウントであれば、「一元的な文書管理システム」上で電子決裁が行われた文書を更新できることを知り、平成29年4月4日(火)夜、当該権限を設定された配下の国有財産審理室の職員に対して当該システムにログインするよう依頼した上で、当該職員のコンピュータを借りて作業を行った(*27)。なお、当該職員は、改ざん作業自体は全く関知していなかった。
(*26)「文書5(特例承認)」については、国有財産業務課長が該当。
(*27)本省理財局の国有財産審理室長は、「一元的な文書管理システム」において「文書5(特例承認)」の決裁文書の更新処理を行えば、元の決裁文書は上書き保存されて無くなるものと考えていたが、実際には、元々の文書もそのまま保存されていた。
(3)「文書1(貸付決議1)」「文書3(売払決議)」の改ざんの経緯
1 上記の通り近畿財務局に対して「文書4(特例申請)」の書き換えの指示が行われた平成29年2月26日(日)には、当該指示の内容も踏まえつつ、本省理財局の国有財産審理室長及び配下の国有財産審理室の職員が、国有財産企画課長にも報告の上で、近畿財務局に対して、「文書1(貸付決議1)」や「文書3(売払決議)」等についても、各種経緯が記載された箇所の短縮化などを指示していた(*28)。
(*28)平成29年2月下旬、各種応接録の廃棄が進められる中で、近畿財務局において、平成28年3月頃の経緯を裏付ける記録として、「文書3(売払決議)」に「森友学園事案に係る今後の対応方針について(H28.4.4)」と題する参考メモを追加することが検討され、一時期は決裁文書に編綴されていたが、最終的には外されていた。
2 当時、本省理財局においては、遠からず各種決裁文書の公表を求められ、国会審議等における質問の材料となりかねないとの認識が共有されていた。このため、平成29年2月27日(月)、国有財産企画課及び国有財産審理室から理財局長に対して、まずは「文書3(売払決議)」の内容を報告した。この際、理財局長は、このままでは外には出せないと反応したことから、配下の職員の間では、記載を直すことになるとの認識が改めて共有された。また、理財局長から総務課長及び国有財産企画課長に対して、担当者に任せるのではなくしっかりと見るように、との指示があり、指示を受けた両者は、記載内容を整えた上で理財局長の了解を得ることが必要になると認識した。
3 平成29年3月2日(木)の参議院予算委員会において、国会議員から、森友学園案件に関する決裁文書を同委員会に提出するよう要求があった(なお、同年3月17日(金)にも、別の国会議員から、同様の要求があった。)。このため、同日以降、本省理財局の国有財産審理室の職員から近畿財務局に対して改めて各種決裁文書の送付を求め、近畿財務局側では、同年3月3日(金)以降、各種決裁文書をスキャンして電子ファイル化する作業を行った上で、同年3月6日(月)から8日(水)頃にかけて、決裁文書の一式を本省理財局側に送付した。
4 本省理財局では、まずは「文書1(貸付決議1)」と「文書3(売払決議)」について、総務課長、国有財産企画課長、国有財産審理室長及び配下の国有財産審理室の職員が相談して検討を進め、平成29年3月8日(水)にかけて、理財局次長、さらには理財局長に対して、複数回にわたり、検討状況が報告された。
5 平成29年3月7日(火)未明、本省理財局の国有財産審理室の職員から近畿財務局に対して、「文書1(貸付決議1)」や「文書3(売払決議)」等の書き換え案が送付されたが、この段階では、小幅な書き換えにとどまっていた。その後、理財局長を含めて行った議論を踏まえ、同年3月8日(水)にかけて、まずは「文書3(売払決議)」の作業を先行して行った上で提出・公表するとの方針とともに、貸付契約までの経緯の記述を全て削除するほか、国土交通省大阪航空局の対応状況を削除する等の更なる書き換え案が、近畿財務局に対して示された。
6 近畿財務局の統括国有財産管理官の配下職員は、そもそも改ざんを行うことへの強い抵抗感があったこともあり、本省理財局からの度重なる指示に強く反発し、平成29年3月8日(水)までに管財部長に相談をした。また、本省理財局の総務課長と近畿財務局の管財部長との間でも相談がなされた。結論として、近畿財務局においては、統括国有財産管理官の配下職員はこれ以上作業に関与させないこととしつつ、本省理財局が国会対応の観点から作業を行うならば、一定の協力は行うものと整理された。
7 他方、本省理財局においては、国会審議への対応や、国会議員等からの説明要求や資料要求等への対応に追われており、「文書3(売払決議)」の書き換え内容については、平成29年3月20日(月・祝)に、理財局長を含めて改めて議論を行うこととなった。その際、理財局長からは、同年2月から3月にかけて積み重ねてきた国会答弁を踏まえた内容とするよう念押しがあった。遅くともこの時点までには、理財局長も、決裁文書の書き換えを行っていることを認識していたものと認められる。同日の議論を踏まえて、翌日21日(火)までに、売払いに至る経緯を加筆した案が作成され、近畿財務局に共有された。
8 「文書3(売払決議)」のほか、「文書1(貸付決議1)」について同様の作業が必要となることは、本省理財局の幹部職員の間で認識されており、平成29年3月20日(月・祝)に理財局長も含めて議論を行った上で、書き換え案が近畿財務局に共有された。
9 しかし近畿財務局側では、その時期、統括国有財産管理官の配下職員による本省理財局への反発が更に強まっていたため、本省理財局においては、各種決裁文書の書き換え案として近畿財務局に送付した内容が実際にどの程度反映されているのか、確認できない状況が続いた。
10 会計検査院による近畿財務局への実地検査の開始が近づいてきた平成29年4月上旬に、本省理財局の総務課長から局長に対して、近畿財務局側には強い抵抗感があるとの状況が報告された。理財局長は、必要な書き換えは行う必要があるとの反応であったため、総務課長から国有財産審理室長及び近畿財務局の管財部長に対して、最低限、政治家関係者からの照会状況の記載と、それまでの国会答弁との関係が問題となりかねない箇所については書き換えが必要である旨が伝えられた。さらに国有財産審理室長から近畿財務局の管財部次長に対してもこの内容が伝達されるとともに、配下の国有財産審理室の職員がその時点までに作成していた各種決裁文書の書き換え案が改めて送付された。
11 近畿財務局においては、管財部次長が、平成29年4月8日(土)、本省理財局の指示を踏まえた作業を行った。その上で、同年4月10日(月)、会計検査院による実地検査への対応のために近畿財務局に出張してきた本省理財局の国有財産審理室長に状況を伝達するとともに、管財部長にも報告をした。また、国有財産審理室長から本省理財局の総務課長に対しても、報告がなされた。
(4)その他の決裁文書の改ざんの経緯
1 財務省が平成30年3月14日(水)に公表したとおり、「文書8(予定価格決定)」については、平成27年6月、当初添付されていたメモ「公租公課相当額の取扱いについて(考え方の整理)」の抜取りが行われていた(*29)。当該文書は、当時、森友学園の理事長から情報公開請求を受けており、本省理財局の国有財産業務課との相談内容が記載された当該メモを開示すると、森友学園側から本省理財局に対して直接働きかけが行われるようになりかねないことを懸念して、当該メモを開示しない扱いとするためのものであった。これは、近畿財務局の当時の統括国有財産管理官及びその配下職員の判断で行われたものであり、当時の管財部長も、さらには本省理財局も、関与していなかった。
(*29)財務省ホームページ参照。https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/search_kessaibunsho.htm
2 近畿財務局においては、上記の通り、平成29年2月21日(火)の国会議員団との面会を受けて各種決裁文書における政治家関係者に関する記載の取扱いについて問題意識を持ち、本省理財局とも相談の上で、「文書4(特例申請)」のほか、「文書6(承諾書提出)」の冒頭に記載があった「鴻池祥肇議員からの陳情案件」との記載の削除を行った。さらに、同年2月23日(木)以降は、応援の職員を呼び寄せて体制を強化した上で、各種決裁文書において政治家関係者の記載がある箇所を確認する作業を進めていた。
3 他方、本省理財局の国有財産審理室では、国会対応等の業務の必要に応じて、近畿財務局から各種決裁文書の送付を受けていた。その後、国有財産企画課長、国有財産審理室長及び配下の国有財産審理室の職員の間で、近畿財務局が作成した決裁文書を取り寄せた上で問題の有無を確認していくべきとの認識が共有され、まずは森友学園案件に係る行政文書のリストを作成した上で、近畿財務局との間で共有した。さらに上記のとおり、平成29年3月2日(木)以降、近畿財務局に対して改めて各種決裁文書の送付を求め、同年3月6日(月)から8日(水)頃にかけて一式が送付されたことを受け、書き換え内容の検討を進めた。
4 本省理財局において、一連の改ざん作業の過程で理財局長まで相談を行っていた決裁文書は、「文書1(貸付決議1)」「文書3(売払決議)」であり、事後的に報告していたのは「文書4(特例申請)」「文書5(特例承認)」であった。残る文書については総務課長も十分認識しておらず、上記の文書との整合性を確保するため、国有財産企画課長にも相談しながら、国有財産審理室長及び配下の国有財産審理室の職員によって作業が進められたものであった。
(5)国土交通省大阪航空局と共有していた決裁文書の取扱い
1 森友学園を相手方とする国有地処分の対価は、国土交通省所管の自動車安全特別会計空港整備勘定の収入となるものであることから、その関係の事務を担当する同省大阪航空局との間で、近畿財務局が作成した「文書1(貸付決議1)」等の決裁文書の一部が共有されていた。
2 平成29年3月以降、会計検査院が森友学園案件についての会計検査を行うことが決まり、本省理財局の国有財産審理室の職員から国土交通省の本省航空局に対して、同省大阪航空局から会計検査院に対する資料提出の時期や、既に提出しているのであれば近畿財務局の文書が含まれているのかについて照会したところ、その時点では未提出である旨の回答があった。さらに、近畿財務局が同省大阪航空局に共有した文書は最終版でないことを伝達した上で、当該文書の所在を確認したところ、同省の本省航空局にあるようだ、との回答があった。
3 平成29年4月下旬頃、国土交通省本省航空局から近く会計検査院に対して資料を提出する旨の連絡があり、本省理財局の国有財産審理室の職員が国土交通省本省に出向いて、近畿財務局が作成した決裁文書の差し替え作業を行った。しかし国土交通省側では、差し替えを行った資料ではなく、別途準備していた資料(近畿財務局の元々の決裁文書が添付されているもの)を会計検査院に提出したため、結果として、財務省及び国土交通省から、内容の異なる文書が提出されることとなった。
(6)改ざん後の決裁文書の取扱い
1 森友学園案件については、平成29年3月6日(月)に参議院予算委員会において会計検査院に対する会計検査の要請があり、同年3月7日(火)に会計検査院が受諾した。これに対して、本省理財局では国有財産企画課及び国有財産審理室が準備作業を行った。近畿財務局は、同年4月11日(火)以降に実地検査を受け(*30)、さらにその後、会計検査院の求めに応じて、同年4月21日(金)に、改ざん後の決裁文書一式の写しを提出した(*31)。
(*30)平成29年4月11日(火)に会計検査院による近畿財務局への実地検査が開始された後、翌日12日(水)になって、本省理財局の国有財産企画課長が「文書3(売払決議)」のうちの経緯資料の内容について、それまでの国会等での説明との整合性等の観点から懸念があることに気付き、近畿財務局に出張中の国有財産審理室長に対して、差し替えが可能かどうか相談した。さらに国有財産審理室の職員から近畿財務局側に対しても資料差し替えの指示がなされ、結果的に、同年4月13日(木)に指示通り差し替えが実行された。
(*31)ただし、平成29年4月13日(木)に差し替えが行われた「文書3(売払決議)」のうちの経緯資料については、当該差し替え前のものを提出しており、後日に国会議員からの資料要求や情報公開請求を受けて本省から提出した文書(当該経緯資料について差し替えを行った後のもの)との間で不整合が生じた。
2 平成29年5月上旬に、会計検査院から近畿財務局に対して、財務省と国土交通省が提出した「文書1(貸付決議1)」等について、内容の相違や過不足がある旨の照会があった。近畿財務局から照会を受けた本省理財局の国有財産審理室は、国土交通省本省航空局に問合せをするとともに、総務課長及び国有財産企画課長に相談して、財務省から提出したものが最終版である旨を回答するよう、近畿財務局の担当職員に伝達した。
3 情報公開請求に対して改ざん後の決裁文書を開示したのは、平成29年3月3日(金)に請求を受けて同年5月2日(火)に開示した「文書3(売払決議)」が初めてであり、その後も順次対応された(*32)。
(*32)いずれの請求についても、本省では大臣官房文書課の職員、近畿財務局では総務部総務課の職員が対応窓口となったが、当該職員らは改ざんについては全く関知していなかった。
4 国会議員からの資料要求への対応については、平成29年3月2日(木)及び17日(金)の参議院予算委員会における国会議員からの資料提出要求を受けて、同年5月8日(月)に同委員会理事会に対して、改ざん後の「文書3(売払決議)」を提出した(*33)。
(*33)いずれの場合も、本省大臣官房文書課の職員が対応窓口となったが、当該職員は改ざんについては全く関知していなかった。
5 本省理財局では、平成29年7月、理財局長が交代するなどの定期人事異動があったが、新たに転入してきた幹部職員に対しては、決裁文書の改ざんについては説明されなかった。
VI.一連の問題行為の総括
(1)一連の問題行為の目的等
1 応接録の廃棄や決裁文書の改ざんは、国会審議において森友学園案件が大きく取り上げられる中で、更なる質問につながり得る材料を極力少なくすることが、主たる目的であったと認められる。その背景として、国会対応を担当する本省理財局において、森友学園案件を担当する近畿財務局の各種文書の状況を十分把握しきれておらず、それらを精査する時間的余裕がなかったことも影響していたものと考えられる。
2 政治家関係者からの照会状況や森友学園との交渉状況に関する応接録は「1年未満保存」の文書であり、当時の「財務省行政文書管理規則」に則り、保存期間が終了した応接録は廃棄することとされていたが、実際には廃棄されず残されているものがあった。国会議員からの確認等を受けて、本来は、応接録の存否を確認した上で、残っている応接録があるならば求めに応じて提出し、その場合に生じ得た1つ1つの質問に対して丁寧に答弁していくべきであったし、そうすることは不可能ではなかったと考えられる。しかしながら、本省理財局の局長は応接録の存否を確認せず、他の幹部職員も国会審議が相当程度紛糾することを懸念して、保存期間終了後の応接録は廃棄している旨を説明するにとどめることを志向したものと認められる。しかしながら、そうした幹部職員の考えを踏まえて廃棄が徹底されたわけではなく、特にサーバ上には応接録が多く残されていたことが実態だったと認められる。
3 決裁文書については、本省理財局の局長以下の幹部職員としては、それぞれの決裁文書の作成目的に照らして必要な記
載は残すことを前提としつつ、
- 政治家関係者からの照会状況に関する記載など、決裁の内「容には直接の関係がなく、むしろ国会審議で厳しい質問を受けることとなりかねない記載は、含めないこと、
- 本省との調整状況に関する記載や了解を得た旨の記載は、単に本省理財局の国有財産審理室など担当部局とのやりとりを記載しているだけであるにもかかわらず、様々な憶測を招きかねないことから、極力含めないこと、
- 国土交通省大阪航空局の対応状況に関する記載は、地下埋設物等の撤去のための予算確保の調整状況への関心を引き起こし、新たな質問の材料となりかねないことから、極力含めないこと、
- 森友学園から国に対する損害賠償の可能性に関する検討経緯に関する記載や、標準書式との差異(*34)に関する記載は、森友学園を優遇していたのではないかと誤解され、その理由等について更に厳しい質問を受けるきっかけとなりかねないことから、極力含めないこと、
- さらに、森友学園案件についての国会審議における理財局長の答弁について誤解を生じさせかねないような記載は、極力含めないこと、
といった考え方により、改ざんを行う判断をしたものと認められる。本来は、元々の決裁文書を提出した上で、その場合に生じ得た1つ1つの質問に対して丁寧に答弁していくべきであったし、そうすることは不可能ではなかったと考えられるが、当時の本省理財局の幹部職員は、国会審議が相当程度紛糾するのではないかと懸念し、それを回避する目的で改ざんを進めたものと認められる。
(*34)本省理財局通達「国有地の社会福祉施設の整備を目的とした社会福祉法人等に対する定期借地権の設定について」(平成23年3月31日財理第1539号)において、未利用国有地について公的用途に供するために定期借地権を設定して貸付けを行う場合の契約の標準書式が定められている。森友学園案件における貸付契約においては、当該標準書式では対応できない内容があったことから条項の追加・修正を行っており、そうした差異の内容が、元々の「文書1(貸付決議の)」に盛り込まれていた。
4 本省理財局長本人は、当時、連日の国会審議への対応に追われており、配下職員との議論も、国会答弁資料を読み込んだ上で、なお空いた時間で担当者等を局長室に呼び、短時間で済ませるしかないのが実態であった。こうした状況にあって、平成29年2月下旬以降、国会議員からの資料要求等への対応に関する配下職員からの相談に対して、国会審議を更に紛糾させかねない対応は避けるべきであり、提出する前に中身をよく精査すべきとの指示をしていたものと認められる。他方で、当初は、近畿財務局等が作成していた文書の全体像や、改ざん対象の文書の位置付けを正確に把握しておらず、そのことが、誤った判断を行った一因になったとも考えられる。さらにその後、決裁文書の書き換えを行っていることを認識したにもかかわらず、進行中の作業を止めるのではなく、むしろ継続させたものと認められる。
5 また、決裁文書の改ざんを行うことについて、本省理財局の次長、総務課長、国有財産企画課長及び国有財産審理室長を含めた職員に躊躇がないわけではなかったが、
- 元々の決裁文書は、本省理財局の感覚からすれば、決裁のために必要ではない情報が多く含まれていると考えたこと、
- 虚偽の内容を追加しているわけではなく、また、改ざん後の文書であっても、決裁の本質的な内容が変わるものではないと考えたこと、
- 連日の国会審議への対応のほか、説明要求や資料要求への対応により職員が疲弊しており、それ以上議論の材料を増やしたくなかったこと、
から、最終的には許容範囲だと考えて、改ざん作業を止めるまでには至らなかったものと認められる。
6 さらに、本省理財局において改ざんに関与した職員の一部は、改ざんを行った決裁文書は元々近畿財務局や本省理財局が作成したものであり、決裁権限を有する職員が決裁の本質的な内容を変えない範囲の書き換えを行い、そうした文書を国会や会計検査院等に提出することは、ぎりぎり許される対応ではないか、と考えていたとしている。
7 近畿財務局においては、上記の通り、応接録の廃棄について必ずしも徹底されなかったほか、決裁文書の改ざんにも多くの職員が反発していたが、主に管財部長や管財部次長の判断により、本省理財局の立場を慮って、作業に協力したのが実態だと認められる。
(2)一連の問題行為の評価
1 国権の最高機関である国会への対応として、上記のような決裁文書の改ざん作業を行い、改ざん後の文書を提出したことは、あってはならないことであり、不適切な対応だったと言わざるを得ない。さらに、行政府における文書管理のあり方としても、一旦決裁を経た行政文書について、事後的に誤記の修正等の範疇を超える改ざんを行ったことは、「公文書等の管理に関する法律」の趣旨に照らしても不適切な対応だったと考えられる。
2 上記のような応接録の取扱いについても、国権の最高機関である国会への対応として、不適切な対応だったと言わざるを得ない。保存期間が終了した応接録を適切に廃棄していくこと自体は法令に基づく取扱いであり、通常であれば、幹部職員からその趣旨を徹底するよう求めることには問題はないが、国会審議等において各種応接録の存否が問題になった後に廃棄を進め、存在しない旨を回答したことは、不適切である。
3 会計検査院による会計検査に対して、廃棄されずに残された応接録の存在を明かさなかったり、改ざん後の決裁文書を提出したことは、不適切な対応である。この会計検査が、参議院予算委員会の要請に基づき行われているものであることを踏まえれば、国権の最高機関である国会との関係でも、問題のある対応だったと言わざるを得ない。
4 情報公開請求に対して、廃棄されずに残された応接録についても「文書不存在」と回答したり、改ざん後の決裁文書を開示したことは、不適切である。なお、残された応接録や元々の決裁文書については、上記のとおり公表しているところである。
(3)本省理財局における責任の所在の明確化
1 一連の問題行為は、財務大臣及び事務次官等に一切報告されぬまま、本省理財局において、国有財産行政の責任者であった理財局長が方向性を決定づけたものであり、その下で、総務課長が関係者に方針を伝達するなど中核的役割を担い、国有財産企画課長及び国有財産審理室長が深く関与していたものであると認められる。
2 当時の理財局長【停職・3月相当】
国会や会計検査院等への対応に際して、応接録の廃棄や決裁文書の改ざんの方向性を決定付けたものと認められる。一連の問題行為の全貌までを承知していたわけではないが、国有財産行政の責任者である本省理財局の局長であり、さらに、一連の問題行為が森友学園案件に関する自身の国会答弁との関係に起因していたことも踏まえれば、問題行為の全般について責任を免れるものではない。既に平成30年3月9日(金)付で「減給20%・3月」の懲戒処分を受けた上で辞職しているが、今回の調査により判明した事実を踏まえれば、「停職・3月」の懲戒処分に相当するものと認められる(*35)。
(*35)当時の理財局長は、平成30年3月9日(金)の辞職時に、麻生財務大臣からの「今後の調査の結果次第では、更に重い懲戒処分に相当すると判断される可能性もあることから、その場合は「指示に従うべし」との申渡しを了解している。また、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条の3第2項は「(中略)退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。」と定めているが、本人を取り巻く状況がこの規定の後段に定める「特別な事情」に該当するものとして、この規定の前段にかかわらず、退職日から1月以上が経過した後であっても退職手当の支給が留保されることを了解している。その上で、今回の調査結果を踏まえれば、今後支払うべき退職手当から、在職中に「減給20%・3月」ではなく「停職・3月」の懲戒処分を受けていたと仮定した場合における停職期間中の俸給相当額及び当該仮定に基づき退職手当を再計算した場合の減額分を控除することが妥当と考えられる。
3 当時の理財局次長【戒告】
一連の問題行為を承知しており、国有財産行政を担当する本省理財局の次長として、監督責任を免れない。これを踏まえ、「戒告」の懲戒処分を実施する。
4 総務課長【停職・1月】
一連の問題行為について、理財局長に最も近い立場にあって、本省理財局内及び近畿財務局に方針を伝達するなど、中核的な役割を担っていたと認められる。一部の問題行為については関知していなかったが、これも他の問題行為との整合性を確保するために行われていたものであることを考えれば、問題の全般について責任を免れるものではない。さらに、平成29年7月の人事異動後に総務課長の職に留任した後も、後任の理財局長ら転入してきた幹部職員に対して、問題の所在を説明していない。これらを踏まえ、「停職・1月」の懲戒処分を実施する。
なお、配下の当時の総務課職員(課長補佐級)は、一連の問題行為には関与していなかったが、理財局長の国会答弁資料のとりまとめに当たる立場にあり、また、総務課長の直下にあって問題行為が行われていることを認識していたにもかかわらず、有効な対応をとれなかった。これを踏まえ、「口頭厳重注意」の矯正措置を実施する。
5 当時の国有財産企画課長【減給20%・3月】
一連の問題行為について、理財局長の下で、総務課長とともに、本省理財局内で国有財産審理室長らが行った作業を事実上監督するなど、深い関与が認められる。これを踏まえ、「減給20%・3月」の懲戒処分を実施する。
なお、配下の国有財産企画課職員(課長補佐級)は、一連の問題行為には関与していなかったが、理財局長の森友学園案件に関する国会答弁資料のとりまとめに当たる立場にあり、また、国有財産企画課長の直下にあって問題行為が行われていることを認識していたにもかかわらず、有効な対応をとれなかった。これを踏まえ、「口頭厳重注意」の矯正措置を実施する。
また、別の当時の国有財産企画課職員(課長補佐級)についても、一連の問題行為には関与していなかったが、地下埋設物の撤去費用について、森友学園の顧問弁護士に対して事実と異なる説明ぶりを提案したことは、不適切な対応であった。これを踏まえ、「口頭厳重注意」の矯正措置を実施する。
6 当時の国有財産審理室長【減給20%・2月】
一連の問題行為について、理財局長及び総務課長の下で、国有財産企画課長とも相談しつつ、国有財産審理室の配下職員とともに作業を進めたほか、近畿財務局にも各種の指示を行うなど、深い関与が認められる。また、森友学園案件の事案終了前から在職しており、的確な情報提供を行い得る立場であったにもかかわらず、有効な対応を行えなかった。これらを踏まえ、「減給20%・2月」の懲戒処分を実施する。
なお、配下の国有財産審理室職員(課長補佐級)は、一連の問題行為について、本省理財局の幹部職員の指示を受けて作業を進めたほか、近畿財務局にも各種の指示を行うなど、相当程度の関与が認められる。これを踏まえ、「戒告」の懲戒処分を実施する。
また、別の当時の国有財産審理室職員(係長級)についても、一連の問題行為について、本省理財局の幹部職員の指示を受けて作業の一端を担ったほか、F近畿財務局にも指示を行うなどの関与が認められる。これを踏まえ、「文書厳重注意」の矯正措置を実施する。
7 当時の本省理財局に在籍していたその他の職員は、一連の問題行為が進行していく過程で何らかの情報に接したり、一部作業に形式的に関与することはあっても、問題行為が行われていること自体を認識していなかったことから、責任は問わないこととする。
(4)近畿財務局における責任の所在の明確化
1 近畿財務局長【戒告】
一連の問題行為は本省理財局の指示により行われたものであるが、近畿財務局の管財部職員から状況報告を受ける立場にあり、監督責任が認められる。これを踏まえ、「戒告」の懲戒処分を実施する。
2 管財部長【戒告】
一連の問題行為は本省理財局の指示により行われたものであるが、本省理財局の総務課長及び国有財産審理室長との間の調整役を担っていたほか、管財部の配下職員からの状況報告もあって全体像を把握しており、監督責任が認められる。これを踏まえ、「戒告」の懲戒処分を実施する。
3 管財部次長【戒告】
一連の問題行為は本省理財局の指示により行われたものであるが、本省理財局の国有財産審理室長との間の調整役を担っていたほか、管財部の配下職員からの状況報告もあって全体像を把握し、さらに作業にも従事するなど、相当程度の関与が認められる。これを踏まえ、「戒告」の懲戒処分を実施する。
4 当時の統括国有財産管理官【口頭厳重注意】
一連の問題行為は本省理財局の指示により行われたものであるが、配下職員とともに一定の作業に従事していた。これを踏まえ、「口頭厳重注意」の矯正措置を実施する。なお、当時の配下職員は、一定の作業に従事していたものの、本省理財局からの指示に明確に反発して幹部職員にも相談していた経緯を踏まえ、責任は問わないこととする。
5 平成27年6月に「文書8(予定価格決定)」に当初添付されていたメモ「公租公課相当額の取扱いについて(考え方の整理)」の抜取りを行った当時の統括国有財産管理官及びその配下職員(課長補佐級)に対して、「職務上の注意」を実施する。
(5)現在の本省理財局の幹部職員の責任
1 現在の理財局長【文書厳重注意】
平成29年7月に着任して以降、平成30年3月2日(金)の報道に至るまで、一連の問題行為を全く認識していなかったが、国有財産行政の責任者である本省理財局の局長として、この間、配下に問題行為を認識していた職員がおりながら有効な対応を行えず、問題行為の公表が遅れたことの結果責任は免れない。これを踏まえ、「文書厳重注意」の矯正措置を実施する。
2 現在の理財局次長【口頭厳重注意】
平成29年7月に着任して以降、平成30年3月2日(金)の報道に至るまで、一連の問題行為を全く認識していなかったが、この間、配下に問題行為を認識していた職員がおりながら有効な対応を行えなかった。これを踏まえ、「口頭厳重注意」の矯正措置を実施する。
(6)本省理財局職員・近畿財務局職員以外の責任
1 当時の事務次官【減給10%・1月相当】
一連の問題行為を全く認識していなかったが、事務方トップの事務次官として理財局長らを適切に指揮すべき立場にあり、監督責任を免れない。既に平成29年7月5日(水)付で辞職しているが、上記を踏まえれば、「減給10%・1月」の懲戒処分に相当するものと認められる(*36)。
(*36)在職時の給与1月分の10%に相当する金額を自主返納する。
2 当時の大臣官房長【文書厳重注意】
一連の問題行為を全く認識していなかったが、国会対応や文書管理等に責任を負うべき立場にあり、一定の責任は免れない。これを踏まえ、「文書厳重注意」の矯正措置を実施する。
VII.その他の決裁文書に関する調査
(1)調査の概要
1 森友学園案件に関する決裁文書の改ざんが明らかになったことを踏まえ、他部局において同様の事例がないかを確認するため、本省及び近畿財務局を含む各財務局において、決裁文書に関する調査を実施した。
2 具体的には、平成29年度中に決裁が完了した文書のうち、「一元的な文書管理システム」上で電子決裁を行ったものについては、事後的に更新を行った場合にはシステム上修正履歴が残ることから、まずは修正履歴の有無を全件確認した。当該システムでは、一旦電子決裁を完了した後であっても、誤記の修正や正本への差し替え(*37)等が行われ得ることを想定して、事後的な更新が可能とされているが、そうした範疇を超える改ざんが行われていれば問題であることから、そうした事例があるかどうかを確認した。
(*37)実務上、決裁プロセスにおいては対象となる文書の正本が確定しておらず、決裁完了後に差し替えを行う場合がある。
3 さらに、紙媒体で決裁を行った文書も含め、平成29年度中に決裁が完了した文書について、事後的に、誤記の修正や正本への差し替え等の範疇を超える改ざんを行ったことがあるか否かについて、聞き取り調査を行った。
(2)本省に対する調査の結果
1 本省においては、平成29年度中に電子決裁が完了していた20,878件のうち、124件(0.6%)について、決裁完了後の更新履歴が確認されたが、このうち120件については、誤記の修正や正本への差し替え等を行ったものであった。
2 残る4件のうち2件は、
- 財務大臣に本省分の年次災害報告書を報告するための決裁について、3件の労務災害を報告するということで決裁を完了した後、内容に誤りが見つかったため(*38)、件数を0件へと修正した事案、
- 国家公務員宿舎の維持等に関する審査結果を各省庁に通知するための決裁について、審査段階で複数の宿舎が対象から漏れていたことから、改めて、漏れていた宿舎の審査を行い、決裁に追記した事案、
であった。いずれの事案も、修正を行う旨及びその内容を最終決裁権者まで報告して了解を得ていたが、改めて決裁を取ることまではしておらず、修正後の内容について決裁権者の了解が得られているかを検証できない状況となっていた。
(*38)正しくは休業日数1日以上の労務災害を報告すべきであったが、当初は、誤って、休業日数0日の労務災害を報告してしまっていた。
3 さらに残る2件は、いずれも大臣官房秘書課における事案であり、
- 職員の勤務時間を定めるために必要な決裁について、既に期限を過ぎていたことから、決裁手続を経ることなく、決裁が完了していた他課職員の勤務時間を定める文書に対象職員を追加することで処理した事案
- 職員の出張決裁について、出張日前日まで予定が流動的であったことから、事後的に、同日までに決裁が完了していた「別の出張決裁の内容を差し替えることで対応した事案(*39)であった。
(*39)当該差し替えにより上書きされた別の出張決裁については、改めて決裁が取り直されていた。
4 いずれの事案も、決裁の内容を決裁権者に報告することなく、別の決裁済み案件に事後的に追加・差し替えを行う形で処理していたものであり、不適切な取扱いである。これが財務省職員の服務に関する業務を担当する大臣官房秘書課で生じた事案であることも踏まえ、これらの不適切な行為を行った職員(係員級)2名のほか、行為自体は認識していなかったが直属の上司であり最終決裁権者でもある職員(課長補佐級)及び監督責任を有する秘書課長に対して、「口頭厳重注意」の矯正措置を実施する。
5 なお、職員に対する聞き取り調査においては、これ以外の問題は判明しなかった。
(3)財務局に対する調査の結果
1 財務局においては、平成29年度中に電子決裁が完了していた169,708件のうち、436件(0.3%)について、決裁完了後更新履歴が確認されたが、このうち434件については、誤記の修正や正本への差し替え等を行ったものであった。
2 残り2件は、単身赴任届や住居届を財務事務所から財務局本局に届け出る決裁について、実際に申請書類が提出された日付では単身赴任手当や住居手当の支給が翌月になってしまうことから、当月から手当を支払えるようにするため、当該財務局本局の人事担当部局の職員(係長級)から当該財務事務所に指示をして、当該申請書類の提出日を書き換えさせた事案であった。手当の支給に関する不適切な取扱いであり、書き換えを指示した当該職員に対して、「口頭厳重注意」の矯正措置を実施する(*40)。
(*40)決裁書類の書き換えにより過払いが生じた単身赴任手当や住居手当については、受領者に対して、過払い分を国庫に返納させる。
3 なお、職員に対する聞き取り調査においては、これ以外の問|題は判明しなかった。
元稿:HUFFPOST 主要ニュース 政治 【政局・疑惑・「森友改ざん報告書」】 2018年06月05日 10:06:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。












 </picture>
</picture>
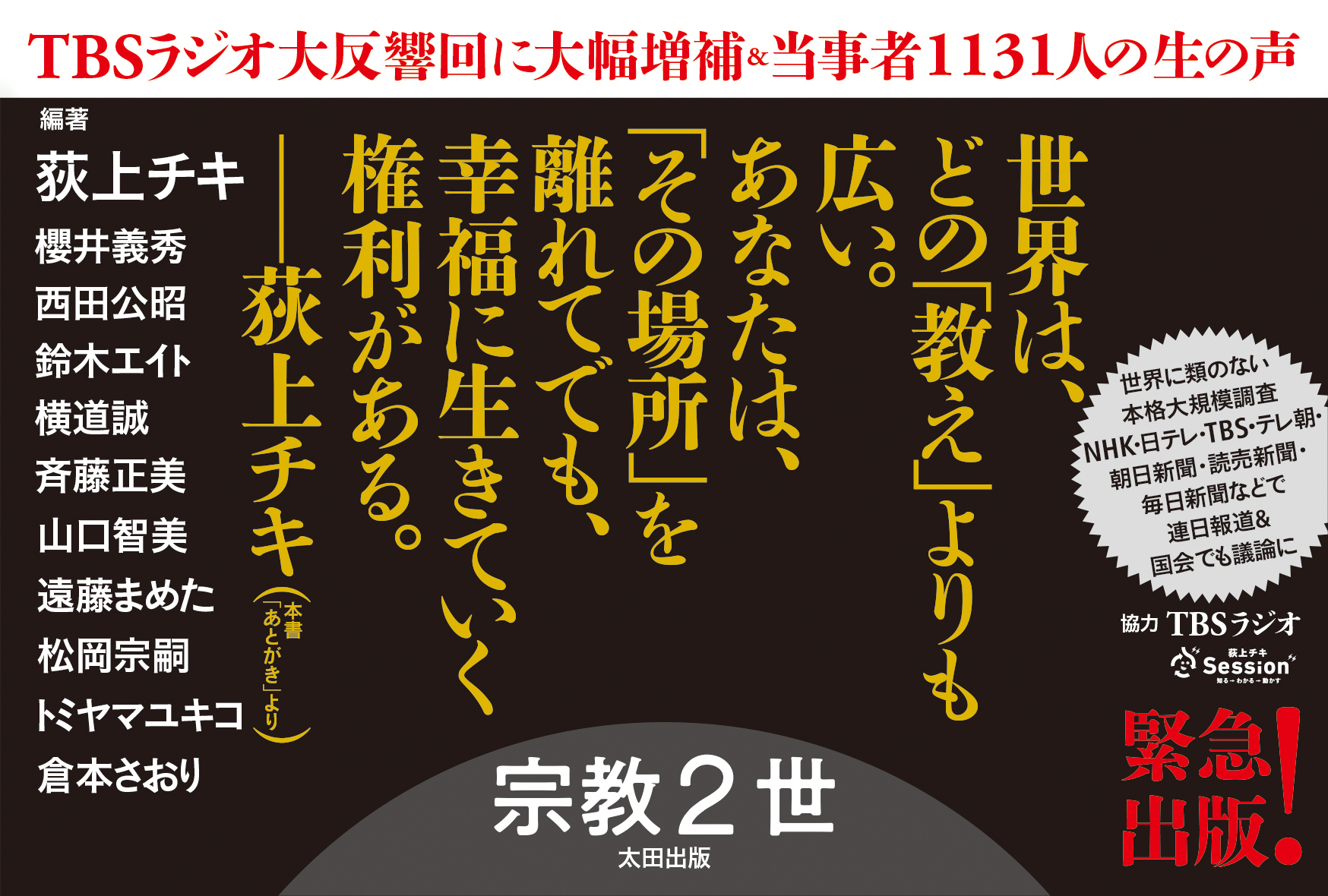
 </picture>筆者撮影・修正
</picture>筆者撮影・修正 </picture>
</picture>

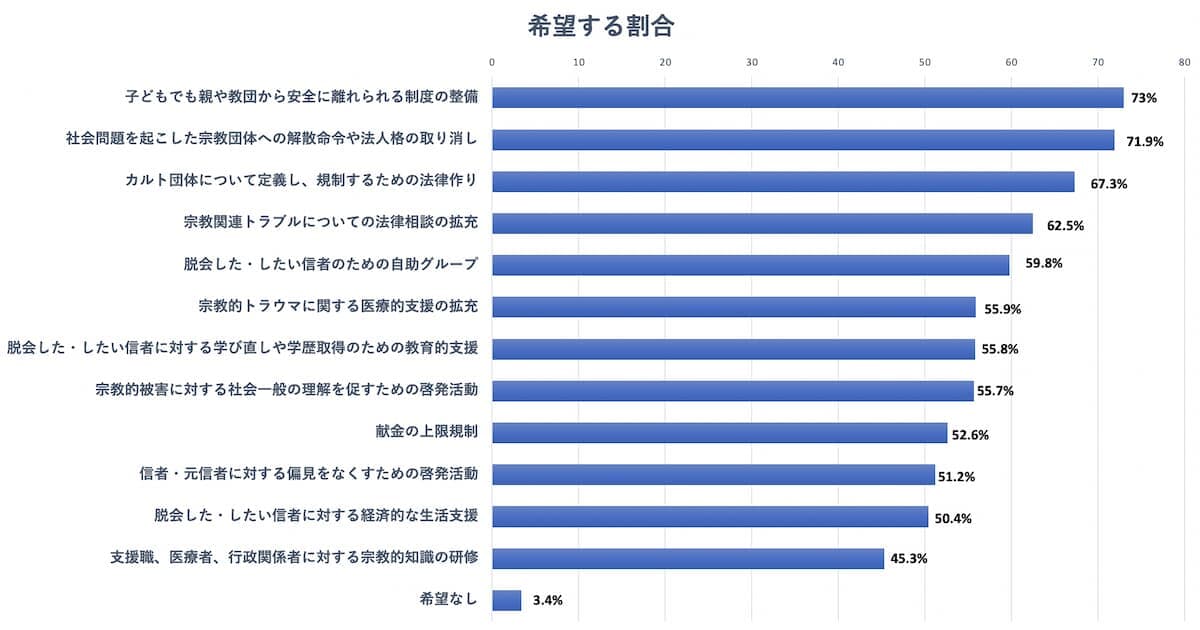
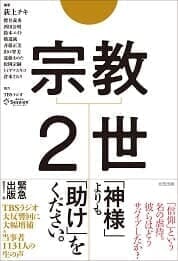
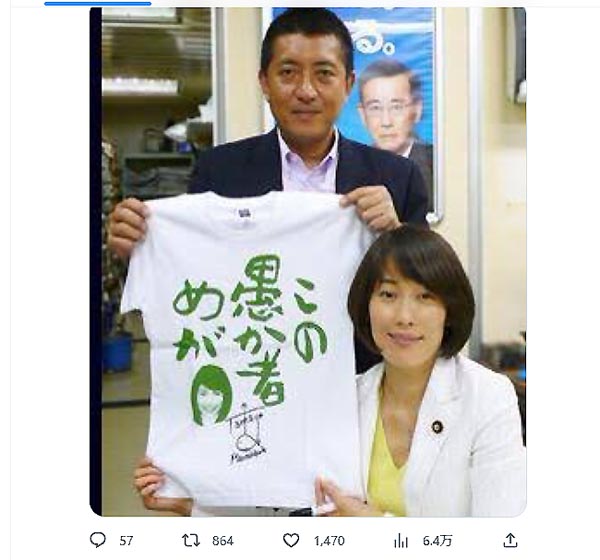 </picture>
</picture>









 都知事選は圧勝した小池氏だが photo/gettyimages
都知事選は圧勝した小池氏だが photo/gettyimages






