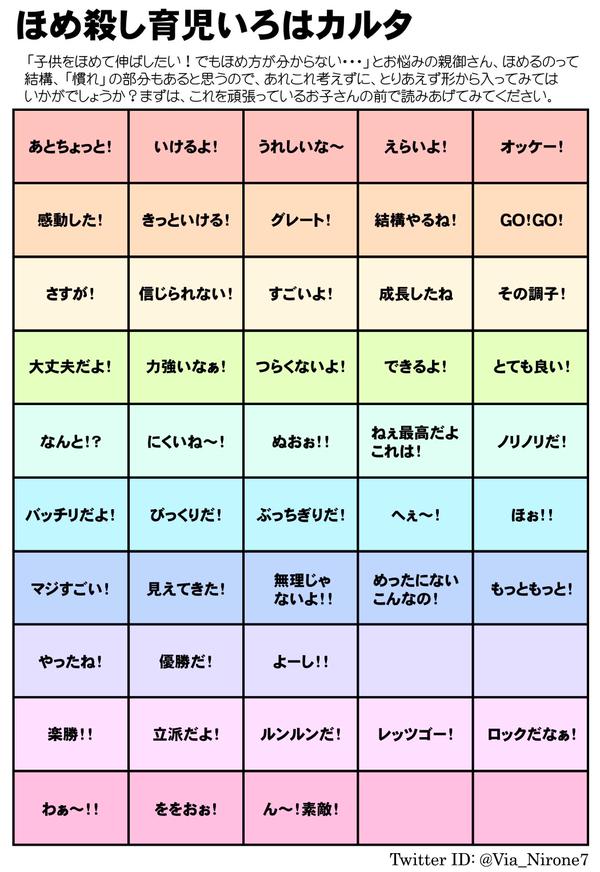バンビは春休み、私の仕事がある日は放課後等デイサービスや移動支援サービスを利用して過ごしています。
放課後等デイサービスって、今すごーく増えている。これはほんとにこの5年で大きく変わったと肌で感じる。
利用する人もすごく多くて、週5で(ヘタしたら土曜日も)預けられている子もいるみたい。
まぁ、今 母親も働いてる人は多いし、それ自体は悪いことではないけどね。
でも、デイは障害児だけの集団なので、そこまで必要なら学童保育の利用を考えてもいいのかなとも思うけど。
ただ、うちの区では いままで健常児は小3まで、障害児は小6まで学童保育を利用することができて
そうすると、4年生以上は同学年の子がいないわけで、”何で学童来てるの?”と言われたり
そういうのが段々面白くなくなって、本人が学童保育に行きたがらなくなる って話は聞いたことある。
(新年度からは健常児も小6まで入れることになるらしいけど、今は塾とか習い事とかでみんな忙しいから
どこまで利用者が増えるかはわからないなぁ。)
それに、学童保育よりデイの方が利用者としては料金が安く済むのも事実だし。
そうなんだけど、でもなんかね、ただ預かってもらえたら親の自分が楽だから っていうんじゃなくて
(それも否定はしないけど)
子どもにいろいろな社会体験をさせる とか
何を目的に預けるのか考えた方がいいんじゃないかと思うんだよね。
あと事業所の方もいっぱいできてるけど
(ニーズが見込めて、さらにそこに福祉として税金が投入されるのでみんな参入するわけね。)
でも、ほんと運営方針とか活動内容とかには事業所によって違いがすごくあると思う。
よく見て選ばないとダメだなー って感じる。
たぶん この先は淘汰されていくことになるのかもしれないけど。
本来、放課後等デイサービスの定義って
学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。
・自立した日常生活を営むために必要な訓練
・創作的活動、作業活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供
本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援を行います。
ってなってる。
つまり、単なる日中一時保護とは違うはずなんだよね。
バンビはあえて2ヶ所の事業所を利用しているけど
A事業所は ただ子供を預かっているだけなカンジ。
宿題は見てくれるけど、創作的活動とかはやってなくて パソコンで動画見たり、ゲームしたりしている。
B事業所は 今日はクッキーを作るとかで、材料の買い出しからやっておやつにそのクッキーを食べたり。
本来の定義に沿っているカンジ。
時間もA事業所は 朝何時にお迎えかは前日の夜電話が来るけど
B事業所は 前月の時点でスケジュールはきちんと決まっている。
連絡帳のフォーマットも書かれている内容も全然違う。
管理者、あるいは経営者?の感性の問題なんだろうか。
そんなわけでいずれA事業所は切って、他を探さなければダメだろうな と思っているところ。
選択肢がたくさんあるわけだから、利用者の方も目を肥やして子どものためにより良い環境を与えてあげたらいいと思っている。
あとね、放課後等デイサービスって18歳までしか利用できないんだよね。
子供が高等部卒業して就労して、企業就労で5時まで働くような状況なら良いけど
作業所とか生活介護事業所とかだと 3時半とか4時には終わるわけ。
それも大抵近所だし、小学生並の時間に帰宅して
それでも一人で留守番ができたり、余暇活動ができる子はいいけど
見守りが必要は子は その時間に親も帰宅しなければならなくなる。
そしたら働けなくなるってこともあるわけね。
それじゃ困るから18歳以降の見守りサービスを って動きが出ている って新聞記事を目にしたので
うちの区はどうなんですか? って、育成会の理事会で質問してみたんだけど
「確かにそうなんだけど、まだ問題にもなっていない。」って答えを聞いて愕然とした。
こりゃ、バンビを企業就労できるか、一人で留守番できる子に育てるか(後者の方が確立高いか)
そっちの方が見込みありそうだよ...。
やっぱり、現状楽な方に流されてると後で痛い目を見たりするし
ある程度先の見通し立てて生きていかないと いざという時困る気がする。
今言ってすぐルールは変わらないからねー。
”何とかなる”って考えてると、何ともならなかった時がツラいよん。
メールはこちらまで → yakkoxhs@gmail.com
放課後等デイサービスって、今すごーく増えている。これはほんとにこの5年で大きく変わったと肌で感じる。
利用する人もすごく多くて、週5で(ヘタしたら土曜日も)預けられている子もいるみたい。
まぁ、今 母親も働いてる人は多いし、それ自体は悪いことではないけどね。
でも、デイは障害児だけの集団なので、そこまで必要なら学童保育の利用を考えてもいいのかなとも思うけど。
ただ、うちの区では いままで健常児は小3まで、障害児は小6まで学童保育を利用することができて
そうすると、4年生以上は同学年の子がいないわけで、”何で学童来てるの?”と言われたり
そういうのが段々面白くなくなって、本人が学童保育に行きたがらなくなる って話は聞いたことある。
(新年度からは健常児も小6まで入れることになるらしいけど、今は塾とか習い事とかでみんな忙しいから
どこまで利用者が増えるかはわからないなぁ。)
それに、学童保育よりデイの方が利用者としては料金が安く済むのも事実だし。
そうなんだけど、でもなんかね、ただ預かってもらえたら親の自分が楽だから っていうんじゃなくて
(それも否定はしないけど)
子どもにいろいろな社会体験をさせる とか
何を目的に預けるのか考えた方がいいんじゃないかと思うんだよね。
あと事業所の方もいっぱいできてるけど
(ニーズが見込めて、さらにそこに福祉として税金が投入されるのでみんな参入するわけね。)
でも、ほんと運営方針とか活動内容とかには事業所によって違いがすごくあると思う。
よく見て選ばないとダメだなー って感じる。
たぶん この先は淘汰されていくことになるのかもしれないけど。
本来、放課後等デイサービスの定義って
学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。
・自立した日常生活を営むために必要な訓練
・創作的活動、作業活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供
本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援を行います。
ってなってる。
つまり、単なる日中一時保護とは違うはずなんだよね。
バンビはあえて2ヶ所の事業所を利用しているけど
A事業所は ただ子供を預かっているだけなカンジ。
宿題は見てくれるけど、創作的活動とかはやってなくて パソコンで動画見たり、ゲームしたりしている。
B事業所は 今日はクッキーを作るとかで、材料の買い出しからやっておやつにそのクッキーを食べたり。
本来の定義に沿っているカンジ。
時間もA事業所は 朝何時にお迎えかは前日の夜電話が来るけど
B事業所は 前月の時点でスケジュールはきちんと決まっている。
連絡帳のフォーマットも書かれている内容も全然違う。
管理者、あるいは経営者?の感性の問題なんだろうか。
そんなわけでいずれA事業所は切って、他を探さなければダメだろうな と思っているところ。
選択肢がたくさんあるわけだから、利用者の方も目を肥やして子どものためにより良い環境を与えてあげたらいいと思っている。
あとね、放課後等デイサービスって18歳までしか利用できないんだよね。
子供が高等部卒業して就労して、企業就労で5時まで働くような状況なら良いけど
作業所とか生活介護事業所とかだと 3時半とか4時には終わるわけ。
それも大抵近所だし、小学生並の時間に帰宅して
それでも一人で留守番ができたり、余暇活動ができる子はいいけど
見守りが必要は子は その時間に親も帰宅しなければならなくなる。
そしたら働けなくなるってこともあるわけね。
それじゃ困るから18歳以降の見守りサービスを って動きが出ている って新聞記事を目にしたので
うちの区はどうなんですか? って、育成会の理事会で質問してみたんだけど
「確かにそうなんだけど、まだ問題にもなっていない。」って答えを聞いて愕然とした。
こりゃ、バンビを企業就労できるか、一人で留守番できる子に育てるか(後者の方が確立高いか)
そっちの方が見込みありそうだよ...。
やっぱり、現状楽な方に流されてると後で痛い目を見たりするし
ある程度先の見通し立てて生きていかないと いざという時困る気がする。
今言ってすぐルールは変わらないからねー。
”何とかなる”って考えてると、何ともならなかった時がツラいよん。
メールはこちらまで → yakkoxhs@gmail.com