昨日、Sexy Beat という佳作映画を紹介しました。Sexyはともかく Beatといえるような音楽はなかったなと気になっていました。何のことはない。よく読んだらBeatではなく、Beast(野獣)でした。Sexy Beast、直訳すれば、「セクシーな野獣」です。安物タイトルではどちらも変わりませんね。感想文もほとんど変える必要がないので、そのままにしておきます。Sexyの対象は、やはり女ではなく男に向かっています。だから、Sexy Beast、ドン・ローガンは怖いのです。
The Godfather – Orchestral Suite. - The Danish National Symphony Orchestra (Live)
NHKのBSで放映していた。Ⅰは見逃して、Ⅱは全編、Ⅲは後半のみ。あらためて、Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ だと思った。あるいは、Ⅰ>Ⅱ≠Ⅲ ではないかとも。
しかし、絵はどの作品とも凄いと感心した。何回も観ているのと、こちらが30年以上年齢を重ねたせいか、主筋や主役より、脇の物語や脇役に注意がいってしまう。たぶん、「ゴッドファーザーおたく」のような人が日本にもたくさんいて、なかにはびっくりするほど詳しい人がいるだろうと思う。そんな人の話が聞けるときっと楽しいでしょう。
ここでマイフェバリットな役や俳優を思い出してみると、PERTⅠでは、悪徳警官マクラウスキー警部(スターリング・ヘイドン)、麻薬ビジネスをコルレオーネファミリーに持ちかけるソロッツォ(アル・レッティエリ)が印象深かったですね。PERTⅡでは、ファミリーを裏切ってFBI側の証人になる「天使のフランキー」(マイケル・ガッツォ)が厚ぼったい口髭としゃがれ声と太い腹の男っぽさで、子分のチッチ(ジョー・スピネル)と共に味わい深い。シリーズを通してなら、やはり、トム・へイゲン(ロバート・デュヴァル)の静謐な佇まいとフレド・コルレオーネ(ジョン・カザール)の哀切が心に残ります。
しかし、ゴッドファーザーシリーズの数多(あまた)ある役と俳優の中で、いちばん好きを上げよといわれれば、この人のこの役と迷いません。マイケルに影のように寄り添う殺し屋アル・ネリ(リチャード・ブライト)です。

この人は、S・マックイーンとアリ・マッグロウが共演して後に結婚するきっかけになった、「ゲッタウエイ」(1973)が初見でした。ほとんど、一目惚れのように気に入りました。「ゲッタウエイ」は、マックイーン扮する銀行強盗が奪った金を持ってアリ・マッグロウの妻と逃避行をするロードムービーでした。追いかけるのは、警察ではなく犯罪ボスが送った殺し屋。「ゴッドファーザーPERTⅠ」でソロッツオを演じたアル・レッティエリ。この人もむせかえるような男臭さで圧倒的でした。
さて、アリ・マッグロウが駅のコインロッカーにカバンを預けようとすると、カウボーイハットにこざっぱりとした旅行姿のリチャード・ブライトが声をかけて手伝います。金の詰まったズッシリ重いカバンをロッカーに入れ、鍵をアリ・マッグロウに渡しました。「ご親切にありがとう」と感謝する女。「どういたしまして」と西部の男らしく帽子のひさしに指を添えて返礼します。
マックイーンと落ち合って、ロッカーに戻ります。どうしてか鍵が開かない。係員を呼んで開けさせると、中は空っぽ。「そんなはずはないわ! 親切な男の人が手伝ってくれて・・・アッ」と手で口を覆う女。カウボーイハットはあらかじめ持っていた別の鍵とすり替えたんですね。マックイーンはカゴ抜け詐欺に引っかかったとすぐに気づき、「駅で待っていろ!」と女に言い残し探し歩く。
やがて、運よく見覚えのあるカバンを提げたカウボーイハットの男を見つけ、懸命に追いかけるが、やがて見失ってしまう。出発していく列車を見送りながら立ち尽くすマックイーン。汗が吹いています。一方、逃げた男は走り出した列車に飛び乗り、車中の人となる。後ろを気にしながら、少しでも先に逃げようとするかのように、前の車両へ車両へと足早に歩いていく。頃合いと席についてほっとする。
ほかの乗客はほとんどいない。汗だくでまだ眼が落ち着かない。ようやく息を整え、近くに人がいないか振り返ってから、膝上に置いたカバンを開けてみる。唸る札束。びっくりして目を丸くするケチな詐欺師。カバンを閉じて、興奮を抑え込もうと努める。沸き上がる嬉しさに笑顔が広がる。愛しそうにカバンを撫で回す。と、隣の席に誰か座った。(アッ、追いかけてきた男だ)と思うまもなく、パンチが喰らわされ・・・。
安っぽい格好をした、貧弱な体格で卑小な顔つきの、めまぐるしく青い眼が動く小心な男。リチャード・ブライトはそんな小悪党を演じて、とてもカッコウがよかった。最低の男が最高の幸運を引き当て、すぐにまた最低の男に戻る、ケガ付きで。しかし、観客は途中からこのケチな詐欺師に同情してしまうのを止められない。俺たち自身だからだ。
命金を追うマックイーンに感情移入しなければならないのに、逃げるネズミの詐欺男に猫から逃げ切ってくれと思ってしまうのだ。リチャード・ブライトが徹底した卑小を造型したおかげで、観客の我が事になった。見事に負け切ってみせて、大スターを食い、脇役・ちょい役にも、それぞれ生き延びようとする人生があることを観客に思い出させた。それは胸が空くカッコウのよさだった。
そのリチャード・ブライトが、「ゴッドファーザー」に寡黙で凄腕の殺し屋アル・ネリで登場したときは、バンザイしたくなりました。ケチな詐欺師と同様、冷徹な殺し屋になりきりました。PERTⅡでは、終盤、大司教を殺すためにバチカンへ旅立つ列車のコンパートメントに座っています。膝上にはチョコレートの小箱。これはもう、「ゲッタウエイ」の列車シーンのパロディではないかと。引用されるほど、秀逸なシーンとして語り継がれているのだと思えてしまいます。
コンパートメントを買い切ったとは、出世したな、リチャード・ブライト、よかったよかった、と肩を叩きたくなりました。高価そうなチョコレートの詰め合わせ箱を開いて、そのひとつを小さめの口に頬張る。その手つきは慎重です。箱の底に隠された拳銃を確かめ、車窓の夜を見遣る。チョコレートを咀嚼する少し野卑な口許。殺し屋とチョコレートの意外な組み合わせが、リチャード・ブライトを得て効いていました。今回、PERT.Ⅱ 観ていて、このアル・ネリはかなり重要な役だと確認しました。
こんな場面があります。ドン・マイケルの執務室。マイケルの他に幾人かの幹部がいて話し合っています。アル・ネリはいつものように後ろに立ち控えています。セーター姿です。いつのまにか、室内に設けられたミニバーのカウンター前にいます。アル・ネリは、(退屈だなあ)とばかり、授業中に中学生が居眠りをするような格好で、バーカウンターに俯せ手の甲に頬を乗せます。くつろいだグレートデンのようです。考えてみれば、ドンの前で不作法な振る舞いです。しかし、誰も気にしません。
ボデイガード兼殺し屋のアル・ネリは、ドンであるマイケル・コルレオーネの忠実な犬なのですが、グレートデンのようにどこか主人の力量を推し量っているようなところがあります。この主人は、本当に自分の飼い主たる資格を持つ、強く賢い男なのかと。マイケルもコーヒーを持ってこさせ、車や部屋のドアを開けさせるアル・ネリの視線を、ときに気にしたりします。その無表情な瞳に自分がどう映っているかを。ただの主人と犬、親分と子分の関係ではないようです。
なぜ、マイケルは、「ママが死ぬまでは、フレドの身は安全だ」と聞こえよがしにいわなければならなかったのか。自分に言い聞かせ、アル・ネリに聞かせるためでした。裏切り者には死を、というファミリーの掟を兄だからと、すぐには実行せず延期することへの後ろめたさ。あるいは、言い換えれば、「ママが死ぬまでの命だ」とアル・ネリらファミリーのメンバーに宣言したという意味でしょうか。ドンとしての義務と兄弟としての情愛に、身を引き裂かれるマイケルという場面なのでしょうか。
マイケルとアル・ネリの視線の交差を俺はそうは見ませんでした(ねえ、こういうときに目線という言葉はないでしょう?)。互いに冷たい視線です。
アル・ネリはPERT.Ⅰでは、交通警官に偽装して、コルレオーネ・ファミリー潰しの黒幕であるドン・バルジーニ(リチャード・コンテ)を仕止めます。PERT.Ⅲでは大司教を葬ります。いわば、コルレオーネ・ファミリーの最終兵器です。アル・ネリは命令に従うだけで、殺す人間に好悪や愛憎などの感情はもちろん、組織の中での功名心すらなさそうです。アル・ネリは出世しない。あいかわらず、ドンの傍らに控え、自分の組や縄張りを持っているようには描かれていません。
契約に基づく報酬や疑似家族共同体の絆といった生臭さとアル・ネリは結びつきません。ただ、無垢な暴力を行使する。アル・ネリのような男こそ、マフィアの伝統と組織が造り上げた人間なのです。マフィアというシステムがつくった生ける死に神なのです。「天使のフランキー」なら、ローマ帝国の闘士と褒めそやすかもしれないが、マイケルにとっては、変革しようとしたファミリーの象徴のような存在ではないでしょうか。マイケルはケイに、「ファミリーを合法化する」と幾度も約束します。そのとき、マイケルは本気でした。しかし、結局はできなかった。
マイケルは母の死後、フレド殺しをアル・ネリに命じます。別の見方をすれば、アル・ネリがマイケルに命じたのです。フレドを殺すように。それこそがファミリーの掟であり、掟こそがファミリーだからです。実際のイタリア系マフィアがどうであるかは関係ありません。この映画では、ファミリー(家族)を超えたファミリー(システム)の残酷を描いているからです。マイケルは、アル・ネリにフレド殺しを命ずることで、生涯を賭けて闘ったファミリー(システム)に膝を屈しました。
したがって、「ゴッドファーザー」は、アル・ネリがフレドを撃った湖水の場面で終わったと思えます。ボートハウスで銃声を聴くマイケルは、守るべき家族を殺したことで、あらためて家族を失い、もはや死んだも同然なのです。かつて、「ゲッタウエイ」で逃げるネズミだったリチャード・ブライトは、「ゴッドファーザー」では、ファミリー(システム)の死神として、ドン・マイケルを打ち負かします。マーロン・ブランドより、ロバート・デニーロより、アル・パチーノより、リチャード・ブライトとジョン・カザールをコッポラは描きたかった。どの場面より、このフレド殺しの場面こそ重要だと考えたのではなかったか。
寂しい湖水のボートにいるのは、フレドとアル・ネリだけでした。「ゴッドファーザー」は象徴的な場面の多い映画でしたが、ほとんど寓話的なほど象徴的な場面ではなかったかと思っています。つまり、アル・ネリ=リチャード・ブライトは、隠れた主役だったのです、といえば、そりゃ言い過ぎでしょう。最近見かけませんがリチャード・ブライト、元気でしょうか。
(敬称略)
NHKのBSで放映していた。Ⅰは見逃して、Ⅱは全編、Ⅲは後半のみ。あらためて、Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ だと思った。あるいは、Ⅰ>Ⅱ≠Ⅲ ではないかとも。
しかし、絵はどの作品とも凄いと感心した。何回も観ているのと、こちらが30年以上年齢を重ねたせいか、主筋や主役より、脇の物語や脇役に注意がいってしまう。たぶん、「ゴッドファーザーおたく」のような人が日本にもたくさんいて、なかにはびっくりするほど詳しい人がいるだろうと思う。そんな人の話が聞けるときっと楽しいでしょう。
ここでマイフェバリットな役や俳優を思い出してみると、PERTⅠでは、悪徳警官マクラウスキー警部(スターリング・ヘイドン)、麻薬ビジネスをコルレオーネファミリーに持ちかけるソロッツォ(アル・レッティエリ)が印象深かったですね。PERTⅡでは、ファミリーを裏切ってFBI側の証人になる「天使のフランキー」(マイケル・ガッツォ)が厚ぼったい口髭としゃがれ声と太い腹の男っぽさで、子分のチッチ(ジョー・スピネル)と共に味わい深い。シリーズを通してなら、やはり、トム・へイゲン(ロバート・デュヴァル)の静謐な佇まいとフレド・コルレオーネ(ジョン・カザール)の哀切が心に残ります。
しかし、ゴッドファーザーシリーズの数多(あまた)ある役と俳優の中で、いちばん好きを上げよといわれれば、この人のこの役と迷いません。マイケルに影のように寄り添う殺し屋アル・ネリ(リチャード・ブライト)です。

この人は、S・マックイーンとアリ・マッグロウが共演して後に結婚するきっかけになった、「ゲッタウエイ」(1973)が初見でした。ほとんど、一目惚れのように気に入りました。「ゲッタウエイ」は、マックイーン扮する銀行強盗が奪った金を持ってアリ・マッグロウの妻と逃避行をするロードムービーでした。追いかけるのは、警察ではなく犯罪ボスが送った殺し屋。「ゴッドファーザーPERTⅠ」でソロッツオを演じたアル・レッティエリ。この人もむせかえるような男臭さで圧倒的でした。
さて、アリ・マッグロウが駅のコインロッカーにカバンを預けようとすると、カウボーイハットにこざっぱりとした旅行姿のリチャード・ブライトが声をかけて手伝います。金の詰まったズッシリ重いカバンをロッカーに入れ、鍵をアリ・マッグロウに渡しました。「ご親切にありがとう」と感謝する女。「どういたしまして」と西部の男らしく帽子のひさしに指を添えて返礼します。
マックイーンと落ち合って、ロッカーに戻ります。どうしてか鍵が開かない。係員を呼んで開けさせると、中は空っぽ。「そんなはずはないわ! 親切な男の人が手伝ってくれて・・・アッ」と手で口を覆う女。カウボーイハットはあらかじめ持っていた別の鍵とすり替えたんですね。マックイーンはカゴ抜け詐欺に引っかかったとすぐに気づき、「駅で待っていろ!」と女に言い残し探し歩く。
やがて、運よく見覚えのあるカバンを提げたカウボーイハットの男を見つけ、懸命に追いかけるが、やがて見失ってしまう。出発していく列車を見送りながら立ち尽くすマックイーン。汗が吹いています。一方、逃げた男は走り出した列車に飛び乗り、車中の人となる。後ろを気にしながら、少しでも先に逃げようとするかのように、前の車両へ車両へと足早に歩いていく。頃合いと席についてほっとする。
ほかの乗客はほとんどいない。汗だくでまだ眼が落ち着かない。ようやく息を整え、近くに人がいないか振り返ってから、膝上に置いたカバンを開けてみる。唸る札束。びっくりして目を丸くするケチな詐欺師。カバンを閉じて、興奮を抑え込もうと努める。沸き上がる嬉しさに笑顔が広がる。愛しそうにカバンを撫で回す。と、隣の席に誰か座った。(アッ、追いかけてきた男だ)と思うまもなく、パンチが喰らわされ・・・。
安っぽい格好をした、貧弱な体格で卑小な顔つきの、めまぐるしく青い眼が動く小心な男。リチャード・ブライトはそんな小悪党を演じて、とてもカッコウがよかった。最低の男が最高の幸運を引き当て、すぐにまた最低の男に戻る、ケガ付きで。しかし、観客は途中からこのケチな詐欺師に同情してしまうのを止められない。俺たち自身だからだ。
命金を追うマックイーンに感情移入しなければならないのに、逃げるネズミの詐欺男に猫から逃げ切ってくれと思ってしまうのだ。リチャード・ブライトが徹底した卑小を造型したおかげで、観客の我が事になった。見事に負け切ってみせて、大スターを食い、脇役・ちょい役にも、それぞれ生き延びようとする人生があることを観客に思い出させた。それは胸が空くカッコウのよさだった。
そのリチャード・ブライトが、「ゴッドファーザー」に寡黙で凄腕の殺し屋アル・ネリで登場したときは、バンザイしたくなりました。ケチな詐欺師と同様、冷徹な殺し屋になりきりました。PERTⅡでは、終盤、大司教を殺すためにバチカンへ旅立つ列車のコンパートメントに座っています。膝上にはチョコレートの小箱。これはもう、「ゲッタウエイ」の列車シーンのパロディではないかと。引用されるほど、秀逸なシーンとして語り継がれているのだと思えてしまいます。
コンパートメントを買い切ったとは、出世したな、リチャード・ブライト、よかったよかった、と肩を叩きたくなりました。高価そうなチョコレートの詰め合わせ箱を開いて、そのひとつを小さめの口に頬張る。その手つきは慎重です。箱の底に隠された拳銃を確かめ、車窓の夜を見遣る。チョコレートを咀嚼する少し野卑な口許。殺し屋とチョコレートの意外な組み合わせが、リチャード・ブライトを得て効いていました。今回、PERT.Ⅱ 観ていて、このアル・ネリはかなり重要な役だと確認しました。
こんな場面があります。ドン・マイケルの執務室。マイケルの他に幾人かの幹部がいて話し合っています。アル・ネリはいつものように後ろに立ち控えています。セーター姿です。いつのまにか、室内に設けられたミニバーのカウンター前にいます。アル・ネリは、(退屈だなあ)とばかり、授業中に中学生が居眠りをするような格好で、バーカウンターに俯せ手の甲に頬を乗せます。くつろいだグレートデンのようです。考えてみれば、ドンの前で不作法な振る舞いです。しかし、誰も気にしません。
ボデイガード兼殺し屋のアル・ネリは、ドンであるマイケル・コルレオーネの忠実な犬なのですが、グレートデンのようにどこか主人の力量を推し量っているようなところがあります。この主人は、本当に自分の飼い主たる資格を持つ、強く賢い男なのかと。マイケルもコーヒーを持ってこさせ、車や部屋のドアを開けさせるアル・ネリの視線を、ときに気にしたりします。その無表情な瞳に自分がどう映っているかを。ただの主人と犬、親分と子分の関係ではないようです。
なぜ、マイケルは、「ママが死ぬまでは、フレドの身は安全だ」と聞こえよがしにいわなければならなかったのか。自分に言い聞かせ、アル・ネリに聞かせるためでした。裏切り者には死を、というファミリーの掟を兄だからと、すぐには実行せず延期することへの後ろめたさ。あるいは、言い換えれば、「ママが死ぬまでの命だ」とアル・ネリらファミリーのメンバーに宣言したという意味でしょうか。ドンとしての義務と兄弟としての情愛に、身を引き裂かれるマイケルという場面なのでしょうか。
マイケルとアル・ネリの視線の交差を俺はそうは見ませんでした(ねえ、こういうときに目線という言葉はないでしょう?)。互いに冷たい視線です。
アル・ネリはPERT.Ⅰでは、交通警官に偽装して、コルレオーネ・ファミリー潰しの黒幕であるドン・バルジーニ(リチャード・コンテ)を仕止めます。PERT.Ⅲでは大司教を葬ります。いわば、コルレオーネ・ファミリーの最終兵器です。アル・ネリは命令に従うだけで、殺す人間に好悪や愛憎などの感情はもちろん、組織の中での功名心すらなさそうです。アル・ネリは出世しない。あいかわらず、ドンの傍らに控え、自分の組や縄張りを持っているようには描かれていません。
契約に基づく報酬や疑似家族共同体の絆といった生臭さとアル・ネリは結びつきません。ただ、無垢な暴力を行使する。アル・ネリのような男こそ、マフィアの伝統と組織が造り上げた人間なのです。マフィアというシステムがつくった生ける死に神なのです。「天使のフランキー」なら、ローマ帝国の闘士と褒めそやすかもしれないが、マイケルにとっては、変革しようとしたファミリーの象徴のような存在ではないでしょうか。マイケルはケイに、「ファミリーを合法化する」と幾度も約束します。そのとき、マイケルは本気でした。しかし、結局はできなかった。
マイケルは母の死後、フレド殺しをアル・ネリに命じます。別の見方をすれば、アル・ネリがマイケルに命じたのです。フレドを殺すように。それこそがファミリーの掟であり、掟こそがファミリーだからです。実際のイタリア系マフィアがどうであるかは関係ありません。この映画では、ファミリー(家族)を超えたファミリー(システム)の残酷を描いているからです。マイケルは、アル・ネリにフレド殺しを命ずることで、生涯を賭けて闘ったファミリー(システム)に膝を屈しました。
したがって、「ゴッドファーザー」は、アル・ネリがフレドを撃った湖水の場面で終わったと思えます。ボートハウスで銃声を聴くマイケルは、守るべき家族を殺したことで、あらためて家族を失い、もはや死んだも同然なのです。かつて、「ゲッタウエイ」で逃げるネズミだったリチャード・ブライトは、「ゴッドファーザー」では、ファミリー(システム)の死神として、ドン・マイケルを打ち負かします。マーロン・ブランドより、ロバート・デニーロより、アル・パチーノより、リチャード・ブライトとジョン・カザールをコッポラは描きたかった。どの場面より、このフレド殺しの場面こそ重要だと考えたのではなかったか。
寂しい湖水のボートにいるのは、フレドとアル・ネリだけでした。「ゴッドファーザー」は象徴的な場面の多い映画でしたが、ほとんど寓話的なほど象徴的な場面ではなかったかと思っています。つまり、アル・ネリ=リチャード・ブライトは、隠れた主役だったのです、といえば、そりゃ言い過ぎでしょう。最近見かけませんがリチャード・ブライト、元気でしょうか。
(敬称略)
さて、「Sexy Beat」だが、なんとイギリス映画である。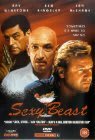
おもな場面は日射しの強いスペインの海岸の別荘。主演がレイ・ウインストン、共演がベン・キングスレイ。レイはイギリス映画には欠かせない名脇役、ベンは国際的な名優といってよい位置だろう。この二人の映画が「セクシービート」。金髪ビキニ娘が意味もなくうろうろ、ドンチャカ音楽に尻振って踊る場面を予想したが、そんなSexyやBeatはどこにもなかった。どうしてこのタイトルなのか、いまだにわからない。
スペインで悠々自適の隠退生活を送るギャングに、ロンドンから悪事を持ちかけに旧知のギャングが訪ねてくる。嫌がる引退ギャングのガル(レイ・ウインストン)、強引な悪事持ちかけギャングがドン・ローガン(ベン・キングスレイ)。この二人の映画を観てきた人なら、配役が逆だろうと思うはずだ。粗暴で相手を震え上がらせる役柄ばかり演じてきた傲岸な面構えの大男のレイこそ恐喝男向きだし、由緒正しいイングリッシュを駆使するインテリ役が相場のベンなら怯える男がふさわしい。ところがこの映画のベン・キングスレイ、ちょっと見にはわからない。
ガンジーを演じたインド系の黒い髪と瞳を染め変えた扮装もさることながら、英語らしいとわかるくらいの不明瞭な発音で口汚く罵り怒鳴る口調が、まったく違うのだ。ロイヤル・シェークスピア・カンパニー出身のシェークスピア役者が、ロンドンの下町の下層の下品な英語をまくしたてる。適切な例が浮かばないが、強いていえば、日本ならやんごとなき皇族の口から、河内弁が飛び出すようなものか。怒鳴り声の迫力以上に、ちょっと日本語の語彙には見当たらないと思えるほど罵倒が辛辣をきわめる。気の弱い人なら、卒倒しそうなくらいに凄まじい。
一流の金庫破りとしてギャング仲間から一目置かれていたガルも、ドンの無理強いをはねのけるどころか、自分だけでなく傍らの愛妻や親友を侮辱され、いきなり殴られ蹴られても、機嫌を損ねまいとおどおどしている。しかし、この怖ろしいドン・ローガンさえ、さらに大物のテディ・ベス(イアン・マクシェーン)の使いにしか過ぎないのだ。眩く暑いスペインで天国を楽しんでいたのに、ドンの虚ろな眼光は冷たく暗いロンドンを覗かせる。追いつめられたガルは危機を脱せるのか?
という暗黒街と犯罪計画、犯罪者をめぐる心理サスペンスなのですが、ひじょうにホモセクシャルな映画でもあります。ホモセクシャルといっても、「モーリス」のような上流階級の美少年や美声年が恋をするような耽美なゲイではありません。「カマ野郎!」という罵り言葉が日常であるような、血と汗と肉にまみれ、骨がきしむ暴力と残酷な死をやりとりする男たちの間の、ホモセクシャルとしか呼びようのない切迫した感情が、この映画の全編を流れています。そうしたホモセクシャルの典型が、ドン・ローガンに扮したベン・キングスレイなのです。
つまり、この映画は、足を洗った金庫破りが、犯罪組織によって犯罪に引き戻されようとするが抵抗するという映画ではない。少なくともガルが忌避したのは、犯罪組織という機能集団が結ぶホモセクシャルな共同体のメンバーに戻ることなのです。その男たちの世界では、sexyとは陰惨な振る舞いであり、不吉なbeatに煽られるものなのです(無理矢理かな)。CATVやスカパーを視聴しているなら、繰り返し放映されているはず。観て損はありません。
(敬称略)
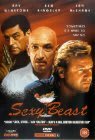
おもな場面は日射しの強いスペインの海岸の別荘。主演がレイ・ウインストン、共演がベン・キングスレイ。レイはイギリス映画には欠かせない名脇役、ベンは国際的な名優といってよい位置だろう。この二人の映画が「セクシービート」。金髪ビキニ娘が意味もなくうろうろ、ドンチャカ音楽に尻振って踊る場面を予想したが、そんなSexyやBeatはどこにもなかった。どうしてこのタイトルなのか、いまだにわからない。
スペインで悠々自適の隠退生活を送るギャングに、ロンドンから悪事を持ちかけに旧知のギャングが訪ねてくる。嫌がる引退ギャングのガル(レイ・ウインストン)、強引な悪事持ちかけギャングがドン・ローガン(ベン・キングスレイ)。この二人の映画を観てきた人なら、配役が逆だろうと思うはずだ。粗暴で相手を震え上がらせる役柄ばかり演じてきた傲岸な面構えの大男のレイこそ恐喝男向きだし、由緒正しいイングリッシュを駆使するインテリ役が相場のベンなら怯える男がふさわしい。ところがこの映画のベン・キングスレイ、ちょっと見にはわからない。
ガンジーを演じたインド系の黒い髪と瞳を染め変えた扮装もさることながら、英語らしいとわかるくらいの不明瞭な発音で口汚く罵り怒鳴る口調が、まったく違うのだ。ロイヤル・シェークスピア・カンパニー出身のシェークスピア役者が、ロンドンの下町の下層の下品な英語をまくしたてる。適切な例が浮かばないが、強いていえば、日本ならやんごとなき皇族の口から、河内弁が飛び出すようなものか。怒鳴り声の迫力以上に、ちょっと日本語の語彙には見当たらないと思えるほど罵倒が辛辣をきわめる。気の弱い人なら、卒倒しそうなくらいに凄まじい。
一流の金庫破りとしてギャング仲間から一目置かれていたガルも、ドンの無理強いをはねのけるどころか、自分だけでなく傍らの愛妻や親友を侮辱され、いきなり殴られ蹴られても、機嫌を損ねまいとおどおどしている。しかし、この怖ろしいドン・ローガンさえ、さらに大物のテディ・ベス(イアン・マクシェーン)の使いにしか過ぎないのだ。眩く暑いスペインで天国を楽しんでいたのに、ドンの虚ろな眼光は冷たく暗いロンドンを覗かせる。追いつめられたガルは危機を脱せるのか?
という暗黒街と犯罪計画、犯罪者をめぐる心理サスペンスなのですが、ひじょうにホモセクシャルな映画でもあります。ホモセクシャルといっても、「モーリス」のような上流階級の美少年や美声年が恋をするような耽美なゲイではありません。「カマ野郎!」という罵り言葉が日常であるような、血と汗と肉にまみれ、骨がきしむ暴力と残酷な死をやりとりする男たちの間の、ホモセクシャルとしか呼びようのない切迫した感情が、この映画の全編を流れています。そうしたホモセクシャルの典型が、ドン・ローガンに扮したベン・キングスレイなのです。
つまり、この映画は、足を洗った金庫破りが、犯罪組織によって犯罪に引き戻されようとするが抵抗するという映画ではない。少なくともガルが忌避したのは、犯罪組織という機能集団が結ぶホモセクシャルな共同体のメンバーに戻ることなのです。その男たちの世界では、sexyとは陰惨な振る舞いであり、不吉なbeatに煽られるものなのです(無理矢理かな)。CATVやスカパーを視聴しているなら、繰り返し放映されているはず。観て損はありません。
(敬称略)

年度末が迫って忙しいのに、CATVで「Sexy Beat」、BSで「ゴッドファーザーⅡ」と「Ⅲ」、同じく今夜のBSで、「欲望という名の電車」の後半30分を観てしまった。仕事をさぼって本を読んだり、じゅうぶんな睡眠をとるべきなのにTVの映画を観てしまう。たぶん、大人のすることではないが、子どもの楽しみでもない。この瘡蓋(かさぶた)を剥がすに似た痛みとスリルは。
まず、「Sexy Beat」。ひどいタイトル。安い予算。検索しても公式ホームページなどは出てこない。さすがに、IMDB(インターネットムービーデータベース)には紹介があった。2人がプロット(あらすじ)を書いていた。
映画紹介のブログなどであらすじを書いているのを見かけ、ときどき思うのだが、書く人はおもしろいのだろうか。まだ観てない人は読みたくないし、すでに観た人は読む気になれないはずだから、たぶん書いている人だけがおもしろいのだろう。他人の楽しみにケチをつけるつもりはない。ただ、同じ書くなら自分だけのあらすじを書いた方がずっとおもしろいのにと思う。雑誌や新聞の映画欄が載せるような最大公約数のあらすじではなく、自分にとってのあらすじが、映画を観たならきっとあるだろうと思う。
たとえば、「欲望という名の電車」は、俺にとってはブランチとスタンリーが惹かれ合う物語以上に、ステラの映画だ。ラストシーンのステラは夫スタンリーとの別れを決意して幼子を抱きしめる。その姿に重なるように、「ステラーッ」と叫び呼ぶスタンリーの声は物苦しい。ステラはなぜスタンリーと別れる決心をしたのか。姉を犯して狂わせたスタンリーに怒ったのではなく、姉とはいえ他の女に心を移したのが許せなかったのでもなく、ブランチの出現によってスタンリーが自らを失いあがくのを見せられ、妻である自分や子どもが眼中にないことを思い知らされたから、スタンリーを捨てるのだ。スタンリーが、家族や生活の内にではなく、その外に夢を見る姉と同じ退嬰的な人間と見破ったわけだ。
「ステラ、生き続けるのよ」とかけられた言葉は、もちろん、第一義的には、「スタンリーのような下劣な男でも、暮らしていくには必要よ。我慢しなさい」という意味だが、「ステラ、現実を生きるのよ」という、より高次な意味が重ねられている。それは同時に、「ブランチのように現実を避けてはいけない」という戒めであり、現実にどう対処するかという選択をうながしている。だから、ステラは、「2度と私に触れないで」とスタンリーを拒否し、「今度こそ別れる決心がついたわ」と貧しい家の前に立ち、周囲を見回すのだ。これが見納めのように。
「ステラーッ」と叫ぶスタンリーの声が重なる。ステラと観客はそこでもうひとつの現実をはっきりと知る。気の狂いかけた姉の世話をし、生活苦に苛立つ粗暴な夫をなだめすかして、すべてを与えて家庭を支えてきたのは誰かを。誰の力によるものかを知る。現実に打ちのめされながらも、現実を変える力を持つ者の名を胸に刻むのだ。ここで、「ブランチとスタンリー」という悲恋映画から、「ステラの選択」という自立の映画となる(後半30分だけ観たせいで、よけいにそう思えたかもしれないが)。エリア・カザンらしい教科書みたいに左翼的な映画だ。
(敬称略)
















