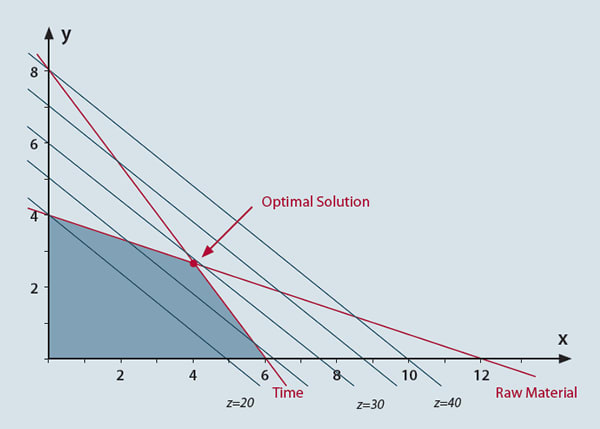でかいキング・サーモンの真っ黒な口から
ニシンのアタマがいくつも吐き出される。その
アタマははすかいにすっぱりと切られている
舌を巻く職人芸だ。本物の鮭釣り漁師と、
その鋭く滑らかな餌細工ナイフとの。
アタマを切られたニシンの本体の方は眩しい銀色の擬餌鉤の
十八インチ後ろにセットされる。アタマはぎゅっと
横に向けられて、斑になった水の中で沈み
回転するようになっている。やがて、それらの
アタマは我々の船にもう一度現れる。あろうことか、今度はぽっくり開いた
鮭の口からぐちやぐちゃになって吐き出されるのだ! それは後味の悪い
おとぎ話の歪んだ塊り。その話の中ではどのような祈りも叶えられず、
どのような協定も結ばれず、どのような約束も守られない。
我々はアタマを九つ数えた。まるで数えることじたいがすでに、後日
それを語ることであるかのように。それらを海に、それらがもともといた
場所に、投げ捨てるときに「ジーザス」と君は言う、「ジーザス」
僕はモーターを始動させた。そしてもう一度我々は、ニシンを取り付けた針を
水に投げ入れる。それまで君はプリンス・オブ・ウェールズ島でモルモン教徒の
ために伐採の仕事をしたときのことを話していた(酒もダメ、
汚い言葉もダメ、女もダメ。一切ダメ、そこには仕事と
給料があるだけ)。それから君はふと黙り込み、ナイフをズボンで
拭いて、カナダの方を、そしてもっと先の方をじっと見やる。
その朝ずっと君は何かを僕に語りたがっていた。そして君は喋り
はじめる。どれくらい
君の奥さんが君と別れたがっているか、君に「去って」もらいたがって
いるか、なにしろ君が消えてしまえばそれでいいのだ。
どこかに消えて、そのまま戻ってこないでよ、と
彼女は言った。「さっさと出ていってよってさ。あいつはきっと俺が帆桁に
ぶっつけられて死ねばいいと思ってる」ちょうどそのときにどすんという衝撃。
水面が泡立ち、糸がたぐり出される。それはどんどんたぐり
出されていく。
レイモンド・カーヴァー“ Out ”
村上春樹 訳 『出て行く』
ところで、キングサーモン(マスノスケ)の独特の紅色はアスタキサンチンに由来。この
アスタキサンチン、自然界が生み出す代表的な色素の1つカロテノイドの一種で、キサン
トフィル類の仲間です。ヘマトコッカスなどの藻類に含まれるアスタキサンチンは、食物
連鎖によりオキアミやサクラエビやサケの体に蓄えられ、イクラや筋子を美しく彩ってい
る。β-カロチンなどと同じカロテノイドの仲間で、サケ・エビ・カニや海藻などの魚介
類に多く含まれる赤い色素だが、その抗酸化力はビタミンEの千倍と「史上最強のカルテ
ノイド」。つまり、血中脂質の活性酸素を抑え、血管を若々しく保ったり、免疫細胞を活
性酸素から守ることで免疫力を高めるとか。またアスタキサンチン自体がガンの増殖を抑
制することも知られ、脳関門を通過することができるため、目の病変の予防と治療に効果
があるとされる。このように抗酸化物質としてのカルテノイドは、生物が活性酸素から自
分を守るために身につけたと考えられていて、トコトリエノール・ビタミンC・ビタミン
Eなどは細胞膜が酸化されるのを防いでくれる。さらにウコン(クルクミン)・ローズマ
リー・セレンなどにも抗酸化作用があり、これらの水溶性・脂溶性の抗酸化物質を上手に
組み合わせることでその効果が相乗的に高まり、持続性も向上するといわれている(活性
酸素の中でも特に毒性の強い「一重項酸素」の酸化反応と、体の組織を連鎖的に障害して
いく「過酸化脂質」の生成を抑制する力が強いことがわかっている)。
さて、サケの母川回帰の原理は「座標説」が有力になりつつあるが、長い旅路の果てに元
の生誕地にたどり着くためのパワーとその源に思いを馳せるときこの、赤い色素、アスタ
キサンチンの果たす機能が大きいのではと想像し今後の研究に期待した次第。
※近年アスタキサンチンがビタミンE(α-トコフェロール)の100~1,000倍、
β-カロテンの約40倍もの強力な抗酸化作用を有することが見いだされ、従来単なる色
素として扱われていた時代から、現在アスタキサンチンは健康食品として業界から期待さ
れるまでに至っている。アスタキサンチンの有するその他の機能特性として、抗炎症作用、
抗動脈硬化作用、糖尿病に対する作用、光障害に対する網膜保護作用、日周リズム調節作
用、免疫賦活作用、抗ストレス作用、筋肉持続力向上作用、精子の質向上作用や膀胱がん
誘発抑制等数多くの報告がなされている。また、皮膚に対する作用としては、色素沈着抑
制、メラニン生成抑制および光加齢抑制の効果が報告されている。
【デジタル革命渦中の経済学】
京都大の山中伸弥教授がノーベル医学・生理学賞を受賞し、19人目の日本人受賞者とな
ったが、経済学賞の受賞者はまだいない。世界第3位の経済大国としては意外に思えるが、
経済学者からは「日本では政府が経済学のアイデアを採用しようとせず、研究者が生きた
経済を直接相手にする機会が少ない」という不満の声がある。長期の経済低迷が続くなか、
政府は優れた“日の丸経済学者”の研究成果を取り込む余地がありそうだ。「日本は経済
学を現実の政策に活用する姿勢に欠ける。それが根本問題だ」。
日本人の受賞者が出ない理由について、東京大大学院経済学研究科の松島斉教授は、経済
学賞受賞者を多数輩出している欧米では、優秀な経済学者を政権に迎えることも珍しくな
いと指摘する。クリントン政権で大統領経済諮問委員会(CEA)の委員長を務めたジョ
セフ・スティグリッツ・コロンビア大教授や、レーガン政権でCEA委員を務めたポール・
クルーグマン・プリンストン大教授などが代表格で、両氏とも経済学賞を受賞している。
松島教授は「自分の理論を実際に経済政策にあてはめることで、生きたデータが入り、さ
らに研究内容が高まる。日本の経済学がレベルアップするのに必要なのは、研究費増額な
どの支援ではなく、こういう根本的な姿勢だ」と強調する。また、日本語による論文がネ
ックになっているとの見方もある。ノーベル賞では、論文の引用量の多さが選考に大きく
影響するが、日本語で論文を発表すれば海外の研究者の引用は望めない。日本経済学会は
1995年、英文で出版された学術論文などで国際的な業績を挙げた45歳未満の若手経済学
者を表彰する「中原賞」を創設。海外の大学で研究する経済学者など、若手の発掘に寄与
している。さらに、世界経済が直面している不況の原因や金融財政政策に関しては、日本
人による研究の方が、欧米諸国より進展している事例もあるという。英国在住のある経済
学者は「今後このような研究が認められ、経済学賞を受賞する日本人研究者も出てくるの
では」とみている。米情報会社のトムソン・ロイターは12年のノーベル経済学賞の有力
候補の一人に、米プリンストン大の清滝信宏教授を挙げており、近い将来の日本人受賞の
可能性もありそうだという。そんなことも含め、積極的にチャレンジする甲斐もあるとい
うものだろう。さて、問題はその時間をどう捻出するかだが、ところが眼精疲労はマック
スだ!