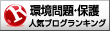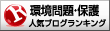戸惑い。本書を読み始めた最初の感覚は正直いって「戸惑い」でした。経済学について全く知らない方、あるいは経済学に十分疑問を感じている方でも、ひょっとしたら僕と同様に戸惑われた方がいらっしゃるかもしれません。
なぜ戸惑ったのか。それは、なぜ保護貿易が状況によって経済厚生の増大に資するのか直感的に理解し難かったからです。
一般に通説とは分かりやすく、直感的に受入れやすくできています(だからこそ通説となりうるのですが)。本書で取り上げられている貿易の例で言えば、仮に経済学を学んだことがない人でも高等学校の世界史では世界恐慌の後に列強が保護主義傾向を強め、ブロック経済を形成したことが世界大戦の引き金の一つとなったというように習いますし、自由貿易は「自由」という言葉から「望ましいもの」と想起されるために、「自由貿易に則った方が最適な資源配分を実現でき、経済厚生を最大化する」と言われれば直感的に納得してしまいがちです。
分かりやすく、すんなり頭に入ってくることを人は「正しい」と認識してしまう傾向にあります。しかし、現実を仔細に検討すると「分かりやすい」ことが必ずしも「正しい」とは限らないということに気づきます。これは当ブログの「
崩壊する世界、繁栄する日本」でも述べたことですが、例えば「赤字国債の増大は、将来世代に借金のツケを回すことになる」というステレオタイプは「赤字=マイナス」、「国債=借金」といったイメージと結びつきやすいためか、赤字国債の増大=マイナスの増大であり、「今は良くてもそのツケは将来世代が負担することになりますよ」と言われれば何となく「そうかな」と納得してしまいがちです。しかし、現実を冷静に見てみると、過去に起こった「借金のツケ」が現世代の過剰な負担となっている様子はありませんし(税や社会保障費などの国民負担率は今もって先進国の中で最も低いレベルにあります)、リーマンショック以降、実際に国家が破綻したアイスランドのようなケースが次々と登場しているような未曾有の状況でも、「先進国屈指の借金大国」であるはずの日本が破綻する気配はありません。国債の金利も低い水準のままです。
一方で保護貿易は「保護=閉鎖的=自己中心的」というイメージと結びつきやすく、また保護主義が先の大戦の遠因となったという認識が一般に浸透しているためか、疑うことなくマイナスイメージとして受け取られています。言葉が認識に与える影響は意外と大きいのです。
さて感覚的な話が長くなってしまいましたが、そろそろ本題に入りたいと思います。
本書は『自由貿易の罠、覚醒する保護主義』のタイトルの通り、近代社会で一貫して支配的だった自由貿易主義の限界と、現在のような混乱した経済状況下においては保護主義も積極的に評価しうることを述べています。しかし、より重要なことは、ここ20年の経済政策において支配的だった合理主義的アプローチからプラグマティック(実際的)なアプローチへと意思決定の態度を変換しなければ、現在起きている危機に対応することは難しいということを指摘している点にあると思います。
主流派経済学に見られる合理主義とは、簡単に言えば経済主体が完全情報の下で合理的選択をするものと仮定した場合、市場の価格調整メカニズムによって市場均衡(最適な資源配分=経済厚生の最大化)を達成しうるという、理論的に導き出された理想形があり、その理想形に実際社会そのものを当てはめていこうというものです。勿論、現実には市場メカニズムが機能しない「市場の失敗」が起こりうることも認識されてはいますが、それらは理想形に到達する過程における逸脱、あるいは理想形を実現するために許容されるべき一時的犠牲として扱われており、「市場メカニズムこそが最適な資源配分(経済厚生)を実現する」という原則はあくまで変わりません。
しかし、そもそも「市場が最適資源配分を実現する」という結論は、経済主体の「完全情報に基づく合理的選択」という、およそ現実社会ではあり得ない仮定の下で導き出されたものです。あり得ない仮定に基づくのであれば、導き出された結論も「ある一定条件における傾向」を示すものにはなるにせよ、そのまま現実社会に当てはめられるものでないことは、かえって経済学について全く知らないという人の方が理解できると思うのですが、実際にこの20年わが国を支配してきた論調は「日本経営異質論」、「50年体制」、「規制緩和」、「痛みを伴う構造改革」と色々名前を変えてはいるものの、基本的には市場原理こそ普遍の真理とみなすものだったのです。
さらに、そもそも経済学が理想とする市場均衡はあくまで経済厚生を最大化(資源配分の最適効率)すると言っているのに過ぎないのであって、必ずしもそれは社会厚生を高めることと同義ではありません。この点はしばしば混同されていますが、現実には市場は社会厚生の観点から望ましくない結果を生み出すことが度々あります。例えば環境破壊などがそうですが、これを「市場の失敗」と呼んでいます。
20年もの長きに渡り、市場原理を普遍と見なし現実社会に適用しつづけた結果、「雇用問題」、「格差問題」、「治安問題」など文字通り「市場の失敗」が表面化したことは最早誰の目にも明らかであるように思えます。それにもかかわらず、未だに市場原理の普遍性を疑うどころか、「失敗したのは市場化への改革が不徹底だったからだ」と主張する風潮が見られます。まるで市場原理主義のほか思考の縁を失ってしまったかのようです。ここまでドグマチック(教条的)になりますと経済学は科学というより一種の宗教であると言えるでしょう。
しかしながら本書は、市場の果たす役割そのものを否定されるべきものとして扱い、保護主義こそが善であると述べているのではありません。そのような態度こそ本書で否定されているドグマティズムです。そうではなく、ある条件下で導き出された理論は、現実社会の一側面における傾向を示すのに過ぎないのであって普遍的真理などではないこと、またそうしたドグマに陥らないためにはプラグマティックな思考態度が必要であると述べているに過ぎないのです。
プラグマティックな思考態度とは、人は誤りを犯すものであるという限界を踏まえたうえで、現実社会の問題を認識し、それを解決するためにはどうしたらよいかという仮説を立て、そしてそれを実行し、結果が良いものであろうとなかろうと、結果から得られた経験を次の仮説のためにフィードバックするというものです。これは何も目新しいものではなく、民間企業で広く受け入れられているマネジメントシステム、「PDCAサイクル」そのものです。
そしてそのサイクルを回すためには、産業政策について述べている本書の例では政府と民間、企業組織内で言えば経営者と社員、企業と利害関係者といった複数人によるコミュニケーションが欠かせないと言います。そしてコミュニケーションの結果、ある一定の合意を得るには彼らの間に近似的な価値観や利害がなければなりません。それを構成するのが企業であれば企業理念や企業文化ということになるでしょうし、民主主義社会においては家族、地域社会、国家などになるでしょう。
そういった意味で、本書の主題である「産業政策のプラグマティズム」の根底も著者のこれまでの著作、「
恐慌の黙示録」、「
経済はナショナリズムで動く」、「
国力論-経済ナショナリズムの系譜」で一貫して述べられた「経済はその本質からしてナショナリスティックな性格を帯びる」という主張へと帰結していくのです。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした
 よろしければクリックおねがいします!
よろしければクリックおねがいします!
↓