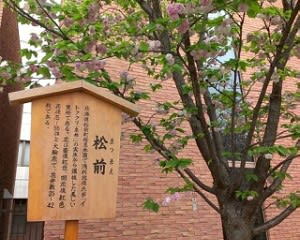○小島道裕『洛中洛外図屏風:つくられた〈京都〉を読み解く』(歴史文化ライブラリー) 吉川弘文館 2016.4

京都の名所と市街、そして人々の風俗を描いた「洛中洛外図屏風」は、室町から江戸にかけて、多くの作品が描かれた。本書の巻末には、主な洛中洛外図の一覧があって、「室町~安土桃山」の最初期に6件、「江戸初期」に28件、「江戸中期以降」に10件、参考として「洛外名所図系」に4件が挙がっている。作者や特徴、所蔵者を付記した、たいへん有用なリストである。
はじめに画中に室町幕府を描いた(模本を含む)「初期洛中洛外図屏風」(第一定型)の四本「歴博甲本」「東博模本」「上杉本」「歴博乙本」について、誰(発注者)が何を描こうとしたのかを詳しく読んでいく。これが、いちいち面白い。室町幕府というと「花の御所」をすぐに思い出すが、実際にはかなり頻繁に移動してる。「上杉本」に描かれたのは「花の御所」だが、「歴博甲本」は「柳の御所」が細川高国邸の近くにあった、きわめて短い時期の風景を描いたものと考えられている。細川邸や将軍邸には屋敷の主人らしき姿があるが、近衛邸は母屋の戸を開け放って、従者の姿だけが描かれている。著者はこれを「留守表現」と呼び、屋敷の主人は画面の別のところに描かれていますよ、というサインと考える。そして、将軍邸前の直垂・風折烏帽子で顔の白い二人連れを、近衛家の父子に比定する。なんと、楽しくて鮮やかな推理!
「上杉本」には華麗な花の御所(今出川御所)が大きく描かれているが、屏風の制作時期や伝来についての研究が進んだ結果、これは上杉謙信が、当時、実際には存在しなかった花の御所に足利義輝を訪ねる架空の情景という、黒田日出男氏が提案した解釈が支持されている(あ、黒田先生の『謎解き洛中洛外図』は読んでいないんだった!)。なお、当時、実際に幕府があった斯波邸(二条御所)には、赤毛氈覆いの馬が二頭描かれていて、権威を表しているという。ちなみに花の御所も斯波邸も粉本に基づく描写で、実態に即していないというのも面白い。
さらに著者は、描かれた都市風俗にも細やかな目を向ける。「歴博甲本」には床屋が描かれているが、元来、剃刀は用いず(剃るのは出家のときだけ)、月代の手入れには毛抜きが使われたというのは初めて知った。同本には、地理的に狩野図子と見られるあたりに狩野屋敷が描かれており、扇に絵付けする絵師(元信か)の姿も描かれている(
跡地を訪ねたことあり)。「歴博乙本」では商いの看板が目立っており、実際の京都が、中世都市から近世都市に変化する様子を反映していると考えられる。近世には、都市風俗への関心を中心テーマとする特異な屏風「舟木本」が描かれた。この屏風は、店舗や看板、遊里、芸能、喧嘩など、どの場面を切り取っても面白い。
また「洛中洛外図屏風」が四季絵(月次屏風)の様式を持っているというのも、あまり考えたことがない視点だった。だから祭礼などの年中行事が画中に描かれるのか。中には、四季の行事がぐるりと一周するように配置されたものもある。「上杉本」は、上京の町屋の部分で、歳末から正月にかけての光景を全面展開しているという。
寛永三年(1626)後水尾天皇の二条城行幸は、その後ずっと「洛中洛外図屏風」の定番風景となった。つまり、これ以降「洛中洛外図屏風」はアップデートをやめてしまい、「美しい京都」の絵として量産され、消費されるようになる。実は江戸の風俗(一人立ち獅子舞)が紛れ込んでいたり、有職故実研究の結果、あるべき古代の姿に戻す試みが行われたり、この時代の作品もなかなかに面白い。
とにかく「絵画を読む」ことが好きな人間には、息つくひまのないほど面白い本だった。著者は国立歴史民俗博物館(れきはく)の先生で、かつて歴博で、洛中洛外図屏風(甲本)の複製品を使って、左隻と右隻が向き合わせになるように展示した(実際の京都の地理と合致する)ことについて書いている。本書の図版は、2012年の『都市を描く』展の会場風景のようだが、私はもっと古く、2007年の『
西のみやこ、東のみやこ』展でも同様の展示を体験したような記憶がある、私は、このとき初めて「洛中洛外図屏風」の見方を理解したのである。
また、著者は、2015年の京都文化博物館の特別展『
京(みやこ)を描く』にも関わられたとのこと。あれも記憶に残る、たいへん面白い展覧会だった。絵画史料の読み方は、私が学生だった頃に比べると、格段に精緻になり、かつ最新の研究成果を一般市民も享受できるのは、本当にありがたいことだと思う。