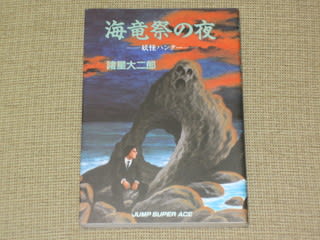諸星大二郎 1988年 創美社発行
古事記のはなしで、つい諸星大二郎を思い起こしてしまったんで、そのついでに、やっぱ稗田礼二郎にいっときますか。
この単行本が出たのは、1988年なんだけど、そのちょっと前ごろから「暗黒神話」とか「孔子暗黒伝」とかが、こういうA5版で出てたんで、これも「妖怪ハンター」をただ版を替えただけかと思って、オリジナルを持ってる私としては、長く買わないでおいちゃってた。
そしたら、全然知らなかった、新しい稗田礼二郎シリーズも入ってんだもんなー、早く言ってよって感じ。
もともとの「妖怪ハンター」(1978年)は、5話。
「黒い探究者」「赤いくちびる」「生命の木」「闇の中の仮面の顔」「死人帰り」。
これは雑誌掲載された発表順でいくと、
「黒い探究者」1974年ジャンプ37号
「赤いくちびる」1974年ジャンプ38号
「死人帰り」1974年ジャンプ39~41号 (※以上5週で連載オワリ…)
「生命の木」1976年ジャンプ8月20日増刊号
「闇の中の仮面の顔」1978年単行本発行の際に書き下ろし。
で、今回とりあげてる「海竜祭の夜」のコンテンツは、
「海竜祭の夜」(1982年ヤングジャンプ9号)
「ヒトニグサ」(1982年ヤングジャンプ39号)
「黒い探究者」(上掲)
「赤い唇」(上掲)
「生命の木」(上掲)
「幻の木」(1987年ヤングジャンプグレート青春号Vol6)
「花咲爺論序説」(1985年ヤングジャンプ39号)
「闇の中の仮面の顔」(上掲)
「肉色の誕生」(1974年これは「アダムの肋骨」にも収録されてて、稗田礼二郎ものとは違う)
ちなみに“妖怪ハンター”って名称は、最初のジャンプ連載のときに編集者がつけたもので、著者は気にいっていない。
なので、「海竜祭の夜」~「闇の中の仮面の顔」については、“稗田礼二郎のフィールド・ノートより”ってくくりにしてる。
扉絵のとこにはサブタイトルとして“(あるいは妖怪ハンターと呼ばれた男の手記)”って申し訳程度に入ってるけど。
で、80年代に入って描かれた稗田礼二郎ものである「海竜祭の夜」は、平家物語が扱われてる。
おなじく「ヒトニグサ」は、おなじみの江戸時代の学者・室井恭蘭の「妖魅本草録」(探しても無いぞ、そんな本w)と、水引村の口承伝説から始まってる。
で、「黒い探究者」は、稗田礼二郎の最初のものだけど、ここで古事記には神話以上の事実があるという認識をもっていた稗田が、事件に巻き込まれ、「アメツチハジメ ヒラケシトキ タカマノハラニ ナレルカミノ ナハ アメノミナカヌシノミコト…」で始まる、古事記の神代記を呪文として唱え、比留子古墳の禁断の扉を開けるっつーもんだ。
人間の歴史からは封じ込められちゃってるけど、この世には「えたいのしれないもの」がいるかもしれない、ってのは妖怪ハンターの基本。
それが神話とか伝説のたぐいで残されているんで、その謎を解き明かしてく、よくできたウソ。(著者いわく「うまく嘘をついてナンボの商売ですから」)
「花咲爺論序説」は、文字どおり花咲爺がベース。
灰をまいて枯れ木に花を咲かすのは、山林を焼いた灰による生命力の復活という、焼畑農耕民の伝承であり、縄文中期からすでに伝えられてたってのが、稗田の説。
「幻の木」は、瓜子姫とアマノジャクの話。
で、このふたつは、世界中で神話や伝説となっている、神々と地上をつなげる存在である世界の中心にある巨木や、人類の進化と生命の源である「生命の木」を追い求める話につながってくんだけど、それはまたべつの機会に。
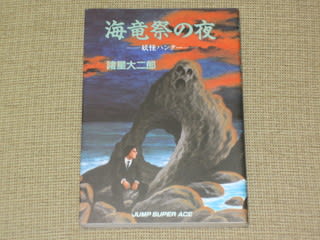
古事記のはなしで、つい諸星大二郎を思い起こしてしまったんで、そのついでに、やっぱ稗田礼二郎にいっときますか。
この単行本が出たのは、1988年なんだけど、そのちょっと前ごろから「暗黒神話」とか「孔子暗黒伝」とかが、こういうA5版で出てたんで、これも「妖怪ハンター」をただ版を替えただけかと思って、オリジナルを持ってる私としては、長く買わないでおいちゃってた。
そしたら、全然知らなかった、新しい稗田礼二郎シリーズも入ってんだもんなー、早く言ってよって感じ。
もともとの「妖怪ハンター」(1978年)は、5話。
「黒い探究者」「赤いくちびる」「生命の木」「闇の中の仮面の顔」「死人帰り」。
これは雑誌掲載された発表順でいくと、
「黒い探究者」1974年ジャンプ37号
「赤いくちびる」1974年ジャンプ38号
「死人帰り」1974年ジャンプ39~41号 (※以上5週で連載オワリ…)
「生命の木」1976年ジャンプ8月20日増刊号
「闇の中の仮面の顔」1978年単行本発行の際に書き下ろし。
で、今回とりあげてる「海竜祭の夜」のコンテンツは、
「海竜祭の夜」(1982年ヤングジャンプ9号)
「ヒトニグサ」(1982年ヤングジャンプ39号)
「黒い探究者」(上掲)
「赤い唇」(上掲)
「生命の木」(上掲)
「幻の木」(1987年ヤングジャンプグレート青春号Vol6)
「花咲爺論序説」(1985年ヤングジャンプ39号)
「闇の中の仮面の顔」(上掲)
「肉色の誕生」(1974年これは「アダムの肋骨」にも収録されてて、稗田礼二郎ものとは違う)
ちなみに“妖怪ハンター”って名称は、最初のジャンプ連載のときに編集者がつけたもので、著者は気にいっていない。
なので、「海竜祭の夜」~「闇の中の仮面の顔」については、“稗田礼二郎のフィールド・ノートより”ってくくりにしてる。
扉絵のとこにはサブタイトルとして“(あるいは妖怪ハンターと呼ばれた男の手記)”って申し訳程度に入ってるけど。
で、80年代に入って描かれた稗田礼二郎ものである「海竜祭の夜」は、平家物語が扱われてる。
おなじく「ヒトニグサ」は、おなじみの江戸時代の学者・室井恭蘭の「妖魅本草録」(探しても無いぞ、そんな本w)と、水引村の口承伝説から始まってる。
で、「黒い探究者」は、稗田礼二郎の最初のものだけど、ここで古事記には神話以上の事実があるという認識をもっていた稗田が、事件に巻き込まれ、「アメツチハジメ ヒラケシトキ タカマノハラニ ナレルカミノ ナハ アメノミナカヌシノミコト…」で始まる、古事記の神代記を呪文として唱え、比留子古墳の禁断の扉を開けるっつーもんだ。
人間の歴史からは封じ込められちゃってるけど、この世には「えたいのしれないもの」がいるかもしれない、ってのは妖怪ハンターの基本。
それが神話とか伝説のたぐいで残されているんで、その謎を解き明かしてく、よくできたウソ。(著者いわく「うまく嘘をついてナンボの商売ですから」)
「花咲爺論序説」は、文字どおり花咲爺がベース。
灰をまいて枯れ木に花を咲かすのは、山林を焼いた灰による生命力の復活という、焼畑農耕民の伝承であり、縄文中期からすでに伝えられてたってのが、稗田の説。
「幻の木」は、瓜子姫とアマノジャクの話。
で、このふたつは、世界中で神話や伝説となっている、神々と地上をつなげる存在である世界の中心にある巨木や、人類の進化と生命の源である「生命の木」を追い求める話につながってくんだけど、それはまたべつの機会に。