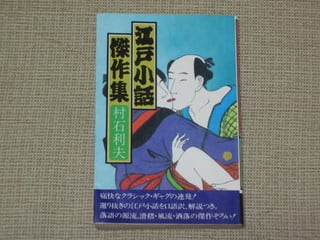村石利夫 昭和55年 大泉書店
これは、『日本風流小咄集』といっしょに去年11月に古本まつりで買ったやつ、何が読みたいというのでもなく、なんとなくシャレで。
読んでみたら、こっちのほうがバカバカしくいい話が多くて、おもしろいっつーか好感もてた。
当然のように、落語の元ネタみたいのが、あちこちにある
大きく4部構成に分かれてて、1.野暮、2.色恋、3.阿呆、4.滑稽として、そのなかではご丁寧なことに年代順に並べてある。
身元がはっきりしてるわけで、出典の刊行物の名前もそれぞれ明記されてる、なんとなく聞いた話を集めたのとは違うってことか。
野暮ってのは、ケチなやつを笑うような話が多いけど、36話でボリュームとしてはそれほどでもない。
色恋ってのは、そうはいうけどいわゆるロマンスぢゃなくて、当然シモネタ中心である、43話。
阿呆は、江戸的ナンセンスというか、かなりバカバカしいやつで、大ボケかましたりホラ吹くのがいい、31話。
滑稽がいちばん多くて134話、もちろんそれぞれオチがついてんだけど、シャレがきいてる感じがする。
落語ネタそのものをいくつかあげると。
落語の「茶の湯」で、ご隠居特製のいい加減な菓子を投げ捨てるやつは、本書では「茶菓子」って題だけど、安永五年の常笋亭君竹撰『立春噺大集』のなかの「あてちがひ」という話だって。(p.28)
「千早振る」は、安永五年の来風山人序『鳥の町』のなかの「講釈」にそのまんまあるとか。(p.69)
「千両みかん」は、明和九年の山風作『鹿の子餅』のなかの「蜜柑」という話。(p.102)
「親子酒」のオチのとこは寛政元年の百成作『ふくら雀』のなかの「生酔」。(p.113)
「火事息子」の原型は、享和元年の作者不明の『笑の友』のなかの「恩愛」だっていうけど、現在の落語のほうが母親も出てきたりして、ちょっと人情をふくらませてあるようだ。(p.207)
ちなみに、「あくび指南」と構造は同じだけど、教えることがちがうので、享和二年の桜川慈悲成作『一口饅頭』のなかの「小言しなん所」なんてのもある。(p.215)
その他、まくら、小話含めると、なんだ21世紀になってもあいかわらずよく聞く話ってのは江戸時代にできてたんだ、って感心する。
どうでもいいけど、ひとつ「上戸と下戸」って話があって(p.174)、上戸が下戸のことをいじると、
>下戸「いやなことをいうやつだ。そういうおぬしはどうなんだ」
>上戸「おれか、おれは蔵とはいかないが、店をあちこちに出した」
>下戸「店か、して、どんな店だ」
>上戸「しれたことよ、小間物屋だ」
ってのでオチになってんだけど、酔っ払いがヘドを吐くことを「小間物屋を開く」とか「小間物店を並べる」とかっていうんだって解説を読まないと、わかんなかった。
言うんだ、そんなこと? 酔っ払い歴は長いけど、聞いたことなかった。
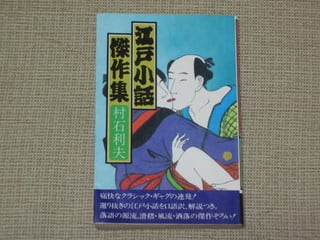
これは、『日本風流小咄集』といっしょに去年11月に古本まつりで買ったやつ、何が読みたいというのでもなく、なんとなくシャレで。
読んでみたら、こっちのほうがバカバカしくいい話が多くて、おもしろいっつーか好感もてた。
当然のように、落語の元ネタみたいのが、あちこちにある
大きく4部構成に分かれてて、1.野暮、2.色恋、3.阿呆、4.滑稽として、そのなかではご丁寧なことに年代順に並べてある。
身元がはっきりしてるわけで、出典の刊行物の名前もそれぞれ明記されてる、なんとなく聞いた話を集めたのとは違うってことか。
野暮ってのは、ケチなやつを笑うような話が多いけど、36話でボリュームとしてはそれほどでもない。
色恋ってのは、そうはいうけどいわゆるロマンスぢゃなくて、当然シモネタ中心である、43話。
阿呆は、江戸的ナンセンスというか、かなりバカバカしいやつで、大ボケかましたりホラ吹くのがいい、31話。
滑稽がいちばん多くて134話、もちろんそれぞれオチがついてんだけど、シャレがきいてる感じがする。
落語ネタそのものをいくつかあげると。
落語の「茶の湯」で、ご隠居特製のいい加減な菓子を投げ捨てるやつは、本書では「茶菓子」って題だけど、安永五年の常笋亭君竹撰『立春噺大集』のなかの「あてちがひ」という話だって。(p.28)
「千早振る」は、安永五年の来風山人序『鳥の町』のなかの「講釈」にそのまんまあるとか。(p.69)
「千両みかん」は、明和九年の山風作『鹿の子餅』のなかの「蜜柑」という話。(p.102)
「親子酒」のオチのとこは寛政元年の百成作『ふくら雀』のなかの「生酔」。(p.113)
「火事息子」の原型は、享和元年の作者不明の『笑の友』のなかの「恩愛」だっていうけど、現在の落語のほうが母親も出てきたりして、ちょっと人情をふくらませてあるようだ。(p.207)
ちなみに、「あくび指南」と構造は同じだけど、教えることがちがうので、享和二年の桜川慈悲成作『一口饅頭』のなかの「小言しなん所」なんてのもある。(p.215)
その他、まくら、小話含めると、なんだ21世紀になってもあいかわらずよく聞く話ってのは江戸時代にできてたんだ、って感心する。
どうでもいいけど、ひとつ「上戸と下戸」って話があって(p.174)、上戸が下戸のことをいじると、
>下戸「いやなことをいうやつだ。そういうおぬしはどうなんだ」
>上戸「おれか、おれは蔵とはいかないが、店をあちこちに出した」
>下戸「店か、して、どんな店だ」
>上戸「しれたことよ、小間物屋だ」
ってのでオチになってんだけど、酔っ払いがヘドを吐くことを「小間物屋を開く」とか「小間物店を並べる」とかっていうんだって解説を読まないと、わかんなかった。
言うんだ、そんなこと? 酔っ払い歴は長いけど、聞いたことなかった。