クレイグ・ライス/小泉喜美子訳 一九七七年 ハヤカワ・ミステリ文庫版
というわけで、前回の『大はずれ殺人事件』のつづき、原題「THE RIGHT MURDER」は1941年の作品。
最初、なんでもいいからライスをもう一冊と思ってたときに、この本を見つけたんだけど、大はずれと大あたりは二冊セットでその順番で読むべしということらしいので、二冊そろって買える機会を待って古本を手に入れた。
で、すぐ続けて読むこととした、前作でシカゴ社交界の女王モーナ・マクレーンとの賭けに勝つことができなかったジェークとヘレンがどんなことをするのか期待して。
物語は前作のすぐあと、あれがクリスマスころの出来事だったんだけど、本作はその年の大晦日、弁護士のマローンが「天使のジョーのシティ・ホール・バー」でひとりジンを呑んでいるところから始まる。
ひとりで呑んでいると言っても、楽しくとか渋くとかぢゃなく、泣いてがぶ飲みしてるのは、ジェークとヘレンがバーミュダへ新婚旅行へ行ってしまって淋しいからだそうで。
そこへ、年が変わろうかというときのちょっと前に、見知らぬ男が入ってきて、彼の名前を呼んで手を握って、そして倒れた。
マローンに何かの鍵を手渡したまま死んでしまったその男は、あばらにナイフを刺されたまま、そこまでたどりついたのだった。
というわけで巻き込まれてしまったマローンは、警察にしょっぴかれて尋問されるが誰だか知らないとしか答えようがない、ただし鍵を受け取ったがそれを失くしてしまったとか余計なことは言わない、なんだかんだいって事件は自分で解決する探偵タイプの弁護士。
そこへジェークから金を送れという電報がくる、なんだろうと思っていると、ヘレンがやってきて彼とは別れたなんていう。
ジェークに金を送ろうとしたが、手元に全然カネがなくて事務所の家賃の支払いもままならないマローンが、カネ借りるつてをさぐるとこはおもしろい。
>彼は受話器をとり上げ、きっちり十四人の番号を次々と呼び出した。初めの十三回のうち、五人は市内にいず、二人は刑務所に入っており、六人は文なし、一人は電話をとり外されていた。(p.36)
という調子、なんかこういうテイストが、なんとなくデイモン・ラニアンのブロードウェイシリーズを思い出させる。
街で酒飲んでるとこの雰囲気なんかも似てるような気がする、時代背景だいたい同じようなもんだからだろうか、大戦時中のアメリカ、っていうか何となく禁酒法の反動のようなもののある時代というか。
で、ヘレンはジェークと別れたという口実でモーナ邸の客になる、狙ってるのはモーナの殺人のしっぽをつかんで賭けに勝つこと。
戻ってきたジェークももちろん前作に引き続いて、こんどこそモーナとの賭けに勝つ、ナイトクラブを手に入れる、それでヘレンの鼻を明かすとファイトを燃やす。
二人の友人であるマローンは、二人がいま鉢合わすとまた喧嘩するだけで、ほとぼり冷めれば仲直りするだろうから、なんとか二人が顔を合わせないようにとウソついたりしてあっちこっち別のとこ行かせるようにする。
そして、マローンがモーナ邸に招かれた日に、そこで新たな殺人が起きる。
モーナ邸の客人は、先代の不動産での財産を引き継ぐ東洋で長年過ごした男と夫人、その親類でカメラマン志望の若者、酔っ払ってばかりの青年などだが、被害者のことは誰も詳しくない。
被害者はまたもやマローンに用があったらしいことから行きがかり上しかたないマローンと、意外な場所で劇的再会をしたジェークとヘレンが真相解明に向かうことになる。
マローンは職業的正義感のようなものに突き動かされているが(だってカネにはなんない仕事だし)、ジェークとヘレンのお目当ては賭けに勝つことにしかない。
どちらかというと、結婚したばかりなのにキミとふたりでいる時間がないよとかこぼすジェークにくらべると、ヘレンのほうがドライである。
どうでもいいけど、このシリーズは、誰かが状況に不満があったりすると、「不必要なほどの悪態を並べたてた」とか「意地悪い口調で悪態をついたあげく」とか「小声で何か悪態をついたが」とか「いまいましげに悪態をついて」とか「とか何とか口汚いことを呟いて」なんて表現がでてくる。
実際に汚い言葉を並べないで、シレっと地の文で書くとこが妙におもしろくて、登場人物のセリフなんかより印象に残ってしまう。
ときには、鼻を鳴らすってのはしょっちゅうだけど、「軽蔑するような音を歯で鳴らして見せた」とか「唇と舌とで、失敬な、変な音をたてた」とか言語になってないこともある。
本作でおもしろいのは、「アルファベットのAからZに至るありとあらゆるさまざまな言葉を使って罵倒した(p.20)」ってやつ、さすが弁護士であるマローン。
クレイグ・ライス/小泉喜美子訳 一九七七年 ハヤカワ・ミステリ文庫版
先日おそまきながら『素晴らしき犯罪』でクレイグ・ライスを初めて読んだんだが。
どうせ一冊では済まないだろうと思って、同じ時期に買っといたのが、これ。
原題「THE WRONG MURDER」、1940年の作品。
主な登場人物は、こないだ読んだのと同じで、ジェークとヘレンの夫婦と弁護士のマローン。
時系列的には『素晴らしき犯罪』よりこっちのほうが前で、ジェークとヘレンが結婚したばっかりのところ。
(その前の出会ったところからの物語もあるらしいが、そこまでさかのぼって読むとは思わない、いまんとこ。)
舞台はシカゴ、クリスマス直前週に、世界でもっとも混雑している街角といわれてるステートとマディスンの交差点で、大群衆の真っただ中で一人の小男が背中から銃で撃たれて死んでるのがみつかるところから第一章は始まる。
第二章は、その前日のパーティの話、ジェークとヘレンの結婚当日のことになる、そこにシカゴ社交界のいちばんの注目人物モーナ・マクレーンが現れる。
結婚と離婚を華やかに繰り返しつつ、大西洋横断の単独飛行をしたこともあり、ベストセラーを一冊書いたこともある彼女は、やおら殺人を試してみるつもりだと物騒なことを言いだす。
「私が殺人をします、そして、あなたがそのしっぽをつかむの。あなたにはつかめないと私は賭けますわ」と言って、ジェークと賭けをする、シカゴ中のカネの半分近くを持っているといわれる彼女が賭けるのはシカゴの最高のナイトクラブ「カジノ」。
億万長者の跡とり娘を花嫁にしたのに、元新聞記者のジェークはただいま無職なので、その賭けにのる、大いに乗り気になる。
「私の殺人は、白昼、公共の道路上で、手に入る限りのいちばんありきたりの武器によっておこないます。目撃者もたくさんいることにしてもよろしいですわ」しかも「殺されても誰も嘆かず、私が個人的に動機を持っているある人間」とまでモーナはいう。
ぢゃあ第一章の雑踏のなかでの殺人は、これのことかいって思わざるをえない、そういう読み方をしてくことになる。
私なんかは読む順番まちがえて、ジェークが「カジノ」を手に入れること知っちゃってるんで、犯人決まってるし結末わかってるしどうすんのよって気持ちで読んでくんだが、そう単純なものでもなかった。
ただの謎解き、犯人あてクイズぢゃないからねえ、この物語は。どっちかっていうと、ジェークとヘレンとマローンがどたばたするコメディっぷりが主なんぢゃないかと。
まず、その結婚当日の夜だというのに、ヘレンは父親を空港に送っていく途中で、粗暴運転でつかまって留置場にぶちこまれる。
マローンが彼女を出してつれてくるのを待ちわびるジェークは、向かいの部屋にいたテネシーから来た老婦人の招きにより、本場のコーン・リカーで酔っ払って昼まで寝てしまう。
どうでもいいけど、主要登場人物たちはよく酒を飲む、しばしば出てくるのはライ・ウイスキーってやつだが、ときどきそれをジンのチェイサーにしてたりする。
で、夜中に帰ってきて朝9時まで待ってたヘレンは父のとこへ行っちゃったりして、新婚の二人はすれちがってばかり。
犯人捜し、というかモーナのしっぽつかみに躍起になるジェークは、被害者の部屋へ忍び込んで手掛かりを探そうとするが、警察につかまって留置場行き。
そこで、弁護士のマローンをわきにおいといて、ブロンド美人のヘレンは「シカゴ全市の警官の心をとろけさせるような微笑」と「涙、そして、声をしのんだすすり泣き」の演技で、夫の釈放を簡単に勝ち取る。
留置場から出ると、すぐに地元のギャングのつかいがやってきて、ボスのとこに来てもらおうかと言い、事態は複雑になってく。
そこでも、車に乗り込んできた拳銃持った男を、ヘレンは得意の暴走運転で気絶させるという活躍ぶり、雪道を猛スピードでドリフトさせるその走りには誰も正気ぢゃあ乗ってられない。
ヘレンの行動力と奔放ぶりはすごい、マローンには「きみの思慮分別を信じるくらいなら、どこかの家を一軒、投げとばせと言われるほうがましだとぼくは思っている」と言われちゃうけど。
かくして、騒動を巻き起こしながら、賭けに勝ちたいがためにジェークとヘレンは事件を追っていき、マローンはそれに引きずられてく。
本当に大金持ちのモーナが起こした殺人なのか、だったら動機はなんなのか、彼女と被害者を結びつけるものはなにか、犯人わかってる前提で真相にせまろうとする、ちょっと変わった物語ではあるが。
登場人物の過去のグチャグチャも持ち出されたり、新たな惨劇も起きたりして、そんな簡単単純な解決で幕引きとはならない。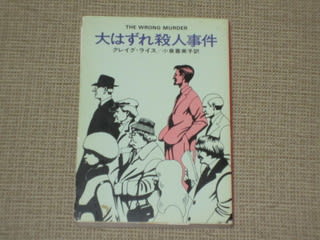
荻野目洋子 1992年 ビクター
このアルバムについては、このブログにちゃんと「荻野目ちゃん」カテゴリーで入れて並べてなかったことに気づいたので。
前に、クリスマス時期のうたでは、このアルバムのラストナンバー『思い出のクリスマス』が好きだという話を書いたんだけど。
おそろしいことに、それって2009年12月の記事だった、10年前のことだ。
なにも変わっていないなオレ、っていうか10年どころかこれの発売当時の27年前から変わってないんだけどね。
たぶん、あと10年経っても変わんない。 サヨナラ言わずに
サヨナラ言わずに 「大好きだよ」って言ったあの日 Last X'mas Eve
「大好きだよ」って言ったあの日 Last X'mas Eve
とか口ずさんでんだろうな、この季節になると、いくつになっても。
ほかに好きな曲は、『ラストダンスは私に』もいいんだけど、『She's just a rival』はやっぱ長年のフェイバリット。 恋の バランスが 私へと 傾くのよ
恋の バランスが 私へと 傾くのよ
のとこでグッとテンションがあがる、いつ聴いても。
(2020年1月21日付記)アルバム全体としては、なんていうか、曲順の並びがすごく馴染んぢゃってるものがあって、私としてはアタマっから順に聴かないとしっくりしない一枚ではある。
1.REPLICAのKISS
2.ラストダンスは私に
3.いつまでもDON'T LET ME DOWN
4.NUDIST
5.Joy Luck Club
6.SMILE FOR ME
7.おねがいPOST MAN
8.She's just a rival
9.わかってないよねCHI,CHI
10.HIT IT
11.思い出のクリスマス
ヨーゼフ・ロート作/池内紀訳 2013年 岩波文庫
これを読みたくなったのは、丸谷才一の『快楽としての読書 海外篇』のなかの、「すばらしい幸福」という章(初出は1990年「週刊朝日」)でとりあげられていたからで。
>われわれの人生には喪失といふことがあつて、これはいくら嘆いたつて仕方がないのだが、それでも充分に嘆くに価するし、また、とりわけ小説であつかふのに向いてゐる。それをじつにきれいに書いてみせたのが、ヨーゼフ・ロートといふユダヤ人作家だつた。
で始まり、
>この短篇小説はロートの最晩年の作で、死後に発表されたが、作柄といひ、完成度といひ、現代の古典とも称すべき名作だらう。
と結ばれている、そんな評を読んだら、知らないでいるのはかなり残念な気がしてきた。
そしたら白水社の「ライ麦畑~」でおなじみの大きさのを探そうとしてたのに、近年になって岩波文庫で出てるのがあると知ったので、そっちにしてみた。
古本を見つけに行ったのに、ふつうに書店で新刊を買うことになってしまった、いいんだけど。
収録作は短篇五つ。
「蜘蛛の巣」
第一次世界大戦後のドイツで、軍隊から学生になっていたテオドールがまた軍隊に戻り、いろんなスパイみたいな連中とかかわりながら、動乱を制圧したりして偉くなっていく。
ナチスドイツをモデルにしてんだろうと思ったら、解説を読んだら1923年の作品なんで、ヒトラーたちがそういう熱狂的支持を受ける前のことであり、独裁者の登場とか親衛隊的なものの跋扈とかの予言をしてたことになるってのには驚いた。
「四月、ある愛の物語」
四月のある夜に町についた「私」が、居酒屋の真向かいにある郵便局の二階の窓に姿をみせる美しい娘にホレるんだが、なかなか会いにいけない。
給仕女のアンナとか、とほうもなくノッポな鉄道助手とか、カフェの給仕でロシア革の財布をもったイグナーツとか、登場人物がちょっと風変わりな感じ。
「ファルメライヤー駅長」
オーストリア鉄道のファルメライヤー駅長は、1914年3月のある日、急行列車と貨物列車の衝突事故からヴァレヴスカ伯爵夫人を救出し、彼女に恋をする。
戦争がはじまるとファルメライヤーは軍に入り東部戦線に出撃するが、キエフ近くで伯爵夫人と再会する。
「皇帝の胸像」
旧オーストリア=ハンガリー君主国の直轄領のひとつだったロパティニー村に住むモルスティン伯爵は、皇帝を敬愛していた。
大戦後にポーランド共和国が誕生したあとも、騎兵大尉の制服を着て、屋敷の戸口に立てたフランツ・ヨーゼフ皇帝の胸像に敬礼する毎日をおくった。
「聖なる酔っぱらいの伝説」
1934年のある春の宵に、セーヌ川の橋の下にいた宿無しの飲んだくれのアンドレアスは、見知らぬ年配の紳士から二百フランをもらう。
カネを返すんだったら、バティニョルのサント・マリー礼拝堂の小さな聖女テレーズさまに納めてくれればよいと紳士は言った。
アンドレアスは、ひょんなことから千フランを見つけたり、小学校のとき友達でいまは有名なサッカー選手と再会したり、幸運に恵まれるが、二百フランを返そうと礼拝堂に行こうとするたびに、近くの酒場で誰かにみつかってペルノーとかで飲んだくれてしまい、テレーズさまのとこまでたどりつけない。
作者自身が深酒で健康を損ない、ホテルを出たところでバッタリ倒れて死んだってのを読んだあとに知ると、なんともいえない気になった。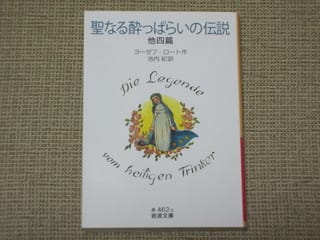
薄田泣菫 1998年 岩波文庫版
これを読みたくなったのは、丸谷才一の『快楽としての読書 日本篇』のなかの、「詩人は人生を二度生きる」という章でとりあげられていたからで。
いわく、
>大正文学の特質の一つとして、随筆の繁栄をあげることができる。(略)
>そして随筆の時代としての大正を最もしやれた形で示す本は木下謙次郎の『美味求真』と薄田泣菫の『茶話』である。
というんだが、そのあとに、「たとへば芥川龍之介はその愛読者で、灯ともしごろともなると夕刊の配達を心待ちしたといふ」なんていうもんだから、読まずに日本文学を語ってはいけないような気になってしまった。(語んないけど。ちなみに著者名は「すすきだきゅうきん」読めなかったというか知らなかったし。)
でも、おなじ丸谷才一の『遊び時間』のなかの「薄田泣菫の散文」って短い評論をそれより前に読んでるはずなんだけど、そのときは読書欲の触覚にひっかからなかったんだから私もいいかげんなものだ。
いまそっち読み返してみると、「知的であることと暖い肌合とが一致してゐること」「イメージの使ひ方がじつに巧妙なこと」などと好きな理由をあげて、ある書き出しを三行ほど例として抜き出して、「どうです。非常にしつかりとした、落ちついた、よい散文でせう」などと言っている。
で、今回、古本の文庫を買って、読んでみたんだけど、読み始めてすぐに、なんで俺はこんなおもしろいもん知らずにいままできてしまったんだろう、って思った。
新聞コラムだったっていうから、あーでもないこーでもなーいって適当な埋め草的なものを勝手に想像してたんだが、とんでもない、どれ読んでもきっちりしたおもしろさである。
なかみは、筆者私はこう思った的なエッセイなんかぢゃなくて、古今東西の逸話集というのに近いかとおもう、大正時代にこんなおもろい話集めたひとがいたんだ、すごく意外。
全881篇のうち著者自選の154篇ということで、おもしろいやつばかり選ばれてるとはおもうが、それにしたって間延びするところ何もなし。
いや、これ、ガキのころに出会ってたら、なんべんでも繰り返し読んだと思うな、俺。
すぐ使える話のネタ本みたいなとこあって、最近読んだばっかりだからおぼえてたんだけど、丸谷才一の『女性対男性』のなかの一話で、男性がつかった逸話の「初代大統領ワシントンは肉をナイフで口に運んだ」とか「藤田東湖は好物の刺身を手のひらにのせてペロリと食べた」なんてのは、ここにその元ネタがあったりして。
どれが一番二番とはすぐにはあげられないが、たとえば私の好きな馬の話のなかでは「馬の慈善」ってポーランドの話なんかがいいねえ。
慈悲深い主人のコスチウスコオの命令で、馬丁が隣村まで使いに行かされたので、主人の馬に乗っていくことにした。
ところが街角で、貧乏人をみかけると、馬は歩くのをやめて動かない。
馬の上から財布を出して貧乏人にいくらかやると、馬は納得したようにぽかぽか歩き出す、そんなことを繰り返す。
お話のおしまいは次のとおり、
>馬丁は使先から帰って来ると、いきなり主人の室へ駈込んで来た。
>「旦那、もう貴方様の馬に乗る事だけは御免を蒙りやす。たって乗らなければならないものなら、旦那の財布も一緒にお貸しなすって下さい。
>コスチウスコオが、貧乏人さえ見れば施しをくれてやったのは、別段褒めるほどでもないが、馬が何々伯爵夫人などと一緒に、貧民救助が好きだったのは偉いと言わなければならぬ。馬が華族でなかったのは何よりも残念である。(p.111)
んー、この話の〆ようが、なんとも微妙な余韻のようなものがあっていい。
総じてそうなんだけど、あんまり押しつけがましくないというか、どーだーこれが正しいんだーとか、見たかーここがおもしろいだろー、みたいなものを感じさせない独特の距離感からくだされる視線の一言が読んでて心地いい。
日本の話では、たとえば「梅の下かげ」って出雲松平家の茶道師範の岸玄知の話なんかいい。
玄知が街はずれを歩いていると百姓家に見事な梅の樹をみつけた。
売ってくれというと百姓はずいぶんと高い値段を言ったが、玄知は道具をいくつか売って金をつくって払った。
玄知は毎日のように梅の花の下にやってきて酒など飲んでいるが、いっこうに樹を移して持っていこうとしない。
百姓が訊くと、言知は自分の屋敷は狭いし、いままでどおりここにあればいいから預かっておいてくれという。
梅の実がなったらどうすると訊かれると、玄知は花を見ればいいだけだから実は百姓にやるという。
実がなるから金までもらったが、花を見るだけだったら何度来ても文句は言わない、金は返すと百姓はいう。
>百姓が金を取りに家へ帰ろうとするのを、玄知は遽てて引きとめた。
>「いや、止しにしてくれ。花がお前のものなら、幾ら見たって面白くない。自分のものにして初めて熟々と見ていられるのだから。」
>百姓は自分の知らなかった珍しい嘘でも聞かされたように、胡散そうな表情をして首をふった。(p.134)
ストンとオチをつけるってわけぢゃない終わり方がなんとも品がいいんだ。
どうでもいいけど、読んでくうちに、どの話も短いんだが、書き出しの文がいいなあと思うことが多い。
>むかし、江戸に亀田鵬斎という学者が居た。貧しい学者にしても夏はやはり金持同様に暑かったから、鵬斎はいつも六月になると、ずっとすっ裸で暮していた。(p.27「裸体」)
>独逸の鉄血宰相ビスマルクが、ある時ウィルヘルム老帝の御馳走になった事があった。その折の献立がどんなだったかという事は、他人の食膳にあまり興味を持たない私の知らない事だが、唯一つその時卓子の上に載せられていた酒が、三鞭酒だったのはよく知っている。(p.127「愛国心と胃の腑」)
>天竜寺の峨山和尚が、ある時、食後の腹ごなしに、境内の畔をぶらぶらしていた事があった。池には肥えふとった緋鯉だの、真鯉だのが、面白そうに戯けあって、時々水の上へ躍り上るような事さえあった。(p.137「魚を食う人」)
>遣欧米軍の司令官パアシング将軍が、ある日自分の兵卒の宿舎を巡視に出かけた事があった。多くの兵卒が風琴を鳴らしたり、骨牌を弄ったりしているなかに、たった一人、一番年齢の若そうなのが、人の居ない隅っこで、じっと書物に読み耽っているのが将軍の気についた。(p.154-155「司令官と一兵卒」)
などなど、なんてことないようなんだけど、そのつづきを読んでみたくなるんである。
ふと思ったんだが、なんか「今昔物語」とかそういう系譜につらなるノリなのかもしれない。
















