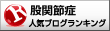残暑お見舞い申し上げます。
昨日、曇天の蒸し暑い中、銀座サロンへ施術に行きました。
電車はお盆なので、大きな荷物を持った人たちと子供たちが
いて、いつもの車内とは全然違います。
腰痛の痛みからか、足の痛みもいつもより出ていましたので、
施術は、かなり痛いものでした。
痛みが強く出ているときは、先生の施術でもなかなか頑固な
ものはすっきりとはいかないようです。
残念…
それだけ悪い、ということなので、大事にしなければ…
私の次の方が、最近知り合った方で、なにげにお話していたら
「あなたくらい(股関節の)動きが良かったら…死んでもいい」
と言われました。
そのくらい、痛みと動きの悪化で、長い間苦しくでいられるのだ、
と感じ… この病気が持つ特性と症状の上下の大きさを改めて
思い… ためいきが出ました。
でも、やっぱり病気に負けてはいけない! ですね。
今日は「お盆」の各行事についてです。
―8月1日―
一般的に盆行事は新暦8月13日から15、16日にかけて、先祖
供養をいたしますが、すでに1日から盆行事は始められています。
この日を「地獄の口開け」といい、地獄にいる亡者も帰って来る日
だと伝えている所が多くあります。
そのような地域の各寺では、この日から施餓鬼棚を設け、先祖の
供養をはじめます。高い竹を立て灯篭を吊るしたり、旗をかかげたり
しますが、これはご先祖さまが家に帰りやすくする目印のための
ものであります。これを寺で行うのは、かつてその地区の人々が
ここで、この祀りを共同で行っていた名残だと思われます。
また「盆の路つくり」といい、村境や山頂までの道の草刈をする
地区もありますが、これも遠く先祖のおられる世界から帰って来ら
れる先祖さま達が、村に帰りやすいようにと思ってのことです。
―七夕(8月7日)―
8月7日に各家で、竹にいろいろ願い事を書いた色紙を結びつ
けて、立てている姿を良く見かけます。その理由を尋ねると、天の川
を隔てて牽牛星と織女星輝いていますが、この日だけはデートする
ことができる。それに供えるのだと答えられます。
これは「乞巧奠(きつこでん)」という伝承で、中国から伝えられた
ものです。この竹のもとにその年の初物を供え、丁寧な所では胡瓜
や茄子で作られた牛や馬をお供えします。牛や馬はご先祖様の
乗り物で、これで家に帰って来てほしいと願い、初物もその収穫を
感謝して先祖に供えているのです。その竹そのものが、先祖さまが
これに依り付くようにと願って立てられたものです。ちょうど、正月の
門松と同じ働きをしていると考えてよいと思います。
この日を「七日盆(なぬかぼん)」といい、墓の掃除をするところも
多くあります。これも掃除をすることで、先祖が墓から家まで帰って
来やすいようにとの願いがもとにあるのです。
また井戸の掃除をする所も僅かですが残っています。
牛を河で洗ったり、昔は女性が河で髪を洗う習慣もありました。
この水に関連する行事は、みそぎにかかわりがあると考えられて
います。この日から先祖を迎える精進潔斎の時に入った名残りだと
考えられます。(平安時代後期は特にこの風習が行われた)
7日は、このように盆の先祖祀りにとっての大切な日であります。