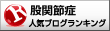今朝は、まだ昨夜からの雨が残ってポツリポツリと降っています。
今日、叔母は16日ぶりの入浴のためにデイサービスへ行きました。
支度(パジャマから洋服に着替えるだけでも…ハァハァフゥフゥ…しんどいしんどいの
連発です。。)
が、無視して聞き流し、、行ってもらいました。
そうでもしないと、行かせられません。悲しいかな。。
行ったと思ったら、もう直ぐ帰ります。
入浴のみの利用なので。
…書いている途中で帰ってきました。。
息子からの母の日プレゼント、やっぱりなしでした。
自分で自分に購入して正解?でした。
友人は、娘(夕食招待おごり)さんから、とお婿さんから(お花をいただいて
すごく嬉しかったそうです。
負けをしみのようですが…
自分に自分でほしいものを購入したので、うらやましいと思わなかった、、、
ほっ…です。
人をうらやむ事は、余りよくないことで、恥ずかしい? ことなので。。
今日は、息子も一時期大変な思いをした、ブラック企業は、果たして、と
思わせるような内容で、面白かったので皆さんに紹介します。
~東京新聞記事より~
『働きアリも休んでいる』
「働きアリには、実は働かないアリがいます」。意外なトリビアから解説するのは、
北海道大農学部の長谷川英祐准教授だ。アリなど社会生活を営む生物を
研究している。
研究によると、ある瞬間の巣を観察すると、働きアリの7割りは休んでいることが
分かった。
観察を続けると、2割りのアリは1ヶ月以上働いた様子がないことが判明した。
働きアリで、いつも働くアリは一部。実は、結構休んでいる。
長谷川氏が説く。
「どの程度になったら仕事に取り掛かるかという『反応閾値』が固体で異なる
からです。人でいえば『腰の軽さ』といえるでしょうか。
すぐ働くアリ、仕事が増えると働くアリ、いよいよという時でなければ働かないアリ、
一つの巣にいろんなアリがいる」
人間社会でも、働き方は人それぞれだ。
だが、自然の営みに無駄はないきず。同じように仕事に反応して一斉に仕事に
取り掛かれば、少数でも効率的に仕事ができようものだ。
多くの企業が「余剰人員」を削減する理由でもある。
だが、長谷川氏は言う。
「確かに、短期的には一斉に働いたほうが効率的です。ですが、それでは全員が
同時に疲れて、同時に動けなくなってしまう。卵や幼虫の世話もできなくなれば
巣は滅びます」
会社でも人を絞ってフル回転すれば、病人が続出し、ミスも多くなるのは道理だ。
いわゆる「ブラック企業」と呼ばれるのも、その類い。
うつ病などメンタル系の病気が増えているのも、人員削減が進む社会と裏表にある。
その点、アリはどうしているのか。
「そこが固体によって反応閾値をたがえている理由です。最初に仕事にかかったアリが
疲れれば、次に反応するアリが仕事にかかる。そのアリが疲れれば、疲労から回復した
アリがまた働く。
アリの行動を模したコンピューターシミュレーションでも、長期的に残るのは『働かないアリ』
のいる巣の方でした。
働かないアリこそ、組織存続の鍵を握るとは意外な発見だ。
一種のリザーブ(控え)要員を置くことで、働きアリは働き続けられるし、組織も栄える。
「働きアリには人員配置を指揮する管理職のようなアリがいない。管理職がいなくても
適切なところに適切な労働力を配分できる仕組みでもある」とも長谷川氏は言う。
やはり自然は賢い。
「生物である以上、疲労は避けられません。アリやハチも過労死する。人間も疲れれば
集中力は落ち、作業効率も下がる。それが組織存続にとっていいことなのか考える
必要があります」と長谷川氏。
効率を追求するあまり、かえって組織を損なうことになりはしないか。
働きアリの働き方に学ぶことは多い。

 どこぞのブラック企業の社長さんに聞かせたい、内容ですね。。
どこぞのブラック企業の社長さんに聞かせたい、内容ですね。。
働き過ぎ、動き過ぎ、、どちらにしても、ちっともよい事はない、と思われます。
くれぐれも、ご自愛くださいね。。
『変形性股関節症に負けないでね!』