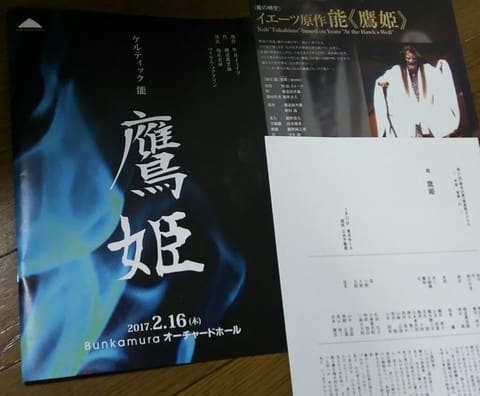昨日は、、 人に逢いに出掛けました… 大好きな「人」に、、
、、 帰り道はそろそろ夕暮れ。。 街路樹や植え込みがもう、 イルミネーションで飾られているのでした。 こんなふうに…


(歩きながらのピンボケ…)
***
tweet のほうに少し書きましたが、
堀辰雄の初期ファンタジー傑作集 『羽ばたき』(長山靖生編、彩流社 2017年2月)という短編集を読んでいます、、(というか読み終えました)
前回、 椿實全作品を読んでいた時にも書きましたが、 前田愛先生の 『都市空間のなかの文学』(筑摩書房 1982年)という本に、 昭和初期の浅草「カジノ・フォーリー」を舞台にした小説 川端康成『浅草紅団』や、堀辰雄の幻想的な短編「水族館」などのことが書かれていて、、
『風立ちぬ』の堀辰雄が、 浅草の踊り子に夢中になる学生や、 男装の麗人かどうかわからない妖しい男(?)の話を書いているのも意外な気もしましたし、、 前からこの堀辰雄のファンタジー短篇集 の事が気になっていたので、 椿實の後にぜひ読もうと。。

新しい本なので、 内容には余り触れないでおきましょう。。
(以下、「水族館」や個々の作品を示すものではありません)
、、 この短編、 あるいは掌編とも言えるような小さな物語を読みながら、、「ファンタジー」という言葉に、 人はどんなものを求めているのだろう… とふと考えたりしていました。 ファンタジー短篇集という言葉、、 そしてこの装画。 可愛らしくもあり、 優しい童話のようでもあり、、 美しい表紙なのですけど…
この表紙画、、 堀辰雄のこの本の中身をうまく表現しているように思います。 少年期から大人への階段をのぼっていく、、 瑞々しい知覚、 甘やかな思慕、 かと思えばひややかな想像、、 静かで美しい彩りでありながらどこかシュールでもある、、
見ると… その足元には…
、、 よく知られているように 堀辰雄は肋膜炎や肺結核で長い療養生活を強いられました。 そうした自身の事ばかりでなく、 関東大震災で母を亡くしたりもしていたのですね。。 そして、昭和二年 帝国大学在学中に師と仰いでいた芥川龍之介の自死。 そのような時期に生み出された「ファンタジー」の文学、、
英語の fantasy は、 「phantasy」が古い語だそうです。 ギリシャ語源の 「幻・像・見えるもの image」という意味がもともとにあって、 phantom 、 phantasm は、 「幻、幻影、幽霊」ですね、
実在(という言葉も何をもって実際に在るというかむずかしいですが…)しないものを、 感じること、 見ること、 想うこと、、 目の前の世界がプリズム越しの世界に変わる、、 そういう「phantasy」
、、では なぜそれを「見る」「想う」かというと… 自分の前の「現実」がそれを必要としているから、、 想わずにはいられないから、、 光が屈曲せずにはいられないから、、 また、 翳の中に襲われるように あちらから勝手にやってくるから、、
だから、 その世界はほんとうは 「在る」のです。 貴方はいるのだし、、 花は匂っているのだし、、 声はとどいているし、、 像は姿を変えた、、 のです。。
子供らが眠る前にお話をきいて、 おやすみなさい… 楽しい夢の世界へ、、という夢への通い路としての物語ではないのですね、、 白日夢のように、 或は狂気のように、、 現実と並んでともに歩いているもの、、
そういう 「phantasy」について、、 読みながら考えさせられていました。
編者の長山靖生さんの解説がとても詳しく、 創作当時の堀辰雄の背景、 時代や取り巻く人々… 作品を味わった後も、 関心の枝葉を大きく伸ばして下さるような解説でした。
『菜穂子』などの長編作品や、 師芥川にも繋がる軽井沢文学圏の人々… もう昔読んだきりだから、 あらためて辿り直してみたい気持ちになっています。

***
以前に書いた R・L・スティーヴンスンの幻想的な物語 『幻の人 "Will O' the Mill"(水車小屋のウィル)』(>>)も、 前回書いた 『椿實全作品』も、 そして 今回の 堀辰雄の短編の中にも、、 「香り」が見せる 「phantasy」の物語がいくつか不思議と連鎖しました。 (椿實は、 最初 生物学を志そうと考えてもいたそうで植物の記述の繊細さ、秀逸さには驚きます、、)
香りと記憶… 香りは 記憶である…
、、またいつか それについても書いてみたいと思いますが、、
雪の匂い…
針葉樹の森の中の 雪の匂い、、、 そろそろ そんな匂いも懐かしく思い出される季節になってきました。。
では またね… 風邪ひきませんように

、、 帰り道はそろそろ夕暮れ。。 街路樹や植え込みがもう、 イルミネーションで飾られているのでした。 こんなふうに…


(歩きながらのピンボケ…)
***
tweet のほうに少し書きましたが、
堀辰雄の初期ファンタジー傑作集 『羽ばたき』(長山靖生編、彩流社 2017年2月)という短編集を読んでいます、、(というか読み終えました)
前回、 椿實全作品を読んでいた時にも書きましたが、 前田愛先生の 『都市空間のなかの文学』(筑摩書房 1982年)という本に、 昭和初期の浅草「カジノ・フォーリー」を舞台にした小説 川端康成『浅草紅団』や、堀辰雄の幻想的な短編「水族館」などのことが書かれていて、、
『風立ちぬ』の堀辰雄が、 浅草の踊り子に夢中になる学生や、 男装の麗人かどうかわからない妖しい男(?)の話を書いているのも意外な気もしましたし、、 前からこの堀辰雄のファンタジー短篇集 の事が気になっていたので、 椿實の後にぜひ読もうと。。

新しい本なので、 内容には余り触れないでおきましょう。。
(以下、「水族館」や個々の作品を示すものではありません)
、、 この短編、 あるいは掌編とも言えるような小さな物語を読みながら、、「ファンタジー」という言葉に、 人はどんなものを求めているのだろう… とふと考えたりしていました。 ファンタジー短篇集という言葉、、 そしてこの装画。 可愛らしくもあり、 優しい童話のようでもあり、、 美しい表紙なのですけど…
この表紙画、、 堀辰雄のこの本の中身をうまく表現しているように思います。 少年期から大人への階段をのぼっていく、、 瑞々しい知覚、 甘やかな思慕、 かと思えばひややかな想像、、 静かで美しい彩りでありながらどこかシュールでもある、、
見ると… その足元には…
、、 よく知られているように 堀辰雄は肋膜炎や肺結核で長い療養生活を強いられました。 そうした自身の事ばかりでなく、 関東大震災で母を亡くしたりもしていたのですね。。 そして、昭和二年 帝国大学在学中に師と仰いでいた芥川龍之介の自死。 そのような時期に生み出された「ファンタジー」の文学、、
英語の fantasy は、 「phantasy」が古い語だそうです。 ギリシャ語源の 「幻・像・見えるもの image」という意味がもともとにあって、 phantom 、 phantasm は、 「幻、幻影、幽霊」ですね、
実在(という言葉も何をもって実際に在るというかむずかしいですが…)しないものを、 感じること、 見ること、 想うこと、、 目の前の世界がプリズム越しの世界に変わる、、 そういう「phantasy」
、、では なぜそれを「見る」「想う」かというと… 自分の前の「現実」がそれを必要としているから、、 想わずにはいられないから、、 光が屈曲せずにはいられないから、、 また、 翳の中に襲われるように あちらから勝手にやってくるから、、
だから、 その世界はほんとうは 「在る」のです。 貴方はいるのだし、、 花は匂っているのだし、、 声はとどいているし、、 像は姿を変えた、、 のです。。
子供らが眠る前にお話をきいて、 おやすみなさい… 楽しい夢の世界へ、、という夢への通い路としての物語ではないのですね、、 白日夢のように、 或は狂気のように、、 現実と並んでともに歩いているもの、、
そういう 「phantasy」について、、 読みながら考えさせられていました。
編者の長山靖生さんの解説がとても詳しく、 創作当時の堀辰雄の背景、 時代や取り巻く人々… 作品を味わった後も、 関心の枝葉を大きく伸ばして下さるような解説でした。
『菜穂子』などの長編作品や、 師芥川にも繋がる軽井沢文学圏の人々… もう昔読んだきりだから、 あらためて辿り直してみたい気持ちになっています。

***
以前に書いた R・L・スティーヴンスンの幻想的な物語 『幻の人 "Will O' the Mill"(水車小屋のウィル)』(>>)も、 前回書いた 『椿實全作品』も、 そして 今回の 堀辰雄の短編の中にも、、 「香り」が見せる 「phantasy」の物語がいくつか不思議と連鎖しました。 (椿實は、 最初 生物学を志そうと考えてもいたそうで植物の記述の繊細さ、秀逸さには驚きます、、)
香りと記憶… 香りは 記憶である…
、、またいつか それについても書いてみたいと思いますが、、
雪の匂い…
針葉樹の森の中の 雪の匂い、、、 そろそろ そんな匂いも懐かしく思い出される季節になってきました。。
では またね… 風邪ひきませんように