







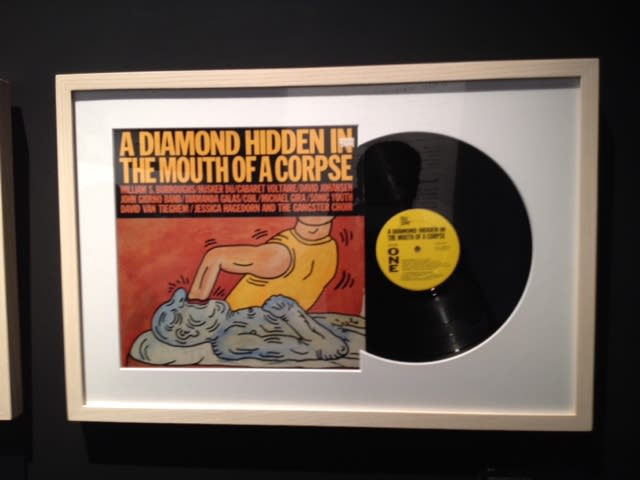






#自分が70mmで観た映画
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月14日 - 21:12
70mmで製作されていても上映は35mmということはたびたびあったけれど、テアトル東京でリバイバルされた「天地創造」「ドクトル・ジバゴ」「屋根の上のバイオリン弾き」あたりは本物の70mmでしょう。「ベン… twitter.com/i/web/status/1…
久しぶりの本格的70mm映画としてちょっと話題になった「遙かなる大地へ」。
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月14日 - 21:13
#自分が70mmで観た映画
「ただで弾いてくれない?」
— kanana*violinist (@kana_vn1222) 2018年8月13日 - 17:49
この言葉があまり好きじゃない。だって音大で技術と精神を研き、全てを音楽に捧げた人に「ただで」って簡単に言ってほしくない。医者に「ただで診て」とは言わないのに、なぜ芸術だとボランティアになってしまうのか。音楽家は死ぬまで勉強。精神を削る命がけの仕事。
歴史学者が教えない歴史、って医者が薦めない治療法みたいなものだからな。
— ネガだいこん (@negadaikon) 2018年8月14日 - 09:16
おまえらは水木しげるのいったいなにを見てたのかと。【悲報】アニメ鬼太郎最新話、戦争の話をするも自虐史観で一気にサヨ太郎になる farmsdesk.com/matome/?p=17834
— Kiichiro Yanashita (@kiichiro) 2018年8月14日 - 20:32
今日の「たまむすび/町山智浩アメリカ流れ者」は、三船敏郎と大東亜戦争に関する話題だった。その中で出てきたのが、戦地での鷺巣富雄(後の漫画家うしおそうじ)との出会い。うしおさんは漫画家としてこの時の出会いをアニメージュの連載『ヒトコ… twitter.com/i/web/status/1…
— ほうとうひろし (@HiroshiHootoo) 2018年8月14日 - 16:11
うしおさんは14年前に亡くなられた。亡くなられる数年前に、太田出版の『スペクトルマンvsライオン丸』の企画制作に関わったことがきっかけで、おつきあいをさせていただいた。この興味深い作品『ヒトコマ賛歌』は未完だったので、書き足しした… twitter.com/i/web/status/1…
— ほうとうひろし (@HiroshiHootoo) 2018年8月14日 - 16:44
うしおさんは「今は円谷英二、手塚治虫、三船敏郎の伝記を3部作として書くことに全精力を傾けているから、それが終わってからだね」と仰られたが、2冊目の手塚伝記の執筆中にお亡くなりになった。その原稿は没後纏められ出版された。… twitter.com/i/web/status/1…
— ほうとうひろし (@HiroshiHootoo) 2018年8月14日 - 16:50
サマータイム導入のあれこれから酷暑を解決する方法を思いついたんですけど、夏の時期は温度計をあらかじめ5度下げておくサマー温度を導入すれば最高30度くらいになるから余裕じゃないですか?ねえマジですごくないですかこれ?ねえすごいですよね?
— tkq (@tkq12) 2018年8月13日 - 16:28
ガラスの鳥居初めて見た⛩綺麗! pic.twitter.com/kBaL13a0L5
— ハラボー (@DJ_HARABO) 2018年8月13日 - 08:27
"Directing is more fun with women. Everything is."
— TATJANA SL (@TATJANASL) 2018年8月14日 - 00:28
Ingmar Bergman
Ingmar Bergman and Liv Ullmann during the filmi… twitter.com/i/web/status/1…
学生時代から吐くほどインディーズ映画に関わってきたけど、周りから「自主映画の技師」と呼ばれ舐められるのが嫌で今は基本、商業映画しか受けないスタンスで生活している。それでも年に1本、完全なインディーズ映画に参加するのは「撮らなければ、演じなければいけない人」を無視できないから。
— 私はネモアス (@nemoasu) 2018年8月14日 - 00:05
映画『ダイ・ハード』のナカトミプラザの見学ツアーのレポート。驚くくらいにそのまんま | ギズモード・ジャパン gizmodo.jp/2018/08/die-ha…
— シネフィルDVD (@cinefilDVD) 2018年8月13日 - 19:59
何色のスーツをお召しになられているケイト・ブランシェットが好きか雑談を小一時間ほどしたい pic.twitter.com/ZawRV8d1Mq
— イヴ (@leon_louise13) 2018年8月12日 - 21:14
川崎市多摩区上空・・・
— akibafudousan (@akibafudousan) 2018年8月13日 - 15:15
危うく竜巻が発生するかと思ったじぇ・・・
上空で雲が巻いた時はやばいと思った。
#竜巻 #雷雨 #ゲリラ豪雨 #川崎市多摩区 pic.twitter.com/m4ZcHwgRAB
「聖杯たちの騎士」 #eiga #映画 goo.gl/7Uhi2p
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月14日 - 08:30
「伝単」。第二次世界大戦中、アメリカ軍が日本人に降伏を促すために撒いたビラです。当時流通していた紙幣に似せて作ることによって、貧困にあえぐ民衆が拾いやすいよう工夫しています。段々と日本が貧しくなっていく様子を伝えています。書肆ゲン… twitter.com/i/web/status/1…
— 書肆ゲンシシャ/幻視者の集い (@Book_Genshisha) 2018年8月13日 - 18:28
『映画の労働者たち 写真と証言』。労組幹部の撮影助手解雇から始まる21年を東映東京制作所闘争記録委員会がまとめた一冊。組合の分裂、潰し合い、技師昇進を餌にした切り崩し、ロックアウト……『Gメン'75』は社員と下請の2班体制だったが… twitter.com/i/web/status/1…
— 高鳥都 (@somichi) 2018年8月14日 - 08:32
『Gメン'75』は東映のテレビ映画としては予算と日数をかけた代表格だったが、TBSから東映→東映東京制作所を経て仕上げの映広や新規設立の東映映像が現場を請け負う多重下請で制作費は削られ、残業代がかかる制作所の組合員を遊ばせてでも街… twitter.com/i/web/status/1…
— 高鳥都 (@somichi) 2018年8月14日 - 08:44
そんな観点で『Gメン'75』を見ると、カット数は多いしテンポは早いし俯瞰や凝った撮影バンバンやってて明らかに現場は大変そうなんですが、実際スタッフの入れ替わりは激しくセブンイレブン(朝7時から夜11時)や吉野家(朝までの完全徹夜)… twitter.com/i/web/status/1…
— 高鳥都 (@somichi) 2018年8月14日 - 09:27
なんか文春オンラインの鈴木敏夫が語る高畑勲みたいな話になってきた。そもそも東映東京制作所はテレビ映画の受注を名目に設立され、労働争議と合理化で撮影所を外された共産党系組合員たちの強制配転先となった。このあたりは『映画秘宝』2015… twitter.com/i/web/status/1…
— 高鳥都 (@somichi) 2018年8月14日 - 09:53
東映の撮影所、制作所、テレビプロ、動画にまたがる労働争議はややこしくて第一組合と会社(+会社側の組合)だけでなく、正社員と契約者、左翼と新左翼の対立もあって多くの団体が存在した。制作所の契約助監督だった山崎充朗は劇画原作者・やまさき十三となり、やがて『夢工場』で苦い青春を描く。
— 高鳥都 (@somichi) 2018年8月14日 - 10:34
「Twitter社にお邪魔」「色々と勉強」か。TwitterJPに公共政策本部なるものがあることを初めて知った。誰が(どんな経歴の人たちが)何を(どういう相手にどういうことを)している部署なのか。猛烈に知りたくなった。 twitter.com/MPD_bousai/sta…
— ガイチ (@gaitifuji) 2018年8月14日 - 12:14
今回のサマータイムの何が怖いって、失敗しないことですよ。前のは失敗してもそれを失敗と認めるだけの柔軟性があった。でも今回のは失敗しない。失敗などとは絶対に認めずに成功への途中と言い張ってずっと押し通す。もしここで止めたら失敗だ、と言い張る顔と声が確実にイメージできること。
— 北野勇作 『昔、火星のあった場所』復刊! (@yuusakukitano) 2018年8月13日 - 20:06
一番早口な言語はどれ?で音節速度は日本語が1位(スペイン語は2位)しかし情報密度に関してはベトナム語100%、英語91%、しかし日本語は49%という、早口だけど中身の薄い言語という結果が。 twitter.com/TapasDeCiencia…
— えぼり (@eboli_ef) 2018年8月14日 - 00:06
⚡️ "ますむらひろしさんの宮澤賢治の漫画化に関するツイート"
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月14日 - 12:54
twitter.com/i/moments/9861…
⚡️中沢けい氏による 「著作経済権と著作人格権」解説
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月14日 - 15:11
twitter.com/i/moments/1029…
#素晴らしいモンスター映画ポスター
— タツ (@tatsu00000) 2018年8月13日 - 19:04
全て、本日現在、秋田県大館市の映画館「御成座」に掲示されているポスター pic.twitter.com/DbS1MgElPn
藤田嗣治先生の手紙は、白い便箋に9ポ活字ほどの小さい字がびっしりと並び、おまけにチビチビとした絵入りでちゃんと色までついていた。あるとき、便箋の間からハラリと小さな紙が落ちた。小さな女の子がオシッコをしている絵で、手紙の追伸に、「お秀がオシッコをしているところ。へへへ」とあった。
— 高峰秀子 (@HidekoTakamine) 2018年8月14日 - 15:00
東映モンスターシリーズ。
— おんばけ@ゆでだこ日本に燃える着ぐるみ (@onbake_Otsuka) 2018年8月13日 - 10:56
#素晴らしいモンスター映画ポスター pic.twitter.com/03Vo5mKto4
#素晴らしいモンスター映画ポスター
— kin_me (@kin_me) 2018年8月13日 - 10:56
「遊星からの物体X」はデザイナーのイマジネーションを刺激する。 pic.twitter.com/2ZKDG8Rl9A
出口治明APU学長曰く「人類の歴史の中で、悲観論が勝利したことは、これまで一回もないんですよ」 なんと勇気づけられる言葉だろう!
— 野崎 優彦 (@nozakimasahiko) 2018年8月14日 - 15:28
HONZ in APU④ 悲観論にとらわれることなく、人生を楽しむこと - HONZ honz.jp/articles/-/448…
【「製作50周年記念『2001年宇宙の旅』70mm版特別上映」を10月に開催】
— 【公式】国立映画アーカイブ 広報 (@NFAJ_PR) 2018年8月14日 - 15:21
本年のユネスコ「世界視聴覚遺産の日」記念特別イベントとして、クリストファー・ノーラン監督とワーナー・ブラザースのもと作成された『2001年宇宙の旅』… twitter.com/i/web/status/1…
沖縄よ独立しろッ。今からでも遅くはないッ。琉球共和国万歳!!何をいっとるんだ?
— 殿山泰司 bot (@Taichanbot) 2018年8月14日 - 16:42
『バーニング』、音楽をイエスのリック・ウェイクマンが手掛けていたり、無名時代のホリー・ハンターが端役で出演しているなど、何気にトリビアの多い本作だが、編集は後に『ヒドゥン』の監督を務めたジャック・ショルダーだったのね。何なら彼が監… twitter.com/i/web/status/1…
— takeman75 (@takeman75) 2018年8月14日 - 04:08
今日は三船敏郎出演『山本五十六』公開50周年!なので国際版ポスターを。 pic.twitter.com/GxkDxXqyhY
— Pakki@Mナンバー探偵 (@0463Zero4063) 2018年8月14日 - 12:39
これが『2001年宇宙の旅』の70mmプリントのケース。どうやら10巻に分かれているようです。
— シネフィルDVD (@cinefilDVD) 2018年8月14日 - 20:03
goo.gl/images/ZpCsUy
Alfred Hitchcock’s films.
— Juan Ferrer (@JuanFerrerVila) 2018年8月13日 - 22:00
Storyboards.
Vertigo (1958).
North by Northwest (1959).
Psycho (1960).
The Birds (1963). pic.twitter.com/nWtr5oALA9
トラック運転席でロジャーに詰め寄った女ゾンビを演じた人‼️(^ν^) pic.twitter.com/8ZZhrbgoQu
— 雷電 (@mq_xt) 2018年8月14日 - 08:06
渋谷パンテオンで催された東京ファンタスティック映画の「アラビアのロレンス」。
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月14日 - 21:11
#自分が70mmで観た映画
ラスト近くで地震があってフィルムが外れ回復するのが大変だった。
リールがトラックのタイヤほどもあるのですと解説していた。 pic.twitter.com/HRdDz8ED3G
これは本当にあった話なんですが、私が高校生の時に学校近くのゲオが至って普通の日にレンタルDVD一本あたり10円を実施したことがありました。店長の気が狂われたのかなと思ってちょっと怖かったので30本しか借りなかったです。
— 映画ランナー (@eigarunner) 2018年8月13日 - 21:37
@YahooNewsTopics QBハウスの値上げ、消費税8%から10%に上げるのを前提にした料金を柔軟に設定できる券売機を予め導入していたから切り替え自体は割と易しいか。
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月13日 - 22:12
12歳でお父さんと「野火」を見てから、戦争を調べ、フィリピンに行き風景を見、当時の無謀な戦争に怒りを覚え、自衛隊に入隊してその仕組みを勉強した15歳の少女が、お母さんとお花を持って深谷シネマに来てくれた。花がみるみる広がるようだ。 pic.twitter.com/dCWp63PngS
— 塚本晋也tsukamoto_shinya (@tsukamoto_shiny) 2018年8月13日 - 22:08
「英国人がこの機を見逃がすはずもなく」「旅行代理店トーマス・クックではトルコ行きの予約が63%増加」:BBC News - Turkey's lira crisis explained bbc.com/news/world-eur…
— the_mathnawi (@the_mathnawi) 2018年8月11日 - 01:18
最強の擬態能力を持つタコ 🐙 pic.twitter.com/oeyoS39Syd
— Sangmin Ahn (@gijigae) 2018年8月12日 - 09:24
今年の夏コミ一番の謎コスプレ。 #C94 #C94コスプレ pic.twitter.com/t5i9TMmWR9
— 大豆の新芽野菜=もやし (@Soy_Sprout) 2018年8月11日 - 13:16
#怪談の日
— kin_me (@kin_me) 2018年8月12日 - 23:06
「怪談ナイト」20周年連続公演を記念して稲川淳二が8月13日を「怪談の日」に制定したそうな。彼が制定したのなら仕方ない。夏といえば怪談なのだけど今までたくさんの怪談映画が作られた。暑い夏はクーラーを使わず怖い映画を観… twitter.com/i/web/status/1…
『ゲッベルスと私』『ヒトラーの忘れもの』『否定と肯定』…ナチズムに関わる作品が欧米では絶えない。一方わが国では絶対主義的天皇制をテーマとする作品は半世紀で数本のみ。天皇明仁氏の人柄が良い事と絶対主義的天皇制批判は別の話。『真空地帯』『人間の條件』『ゆきゆきて、神軍』のような映画を
— Hajime Imai〈今井 一〉 (@WarszawaExpress) 2018年8月12日 - 02:02
米国でも注目の反米放送「ロシア・トゥデイ」、結局何が面白いかといえば、「アメリカ的論理を抜きに世界の再構築は可能か」という、何気にでかい知的命題が背景に感じられる点です。けどアンチ・アメリカイズムを旗印に集めた人材の価値観は一枚岩… twitter.com/i/web/status/9…
— マライ・メントライン@職業はドイツ人 (@marei_de_pon) 2018年2月19日 - 19:23
「青い山脈」のラブレターで「変しい変しい新子さま」とやらかすのがありましたねえ。 twitter.com/tako_ashi/stat…
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月13日 - 02:13
今年の4月「カメラを止めるな!」でイタリアの映画祭に向かう飛行機で偶然隣になった映画好きのおばちゃん。「インディーズ映画なのでご存知ないと思うんですが…」とチラシを渡した。連絡先も交換せず別れた。今日そのおばちゃんからSNSで「おめでとう」ってメッセージがきた。すごいぜ映画。
— 上田慎一郎 (@shin0407) 2018年8月12日 - 23:44
「アリーテ姫」サントラが廃盤になったのは、消費税が上がって内税表示が義務付けられたときに、印刷し直せなかったからです。音楽の千住さんも「細々した中で演奏して下さった方々にCDの売上げから還元出来れば」と言っておられたのに。再販お願いしたいです。オリガさんの歌声も蘇らせたいです。
— 片渕須直 映画「この世界の片隅に」公開中 (@katabuchi_sunao) 2018年8月12日 - 08:33
原一男監督と宮台真司氏のトーク拝聴。「裁判は手打ちであり、関わった個人の感情的な問題は解決しない」と「表現と表出は異なる、使い分ける」で、このところ主に仕事で顕在化していたモヤモヤがいくらか晴れた。思考を言語化して他者に伝えることには大きな意義があると再認識。黙ってたらあかん。
— ぼちぼち人間力研究所 (@homeanddry2018) 2018年8月13日 - 02:18
私が何故、猫で漫画を描いたか。最大の理由は、宮澤賢治の童話を大量に読んだからであり、次が、水俣病の原因調査のために、猫に水銀汚染の魚を食わせての実験画像をテレビで見たせいなのだ。猫は、人間の経済のために喰われ滅びる自然の生命体たちの、象徴だった。
— ますむらひろし (@masumurahiroshi) 2018年8月11日 - 12:47
うつ病の人が遊びに行くのを許せない人が意外といるっぽい。僕もよく言われる。
— まるるんず語録 (@marurunzmemo) 2018年8月12日 - 00:46
ただの怠けと思っているのか「仕事には行けないのに遊びには行けるのか!」と痛い所を突いたつもりで言う人がいる。
何日も休んで体調整えて気圧や気温もマシな… twitter.com/i/web/status/1…
お盆の時期になると俄然活躍するカメヤマローソク。カメヤマの品揃えには見るたび感心する。つい仏壇にお供えしたくなる個人が好きだったお菓子や果物。スイカのローソクはまるでかじってるみたいに溶けるのがいい。透明のロウソクは水輪が涼しげ。… twitter.com/i/web/status/1…
— Green Pepper (@r2d2c3poacco) 2018年8月12日 - 08:38
「労働基準法順守したら潰れる会社が増える」というクソリプがつきましたんですけど、それはまことに喜ばしいことです。ぜひ潰れてほしい。従業員搾取して儲けてる会社なんぞ、がんがん潰れてほしい。ぜひとも潰れてください。市場競争上も不公平。払うべきコストを払っていない。
— えんてん (@on_enten) 2018年8月12日 - 18:37
「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」 #eiga #映画 goo.gl/JD6U13
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月13日 - 08:49
この結果は興味深い。ほかの案件でも見られることだが「あいつらはクズだ」とお互いに言い合う発言に比して、実際の「クズ」は少数であったということ。
— 伊藤 剛 (@GoITO) 2018年8月13日 - 06:56
po-jama-people.info/entry/2018/08/…
光州事件など韓国の民主化闘争をずっと追って来た真鍋祐子先生の解説。「「民主化を求める韓国」という「想像の共同体」を再確認させる場」としての光州事件(もしくはセウォル号事件)。/ 犠牲者193人…韓国国民が38年前の「虐殺事件」を振… twitter.com/i/web/status/1…
— Kawase Takaya (@t_kawase) 2018年8月12日 - 10:51
ジュヌビエーブ・ビジョルドは70年代半ば、ミニシリーズでクレオパトラを演じている。ジョージ・バーナード・ショーの戯曲『シーザーとクレオパトラ』を原作に相手役はアレック・ギネス! 家にあった米国版TV Guide誌の広告でたまたま見… twitter.com/i/web/status/1…
— chuchubabe (@chuchu_babe) 2018年6月16日 - 03:12
う〜む、これは観たいなぁ。
— chuchubabe (@chuchu_babe) 2018年6月16日 - 03:40
アレック・ギネスは『名探偵登場』のバトラー、ベンソンマムやSW eps.IVのオビ=ワンの前あたりだろうか。 pic.twitter.com/EOV8Sv9GQL
@__Mimi_0929__ こちらは1976年。当時、この広告を自宅にあった雑誌で見て妄想を膨らませていました。日本でいえば源氏物語かな… 西洋では舞台やテレビの定番ですもんね。パイパー・ローリーにビュジョルド… どちらも気性が… twitter.com/i/web/status/1…
— chuchubabe (@chuchu_babe) 2018年8月12日 - 15:24
ある日
— さまりな (@HEIB36710512) 2018年8月9日 - 21:55
部活動の部長が全員、先生に呼び出された。先生に「これ、やってね」と紙を渡され指示された。
「延長したい」なんて、誰も言ってないのに。頼んでもいないことを、部長みんなでお願いしに行った。
子供はやりたいなんて言ってないのに… twitter.com/i/web/status/1…
屋外美術館ともいえるエトルタにあるこの庭園。断崖を見渡す絶好の写真スポットもあります。#ノルマンディーへ行こう pic.twitter.com/2Mi1BKI0u2
— Tourisme japonais / トゥーリズム・ジャポネ (@tourismjaponais) 2018年8月12日 - 00:25
【公開日決定!】
— 映画『山中傳奇』 (@sanchudenki) 2018年8月13日 - 11:15
日本、劇場初公開!
4Kデジタル修復・完全全長版
キン・フー監督作品『山中傳奇』
2018年11月24日(土)新宿K's cinemaほか全国順次公開!
公式サイト➡️… twitter.com/i/web/status/1…
8月12日はサミュエル・フラー監督の誕生日。「ショック集団」がうちの地方でどんな風に封切られたかを古い新聞で調べたら・・成人映画三本立ての一本としてでした(これは予測していなかった)。当時、この三本立てを観た客はどんな感想を抱いた… twitter.com/i/web/status/1…
— peluzeus (@peluzeus) 2018年8月13日 - 07:49
ちば先生、中学生時代のマンガが、お友達がキレイに保存してらしたそうです。凄いですね。→ちばてつや『むかし描いた漫画が・・』
— 建築エコノミスト森山 (@mori_arch_econo) 2018年8月13日 - 14:41
⇒ ameblo.jp/chibatetsu/ent… #アメブロ @ameba_officialさんから
左利きの日らしいので過去の絶望をぺた
— 烏海(うかい) (@_ukai_) 2018年8月13日 - 11:11
役所においてある盗難防止の紐付きペンが短くて個人的に死にます
#左利きの日 pic.twitter.com/4I2qpeLeai
アントニ・プジョル(Antoni Pujol)による「死」(1914年)。スペイン、バルセロナにあるニコラウ・ジャンコサ(Nicolau Juncosa)の墓につくられた彫刻です。モンジュイック墓地(Montjuïc Cemete… twitter.com/i/web/status/1…
— 龍國竣/リュウゴク (@Ryuugoku) 2018年8月13日 - 17:38
以前に翻訳のノンフィクションの本で訳者後書きに「原書の最後にある膨大な量の参考文献は日本の読者は興味ないと思われるので削除した」という記述があって、ぶっ飛びました。その結果、研究等には使えない本になってました。本来、日本語の本でも… twitter.com/i/web/status/1…
— 石井晃 (@ishiiakira) 2018年8月11日 - 19:30
何を言いたいのかというと、都市下層民の中に天性の資質として内在している「正しいこと言う行為そのものに反発を抱く傾向」は、なかなか克服しがたいということです。
— 小田嶋隆 (@tako_ashi) 2018年8月13日 - 19:22
本日届いた本。月サンにこのドラマの出だしを語ったところ、ものすごい食いつき
— 井上純一(希有馬) (@KEUMAYA) 2018年8月13日 - 20:25
「No.1はいないデスカ?」「村の住人はいつも何してマスカ?」「村出る出来ないデスカ?」質問責めデスヨ。 pic.twitter.com/qdBDDKWbqV
女性のアルコール依存症がこの十年で二倍になったというニュースが小さく扱われ過ぎだ。増加原因を女性の社会進出や離婚増加など頓珍漢なものに求める記事もある。違うでしょう。酒造メーカーが女性を販売ターゲットにしてCMを乱発したことが最大の原因。女性は彼らにとって未開の沃野だったわけだ。
— 断酒応援bot (@letsdanshu) 2018年8月13日 - 20:30
「あなた個人の誤読で印象に残る語」を募ったところ、驚愕するほどの数の実例をお寄せいただきました。ありがとうございます。その中から、にやっとする例をまとめてご覧に入れます。 pic.twitter.com/dhfYyqy4fj
— 飯間浩明 (@IIMA_Hiroaki) 2016年8月9日 - 21:36
1958年ボリス・パステルナークがノーベル文学賞を辞退した時のコメント「ソ連のあらゆる組織から“我々は読んでないが作品を非難する”という論評と侮辱的な言葉を受けました。私の属する社会では賞の辞退は仕方ないのです、私の選択を尊重して… twitter.com/i/web/status/1…
— それでもソ連bot+ (@cccp2017) 2018年8月12日 - 20:09
スーザン・ソンタグも激プッシュしているので、インテリ層も観るといいです、原一男は絶対に。
— Chika (@Shinoticarf) 2018年8月11日 - 14:05
「驚嘆すべき日本の記録映画、原一男の『ゆきゆきて神軍』は、私の知る最も心に訴える映画である」
『他者の苦痛へのまなざし』より
マナー違反を注意された参加者が『俺が出した金でメシが食える派遣バイトスタッフが偉そうに指図するな!底辺の癖に!』と言って来る事が稀にあるが、それに『いえコミケスタッフは皆ボランティアスタッフです』と冷静に答えるスタッフが本業は弁護士や医師だったりするのがコミケスタッフの怖い所
— さの@ゆた改め【4-8(よのや)】 (@sanoyutaro) 2012年8月12日 - 16:51
ホテルのコインランドリー、100円玉がなく、両替しようと洗濯機の横にある自販機で、
— 神谷洵平 (@jumpeikamiya) 2018年8月12日 - 15:47
110円のクリスタルガイザーを買おうと1010円入れたところ、50円玉が18枚出て来ました。
ご静聴ありがとうございました。
1968 - On the set of "Once upon a time in the West", the director Sergio Leone is pictured while shooting on the s… twitter.com/i/web/status/1…
— Sergio Andreola (@sergioandreola) 2018年8月11日 - 17:30
昔の録画VHSより。ジュエリーマキCMのリー・トンプソン。 pic.twitter.com/GtWsxfLiPP
— クロケット (@crocket8314) 2018年8月11日 - 16:07
あと、「つくり手なんだから、つべこべ言わずに作品で見せてよ」って意見、わかるんだけど、わかるんだけどね。映画の感想くらい言ってもいいでしょうよ。映画監督である前に映画の観客なんだから。それに、たまたまつくってる、つくれてるだけで、そんなに映画監督は偉くないし特別じゃないです。
— 今泉力哉 (@_necoze_) 2018年8月11日 - 16:11
Babe Ruth and Gary Cooper on the set of "The Pride of the Yankees," which earned an incredible 11 Oscar nominations… twitter.com/i/web/status/1…
— Every Oscar Ever (@EveryOscarEver) 2018年8月11日 - 23:03
人間は変るもんだ。そのわりにニッポン社会は本質的にそれほど変わったとも見うけられない。人間と社会は別のものか?
— 殿山泰司 bot (@Taichanbot) 2018年8月12日 - 04:41
長年生きてきた木を大切にし欲しいです!
— 浅野忠信 ASANO TADANOBU (@asano_tadanobu) 2018年8月12日 - 00:15
御茶ノ水駅から延びる明大通りの街路樹プラタナスを伐採はしないで下さい
歩道を25cm広げるのはいいですが長年生きた木はそのまま守れる形で工事してください
ヒートアイランド緩和計画を実現させる… twitter.com/i/web/status/1…
「恐怖」 #eiga #映画 goo.gl/2fFdZr
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月12日 - 09:15
Gary Cooper and Babe Ruth #SummerUnderTheStars #PinstripePride #LetsGoYanks pic.twitter.com/KbeElvo709
— TCM (@tcm) 2018年8月12日 - 09:16
ところで、夏コミの度に、ビッグサイトの冷房がロクに効かない話出るけど、人間一人あたり200Wの熱量として計算するらしいので、東館に10万人いたとしたら2万kWの熱量か。原発2%分のエネルギーと考えると恐ろしいなみたいな事を昨日暑さにうなされて考えてた
— dragoner@日曜東U-17b (@dragoner_JP) 2018年8月11日 - 07:35
DVD化はされているがレンタル化されていない映画のリストを作りました。個人で調べた範囲なので全てを網羅しているわけではありませんが、洋邦合わせて約2000本ほど。近所のツタヤで見つからなかったあの映画が実はそもそもレンタル版が出て… twitter.com/i/web/status/1…
— 寂々兵 (@CinemaYouth3919) 2018年8月11日 - 19:27
#JohnCazale & #MerylStreep. pic.twitter.com/kyQzqoRaQC
— Albert Galera (@AlbertGalera) 2018年8月12日 - 14:55
ランボーに「母音」というソネットがある。「A は黒、E は白、 I は赤、U は緑、O はブルー 母音たちよ、何時の日か汝らの出生の秘密を語ろう」から始まる、母音から感じられる色を謳ったもの。この詩から、ランボーは共感覚者だった… twitter.com/i/web/status/1…
— 竹熊健太郎《地球人》 (@kentaro666) 2018年8月12日 - 14:09
@kentaro666 精神科医の中井久夫氏は語学の天才で翻訳家でもありますが、ドイツ語やフランス語など言語によって色彩感が違うと語っているそうです。
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月12日 - 16:23
無名時代の「エアロスミス」がツアーに使用、小型バンを森の中で発見 cnn.co.jp/showbiz/351239…
— cnn_co_jp (@cnn_co_jp) 2018年8月12日 - 15:27
ツイッターを始めてわかったのは、世の中には、舞台に上がって発言している人に対して、観客席からヤジを飛ばして喜んでる人もいるんだ、ということです。でもね、そこは観客席ではなく舞台なんですよ。舞台で「ヤジを飛ばして喜ぶ」という役をやっているわけです。どっちを選ぶかは自分次第ですね。
— 山口周 (@shu_yamaguchi) 2018年8月12日 - 07:21
準備された予定調和と直感に導かれた即興。有名なキング牧師のワシントンの演説は、準備してあったお堅い内容の原稿を脇にどけ、個人としての想いを即興で語ったものです。経営者も政治家も用意された原稿を読む人が多いけど、そんなもので人は動きません。みんな「自分の言葉」が聞きたいんです。
— 山口周 (@shu_yamaguchi) 2018年8月9日 - 20:24
昨日、仕事の関係で某キリスト教関係団体に電話し、
— OGAWA Kandai (@grossherzigkeit) 2018年8月12日 - 02:04
「あー、来週やっておられますか?」
「16日まで休みなんですよー」
「やっぱお盆で」
「そう、お盆で」
というやり取りをして普通に受話器を置いちゃったんだが、その後ハタと気づく。お盆って、皆さんクリスチャンなんですよね!?
私がとりわけ日本のナショナリズムに強く反対する理由の一つは、「何があっても同胞だけは助けよう」という意識さえもないこと。人質事件なんか特にそうだけど、この国の人間は"同胞"ですら冷たく切り捨てる。日本(人)にとってのナショナリズムなんてただの差別と被害者意識の正当化でしかない。
— 不勉強 (@egeLA5SLQPV55jo) 2018年8月11日 - 09:37
人質事件に限らずだけど、これほど日本社会に「被害者の落ち度探し」が染み付いている理由は、日本社会には「落ち度」があれば例えどれほど正当な理由があろうとバッシングを正当化できるという考えが根強いからじゃないかと思う。全く落ち度の無い人は少ないから、ほぼ確実に正当化できる。
— 不勉強 (@egeLA5SLQPV55jo) 2018年8月11日 - 21:53
9/24(月)~9/27(木)上映『セミドキュメント オカルトSEX』より
— シネロマン池袋 (@cineroman) 2018年8月12日 - 15:58
貴重な昭和の記録が随所に!!大橋巨泉とユリゲラー??? pic.twitter.com/JrsuzGvVy5
本日、18歳未満の女の子の団体を連れた大人の女性が18禁の同人誌を買われました。サークルの目の前で女の子に18禁の同人誌を渡していました。私たちサークル参加者も一般参加者も信頼のもとで頒布してします。大人ならルール守ってください。
— tt🥕2日目西い18b (@tt_osc) 2018年8月11日 - 17:24
後で注意しましたが常習してるようでした。
新刊が出たよ、という話をすると「読みたいけど文庫になるのを待ちます」とコメントされる方、いろいろ事情があると思うので理解はしますが、ただ単行本が売れなかったら文庫化しない、という事実があるとも念頭に置いていただければと。すべての本が文庫になるとは限らないのです。
— 太田忠司 (@tadashi_ohta) 2018年8月11日 - 14:02
8/21(火)より始まる「シネマ・エッセンシャル 2018」では、黒澤明監督の代表作4作品『羅生門』『蜘蛛巣城』『隠し砦の三悪人』『天国と地獄』を上映します。
— 【公式】国立映画アーカイブ 広報 (@NFAJ_PR) 2018年8月12日 - 17:00
展示室では黒澤作品の各国版ポスターを集めた「旅する黒澤明」展を開催中… twitter.com/i/web/status/1…
丸ごとそうだったのかー、と6月の記事で知る。いかにもな代理店発想。買える公園。買える地球。
— 町山広美 (@mcym163) 2018年8月12日 - 08:28
「地上フロアのコンセプトは『買える公園』。西畠清順がプロデュースする「アヲ GINZA TOKYO」では、パークに植えられた世界各地から… twitter.com/i/web/status/1…
Worldmapper は、国別の統計を、各国の面積を変えることにより視覚的に見せてくれるが、2005年に対する2015年の科学工学系の論文出版数の減少をプロットしたものは衝撃的。世界のほとんどは日本、あと見えるのはベラルーシとベ… twitter.com/i/web/status/1…
— Toshiyasu ICHIOKA (@itchy_jp) 2018年8月11日 - 22:59
新藤兼人さんが生前(18年前)私の行く末を心配して、新たに書き上げ預けてくださった玉稿「新ハチ公物語」来年、製作が決定!もし映画化出来ずあの世で会ったら怒られると思ってたから、これでやっと安心。
— 奥山和由 Okuyama Kazuyoshi (@teamokuyama2017) 2018年8月12日 - 10:22
墓参の帰りに池袋北口で食料をあさってたらこんなの見つけた。なんと日本製。残念ながらアヒル卵ではない。 pic.twitter.com/aRRqT2BqHK
— ヒロヲカ (@shirlywang) 2018年8月12日 - 15:33
日本の木材でやるんぢゃなかったんだっけ?
— ケロ爺 (@kero_jiji) 2018年8月11日 - 14:45
ボルネオ島…って事は三菱がらみかな…
↓
日本政府が東京五輪の木材使用でボルネオ島プナン族の生活権を脅かす人権侵害をして森林伐採、世界から14万通の反対署名… twitter.com/i/web/status/1…
韓国映画「タクシー運転手」のソンガンホのコスプレなるものをやっている人がいた pic.twitter.com/gfytzePsrm
— バリカタ煎餅 (@febc147227) 2018年8月12日 - 12:15
すさまじい。必読。
— 江口寿史 (@Eguchinn) 2018年8月12日 - 14:24
「なぜ高畑勲さんともう映画を作りたくなかったか」――鈴木敏夫が語る高畑勲 #1〜#3
bunshun.jp/articles/-/8406
舞台上でマイクが切れる件、断線など他にもいろいろ理由はあるみたいだけどそのほとんどが携帯電話による電波妨害だと聞きました。音響さんに怒ってるツイートを見かけたこともあるけど、それよりも携帯電話を切らない人に怒って。
— めん (@check12_12) 2018年8月10日 - 17:30
梅芸で観たメリーポピンズは大規模な舞台機構やそれに伴う無線機でのやりとりがとても多いという理由で客席では案内係さんたちが開演ギリギリまで必死にアナウンスを入れていました。それでも携帯を触り続ける人が多数。舞台を観に来たくせに舞台進行の邪魔をしないでほしい。
— めん (@check12_12) 2018年8月10日 - 17:30
フラスク・ブックボックスは本の形のケース入ったフラスクです。何のために隠すのかわからないですが不思議と憧れます。 #本の小物
— 愛書家日誌 (@aishokyo) 2018年8月11日 - 18:50
ow.ly/UrC0302z0eX pic.twitter.com/4UOR5athwN
…そんなわけで、コルティナでのオフショットと、フェリーニ、ヴィスコンティ、ブレイク・エドワーズとクラウディア。 pic.twitter.com/EiA9rXyx1B
— chuchubabe (@chuchu_babe) 2018年8月11日 - 01:03
ある旅館の一室で夫婦が心中をして、それからその部屋に落ち武者の亡霊が出るようになった。というわけのわからない理不尽な怪談が好きだ。
— 中野貴雄とギャルショッカーズ (@galshocker) 2018年8月11日 - 10:50
そういや昨日のコミケ、熱中症で動けなくなってる&動けはするけどフラフラで危ないの、私が見た限りは皆10代~20代半ばくらいの若い方ばかりで、「自分の体力はアテにならん」って自覚しだした年代は暑さ対策しっかりしてて元気だったので、なんか新兵とベテラン兵見てる気分だった
— 菊野郎@金曜L-24a (@kikuyarou) 2018年8月11日 - 08:59
これは嫌味のつもりだと思うが、実際に言われたヤツ。嫌味や皮肉のつもりでも、非常にセンスと人間性が悪い。 pic.twitter.com/2VHDfqO89N
— 清水文化@Kindle版気象精霊記発売中 (@Fumika_Shimizu) 2018年8月11日 - 08:12
Falling bookshelf. pic.twitter.com/ajTeNEijim
— History Lovers Club (@historylvrsclub) 2018年8月10日 - 23:11
スーパー8版のエクタクロームのサンプルが世界各国に届き始めてるよ!どうやら9月にコダック公式な発表がありそうですよ。21世紀に新発売のカラーリバーサルのマジ純正の映画用フィルム。発売された楽しみ尽くしましょ! pic.twitter.com/FGdaOgrNKa
— マディ折原 (@muddy_orihara) 2018年8月11日 - 14:06
【資料の整理】まだ渋谷にあった頃の天井桟敷。喫茶部のマッチ。行った日は芝居はやってなくて、確かお茶だけ飲んで帰った。 pic.twitter.com/NPmJp7LIsd
— 村上 知彦 (@murakami_gya) 2018年8月11日 - 03:24
カメラを持って踏み込む権利が、ドキュメンタリーの作り手にあるのかどうか⁉️
— 原一男 (@kazu19451) 2018年8月10日 - 05:11
難しい問題です。
時と場所、相手によりけり!
としか言いようがないでしょうね。
それと激しい自己葛藤と❗️
もうひとつ、奥崎謙三がいつも言うように、独居房… twitter.com/i/web/status/1…
Jean Renoir, Ingrid Bergman and Roberto Rossellini. pic.twitter.com/8RBmO8TutU
— Juan Ferrer (@JuanFerrerVila) 2018年8月9日 - 23:54
Rock Hudson, Cary Grant, Marlon Brando and Gregory Peck (1962). pic.twitter.com/l4fZYxWr5i
— Juan Ferrer (@JuanFerrerVila) 2018年8月11日 - 01:32
業界のジョークで「グレーディング(色調整)をLAでやるとヴィヴィッドに、NYでやるとグレイッシュに、そしてロンドンでやると色がなくなる」と言うのがあるそうですが笑、場所によって違いが出るのは確かで、LAのラボは人の顔をものすごく赤… twitter.com/i/web/status/1…
— シネフィルDVD (@cinefilDVD) 2018年8月11日 - 17:08
『オーシャンズ8』観た。女性8人が主役なのは言うまでもなく最高なのだが、8人の女性全員が声低いってのが私的にとてもエンパワメントされた。世界で一番声の高い女性の国だからな、ここは。 pic.twitter.com/reNSgddSYI
— 涅槃 (@xrayspex7) 2018年8月11日 - 17:09
ビックカメラでえんえん流れている自分でパソコン設定できないという設定の女の子のやたら高い甘ったるい声、なんだろうね。いったん引っかかると、声も内容もどうも耳障りでいけない。
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月11日 - 23:29
「医学部に入っても離職するからケシカラン」「医療現場で役に立たない」「外科を嫌がる」とか騒ぐ人たちは、まずこういう人たちに石を投げるんですよね。
— KAMEI Nobutaka (@jinrui_nikki) 2018年8月11日 - 22:09
手塚治虫=医師にならない
安部公房=医師にならない
渡辺淳一=医師をやめる
山中伸弥=外科医療の現場で役に立たない
柵がとれたという話を聞いたので、私も銀座ソニーパーク見てきました。植栽じゃないんですね。
— ラビット (@plantperformer) 2018年8月2日 - 06:58
見事に全てワイヤーで固定されてました。
この植物たちも売り物になるのかしらねぇ。 #世界一のクリスマスツリー pic.twitter.com/NyVXQ6dZhd
酷いな、この偽物感。ドヤ植栽っつーか、大阪マルビル安藤造花緑化に続いて、なんて嘘っぱちな連中なんだ、ここのデザイナーは。 twitter.com/plantperformer…
— 建築エコノミスト森山 (@mori_arch_econo) 2018年8月11日 - 21:11
ミラーズ・クロッシング
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月11日 - 23:49
#帽子の日 pic.twitter.com/1LLD3OWVB7
これ重要!
— 書記長社労士 (@hisap_surfrider) 2018年8月10日 - 23:31
#厚生労働省 平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表します
mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=…
大島渚デビュー作「愛と希望の街」
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月11日 - 01:02
#鳩の日
元のタイトルは「鳩を売る少年」 pic.twitter.com/s1M3Pnh7UO
妻が手間暇かけて作ってくれた麻婆豆腐の様子が何かおかしい🤔 pic.twitter.com/JTVO3aMaeh
— 井上 恭輔 (きょろ) (@kyoro353) 2018年8月10日 - 15:45
フリードキン『恐怖の報酬』、カウフマン『SF/ボディ・スナッチャー』、カーペンター『遊星からの物体X』、シュレイダー『キャット・ピープル』、デ・パルマ『スカーフェイス』。いずれも伝説的作品のリメイクで、公開時には批判か無視かが相場… twitter.com/i/web/status/1…
— watabe gen (@geeen80) 2018年8月10日 - 09:39
ハウルがベーコンエッグを作るシーンの原画を担当したのは田中敦子さん。宮崎監督や高畑監督の作品で印象的な食のシーンを担当してきており、「カリオストロの城」のスパゲティ争奪、「死の翼アルバトロス」のすき焼き、「じゃりン子チエ」のお好み… twitter.com/i/web/status/1…
— キャッスル (@castle_gtm) 2018年8月10日 - 21:39
「グッバイ・ゴダール!」 #eiga #映画 goo.gl/S9Z3FC
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月11日 - 09:42
こんなバカが日本中で跋扈している。溶解処分! 理由は「毎日の出来事や感想を個人的に書き留めたもの。職務ではなく行政文書に当たらない」。のうのうとこんな理由を垂れられること自体バカの上塗りだろ。
— 北丸雄二 (@quitamarco) 2018年8月11日 - 01:40
▼富士山測候所:日誌を廃棄 68年間… twitter.com/i/web/status/1…
フォールアウトのトム・クルーズ超スカイダイビング
— Whatfat hachi (@whatfathachi) 2018年8月11日 - 06:33
上空7~9km 落下時速265~320キロのジャンプを撮影のためトータル106回
朝1回、昼3 夕暮れ1回等 一日5回越えるジャンプ
(こういう毎日なので)
サイモン・ペグ
「トム… twitter.com/i/web/status/1…
ジップロックは「1枚を裏返しにして繋ぎ合わせると、サイズが倍になる!」なるほどすごい。思いつかなかった。/これは知っておくべき…ジップロックを2枚組み合わせると飛躍的に便利になる labaq.com/archives/51899… pic.twitter.com/J6GJQNIadV
— ヤギの人(お盆) (@yusai00) 2018年8月9日 - 13:17
1972年当時、アイドル女優だったジェニー アガターのグラビアに付けられたキャプション。 pic.twitter.com/HIdwSDpZ6C
— 三一十四四二三 (@31104423) 2018年8月11日 - 10:05
マリモちゃん と テトラちゃんは、同じ意味です。 pic.twitter.com/NSC31DvCHh
— 三一十四四二三 (@31104423) 2018年8月11日 - 10:05
こちらも。東京五輪のスタジアム建設に使う木材。安価調達のためペナンやマレーシアの先住民の権利侵害してまで伐採され、ドイツやスイスの日本大使館に14万人の非難署名が送られる。本件、今日まで日本の大メディアは報道しない悲劇。#オプエド dezeen.com/2017/05/12/jap…
— Naoyoshi Suzuki/鈴木 尚栄 (@naoyoshi_suzuki) 2017年8月2日 - 17:40
1942年8月11日は女優のヘディ・ラマーがホッピングスペクトルラム拡散の特許を取得した日。その原理は後に携帯電話やGPS、無線LANなどで応用、2014年に功績を讃えられ「全米発明家殿堂」入り。画像は彼女のハリウッドデビュー作『… twitter.com/i/web/status/1…
— ♡ Mimi . (@__Mimi_0929__) 2018年8月11日 - 09:51
かつてのサマータイムを実体験した小林信彦さんのコラムより。「日本人の生活感覚と相容れないことは、”往年の4年間の人体実験”によって身にしみている」とも。サマータイム、絶対に無理。
— Tad (@CybershotTad) 2018年8月9日 - 19:12
『最良の日、最悪の日』(小林信彦 著 2000年刊) pic.twitter.com/tKMxdhtfR0
Nice 😃 pic.twitter.com/ku6OoS85Op
— Gaml .y (@m_yosry2012) 2018年8月11日 - 03:23
弁護士一年目で意外だったのが、借金だらけと言いつつ頑なに倒産しない会社、突然辞任する弁護士、突然に自殺する依頼者、着手金を返せという依頼者、無料相談を回る相談者、条文を知らない弁護士、判決を書かない裁判官、裁判官気取りの書記官。修習生の時は綺麗な案件だけ見せられていたと実感。
— ワーキングプア弁護士 (@sokudokubengosi) 2018年8月10日 - 16:57
医師である夫が不貞をした案件よく来るけど、今のところ俺が担当した全てのケースで妻は夫に離婚を求めず不貞相手の女に慰謝料請求をするだけで終わっており、医師の立場の強さに日々感嘆している。 twitter.com/tomyuo/status/…
— ystk (@lawkus) 2018年8月6日 - 14:43
「中高生の熱中症による死亡の4人に1人が野球部員」
— 城之内 みな (@minajyounouchi) 2018年8月10日 - 08:08
こういうデータがあるのに、真夏に連日、高校野球を中継するテレビ局や新聞社。 pic.twitter.com/PRfJDOIKqE
エイドリアン・ブロディ先生が石川の旅館でゆるキャラと写真撮ってるなうらしいんだが…………ゆるゆるすぎない???本当に今日本にいるのかな……
— マホコ (@m0425_0424) 2018年8月10日 - 20:41
instagram.com/p/BmS7ROMn_v0/… pic.twitter.com/gngxci6LYv
伏見稲荷でこんなのしてるブロディ先生、ヤバくないか???????「コンニチワ、オヤスミナサイ」って(脳内思考停止) pic.twitter.com/licU8gFXck
— マホコ (@m0425_0424) 2018年8月10日 - 20:44
御成座さんでの『バーフバリ』マサラ上映会、第一部が終わったのですが、皆さんの盛り上がりが想像の遥か上をいっていた‼!
— ☆しぇりー☆ (@Useira) 2018年8月11日 - 13:54
紙吹雪の量が半端ないのね(≧▽≦) pic.twitter.com/U0G3SOFUmI
作り手の才気は素晴らしい。問題は、彼らを大きいフィールドに導いていけるプロデューサーがいるかという話で。映画でも音楽でも、いきなり大きい舞台に立たされて自滅してく人がけっこういる。日本の業界に欠落しているのは、力と懐のあるプロデューサー。
— 一色伸幸 (@nobuyukiisshiki) 2018年8月10日 - 19:03
まず第一が和泉雅子。瓜ざね顔のいい顔していたね。日活一の美形だ、と僕は思っていた。これで色気がついたらたいした女優になると思って、先を楽しみにしていたら、ある日突然真っ黒に日焼けし、顔のふくれた彼女がテレビに出てきてびっくりした。
— 鈴木清順bot (@seijun_bot) 2018年8月11日 - 14:39
カメラを止めるな!の低予算ぶりが話題になってるが、むしろ基本的には「企画内容に対し必要な予算が確保できてないと失敗する」方が普通であることは認識しておきたい pic.twitter.com/CbdXMVWtXC
— まぐれもの (@maGuremono) 2018年8月11日 - 09:15
ガザについての秀逸なルポ。特派員やフリー記者が書いたものではなくMSFの看護師が見たガザだ。悲惨さや子供の笑顔、侵攻などばかり書く記者たち。だがそのどれもが、このルポほどにガザの苦難の本質を描いてはいない。「ガザの外はどうなってる… twitter.com/i/web/status/1…
— Ryoji Fujiwara (@JP_Fujiwara) 2018年8月11日 - 13:31
《ラドン》1956 pic.twitter.com/vLBfbJWJHL
— BON (@1632bdkrst) 2018年8月11日 - 03:22
警備員人件費上がり、花火上がらず…中止相次ぐ
— うみ@喪中 (@umi_tweet) 2018年8月10日 - 21:20
yomiuri.co.jp/national/20180…
× 各地で警備員の人件費が高騰し、花火大会が中止に追い込まれるケースが相次いでいる
○ 予算不足の花火大会が中止になった。必要な経費を用… twitter.com/i/web/status/1…
昨日の撤去にもめげず、今日も立て看出ています!
— 立て看文化を愛する市民の会 (@tatekan_bunka) 2018年8月10日 - 14:41
#京大オープンキャンパス2018 pic.twitter.com/L3i3u3gMwe
主にアメリカ映画の脚本所蔵サイト。HPで無料で脚本が読める。正確にスペルを打ち込まないと検索できず。私が読んだ脚本はどれも完成作品と異なるシーンも多く興味深し。タクシードライバーは完成作品とスクリプトの重要シーン比較動画がついてい… twitter.com/i/web/status/1…
— 石井岳龍 exSOGO ISHII (@ishii_gakuryu) 2018年8月11日 - 11:18
”戦争プロパガンダには、「『敵』がまず先に攻撃を仕掛けてきたということにすれば、国民に参戦の必要性を説得するのにそれほど時間はかからない」という法則がある。”
— 科学に佇むサンクコスト (@endBooks) 2016年7月22日 - 23:36
📘 sciencebook.blog110.fc2.com/blog-entry-226…
🌐💥『戦争プロパガンダ10の法則』アンヌ・モレリ
中国大陸約6000スクリーンで公開した「万引き家族」が興行成績4860万元(約7億9000万円)を記録、今年公開の日本映画で首位に。「きれいだけど集客につながるとは思えない」てなリプもあったポスターの底力が証明されたようで、それも… twitter.com/i/web/status/1…
— junkTokyo (@junktokyo) 2018年8月7日 - 00:26
「キングスマン:ゴールデン・サークル」の別バージョン。美しい pic.twitter.com/XnxxBPdAJH
— junkTokyo (@junktokyo) 2018年7月29日 - 06:44
#トレマーズ
— 滝番晟 (@takibansei7) 2018年8月9日 - 22:43
シリーズ相関図っぽいもの 改訂 (1~4まで)
はやく ケビン・ベーコン復活の新シリーズが観たいぞ! pic.twitter.com/NtHq3FuKJp
#阪急の日なので阪急の写真を貼る
— ncc1701 (@ncc170116) 2018年8月9日 - 23:02
この場所を潰した阪急百貨店は取り返しのつかないことをした、と今でも思っている。 pic.twitter.com/i1k8i7J5UT
努力は裏切らないらしいんですけど、私が努力を裏切るんですよね。
— 浜ロン (@hamaron_nikki) 2018年8月9日 - 12:35
コミケ会場前のローソン見てきたけど
— りくと (@rd_KU39d) 2018年8月9日 - 08:58
気合いの入れ方凄まじすぎ pic.twitter.com/ECRDCxAxg7
今年は蚊取り線香の切手があるんですねー。丸くてかわいい! pic.twitter.com/A9YgYfQzF9
— 山﨑 理 (@yamazaki_design) 2018年8月9日 - 17:10
@yamazaki_design 外からすみません💧私の所には扇風機が届きました!いろいろあるんですね( ᵕᴗᵕ ) pic.twitter.com/h5MvBQgH0N
— きなこ (@klm_knc) 2018年8月9日 - 23:05
@otakulawyer ドナルド・トランプがアメリカ大統領になり、ベネッセが大学入試テストやって、アムウェイが教員研修担当する時代が来るって、10年前の近未来SFなら「もう少し現実的な設定にせよ」って言われたろうけど、まさか現実に!
— ウラサキ (@hirotourasaki) 2018年8月10日 - 14:17
サマータイム導入を実現するには
— 温故知新 (@marinosuzu1) 2018年8月6日 - 09:29
保育園に子供預ける体制が必要になるわけだ
保育園が7時開くのが一般的の中で、2時間前倒しで5時に開ける必要がある。
保育士の早番は事前準備考えると、
少なくも3時30分には園につかないといけない… twitter.com/i/web/status/1…
2000年問題の時に、あちこちで、かなりヤバイ案件があって、対応に追われた。年末年始を挟んで寝ずの番で待機もした。幸い、大きな障害は起きなかったのだが、案の定、
— タクラミックス (@takuramix) 2018年8月9日 - 11:05
「大騒ぎしたのに大した事なかった。あれはIT業界が金儲けのネタにした… twitter.com/i/web/status/1…
トーキー映画は沈黙を発明した。
— Robert Bresson (@Robert_Bresson) 2018年8月9日 - 18:31
「Yの悲劇」のハッター一家というのも狂気のイメージをまとわせたネーミングということになります。 twitter.com/endBooks/statu…
— 家畜人六号【小暮 宏】 (@yapoono6) 2018年8月10日 - 20:23
友人の子供が通う日本の小学校は、夏休みの炎天下に保護者が校庭の草むしりをする行事があり、去年は回転ノコギリを手に参加したら「根が残るでしょ!」と怒られたらしい。で、今年は台湾と中国の保護者一同でこのマシン片手に1時間で根こそぎ取り… twitter.com/i/web/status/1…
— 台湾人 (@Taiwanjin) 2018年8月10日 - 11:05
日本でもよく知られるジョージアの画家ニコ・ピロスマニ画集
— ロシア・東欧の美術書イスクーストバ (@iskusstvo_shop) 2018年8月10日 - 20:34
「私の絵をグルジアに飾る必要はない。なぜならピロスマニがいるからだ」
パブロ・ピカソがこう語ったことでも知られるジョージアの偉大な画家ピロスマニ。彼はその数奇な人生の中で1… twitter.com/i/web/status/1…
◆富士山測候所:日誌を廃棄 68年間つづった貴重な40冊
— 盛田隆二 (@product1954) 2018年8月10日 - 10:31
mainichi.jp/articles/20180…
気象観測のほか、空襲など太平洋戦争も記録した第一級の歴史資料が失われた。
担当者は「庁舎内のスペースは有限で、必要ないものを… twitter.com/i/web/status/1…
本日8月10日は『未来惑星ザルドス』公開記念日!
— 図解博士_7/20発売 高速バスター ミナル (@skull_bear) 2018年8月10日 - 09:31
最近でも、こんな気骨のあるコスプレが⁈
#ザルドス #未来惑星ザルドス #今日は何の日 pic.twitter.com/6OcIlfUmGB
今日はピロスマニマッチを発見、まとめ買いした。お土産にぴったりじゃないか?ピロスマニ以外にもパラジャノフ、現ジョージアンバンク本店の建築などのマッチも!
— Siontak (@siontak) 2018年8月9日 - 21:06
1個50円弱。 pic.twitter.com/IdjaZRcR1A
八月納涼歌舞伎初日です。香川照之、Twitterを始めました!
— 香川照之 (@_teruyukikagawa) 2018年8月9日 - 21:48
息子に背を抜かれたご報告から。 pic.twitter.com/KRHcIccWSE
@henrich そもそも、みんな国内のことしか議論してないけど。
— としの@事務員ドールP (@toshi_noP) 2018年8月10日 - 15:38
誰かが言ってた>>>海外から日本を見た時のシステムの改修って、誰が金出してだれの責任でやるんだよ!
飛行機とか船舶とか+9:00だけじゃ済まなくなる時点で、どう… twitter.com/i/web/status/1…
これは以前からとても気になっていること。英米で出版されるノンフィクションの場合、根拠を示す引用は不可欠であり、何十ページにもなることも。だが日本では「読者が読みにくくなる」という理由で削除されることが多い。ヘイト本やトンデモ医学本… twitter.com/i/web/status/1…
— 渡辺由佳里 YukariWatanabe (@YukariWatanabe) 2018年8月10日 - 20:04