3時間18分という長尺の割に、ストーリーの波乱といったものはあまりない。
必ずしも悪意がなくても「持てる側」に立った主人公が、「持たざる者」にそれなりに良心の呵責めいた感情を抱きながらかといって何ができるわけでもなく、若く美しい妻(これだけでも傍からは羨まれる)が寄付活動に熱心なのをいかにも世間知らずをたしなめるように(言われる側からすると相当にカチンと来るのがはっきりわかる)上から目線で諭す一方で、そういった自分でも薄々気づいているイヤなところを、出戻りの妹がややもう一人の自分的な視点からちくちく指摘してくるのにまた苛立つ、といったなかなか解きようのない感情のもつれを丹念に大量のセリフとともに描いていく。
トルコというと第三世界(死語かな)という印象が強いが、その中でインテリで経済的に恵まれている層が社会はどうあるべきかといった大きなビジョンを示せず誰が読んでいるのかもわからない地方紙に傍観者的なコラムを寄稿することで自己満足に浸っている、というか浸りたくても冷めてしまっているのが今日的。
カッパドキアの洞窟をそのまま宿泊施設にしている奇観と日常性の両立した設定がおもしろい。内装も贅沢ではないがすこぶる趣味がいい。衛星アンテナがごく貧しい家にもついているのだが、日本でいう地上波テレビというのはないのだろうか。
主人公が引退して物書きをしている元役者というあたりはちょっとタルコフスキーの「サクリファイス」ばり。冒頭から犬や馬といった動物が神話的な登場するあたりも似ている。
つい先日亡くなったオマー・シャリフが映画のロケに来た記念写真の中に登場。「イブラヒムおじさんとイスラムの花たち」というタイトルのうちイスラムという後半を言いよどむ。イスラムの導師なのに傷害でムショから戻ってきてから仕事にもついていない男や、やはり導師なのに卑屈さと狡さと図々しさを使い分けるその弟などイライラさせられるキャラクターが登場し、イスラムあるいは宗教全般が何の役に立っているのかといった疑問を主人公が持っているのがはっきりわかるが、正面切って批判するところまではいけないのがこの主人公の中途半端なところ。
セリフはドラマチックな対立や心理描写とか説明ではなくいかにすれ違うかに使われている感があって、そのあたりがチェーホフをヒントにしたところなのだろう。もう対話がえんえんと続くのだが、会話の方向とダイナニズムではなく、どこまで続くかといったサスペンス自体で見せていく。冒頭から頻繁に鏡を画面に入れて、視線や立場のずれを具体的に形にしている。
面白おかしいといった映画ではないが、重量感と格調で長尺を見せきる。
ひょっこり日本人が宿泊客として顔を見せるが、これがまたワサビは子供の時嫌いだったけれど今は好きといった見事なくらい表面的な会話しか交わさない。日本人を揶揄しているというより、全体の会話のすれ違いっぷりシンボリックな表現に思える。
(☆☆☆★★★)

本ホームページ
公式ホームページ
雪の轍(わだち)@ぴあ映画生活
映画『雪の轍』 - シネマトゥデイ










 家畜人六号【小暮 宏】 @yapoono6
家畜人六号【小暮 宏】 @yapoono6

 実際に言われたクレーム晒す @iwareta_claim
実際に言われたクレーム晒す @iwareta_claim パソコンの神様 @unsuitan
パソコンの神様 @unsuitan
 堤未果 @TsutsumiMika
堤未果 @TsutsumiMika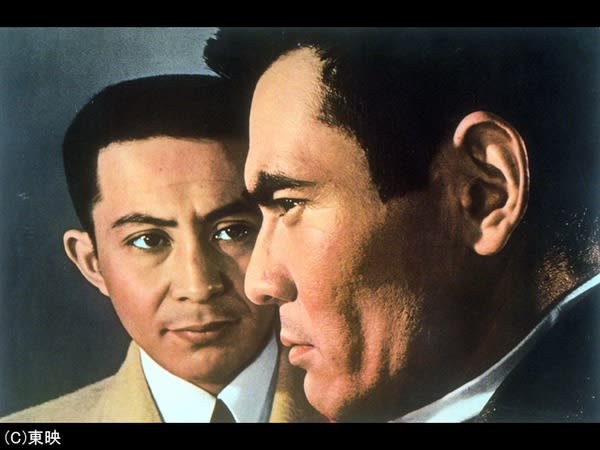

 次郎左衛門 @jirosaemon
次郎左衛門 @jirosaemon
 bubbles-goto @bubblesgoto
bubbles-goto @bubblesgoto
 吉田光雄 @WORLDJAPAN
吉田光雄 @WORLDJAPAN 山本弘(金)東サ-19a @hirorin0015
山本弘(金)東サ-19a @hirorin0015

 会田誠 @makotoaida
会田誠 @makotoaida
 殿山泰司 bot @Taichanbot
殿山泰司 bot @Taichanbot Shoichi_A @Aru29s
Shoichi_A @Aru29s

 E1E1 @e1e1e1e1
E1E1 @e1e1e1e1 佐々木浩久 @hirobay1998
佐々木浩久 @hirobay1998 漆原 健 @urushiharaken1
漆原 健 @urushiharaken1 Tetsuya Kawamoto @xxcalmo
Tetsuya Kawamoto @xxcalmo

 toshi fujiwara/藤原敏史 @toshi_fujiwara
toshi fujiwara/藤原敏史 @toshi_fujiwara
 ñenent @ex_crosstalk
ñenent @ex_crosstalk
 佐々木俊尚 @sasakitoshinao
佐々木俊尚 @sasakitoshinao 想田和弘 @KazuhiroSoda
想田和弘 @KazuhiroSoda ( ^ω^)内藤ライフ 夏コミ一般参加爺 @funky4_U
( ^ω^)内藤ライフ 夏コミ一般参加爺 @funky4_U
 土屋アソビ @wtbw
土屋アソビ @wtbw
 菅野完 @noiehoie
菅野完 @noiehoie
 あなぐらむ(ARROW) @G08U26N
あなぐらむ(ARROW) @G08U26N
 カラパイア @karapaia
カラパイア @karapaia







 @Paraisosaikuda
@Paraisosaikuda


 八郎 @88Chicken8888
八郎 @88Chicken8888


 鈴木智彦 TOMOHIKO SUZUKI @yonakiishi
鈴木智彦 TOMOHIKO SUZUKI @yonakiishi litera @litera_web
litera @litera_web