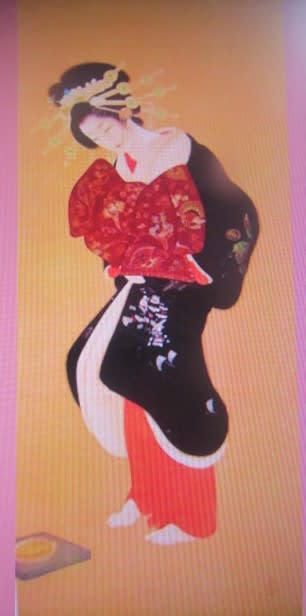おはようございます。
鏑木清方記念美術館のお正月展示には欠かせない名作といえば”ためさるる日”でしょうか。今年も”ご出演”されていました。長崎丸山の遊女の、正月恒例の宗門改めの行事を題材として描いたもの。

宗門改めとは踏絵のこと。江戸時代にキリシタンでない証として聖画像などを踏ませた行事。清方が描いたのは、初期の弾圧が厳しい頃ではなく、年中行事化した後の長崎の丸山遊女の踏絵。馴染みの客から遊女たちに贈られる衣装は”踏絵衣装”と呼ばれ、次第にその艶を競うようになったようだ。
どこに踏み絵?実は、対幅で制作され、これは、右幅の踏絵を待つ遊女。左幅の踏み絵する遊女を描いた絵は一度、どこかで見たことがあるはずと、マイブログ記事を、サントリー、千葉市美、平塚市美の清方展などを辿ってみたが、見当たらない。清方記念館で下図を見たのか?所蔵先も不明。あるいは福富コレクションかも。築地明石町みたいに突如の出現を楽しみに待とう。是非、左右、並べたのを見て見たいものだ。
画像だけはネットで手に入れた。↓
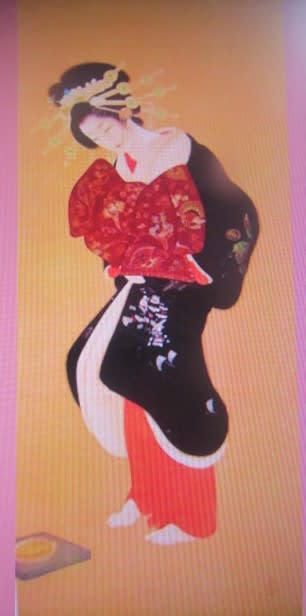
大正7年(1918年)に上野の竹之台陳列館(現在の都美の近く)での第12回文部省美術展覧会に出品したが、右幅の踏絵を待つ遊女がかえって主題を弱くすると考え、左幅のみを出品。この作品で清方は文展推薦(永久無鑑査)となった。また、裕仁親王(後の昭和天皇)が文展に来られた際には、遊女が主題となっていることから取り外されたとのこと(笑)。
ついでながら、先日、東博で見てきた板踏み絵。
板踏み絵 聖母子像(ロザリオの聖母)

ほかに、華やぐ春、よろこぶ春/明治・大正・昭和の正月のテーマで、恒例の、清方の《明治風俗十二ケ月》をもとに名押絵師・永井周山が意匠化した羽子板や、双六、お正月関連の挿絵が展示されていた。もう正月展示は終了で、しばらく、3月12日までコロナではなく、工事のため休館とのこと。
押絵羽子板

餅むしろ

小ゆき

初夢

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!