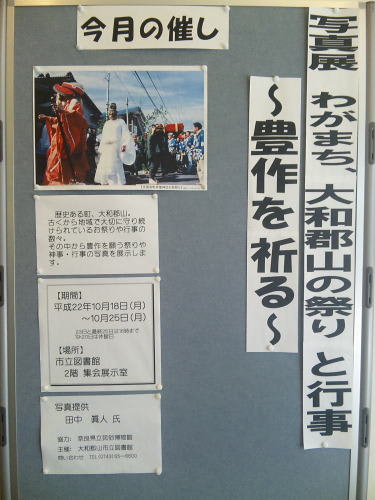奈良市写真美術館へは車で行くことが多い。
電車とバスで行ってみたらどうかとダイヤを調べてみた。
JR奈良駅から市内循環をしているバンビーナバスがある。
それほど多くない本数だ。
歩くにはほど遠い美術館。
それならば、と自転車で行くことにした。
ぶらぶらペダルをこいで高畑町を目指した。
里山に近づけば坂道。少しは力が入る。
あっちを見たり、こっちの横道へ。
ポタポタのポタリング走行だ。
白毫寺町までやってきた。
観光で散策する人らも居る。
西勝寺を通りがかったときに目に入ったポスター。
その中の文字が・・・。
「尼講」とある。
ある地域ではおばあちゃん講とも呼ばれている尼講。
おそらく観音講ではないだろうか。
気にかかる。
そのお寺の隣が宅(たく)春日神社で、近年に造宮された。
こちらも気になる存在だ。
それはともかく目的地はもうすぐだ。
新薬師寺へ向かう団体は修学旅行生たち。
ガイドに連れられて入っていった。
それにつられて・・・ではなく奈良市写真美術館へ。

ところが駐輪場がない。
仕方なく館の人にお願いして停めさせてもらった。
館は臨時休館。
それもそのはず明日からの入江泰吉賞に選ばれた作品の展示会の内覧会なのだ。
その内覧会の前には誉れある授賞式。
写友の野本氏が日経新聞社賞に選ばれた。
氏からご招待を受けてやってきた賑やかしの一人はYクラブのM氏、ならかん氏、あお氏に著名なS氏らと合流した。
彼らは記録係。バシャバシャとシャッターをきる。
穏やかないつもの表情と違った野本氏。
こういう席はさすがに緊張されているのだろう。
講評によれば応募された作品は225数だが写真点数はその6倍。
30枚の組写真となれば、なんとほぼ6000枚の「平城遷都1300年記念・・・あなたが伝えたいもの、残したいもの、まもりたいもの」の写真群だ。
審査委員長は話す。とてつもない審査作業だったと。

聞くところによれば奈良はあまり知らないそうだ。
それがゆえ新鮮な目線で選ばれる。
結果は大和をこだわり続けてきた入江作品とはかけ離れた傾向の作品が選ばれたように思えると内覧会を見終えた写友たちは話す。
模倣ではなく斬新なカメラアイで捉えたその人の心が写真に表現される。
ということではないだろうか。
コンテスト目的ではない長年に亘って大和を撮り続けてきた労作の情景作品。
なかでも私は「祭火まんだら」が秀逸だと思う。
HPで公開(数点は初公開)されたときから見ている作品はどれをとっても圧倒される。
しかし今回の入江泰吉賞は30点の組写真。
テーマがものをいう。
しかもどれをとってもハズレがないことだ。
それだけの枚数を高いレベルで維持するにはそうとうな腕がいる。
もうひとつは並べ方にストーリーが要る。
起承転結の物語り。
イントロから転回を経てエピローグへ。
それは静かに幕を閉じていく大峰山。
写真は戸開式だが・・・。
合間は雰囲気が替わって十津川村の山の情景。
火という物体が躍動し胎内リズムを奏でるように・・・。
次回作はギラギラ感を落としてソフトムードでいかがでしょうか、なんてことを小さな声で・・・思ったのであります。
なお受賞作品の著作権が作者に帰属するっていうのがなによりの賞であります。
(H22.11.19 SB932SH撮影)
電車とバスで行ってみたらどうかとダイヤを調べてみた。
JR奈良駅から市内循環をしているバンビーナバスがある。
それほど多くない本数だ。
歩くにはほど遠い美術館。
それならば、と自転車で行くことにした。
ぶらぶらペダルをこいで高畑町を目指した。
里山に近づけば坂道。少しは力が入る。
あっちを見たり、こっちの横道へ。
ポタポタのポタリング走行だ。
白毫寺町までやってきた。
観光で散策する人らも居る。
西勝寺を通りがかったときに目に入ったポスター。
その中の文字が・・・。
「尼講」とある。
ある地域ではおばあちゃん講とも呼ばれている尼講。
おそらく観音講ではないだろうか。
気にかかる。
そのお寺の隣が宅(たく)春日神社で、近年に造宮された。
こちらも気になる存在だ。
それはともかく目的地はもうすぐだ。
新薬師寺へ向かう団体は修学旅行生たち。
ガイドに連れられて入っていった。
それにつられて・・・ではなく奈良市写真美術館へ。

ところが駐輪場がない。
仕方なく館の人にお願いして停めさせてもらった。
館は臨時休館。
それもそのはず明日からの入江泰吉賞に選ばれた作品の展示会の内覧会なのだ。
その内覧会の前には誉れある授賞式。
写友の野本氏が日経新聞社賞に選ばれた。
氏からご招待を受けてやってきた賑やかしの一人はYクラブのM氏、ならかん氏、あお氏に著名なS氏らと合流した。
彼らは記録係。バシャバシャとシャッターをきる。
穏やかないつもの表情と違った野本氏。
こういう席はさすがに緊張されているのだろう。
講評によれば応募された作品は225数だが写真点数はその6倍。
30枚の組写真となれば、なんとほぼ6000枚の「平城遷都1300年記念・・・あなたが伝えたいもの、残したいもの、まもりたいもの」の写真群だ。
審査委員長は話す。とてつもない審査作業だったと。

聞くところによれば奈良はあまり知らないそうだ。
それがゆえ新鮮な目線で選ばれる。
結果は大和をこだわり続けてきた入江作品とはかけ離れた傾向の作品が選ばれたように思えると内覧会を見終えた写友たちは話す。
模倣ではなく斬新なカメラアイで捉えたその人の心が写真に表現される。
ということではないだろうか。
コンテスト目的ではない長年に亘って大和を撮り続けてきた労作の情景作品。
なかでも私は「祭火まんだら」が秀逸だと思う。
HPで公開(数点は初公開)されたときから見ている作品はどれをとっても圧倒される。
しかし今回の入江泰吉賞は30点の組写真。
テーマがものをいう。
しかもどれをとってもハズレがないことだ。
それだけの枚数を高いレベルで維持するにはそうとうな腕がいる。
もうひとつは並べ方にストーリーが要る。
起承転結の物語り。
イントロから転回を経てエピローグへ。
それは静かに幕を閉じていく大峰山。
写真は戸開式だが・・・。
合間は雰囲気が替わって十津川村の山の情景。
火という物体が躍動し胎内リズムを奏でるように・・・。
次回作はギラギラ感を落としてソフトムードでいかがでしょうか、なんてことを小さな声で・・・思ったのであります。
なお受賞作品の著作権が作者に帰属するっていうのがなによりの賞であります。
(H22.11.19 SB932SH撮影)