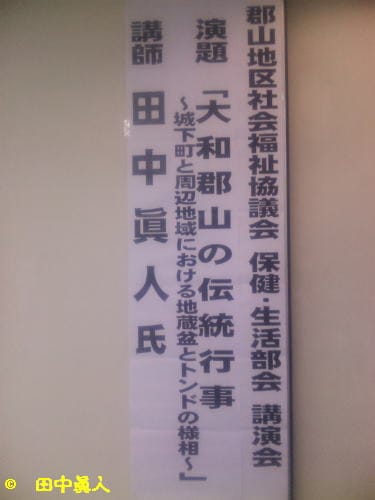山添村毛原の長久寺で涅槃会が行われるのを知ったのはいつだっただろうか。
思い出せない。
子供がお寺の本堂に上がって掲げた涅槃図に手を合わせる。
法要を済ませた子供たちは構造改善センターでカレーライスをよばれる。
今ではそうしているがかつては米を集めに集落を巡っていたという話しを聞いていた。
最初に訪れたのは平成22年2月21日だった。
村人がいうには「子供の涅槃は15日に近い土曜辺りに行われている。本来は中学三年生までの男児であったが少子化によって女児も参加できるようにした。かつては朝からお米集めをしていたが今はない。長久寺でお参りして掛け軸を掲げた構造改善センターに集まる。子どもの膳は大幅に簡略化されて好きなカレーライスになった。それだけではさみしいのでおすまし汁だけは残した」である。
次の年の平成23年も訪れて行事日程を確認したが、その日は大雪警報が発令されるぐらいの大雪だった。
家から出ることもできない積雪11cmとなった2月11日。
山間ではもっと積もったことであろう。
平成24年、25年も同じ2月11日だったと思うが、両年とも急がねばならない行事取材で出向いていたから毛原は訪れることができなかった。
前年の平成26年は2月16日の日曜だった。
前日に予定していたが大雪になったために京都から来られる住職が到着できなかった。
住職が来られなければ法要はできない。
やむなく日程は日延べされたが、降った大雪で到着したのは一時間遅れ。
すでに法要を終えて子供たちはカレーライスを食べていた。
お寺の奥さんが云うには平成27年は2月15日の日曜日だと断言された。
待ちに待った毛原の子供涅槃を拝見できる。
そう思って1時間前に着いた。
お寺は不在であった。
その場に来られた寺世話の婦人に尋ねた。
折角来てもらったが、昨日に終わったと云う。
こういうことは稀にある。
来年こそ拝見したいと思う毛原で佇んでいた。
その場にはロウバイが咲いていた。
記念にワンショット撮って帰路につく。
毛原からはすぐ近くに室生下笠間がある。
通りがかった際に見かけた男性。
Ⅰさんだ。
畑でなにやら作業をしていた。
家に奥さんが居るというので立ち寄った。
逃した毛原の件を伝えたら話してくれる「ねはんのスズメ」の囃し詞。
奥さんの出里は毛原。
今でもしていると感慨深げに台詞が飛び出す。
大きな白い布袋を持つ子供たちが「ねはんのスズメ コメならいっしょう ゼニならヒャクや」と囃して村集落の各戸を巡っていた。
お米とかお金を貰いに廻っていた。
お金は5円だったか、10円だったか。
昭和21、22年のころだから70年前のこと。
戦時中にも拘わらず村を巡っていたと思い出された。
(H27. 2.15 EOS40D撮影)
思い出せない。
子供がお寺の本堂に上がって掲げた涅槃図に手を合わせる。
法要を済ませた子供たちは構造改善センターでカレーライスをよばれる。
今ではそうしているがかつては米を集めに集落を巡っていたという話しを聞いていた。
最初に訪れたのは平成22年2月21日だった。
村人がいうには「子供の涅槃は15日に近い土曜辺りに行われている。本来は中学三年生までの男児であったが少子化によって女児も参加できるようにした。かつては朝からお米集めをしていたが今はない。長久寺でお参りして掛け軸を掲げた構造改善センターに集まる。子どもの膳は大幅に簡略化されて好きなカレーライスになった。それだけではさみしいのでおすまし汁だけは残した」である。
次の年の平成23年も訪れて行事日程を確認したが、その日は大雪警報が発令されるぐらいの大雪だった。
家から出ることもできない積雪11cmとなった2月11日。
山間ではもっと積もったことであろう。
平成24年、25年も同じ2月11日だったと思うが、両年とも急がねばならない行事取材で出向いていたから毛原は訪れることができなかった。
前年の平成26年は2月16日の日曜だった。
前日に予定していたが大雪になったために京都から来られる住職が到着できなかった。
住職が来られなければ法要はできない。
やむなく日程は日延べされたが、降った大雪で到着したのは一時間遅れ。
すでに法要を終えて子供たちはカレーライスを食べていた。
お寺の奥さんが云うには平成27年は2月15日の日曜日だと断言された。
待ちに待った毛原の子供涅槃を拝見できる。
そう思って1時間前に着いた。
お寺は不在であった。
その場に来られた寺世話の婦人に尋ねた。
折角来てもらったが、昨日に終わったと云う。
こういうことは稀にある。
来年こそ拝見したいと思う毛原で佇んでいた。
その場にはロウバイが咲いていた。
記念にワンショット撮って帰路につく。
毛原からはすぐ近くに室生下笠間がある。
通りがかった際に見かけた男性。
Ⅰさんだ。
畑でなにやら作業をしていた。
家に奥さんが居るというので立ち寄った。
逃した毛原の件を伝えたら話してくれる「ねはんのスズメ」の囃し詞。
奥さんの出里は毛原。
今でもしていると感慨深げに台詞が飛び出す。
大きな白い布袋を持つ子供たちが「ねはんのスズメ コメならいっしょう ゼニならヒャクや」と囃して村集落の各戸を巡っていた。
お米とかお金を貰いに廻っていた。
お金は5円だったか、10円だったか。
昭和21、22年のころだから70年前のこと。
戦時中にも拘わらず村を巡っていたと思い出された。
(H27. 2.15 EOS40D撮影)