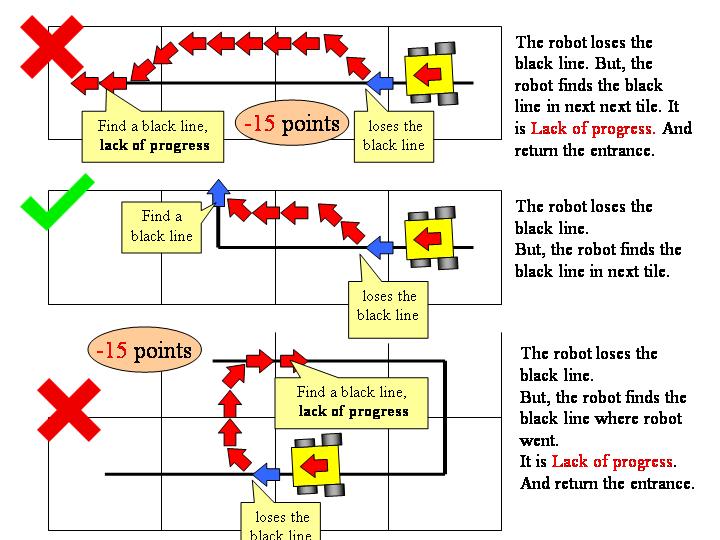今回のお題は「環境条件」です。
1.7 Environmental Conditions:
1.7.1 Teams should expect environmental conditions at a tournament to be different than at their home practice field.
1.7.2 Lighting conditions will certainly vary both in general and along the path in the rescue arena.
1.7.3 Magnetic fields (e.g. generated by underfloor wiring and metallic objects) may be present and effect robot behaviour (every effort will be made by the organizers to locate the rescue arenas away from magnetic fields but this cannot always be avoided).
1.7.4 Spectators take pictures, and cameras will introduce IR and Visible light into the arena and to the robots. Whilst efforts will be made to limit this, it is not possible for organisers to strictly control factors outside of the competition arena. Teams are strongly encouraged to build and program their robots so that sudden changes (eg. camera flash) do not cause major problems. This is good practice in all robotics, both in competitions and in real life situations.
1.7.5 Teams should design their robots to cope with variations in environmental conditions and come prepared to calibrate their robots to contend with the alternate environmental conditions found at the venue.
1.7 環境条件
1.7.1 チームは環境状況が、地元の大会とは異なっているかもしれないと想定しなければなりません。
1.7.2 照明状況は競技アリーナの経路の場所によって異なります。
1.7.3 磁気状況(例えば、床下の配線や金属物によって発生する)は、ロボットに影響があるかもしれません。(主催者は競技フィールドが安定した磁気状況となるように努力をしますが、必ずしも避けられません。)
1.7.4 観客が写真を撮るときに、カメラが赤外線やフラッシュをアリーナやロボットに向けて照射するかもしれません。 これらは主催者が制限をしますが、競技場所以外で徹底することはできないかもしれません。 チームは突発的な問題(例えばカメラのフラッシュ)が発生しても問題を引き起こさないようなロボットやプログラムにすることが望まれる。 これらは、ロボットに対して、競技でも実生活でも通用する良い勉強となる。
1.7.5 各チームは環境の変化に対応できるようにロボットを設計し、会場の状況に合わせてロボットを調整できるような準備しておくこと。
こんな感じでしょうかねぇ。
真っ赤ですね。
これまで蓄積した注意事項を、まとめて入れときました。(という感じですか)
どれもこれも、「当たり前!」のことばかりです。
1.7.1 は・・・俺達がやってきた大会と違うぞ! と文句をいうチームがいたのでしょうか?
1.7.2 影のある部分、光の当たる部分、明るさは場所によって様々です。 でも、そのような外光に惑わされないロボットを作らなくてはいけません。 まあ、レスキューBは外光はほとんど関係ありませんけどね。
外光といえば・・・アトランタ世界大会で見た、天窓から一筋の光がきれいにレスキューアリーナを照らしていた風景が忘れられません。 天使が舞い降りてきても不思議ではありませんでした。
2008年のジャパンオープン沼津も太陽の恵みがさんさんと降り注ぐ素晴しい会場でした。(笑)
さらに、2009年のジャパンオープン大阪の大阪ドームは低い位置からのスポットライトが、競技アリーナの床を反射して、ロボット下側の光センサーを直接攻撃する、これまた素晴しい会場でした。(苦笑)
1.7.3 磁気についてはよく判りません。 M&Yが磁気センサーを使ったのは、2010年の関東ブロック大会からです・・・。 関東ブロック大会(筑波)では、磁気状況がよく、コンパスセンサーが非常に正確に方位を示していました。 しかし、肝心のレッドゾーンに行く前に途中棄権してしまったので、結局コンパスセンサーがその能力を発揮することはありませんでした。(笑)
さらに、ジャパンオープン大阪(大阪工業大学)、シンガポール世界大会と磁気状況が悪く、コンパスセンサーは使い物になりませんでした。
1.7.4 これは、レスキューAの方でも書きましたが・・・赤外線攻撃は・・・ダメでしょう。
まあ、レスキューBでは、あんまり関係ないです。
1.7.5 これらの総合的なまとめですね。 とにかく、「何でも有り」なので、現地で調整してくれたまえ・・・










 だそうです。
だそうです。