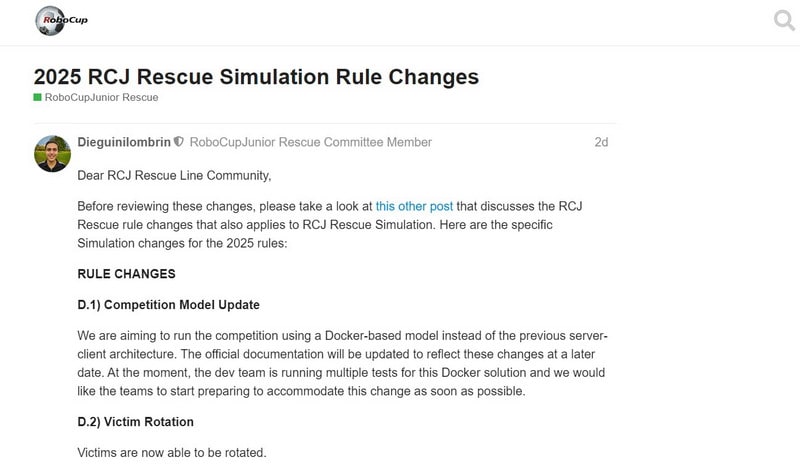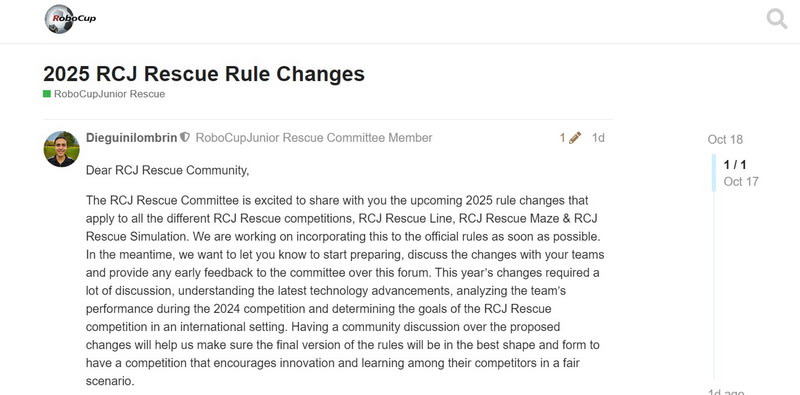先日の RCJ Rescue Rules 2025 の変更内容が Forum に掲載された件で・・・いくつかの意見が投稿されています。(私も、いくつか投稿しました)
その中で、「エンジニアリングジャーナルの提出不要」があります。
A.2) Elimination of Engineering Journal and introducing Presentation Video
The requirement to submit an Engineering Journal has been removed. Instead, each team is required to create and submit a short video presentation showcasing their work. These videos will be presented during the competition and should summarize the key aspects of the team’s project, design process, and innovations. The rubrics for video and TDP will be updated and will continue to have a weight in the team’s final score.
A.2) エンジニアリングジャーナルの廃止とプレゼンテーションビデオの導入
エンジニアリングジャーナルの提出が廃止され、代わりに各チームは自分たちの成果を紹介する短いプレゼンテーションビデオを作成して提出することが求められます。このビデオは競技会中に発表され、チームのプロジェクト、設計プロセス、および革新の主要な要素を要約する内容である必要があります。ビデオとTDP(技術設計文書)の評価基準は更新され、引き続きチームの最終スコアに影響を与えることになります。
これが、Committeeが掲載した元の文章です。
エンジニアリングジャーナルの提出を指せない代わりに、チーム紹介ビデオ(動画)を作成して、提出する、という変更です。
で、この「エンジニアリングジャーナルの提出不要」について、いくつか意見がだされています。
一つ目が SanjaTronic 氏の投稿
Regarding the point “(A2) - Elimination of Engineering Journal and Introducing Presentation Video,” we discussed this as a team and concluded that the removal of the Engineering Journal could be detrimental in future seasons.
「(A2)- エンジニアリングジャーナルの廃止とプレゼンテーションビデオの導入」に関して、私たちはチームとしてこの点を議論し、将来的なシーズンにおいてエンジニアリングジャーナルの廃止が悪影響を及ぼす可能性があると結論しました。
As a team dedicated to documenting our work, we believe the Engineering Journal greatly facilitates the understanding and connection of different areas and knowledge related to the competition. A well-maintained journal not only ensures organized planning but also supports a logical workflow. Additionally, it helps the evaluation committee identify teams that have not complied with regulations, upholding the principle that robots must be designed and programmed exclusively by team members.
私たちは、作業の記録を大切にしているチームであり、エンジニアリングジャーナルが競技に関連するさまざまな分野や知識を理解し、結びつける上で非常に有益であると考えています。よく整備されたジャーナルは、計画を組織的に進めることを保証するだけでなく、論理的なワークフローを支援します。また、評価委員会が規定に従っていないチームを特定するのにも役立ち、ロボットがチームメンバーによってのみ設計およびプログラムされるべきだという原則を守ることができます。
Therefore, we believe the Engineering Journal should not be eliminated but rather used as a source of knowledge and sharing among teams, fostering fair play and camaraderie, but most importantly, promoting learning.
したがって、私たちは工学ジャーナルを廃止するのではなく、知識や情報の共有のための資料として活用し、チーム間でのフェアプレーと友情を促進するだけでなく、何よりも学習を推進すべきだと考えています。
この人の「自分のチームでは作業記録を大切にしている」というのは素晴らしいと思います。ただ、「エンジニアリングジャーナルの廃止が・・・」というのが勘違いしているように思います。 Committee は「エンジニアリングジャーナルを作成しなくて良い。」と言っている訳では無く「エンジニアリングジャーナルを提出しなくて良い。(評価しない)」といっているだけです。
だから、作業記録は継続して作れば良いのではないでしょうか?
それとも、「自分たちは、ちゃんと真面目に作業記録を作っているのだから、評価して得点に加えてくれないと困る」と言っているのでしょうか?
二つ目は moritz_biobrause 氏
I respectfully disagree with @SanjaTronic perspective.
@SanjaTronicの視点には敬意を表しますが、私は異なる意見を持っています。
Last year, our experience showed that the Engineering Journal actually slowed down our development process. I believe that each team has its own unique approach to innovation and problem-solving. In our case, a rapid-iteration methodology allowed us to quickly adapt and refine our solutions, which was a key factor in our success. The requirement to maintain the Engineering Journal was a significant obstacle in this process, as it demanded time that could have been better spent testing and improving our designs.
昨年の経験から、エンジニアリングジャーナルは実際には私たちの開発プロセスを遅らせていたと感じています。私は、各チームには独自のイノベーションと問題解決のアプローチがあると考えており、私たちの場合、迅速な反復法が解決策を迅速に適応し、改善するための鍵となり、成功に繋がったと信じています。エンジニアリングジャーナルの維持がこのプロセスにおける大きな障害となり、設計のテストや改善に使うべき時間が割かれてしまいました。
While I agree that documentation can help organize planning and maintain a logical workflow, I think it’s important to recognize that not all teams benefit from the same methods. For us, the Journal felt restrictive rather than supportive. I do see the value that an Engineering Journal can provide for some teams, however, I think it should remain optional for teams that find it helpful, rather than a requirement for everyone.
ドキュメント化が計画を整理し、論理的なワークフローを維持するのに役立つことには賛成ですが、すべてのチームが同じ方法から利益を得られるわけではないことを認識することが重要だと思います。私たちにとって、ジャーナルは支援的というよりは制約を感じさせました。確かに、エンジニアリングジャーナルがあることで価値を見出すチームもあることは理解していますが、それがすべてのチームにとって必須であるべきではなく、役立つと感じるチームにとってはオプションであるべきだと考えています。
この人の意見は・・・作業記録を作るのに時間がかかってロボット開発に支障がでている。作業記録を作る時間を設計やテストや改善に回したい。
と言うことのようです。
明確には書かれていませんが「作業記録なんて必要ない」と言うことでしょうか?(さすがにそこまでの意見では無い⁉) でも最後の方に、「作業記録が必要と思えるチームだけが作業記録を作れば良い」みたいなことが書かれているので、作業記録はマストではない、という考えなのでしょう。
で・・・これらの意見に対して Rescue Committee の CsabaAbanJr 氏が回答以下のようにしています。
We still consider the creation of the Engineering Journal valuable; however, each team prepares, works, and develops differently, especially in an international setting. This makes it really challenging to evaluate uniformly and fairly without placing a burden on teams to strictly adhere to the rubric. If any criteria are not fully met, teams have two options: either they can supplement it afterward ending in a 90+ page documents that is hard to evaluate objectively, or they will receive fewer points. That is why we decided to change this to a video deliverable, which provides more flexibility to the teams and where creativity is encouraged. The goal of this video is to complement the TDP document to create a better understanding of the competitor’s understanding and development.
私たちは依然としてエンジニアリングジャーナルの作成が価値があると考えていますが、特に国際的な環境において、各チームは異なる方法で準備し、作業し、開発を進めているため、均一かつ公正に評価することが非常に難しくなっています。厳密に評価基準に従わせることは、チームに過度な負担をかけてしまいます。もし評価基準が完全に満たされていない場合、チームには2つの選択肢があります。1つは、後から補足して90ページ以上のドキュメントを作成することで、客観的に評価するのが難しくなるか、もう1つは、評価ポイントが少なくなることです。このため、私たちは評価基準を変更し、プレゼンテーションビデオの提出に切り替えることにしました。これにより、チームにもっと柔軟性が与えられ、創造性が奨励されることになります。このビデオの目的は、TDP文書を補完し、競技者の理解と開発の過程をより良く理解できるようにすることです。
We still encourage teams to develop their own engineering journal without the pressure of being evaluated in their final scores.
なお、私たちは引き続き、チームが最終的なスコアに影響を与えない形で独自のエンジニアリングジャーナルを作成することを推奨しています。
まず、ロボット開発において、作業記録をとるのは「当たり前」のことですよね。
昨日は、ここまでできたから、今日は続きをやるぞ! 昨日は、こんな失敗があったから、その失敗を繰り返さないようにすすめよう・・・
人間、誰しも間違いがあり、その間違いを乗り越えて進むことで成長するのですが・・・その記録が無いということは、瞬間瞬間が行き当たりばったりということ!? いや、僕は記憶力が良いので、記録する必要がないんだ! というのであれば、記録は必要無いのかもしれませんが・・・
で・・・Committeeの言い訳は・・・
・作業記録が必要無いとは言っていない。(作業記録は引き続き作ろうね)
・でも、作業記録を提出させて、作業記録を評価して点数化することはやめる。 だって評価できないんだもん。(評価が難しい)
ということです。
私も、彼らの「評価できない」という意見に「なるほど」と思っています。
(作業記録なんて、評価できないよね。 そして、そもそもドキュメントの評価を、短時間に、公正公平にできるのか? が疑問・・・)