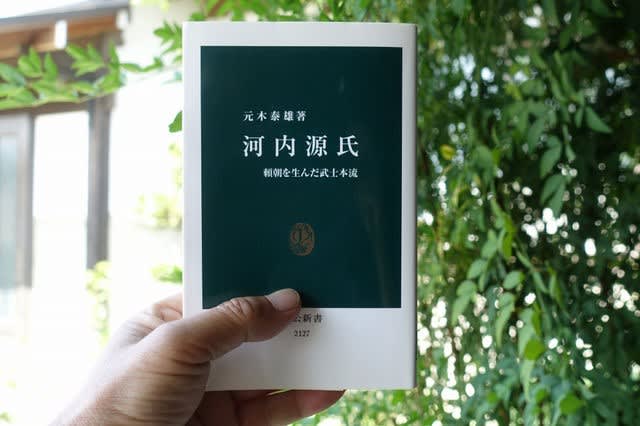
「これはすごい労作だなあ」
本書を半ばまで読まないうちに、わたしはそう確信した。源頼朝登場前夜について書かれた本がどのくらいあるのかよくは知らないけど、本書は保元・平治の乱だけでなく、河内源氏発祥の起源にまで遡り、前九年・後三年の戦役をへて頼朝の登場まで、あまたの史料を渉猟しつくしたうえで、そこに元木泰雄さん独自の新解釈を加えて書き下ろしたものである。
一般読者向けの新書という体裁をとってはいる。
しかし、おそらく専門の研究者すらこの「河内源氏」に対し、敬意を払わずにはいられないのではないか・・・そういう仕上がりになっている。
無知蒙昧な一読者たるわたしなどが、“評価”するとはちゃんちゃらおかしいと、多くの人が思うだろう(^^;) これまでにまとめるため、いったい何年の営々たる努力が積み重ねられてきたことか、脱帽せざるをえない。
《十二世紀末、源頼朝は初の本格的武士政権である鎌倉幕府を樹立する。彼を出した河内源氏の名は武士の本流として後世まで崇敬を集めるが、祖・頼信から頼朝に至る一族の歴史は、京の政変、辺境の叛乱、兄弟間の嫡流争いなどで浮沈を繰り返す苛酷なものだった。頼義、義家、義親、為義、義朝と代を重ねた源氏嫡流は、いかにして栄光を手にし、あるいは敗れて雌伏の時を過ごしたのか。七代二百年の、彼らの実像に迫る。》(BOOKデータベースより)
源頼信、頼義、義家三代のことなら知っている歴史好きは多いだろうが、二流、いや三流ともいえる源氏の末流にまで目配りが行き届き、登場人物の名前はとても覚えきれないほど。紹介文にもあるように、本書が取り上げた期間はおよそ二百年におよぶ。
ここでも主役は系図といってもいいのかもしれない。
巻頭に近いところに、天皇家はもとより、藤原氏(摂関家)、清和源氏、桓武平氏、そして天皇家をめぐる婚姻関係図が掲載されている。これをたびたび参照しないと、さきへすすめない。
武士の発生と、その階級的な形成は平安初期の受領層に遡る。武装集団なので、抗争はしばしば武力闘争になる。現代の暴力団の抗争事件を連想するのは、わたしばかりではあるまい。京と在地をいったりきたりしながら、人脈や資産を築きあげていく。
ときの中央政界の動きにも翻弄されるありさまは、すばらしく見事に検証しつくされているように思える。
単に戦記物をなぞったり、同時代人の記録を鵜呑みにしたりはせず、適切な批判・論評がくわえられていく。そのあたりの手続きが説得力をもっている。
元木泰雄さんは1954年生まれ、京都大学の教授をしておられるようだ。
《長年温めてきた河内源氏論をようやく世に送ることができた。河内源氏こそは
鎌倉幕府を樹立した頼朝を生んだ、まさに平安時代における武士本流に他ならない。近年、様々な議論を呼んでいる武士論を再検討するためにも、河内源氏の実態解明は不可欠と考えられる。》(本書209ページ)
またこうも書いておられる。
《一族の歴史を連続的・包括的に叙述することで、新知見を提示できたと少しばかり自負している。》(同ページ)
一族の歴史を連続的・包括的に叙述するというのは、なまやさしいことではない。京に蟠踞し、栄枯盛衰をくり返す貴族たちの史料は豊富だろうが、地方を根拠とする在地の一族集団の研究は、たいした注目をあびない分、根気のいる仕事となる。
悪くいえば“重箱の隅をつつく”ような地味な検証と省察の連続。だけど、その積み重ねによって、武士たるものの実態が解明される。いわゆる武士道と、実態としての武士が、まるで違う世界に生きていることが見えてくる。
現実と、理念の違いとは、こんなものであろうか?
本書は元木さん(先生)の自負に十分値する、充実の一冊。名著といってもいいかもしれない。
先学の本をなぞり、半分はお茶をにごすような内容の本を、2-3年に一冊、ぽんぽんと書いてしまう先生もたまにはお見受けするが、元木さんは、そういうタイプとはほど遠い存在といっていいだろう。
鎌倉における頼朝の政権は、一朝一夕に誕生したものではない。それはだれでも知っている。頼朝の父、義朝の最期は、本書によって、はじめて詳しく知ることができた。
ノンフィクションとしての歴史記述。
本書こそ、古代と中世を橋渡ししてくれる“核心”を衝く著作のように、わたしには思われる。
武士たちが演じた、欲望と虚栄に満ちた、生と死の峻烈なドラマ(=_=) フィクションではなく、じっさいに演じられた、親子兄弟・親族、骨肉相食む迫真のドキュメント!
読者の大部分は、ある種の諦念と憂愁を感じずには本書を読むことはできないだろう。
評価:☆☆☆☆☆
本書を半ばまで読まないうちに、わたしはそう確信した。源頼朝登場前夜について書かれた本がどのくらいあるのかよくは知らないけど、本書は保元・平治の乱だけでなく、河内源氏発祥の起源にまで遡り、前九年・後三年の戦役をへて頼朝の登場まで、あまたの史料を渉猟しつくしたうえで、そこに元木泰雄さん独自の新解釈を加えて書き下ろしたものである。
一般読者向けの新書という体裁をとってはいる。
しかし、おそらく専門の研究者すらこの「河内源氏」に対し、敬意を払わずにはいられないのではないか・・・そういう仕上がりになっている。
無知蒙昧な一読者たるわたしなどが、“評価”するとはちゃんちゃらおかしいと、多くの人が思うだろう(^^;) これまでにまとめるため、いったい何年の営々たる努力が積み重ねられてきたことか、脱帽せざるをえない。
《十二世紀末、源頼朝は初の本格的武士政権である鎌倉幕府を樹立する。彼を出した河内源氏の名は武士の本流として後世まで崇敬を集めるが、祖・頼信から頼朝に至る一族の歴史は、京の政変、辺境の叛乱、兄弟間の嫡流争いなどで浮沈を繰り返す苛酷なものだった。頼義、義家、義親、為義、義朝と代を重ねた源氏嫡流は、いかにして栄光を手にし、あるいは敗れて雌伏の時を過ごしたのか。七代二百年の、彼らの実像に迫る。》(BOOKデータベースより)
源頼信、頼義、義家三代のことなら知っている歴史好きは多いだろうが、二流、いや三流ともいえる源氏の末流にまで目配りが行き届き、登場人物の名前はとても覚えきれないほど。紹介文にもあるように、本書が取り上げた期間はおよそ二百年におよぶ。
ここでも主役は系図といってもいいのかもしれない。
巻頭に近いところに、天皇家はもとより、藤原氏(摂関家)、清和源氏、桓武平氏、そして天皇家をめぐる婚姻関係図が掲載されている。これをたびたび参照しないと、さきへすすめない。
武士の発生と、その階級的な形成は平安初期の受領層に遡る。武装集団なので、抗争はしばしば武力闘争になる。現代の暴力団の抗争事件を連想するのは、わたしばかりではあるまい。京と在地をいったりきたりしながら、人脈や資産を築きあげていく。
ときの中央政界の動きにも翻弄されるありさまは、すばらしく見事に検証しつくされているように思える。
単に戦記物をなぞったり、同時代人の記録を鵜呑みにしたりはせず、適切な批判・論評がくわえられていく。そのあたりの手続きが説得力をもっている。
元木泰雄さんは1954年生まれ、京都大学の教授をしておられるようだ。
《長年温めてきた河内源氏論をようやく世に送ることができた。河内源氏こそは
鎌倉幕府を樹立した頼朝を生んだ、まさに平安時代における武士本流に他ならない。近年、様々な議論を呼んでいる武士論を再検討するためにも、河内源氏の実態解明は不可欠と考えられる。》(本書209ページ)
またこうも書いておられる。
《一族の歴史を連続的・包括的に叙述することで、新知見を提示できたと少しばかり自負している。》(同ページ)
一族の歴史を連続的・包括的に叙述するというのは、なまやさしいことではない。京に蟠踞し、栄枯盛衰をくり返す貴族たちの史料は豊富だろうが、地方を根拠とする在地の一族集団の研究は、たいした注目をあびない分、根気のいる仕事となる。
悪くいえば“重箱の隅をつつく”ような地味な検証と省察の連続。だけど、その積み重ねによって、武士たるものの実態が解明される。いわゆる武士道と、実態としての武士が、まるで違う世界に生きていることが見えてくる。
現実と、理念の違いとは、こんなものであろうか?
本書は元木さん(先生)の自負に十分値する、充実の一冊。名著といってもいいかもしれない。
先学の本をなぞり、半分はお茶をにごすような内容の本を、2-3年に一冊、ぽんぽんと書いてしまう先生もたまにはお見受けするが、元木さんは、そういうタイプとはほど遠い存在といっていいだろう。
鎌倉における頼朝の政権は、一朝一夕に誕生したものではない。それはだれでも知っている。頼朝の父、義朝の最期は、本書によって、はじめて詳しく知ることができた。
ノンフィクションとしての歴史記述。
本書こそ、古代と中世を橋渡ししてくれる“核心”を衝く著作のように、わたしには思われる。
武士たちが演じた、欲望と虚栄に満ちた、生と死の峻烈なドラマ(=_=) フィクションではなく、じっさいに演じられた、親子兄弟・親族、骨肉相食む迫真のドキュメント!
読者の大部分は、ある種の諦念と憂愁を感じずには本書を読むことはできないだろう。
評価:☆☆☆☆☆



























