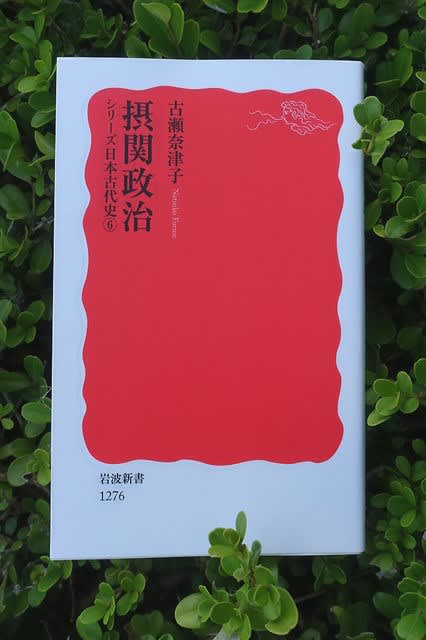
いよいよこの岩波新書シリーズ日本古代史も最終巻まで読んできた。タイトル通り、取り上げているのは藤原道長をその頂点とした摂関政治の時代。
結論をさきにいえば、わたし的には非常に読み応えのある、ずっしりとした一冊であった、新書のボリュームにしては。
読み出してみて、知らないことだらけだということに、すぐに気づいた。「そうか、こんな時代であったのか!」
世界的にも評価の高い「源氏物語」が誕生した社会が、文学的にではなく、歴史的に探求されているのがいやに新鮮。著者の切っ先はかなり鋭い。
古瀬奈津子(ふるせなつこ)さんは1954年生まれ、お茶の水大学の教授で、専攻はいうまでもなく日本古代史。
この第6巻で、古代の総仕上げとなる。わかっていたこと、そして新たに付け加わった学会の知見が、ぎっしりとつめ込まれている。
参考までに、目次をひろっておこう。
はじめに ―藤原道長の「我が世」とは
第一章 摂政・関白制度の誕生
第二章 道長がつくった時代
第三章 「殿上人」の世界
第四章 ひろがりゆく「都市」と「地方」
第五章 国際関係のなかの摂関政治
第六章 頼道の世から「末法」の世へ
おわりに ―「古代貴族」と「律令国家」の終焉
巻末に、図版出典一覧、参考文献、略年表、索引が付されてあり、読者の便を考慮してある。
しかも系図がとても豊富で、人物の系譜がよくわかる。古代史においては血縁・婚姻関係が、国内政治・政権の重要な要件を形成しているからだ。
現在の日本からは想像しにくい、狭いせまい世界の出来事が、そのまま古代史となっていく。おそらくこの時代の日本列島に住んでいた日本人は750~850万人程度(蝦夷や隼人はのぞく)。
《我が世の栄華を満月にたとえた藤原道長。彼が他の貴族を圧倒する力を得たのはなぜか。『枕草子』『源氏物語』などすぐれた女房文学はなぜ生まれたのか。殿上人は、そして都の庶民は、どんな一年を送っていたのか。力をつける地方国司、武士の台頭、そして末法思想と浄土教の広がりなど、古代の終わりと中世への胎動を描く。》(BOOKデータベースより)
藤原氏は、要するに外戚として政権を獲得したのだ。価値の源泉はこの時代はいうまでもなく天皇にある。
易姓革命が当たり前の中国と違って、天皇にとって代わることはできない。摂政、関白、内覧という地位について、天皇を補佐することはできる。しかし、天皇のもう一方の儀礼、祭儀に関する勤めは、天皇にしかできない。藤原氏にできたのは、政務を担当するだけ。
儀礼、祭儀については、天皇がかりに幼い場合であっても、その幼い天皇が基本的にこれをおこなわなければならない。天皇が交代すると“三種の神器”が継承され、正当性の証となる。
すでに蘇我氏が先鞭をつけているが、要するに娘を皇室に入れ、その娘に男子を産ませてること。そして、その男子(皇子)を即位させることで、外祖父として政務を取り仕切る。
その政権の基本的枠組みのことを、古瀬さんはつぎのように述べている。
《天皇制を前提として、政治の実権は摂関が握るというあり方は、その後の日本における政治の仕組みの枠組みとなっていく。摂関政治につづく院政期では院が、そのさきの時代では鎌倉幕府や室町幕府さらに江戸幕府の征夷大将軍が政治の実権を把握する。しかし、天皇制も消滅しないで存続していく。その意味で、摂関政治によってその後の日本の政治権力の枠組みが出来上がったと言える。》(本書216ページ)
第三章「殿上人」の世界、第四章「ひろがりゆく「都市」と「地方」もたいへん内容が濃く、大学での長年の研究成果が披瀝され、読者は失望しなくてすむだろう。
このあいだ藤原道長の「御堂関白記」(倉本一宏 全現代語訳 講談社学術文庫)を上巻のみ買ってきて、ぱらぱらと拾い読みしたが、当時の権力者はそれなりによく仕事をしたのだ。政務と行事への参加が、彼の日常をびっしりうめている。
しかし、早朝からおよそ正午ごろで、それらの仕事から解放される。夜は宴会にいったり、女性の家を訪問したりと、私生活も充実。
この本ではじめて知ったのだが、当時の貴族は、正妻とは同居するのが一般的であったそうだ。正妻=第一夫人の産んだ子が普通は後継者となる。したがって、正妻の発言力はきわめてつよく、資産も持っているのが当然であった。
本書のおかげで、この時代に対する理解がずいぶん深まった(^^;)
シリーズの掉尾を飾るにふさわしい一冊、おすすめですぞ。
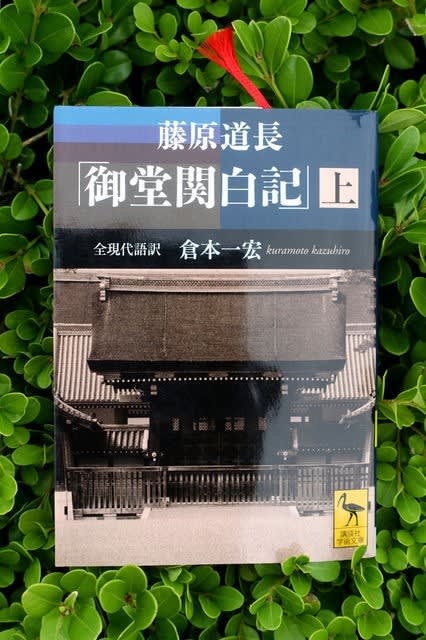
評価:☆☆☆☆☆
結論をさきにいえば、わたし的には非常に読み応えのある、ずっしりとした一冊であった、新書のボリュームにしては。
読み出してみて、知らないことだらけだということに、すぐに気づいた。「そうか、こんな時代であったのか!」
世界的にも評価の高い「源氏物語」が誕生した社会が、文学的にではなく、歴史的に探求されているのがいやに新鮮。著者の切っ先はかなり鋭い。
古瀬奈津子(ふるせなつこ)さんは1954年生まれ、お茶の水大学の教授で、専攻はいうまでもなく日本古代史。
この第6巻で、古代の総仕上げとなる。わかっていたこと、そして新たに付け加わった学会の知見が、ぎっしりとつめ込まれている。
参考までに、目次をひろっておこう。
はじめに ―藤原道長の「我が世」とは
第一章 摂政・関白制度の誕生
第二章 道長がつくった時代
第三章 「殿上人」の世界
第四章 ひろがりゆく「都市」と「地方」
第五章 国際関係のなかの摂関政治
第六章 頼道の世から「末法」の世へ
おわりに ―「古代貴族」と「律令国家」の終焉
巻末に、図版出典一覧、参考文献、略年表、索引が付されてあり、読者の便を考慮してある。
しかも系図がとても豊富で、人物の系譜がよくわかる。古代史においては血縁・婚姻関係が、国内政治・政権の重要な要件を形成しているからだ。
現在の日本からは想像しにくい、狭いせまい世界の出来事が、そのまま古代史となっていく。おそらくこの時代の日本列島に住んでいた日本人は750~850万人程度(蝦夷や隼人はのぞく)。
《我が世の栄華を満月にたとえた藤原道長。彼が他の貴族を圧倒する力を得たのはなぜか。『枕草子』『源氏物語』などすぐれた女房文学はなぜ生まれたのか。殿上人は、そして都の庶民は、どんな一年を送っていたのか。力をつける地方国司、武士の台頭、そして末法思想と浄土教の広がりなど、古代の終わりと中世への胎動を描く。》(BOOKデータベースより)
藤原氏は、要するに外戚として政権を獲得したのだ。価値の源泉はこの時代はいうまでもなく天皇にある。
易姓革命が当たり前の中国と違って、天皇にとって代わることはできない。摂政、関白、内覧という地位について、天皇を補佐することはできる。しかし、天皇のもう一方の儀礼、祭儀に関する勤めは、天皇にしかできない。藤原氏にできたのは、政務を担当するだけ。
儀礼、祭儀については、天皇がかりに幼い場合であっても、その幼い天皇が基本的にこれをおこなわなければならない。天皇が交代すると“三種の神器”が継承され、正当性の証となる。
すでに蘇我氏が先鞭をつけているが、要するに娘を皇室に入れ、その娘に男子を産ませてること。そして、その男子(皇子)を即位させることで、外祖父として政務を取り仕切る。
その政権の基本的枠組みのことを、古瀬さんはつぎのように述べている。
《天皇制を前提として、政治の実権は摂関が握るというあり方は、その後の日本における政治の仕組みの枠組みとなっていく。摂関政治につづく院政期では院が、そのさきの時代では鎌倉幕府や室町幕府さらに江戸幕府の征夷大将軍が政治の実権を把握する。しかし、天皇制も消滅しないで存続していく。その意味で、摂関政治によってその後の日本の政治権力の枠組みが出来上がったと言える。》(本書216ページ)
第三章「殿上人」の世界、第四章「ひろがりゆく「都市」と「地方」もたいへん内容が濃く、大学での長年の研究成果が披瀝され、読者は失望しなくてすむだろう。
このあいだ藤原道長の「御堂関白記」(倉本一宏 全現代語訳 講談社学術文庫)を上巻のみ買ってきて、ぱらぱらと拾い読みしたが、当時の権力者はそれなりによく仕事をしたのだ。政務と行事への参加が、彼の日常をびっしりうめている。
しかし、早朝からおよそ正午ごろで、それらの仕事から解放される。夜は宴会にいったり、女性の家を訪問したりと、私生活も充実。
この本ではじめて知ったのだが、当時の貴族は、正妻とは同居するのが一般的であったそうだ。正妻=第一夫人の産んだ子が普通は後継者となる。したがって、正妻の発言力はきわめてつよく、資産も持っているのが当然であった。
本書のおかげで、この時代に対する理解がずいぶん深まった(^^;)
シリーズの掉尾を飾るにふさわしい一冊、おすすめですぞ。
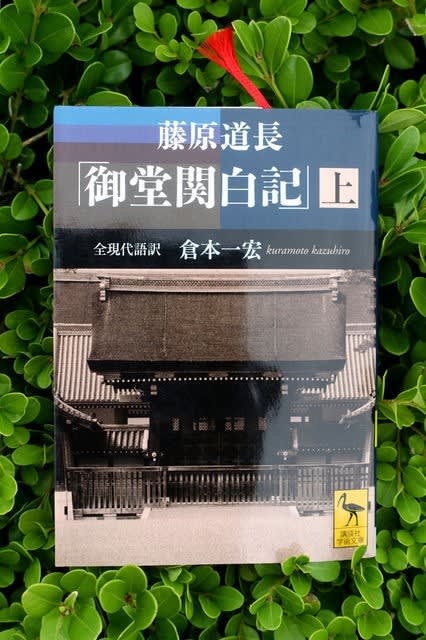
評価:☆☆☆☆☆


























