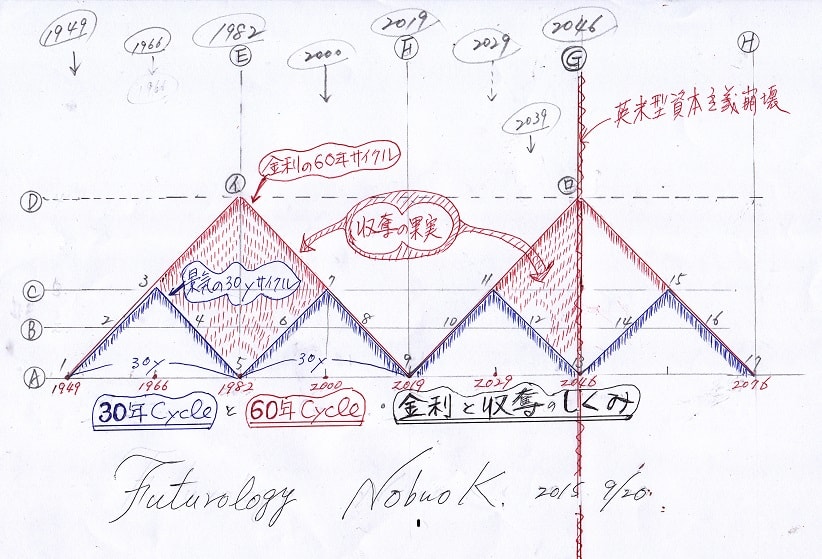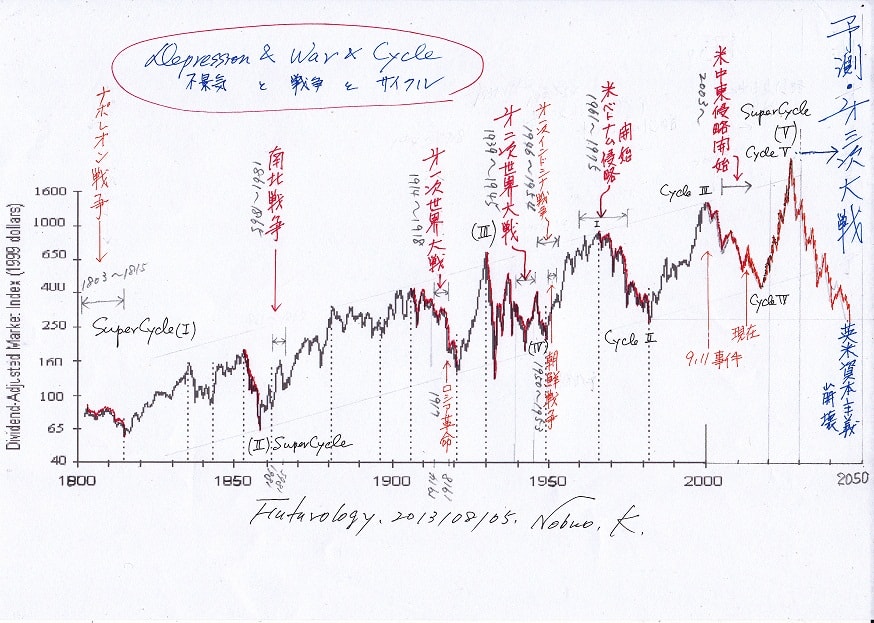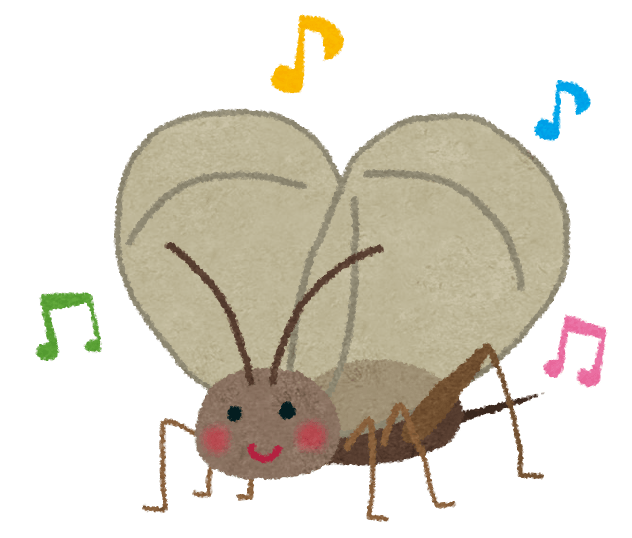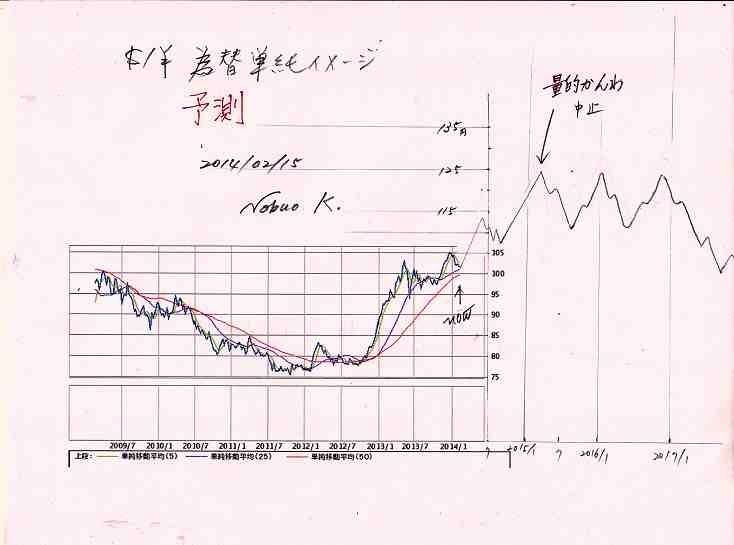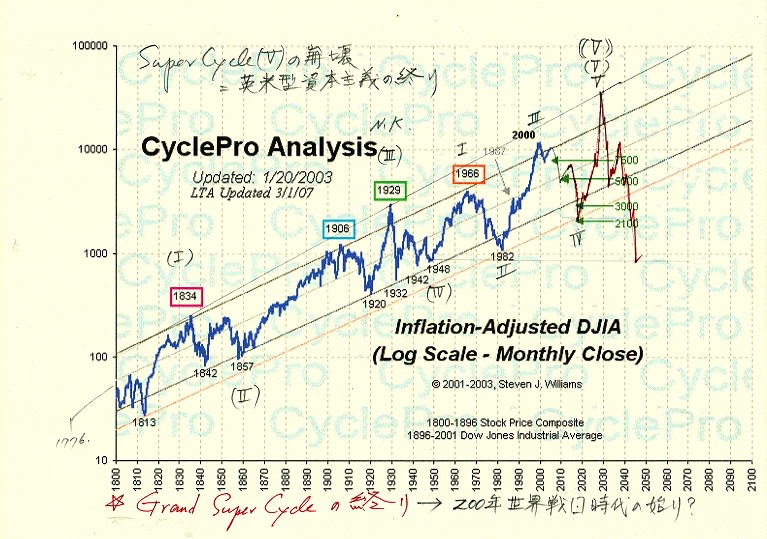MMTの正しさ、リフレ派の誤り、誤解のひどさ
『三橋貴明の「新」経世済民新聞』
2019/07/25
MMTの正しさ、リフレ派の誤り、誤解のひどさ
7月16日にMMT(現代貨幣理論)の主唱者であり、ニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授が来日しました。
衆議院議員会館で講演し、多くのメディアの記者会見にも応じました。
筆者も講演を聞くことができましたが、明快な論理と巧みな比喩を用いて、MMTの本質を展開してくれました。
また三回にわたって三橋TVに出演し、その理論と日本が抱える経済問題についてわかりやすく解説してくれました。
ケルトン教授の説くところは、これまで中野剛志氏、藤井聡氏、三橋貴明氏ら、一部の人たちによってさんざん言われてきたこととほとんど変わりませんが、これを機会に、MMTの主張も含めて、日本経済についての正しい議論をまとめておきたいと思います。
① 自国通貨建ての国債発行額には原則として制約がない。政府はその限りでは、財政赤字を気にする必要はない。
② ただし、インフレ率という制約があり、政府・中銀は、過度なインフレになる兆候が見えた時には、コントロールする必要があるし、それは金利調整や増税などによって可能である。ただしインフレの場合でも、消費増税である必要は全くない。富裕層に優しく、貧困層に厳しい逆進性を持つ消費税は廃止すべきである。
③ リフレ派は、金融緩和を続けることで市場に「予想インフレ率」が高まり、それが投資意欲に結びつくので、デフレ脱却が可能だと主張してきたが、資金需要は高まらなかった。また過度な金融緩和が金利を大幅に引き下げ、金融業界にダメージを与えてきた。
④ 企業の投資意欲を生み出すには、金融政策に特化するのではなく、同時に、政府が国債を発行して積極的に財政政策を打つことが、直接に需要創出につながり、生産活動に結びつくので、有効である。これはアベノミクスの二本目の矢を意味するが、二本目の矢は放たれなかった。
③と④についてちょっと解説を付け加えます。
リフレ派の理論に従って安倍政権(日銀)は6年半にわたり膨大な量的緩和を行ってきたにもかかわらず、「予想インフレ率」は高まりませんでした。
その結果、デフレ脱却はおろか、国民の生活はかえって困窮を招いてしまいました。
これには、量的緩和によって積み重なったお金が、日銀当座預金という特別の口座のお金(マネタリーベース)に過ぎず、一般の企業が引き出すことのできる市中銀行の口座ではないという必然的な事情があります。
だから日銀当座預金に滞留したお金と、マネーストック(金融部門総体の通貨供給量)との間には越えがたい壁がもともとあったのです。
したがって、このデフレ下では、よほどの投資意欲を持った奇特な借り手でも現れなければ(現れなかったのですが)、市中にお金が流れません。
リフレ派経済学者たちは、その壁についての自覚がなく、その無自覚を「予想インフレ率」という空しい期待によって覆い隠してきたわけですね。
⑤ 政府の赤字は民間の黒字。つまり、政府の負債が増えることは、反対側で、民間の預金が増えることを意味する。したがって、国民は、「国の借金」などをまったく気にする必要はなく、むしろ喜ぶべきである。政府・日銀は通貨発行権を持っているので、PB黒字化をしないとやがて政府が財政破綻をきたすなどという財務省の脅しには何の根拠もない。
⑥ 民間に資産が十分にあるから、国債発行の余地があるのではない(「お金のプールは存在しない」――この表現は、三橋貴明氏だけでなく、ケルトン教授も期せずして同じ表現を使っていました)。したがって、民間に十分な資産がある間は国債を発行できるがそれが尽きたら財政破綻するという論理は、完全に間違っている。
⑦ これは一般の銀行が企業や個人にお金を貸すときにも当てはまる。国債の場合も普通の借金の場合も、銀行に潤沢な資金(政府の場合は日銀当座預金)があるから借金できるのではなく、金融機関は、ただ借り手に返済能力があるかどうかを査定したうえで、通帳に金額を書き込むだけである(万年筆マネー)
。
⑧ 経済の話をするときには、政府・日銀の「お財布」の話ばかりしないで、生産のリソースが十分に獲得可能か、企業や消費者にとって政府の政策が適切かどうか、労働者が豊かに暮らせるだけの経済体制になっているかどうかなどに、話題の中心を移すべきである。財政ではなく、経済全体こそが問題なのだ(ケルトン教授は、このことを「眼鏡をかけ替える」と表現しました)。
⑨ MMTには、JGP(雇用保障プログラム)という構想がある。これは、不景気で失業者が増えた時には政府が最低賃金で雇用し、景気が回復すれば、労働者は自動的に高賃金の民間企業に移行するという考えである。つまりデフレ期には、政府が失業者に救済の手を差し伸べるために積極財政策をとり、好景気の時には、その必要がなくなるので、政府の財政もそのぶん縮小することができる。
このJGPについては、ケルトン教授が講演で強調していたにもかかわらず、記者会見でこれに注目した記者はいなかったようです。
また、その後の報道記事でも、ほとんど問題とされませんでした。
メディアが関心を持ったのは、好意的、悪意的両方を含めて、自国通貨を持つ政府には国債発行額の制約はないという一点にもっぱら集中していました。
記者や論者たちの関心がここに集中していたのは、財務省の緊縮路線が人々の頭に刷り込まれてきたために、この「事実」の指摘によほどショックを感じた証拠です。
ですから、MMTについての論評やケルトン教授へのインタビューでの質問では、インフレになったとき抑制できないのではないかという、一種の「インフレ恐怖症」の症状を示すものがほとんどでした。
これに対してケルトン教授からは、「デフレから脱却しなくてはならない時にどうしてそんなにインフレを心配するのですか」と皮肉を言われる一幕もあったようです。
じっさい、日本政府は、デフレの時にインフレ対策というトンデモ政策をやって事態をますます悪化させたくらいですから、もともとインフレ対策については、得意中の得意なのです。
こうした記者や論者は、悪夢を見続けることに慣れ切ってしまって、「目を覚ませ」という声を聞き取ることができず、「たいへんだ、MMTによってデフレから脱却したらハイパーインフレになってしまう!」と錯乱状態に陥ってしまったのでしょう。
ところでJGPですが、これはとてもいいアイデアだと筆者は評価します。
というのは、このアイデアは、アメリカの民主党、共和党の間で盛んな、「大きな政府か小さな政府か」という不毛な二元論を克服する可能性を持っているからです。
不況の時には政府が公共事業を惜しまず提供して失業者を救済し(その財源については、国債発行で十分賄えます)、好況になったらより高給で雇用できる民間企業に彼らを吸収させる――つまり、不況の時には「大きな政府」、好況の時には「小さな政府」というように、柔軟に政府の規模と役割を調整できることになります。
そこには、右か左か、小さな政府か大きな政府かといった、イデオロギー支配が介在する余地はなく、経済の実態に合わせてただプラクマティックな対応機能を政府が備えるだけで十分だという思想が見られるわけです。
ところで、新しいものが出てきた時には、誤解の嵐にさらされるのが常です。
人々は、惰性的な感覚、感情からなかなか自由になれないからです。
MMTは90年代からケインズ派の流れをくむものとして既に存在しており、別に新しい理論ではありません。
ところが財務省のトリックによって、私たちがあまりに家計と政府の財布とを混同する習慣を身につけてしまっていたので、これが上陸した時に、「黒船」のように新しく見えてしまったのです。
この事態に適応できず、さまざまな誤解が生まれましたが、最近、ある人から得た情報で、これぞバカな誤解の決定版という代物に接しましたので、典型例として俎上に載せることにしましょう。
《今仮に、日本政府がMMTの採用を真剣に検討しているというニュースが流れたとすると、私が真っ先にすることは、円建ての銀行預金をドルかユーロ建ての預金に預け替えることだ。
(中略)
MMTによれば、政府の財政需要をまかなうために、日銀は輪転機を回して、円の紙幣をどんどん刷り、それで国債を買うわけだから、円は供給過剰となって価値が下がるに決まっている。これは私だけでなくヘッジファンドなど世界中の投機家も円安を見越して円売りドル買いをするだろうから、ニュースが流れた1時間後には1ドル=300円まで円安となっているかもしれない。
(中略)
私は、MMTは法定通貨(不換紙幣)が国民の信用で成り立っていることをあまりに軽視していると思う。紙幣の価値が、中央銀行が持つ銀や金で裏打ちされている時代と違い、現在はどの国も国の信用(徴税力)だけが裏付けとなっている。MMTを実施すると言った瞬間に、この信用が根底から揺るがされるのだ。
(中略)
円にしてもドルにしても、インフレによる減価で、2019年の1万円や100ドルの価値は1965年の価値のそれぞれ4分の1、8分の1にも満たなくなっている。しかしこの減価は長い時間をかけて徐々に起きたから経済に混乱はあまり生じなかった。それを、MMTのようにこれから不換紙幣をどんどん刷りますと宣言するのは、フーテンの寅さんではないが「それを言っちゃあ、おしまいよ」ではなかろうか。》
http://agora-web.jp/archives/2040455.html
これを書いたのは、元財務省財務大臣審議官の有地浩という人ですが、よっ、さすが財務省、と声をかけたくなるほど、デタラメを振りまいています。
よくもここまで突っ込みどころ満載の文章を書けたものだと、思わずのけぞってしまいます。
まず冒頭から、この人は、MMTについての知識などまるで持ち合わせていないことがわかります。
MMTでは、自国通貨建ての国債発行額には、インフレ率以外に制約はないと言っているので、財政出動の際に、どれくらいのインフレを許容するのかということは、大前提としてあらかじめ繰り込まれています。
したがって、「ニュースが流れた1時間後には1ドル=300円まで円安となっているかもしれない」などという妄想の発生する余地はありません。だいたいなんで1時間後に300円という数字が出てきたのでしょうね。
次に、「日銀は輪転機を回して、円の紙幣をどんどん刷り、それで国債を買う」などといっていますが、財務省出身のくせに、日銀が国債を買う(貸す)際に紙幣など刷らないということを知らないのでしょうか。
そんなことをすれば、国立印刷局広しといえども、すぐに建物の中が一万円札でいっぱいになり、従業員の居場所もなくなってしまうでしょう。
仮に10兆円刷ったら、10億枚という想像を絶する量の紙幣で埋もれることになります。
この人は、お金というものを紙幣でしかイメージしていないのですね。
事実は言うまでもなく、政府が国債を発行するに際しては、ただ日銀当座預金の簿記の借方欄に10兆円と記載されるだけです。
こうして政府は額面10兆円の政府小切手を切り、これを、ある事業を受注した企業や組織に渡します(国債発行は、公共事業、社会福祉事業など、必ず何か具体的な公共投資としてなされるのですから)。
小切手を受け取った企業・組織は、市中銀行にこれを持ち込み、預金通帳に同額の数字を書き込んでもらいます。
銀行は受け取った政府小切手を日銀に持ち込み、日銀当座預金に同額の数字を書き込んでもらいます。
日銀と政府は統合政府ですから、これで政府小切手は、「お金=借用証書」としての役割を終えます。
一方、企業・組織は、労賃、原材料、設備資金などの支払いのために、預金から取引先、従業員などの預金通帳に必要金額の振り込みを行います。
取引先や従業員は、振り込まれた金額を必要に応じて現金紙幣に替えます。
さてこの一連の過程で、現金紙幣が現れるのは、最後の段階だけです。
現金紙幣なんて、そんなに動いていないのですよ。
私たちは、日常生活で現金紙幣を用いていますから、「お金」と聞くとすぐに現金紙幣を思い浮かべてしまいますが、日銀当座預金に書き込まれた数字も、政府小切手も、企業・組織の預金通帳に書き込まれた数字も、すべて「お金=借用証書」なのです。
現金紙幣も、日銀が私たちから借りている借用証書です。
いろいろな形の「お金=借用証書」があるのですね。
この証書の流通を成立させているのは、人と人との信用関係であって、金銀や現金紙幣のような「モノ」ではありません。
有地氏は、このことがまるで分っていません。
いや、ほとんどの人が金本位制の観念を残滓として頭に残しているために、このことを理解していないと言えるでしょう。
テレビ朝日のニュース・ステーションで、ケルトン教授の講演の際に、MMTについて説明をしていました。
紹介してくれることはけっこうなことですが、そのために、現金紙幣の模型を使って、それをぐるぐる回していました。
これでは人々が、紙幣だけをお金と考えたとしても無理はないでしょう。
困ったものです。
有地氏は、MMTの採用を検討しているというニュースが流れただけで、「円建ての銀行預金をドルかユーロ建ての預金に預け替える」そうですが、勝手にやれよと言いたくなります。
この人は、MMT(つまりこの場合は多少大胆な財政出動)が実施されると、たちまち過度なインフレが起きて円が暴落すると信じ込んでいるようですが、MMTがそんなちゃちな理論でないことは、すでに述べました。
また、「通貨が国民の信用で成り立っている」のは事実ですが、いま述べたように、通貨とは、不換紙幣だけではありません。それはごく一部であって、日銀当座預金や銀行預金に書き込まれた数字(万年筆マネー)も、政府小切手もみな通貨です。
MMTが財政出動を促す場合にもこのことは変わりありませんから、「信用が根底から揺るがされる」などということは、200%あり得ません。
それは有地氏のインフレ恐怖症の重篤症状のなかだけでしか起こりえないことです。
さらに有地氏は、「MMTのようにこれから不換紙幣をどんどん刷りますと宣言するのは、フーテンの寅さんではないが『それを言っちゃあ、おしまいよ』ではなかろうか。」などとつまらぬ冗談を吹かしていますが、MMTがどこで「これから不換紙幣をどんどん刷ります」と宣言したのでしょうか。
こういうデマを平然と流すのは、単に誤解や歪曲といったレベルの話ではなく、わざわざ来日してMMTの本質をていねいに説いてくれたケルトン教授に対する失礼極まる愚弄と称すべきでしょう。
日本の「経済識者」の無知ぶりをさらけ出して、世界に対して恥ずかしいと感じるのは、筆者だけでしょうか。
嘆かわしきは、有地氏に代表されるような重症のインフレ恐怖症に罹患した、日本の知的(痴的)病人どもです。
MMTの健全な主張を正確に理解して、このひどいデフレ状況から一刻も早く脱却したいものです。