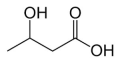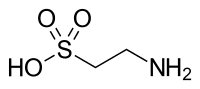★ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170830-00000501-san-bus_all
マツダ、逆張りの「エンジン」強化 EV時代の自動車業界 独自戦略の勝算は?
8/30(水) 10:00配信
マツダの次世代技術の導入計画(写真:産経新聞)
マツダが、環境に優しいエンジン技術に磨きをかけている。英仏政府が2040年にガソリン・ディーゼル車の販売禁止方針を打ち出すなど逆風にあるが、当面は大多数を占めるエンジンの燃費改善が環境負荷の低減に最も有効とみているためだ。マツダは資本提携で合意したトヨタ自動車と電気自動車(EV)の共同開発を進めるが、エンジン開発は競争領域と位置づけ性能の高さを競い合う。
「内燃機関(エンジン)で理想を徹底的に追求し、世界一を目指す」
マツダの小飼雅道社長は燃費性能を現行モデルよりも最大30%程度高めた次世代エンジンを発表した8月8日の記者会見で、こう力強く宣言した。マツダが2019年に投入する次世代エンジンは「スカイアクティブ・エックス」と名付けた。
濃度が薄いガソリンでも燃やすことができる世界初の技術を採用し、燃費を改善。加速性能も高めた。
マツダの小飼社長は8月4日にトヨタとの資本提携合意を発表したが、現時点でトヨタに次世代エンジンを供給する考えはないと説明した。エンジンは各社の技術力が試される心臓部であり、自動車メーカーが最優先に取り組む一丁目一番地。エンジンはガソリン車中心に新興国で需要が強いうえ、ハイブリッド車(HV)にも、家庭で充電できるプラグインハイブリッド車(PHV)にも搭載される。エンジンの重要性は変わらない見通しで、マツダとトヨタが出遅れたEVのように協調領域ではなく、競争領域というわけだ。
マツダが、燃費と加速性能の高さを両立させた次世代エンジンの開発にこぎつけたのは、独自の燃費向上技術「スカイアクティブ」を武器に「理想の燃焼に近づける取り組みを徹底的に進めてきた」(藤原清志専務執行役員)からだ。とりわけマツダはディーゼル車の窒素酸化物(NOx)の排出抑制技術で他社をリードしており、既存のスカイアクティブの燃焼改善にも並行的に取り組むという。
英仏に加え、中国やインド、米国を中心にEV化の流れが広がり、エンジンに対する風当たりは強まりつつある。その中でもエンジン強化の姿勢を打ち出したのは、35年時点でも世界の新車販売に占めるEV割合は約1割にとどまり、HV、PHVを含め8割以上にエンジンが使われるという国際エネルギー機関(IEA)の予測が現実的だとみているからだ。
電気自動車は二酸化炭素(CO2)の排出量は走行時にゼロでも、発電段階で石炭や石油を使用すれば全体ではエンジン車より多いとの試算があるうえ、充電器の整備など普及に向けた課題も多い。それよりもエンジンの燃費を3割改善させればその分、排ガスは減る。電動化技術と組み合わせれば各国で異なる環境規制などに応じた車両開発にもつなげられるとみているわけだ。
それだけにマツダにとって、最大の競争力の源泉となるのは独自のエンジン技術との位置づけは不変で、資本提携するからといってマツダの技術をトヨタに供与するつもりは毛頭ない。
「協力し、競争しあう」
トヨタの豊田章男社長は4日のマツダとの資本提携合意会見でこう述べた。EVや米国での共同工場の立ち上げでは協力するが、デザインやエンジン開発は互いに切磋琢磨(せっさたくま)する分野との認識を示したものだ。
会社の規模でマツダはトヨタの10分の1程度に過ぎないが、豊田氏をして「わたしたちの目指す『もっといいクルマ作り』を実践している会社」と、開発力で高い評価を受けるマツダ。提携を通じて資金力が必要になるEVでは豊富なキャッシュを持つトヨタの力を借りながら遅れを挽回しつつ、得意のエンジンではさらに技術に磨きをかけ、独自性を追求するという“したたか戦略”で、自動車業界の変革期を乗り切る。(経済本部 今井裕治)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
● なんでも極端になるのが、時代の末期と分析しました。USA南軍将軍の像を引き倒すという
暴挙もその一つです。それでは普通の庶民をも敵に回すことになるのが見えないのが
極左に影響を受けている、USA民主党の最大の問題点です。
● 言い換えれば一方の歴史をなかったことにしようというのですから、国民の半分を敵にするのです。
勝てば官軍で、好きなだけ歴史を修正する事が出来ると思ったら、大間違いでしょう。
● 上記、滅びゆく西欧(英仏)で、自動車のガソリンやディーゼルエンジンを禁止するという
決定も馬鹿げており、全くのナンセンス政策です。自分たちが性能の良いエンジンを
作れないから、それを禁止して電気自動車で逆転を狙う浅はかさが見えます。
● システムの老化に伴う、痴呆症状が段々と酷くなっています。電気を造るのも石油製品を
必要とするのですから、地球の温暖化には全く何の影響もありません。
● 大切なのは、石油製品をいかに効率よく燃焼して、エネルギーに変えるかという事です。
発電所が効率よくエネルギーに変換できるのか、それとも自動車の内燃エンジンが
効率よく変換できるのかという問題です。
● 問題はもう一つあります。セキューリティの問題です。発電所や膨大な送電線が一つ故障したら、それこそ
広範囲に影響が出ますが、私の自動車のエンジンが壊れても、他人には何の影響もありません。
またテロリストの狙いは、自動車を個々に破壊するよりも、発電所などの施設を破壊するのが、
● 破壊工作としては効果的でしょう。また内戦や戦争になれば、その意味がもっと分かりやすく
なります。固定した発電所や、原子力発電所、特に送電線は、最も最高のターゲットです。
つまり、相手のエネルギーインフラを先に破壊した方が勝つのです。
● そのリスクを防ぐのは、個々に独立した自動車の内燃機関という事になります。またハイブリッド車
が効率よく発電できるなら、発電所停電の時の良いバックアップとなります。
● 既に世界はテロの嵐が吹き始め、テロを未然に予防することも出来ない今の政権が、内燃機関を
禁止するとは、お笑い種です。そのうち環境の為に、潜水艦も戦艦も飛行機も電気でと
言いかねない極左的冒険と云えましょう。全くばかげています。
● しかしこれば、自ら滅びる為の儀式(慢性自殺)の一つと思えば、理解できます。つまり電気自動車だらけになった時に
世界大戦や内戦が起こり、敵に発電所を破壊されて、すべての機能がマヒする国家となり、
資本主義が頓死するという事です。老衰ではなく、心臓発作による死亡です。
● 世界のお笑い政策の、最も大きい実験と思えば、分かりやすいでしょう。本当に世紀末は
全ての機能が混乱し、頭=支配階級も麻痺するという、良い見本と云えます。
● がんばれ頑張れ、マツダ、痴ほうの英仏は無視せよ、あなた方の判断は、完全に正解です。
マツダ、逆張りの「エンジン」強化 EV時代の自動車業界 独自戦略の勝算は?
8/30(水) 10:00配信
マツダの次世代技術の導入計画(写真:産経新聞)
マツダが、環境に優しいエンジン技術に磨きをかけている。英仏政府が2040年にガソリン・ディーゼル車の販売禁止方針を打ち出すなど逆風にあるが、当面は大多数を占めるエンジンの燃費改善が環境負荷の低減に最も有効とみているためだ。マツダは資本提携で合意したトヨタ自動車と電気自動車(EV)の共同開発を進めるが、エンジン開発は競争領域と位置づけ性能の高さを競い合う。
「内燃機関(エンジン)で理想を徹底的に追求し、世界一を目指す」
マツダの小飼雅道社長は燃費性能を現行モデルよりも最大30%程度高めた次世代エンジンを発表した8月8日の記者会見で、こう力強く宣言した。マツダが2019年に投入する次世代エンジンは「スカイアクティブ・エックス」と名付けた。
濃度が薄いガソリンでも燃やすことができる世界初の技術を採用し、燃費を改善。加速性能も高めた。
マツダの小飼社長は8月4日にトヨタとの資本提携合意を発表したが、現時点でトヨタに次世代エンジンを供給する考えはないと説明した。エンジンは各社の技術力が試される心臓部であり、自動車メーカーが最優先に取り組む一丁目一番地。エンジンはガソリン車中心に新興国で需要が強いうえ、ハイブリッド車(HV)にも、家庭で充電できるプラグインハイブリッド車(PHV)にも搭載される。エンジンの重要性は変わらない見通しで、マツダとトヨタが出遅れたEVのように協調領域ではなく、競争領域というわけだ。
マツダが、燃費と加速性能の高さを両立させた次世代エンジンの開発にこぎつけたのは、独自の燃費向上技術「スカイアクティブ」を武器に「理想の燃焼に近づける取り組みを徹底的に進めてきた」(藤原清志専務執行役員)からだ。とりわけマツダはディーゼル車の窒素酸化物(NOx)の排出抑制技術で他社をリードしており、既存のスカイアクティブの燃焼改善にも並行的に取り組むという。
英仏に加え、中国やインド、米国を中心にEV化の流れが広がり、エンジンに対する風当たりは強まりつつある。その中でもエンジン強化の姿勢を打ち出したのは、35年時点でも世界の新車販売に占めるEV割合は約1割にとどまり、HV、PHVを含め8割以上にエンジンが使われるという国際エネルギー機関(IEA)の予測が現実的だとみているからだ。
電気自動車は二酸化炭素(CO2)の排出量は走行時にゼロでも、発電段階で石炭や石油を使用すれば全体ではエンジン車より多いとの試算があるうえ、充電器の整備など普及に向けた課題も多い。それよりもエンジンの燃費を3割改善させればその分、排ガスは減る。電動化技術と組み合わせれば各国で異なる環境規制などに応じた車両開発にもつなげられるとみているわけだ。
それだけにマツダにとって、最大の競争力の源泉となるのは独自のエンジン技術との位置づけは不変で、資本提携するからといってマツダの技術をトヨタに供与するつもりは毛頭ない。
「協力し、競争しあう」
トヨタの豊田章男社長は4日のマツダとの資本提携合意会見でこう述べた。EVや米国での共同工場の立ち上げでは協力するが、デザインやエンジン開発は互いに切磋琢磨(せっさたくま)する分野との認識を示したものだ。
会社の規模でマツダはトヨタの10分の1程度に過ぎないが、豊田氏をして「わたしたちの目指す『もっといいクルマ作り』を実践している会社」と、開発力で高い評価を受けるマツダ。提携を通じて資金力が必要になるEVでは豊富なキャッシュを持つトヨタの力を借りながら遅れを挽回しつつ、得意のエンジンではさらに技術に磨きをかけ、独自性を追求するという“したたか戦略”で、自動車業界の変革期を乗り切る。(経済本部 今井裕治)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
● なんでも極端になるのが、時代の末期と分析しました。USA南軍将軍の像を引き倒すという
暴挙もその一つです。それでは普通の庶民をも敵に回すことになるのが見えないのが
極左に影響を受けている、USA民主党の最大の問題点です。
● 言い換えれば一方の歴史をなかったことにしようというのですから、国民の半分を敵にするのです。
勝てば官軍で、好きなだけ歴史を修正する事が出来ると思ったら、大間違いでしょう。
● 上記、滅びゆく西欧(英仏)で、自動車のガソリンやディーゼルエンジンを禁止するという
決定も馬鹿げており、全くのナンセンス政策です。自分たちが性能の良いエンジンを
作れないから、それを禁止して電気自動車で逆転を狙う浅はかさが見えます。
● システムの老化に伴う、痴呆症状が段々と酷くなっています。電気を造るのも石油製品を
必要とするのですから、地球の温暖化には全く何の影響もありません。
● 大切なのは、石油製品をいかに効率よく燃焼して、エネルギーに変えるかという事です。
発電所が効率よくエネルギーに変換できるのか、それとも自動車の内燃エンジンが
効率よく変換できるのかという問題です。
● 問題はもう一つあります。セキューリティの問題です。発電所や膨大な送電線が一つ故障したら、それこそ
広範囲に影響が出ますが、私の自動車のエンジンが壊れても、他人には何の影響もありません。
またテロリストの狙いは、自動車を個々に破壊するよりも、発電所などの施設を破壊するのが、
● 破壊工作としては効果的でしょう。また内戦や戦争になれば、その意味がもっと分かりやすく
なります。固定した発電所や、原子力発電所、特に送電線は、最も最高のターゲットです。
つまり、相手のエネルギーインフラを先に破壊した方が勝つのです。
● そのリスクを防ぐのは、個々に独立した自動車の内燃機関という事になります。またハイブリッド車
が効率よく発電できるなら、発電所停電の時の良いバックアップとなります。
● 既に世界はテロの嵐が吹き始め、テロを未然に予防することも出来ない今の政権が、内燃機関を
禁止するとは、お笑い種です。そのうち環境の為に、潜水艦も戦艦も飛行機も電気でと
言いかねない極左的冒険と云えましょう。全くばかげています。
● しかしこれば、自ら滅びる為の儀式(慢性自殺)の一つと思えば、理解できます。つまり電気自動車だらけになった時に
世界大戦や内戦が起こり、敵に発電所を破壊されて、すべての機能がマヒする国家となり、
資本主義が頓死するという事です。老衰ではなく、心臓発作による死亡です。
● 世界のお笑い政策の、最も大きい実験と思えば、分かりやすいでしょう。本当に世紀末は
全ての機能が混乱し、頭=支配階級も麻痺するという、良い見本と云えます。
● がんばれ頑張れ、マツダ、痴ほうの英仏は無視せよ、あなた方の判断は、完全に正解です。