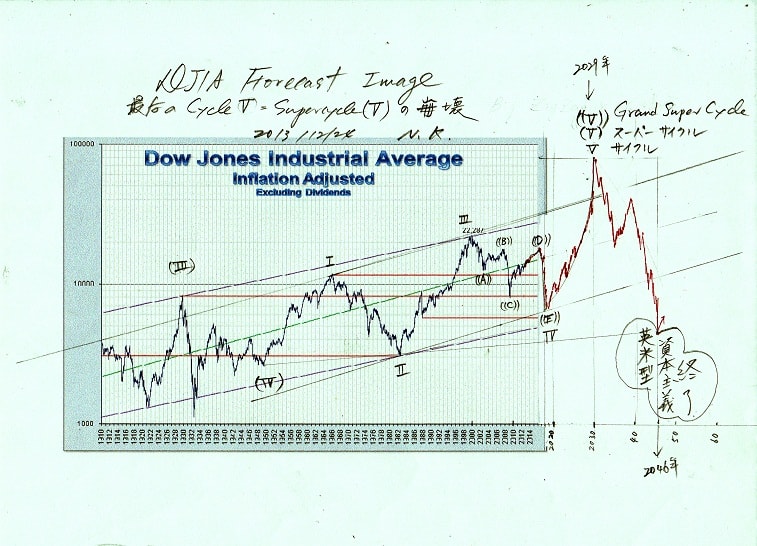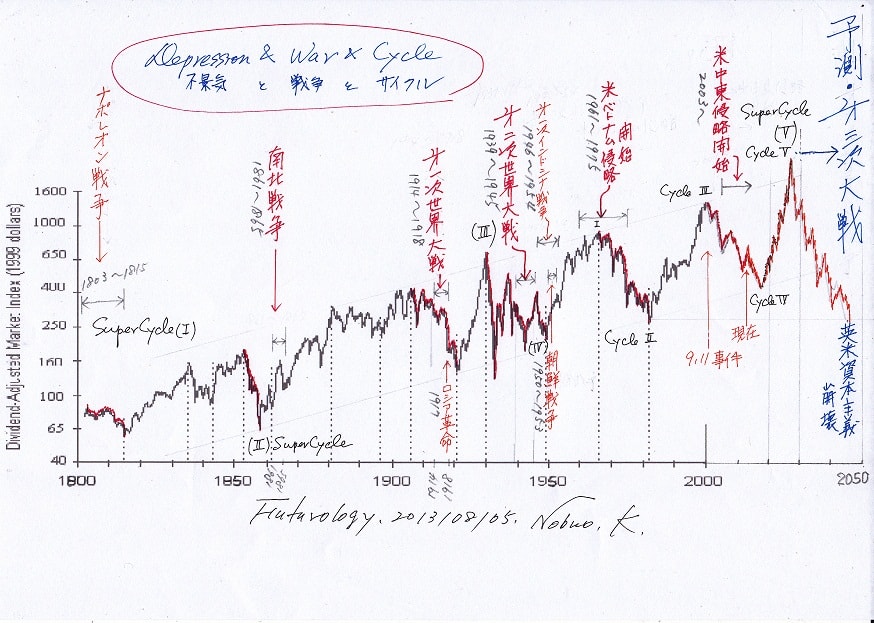ハンサムでない元副総裁
★ http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NC7BVM6JTSE801.html
岩田元日銀副総裁: 円安は「自国窮乏化」-08年と類似
9月22日(ブルームバーグ):元日本銀行副総裁の岩田一政日本経済研究センター理事長は、➊ 今の円安は行き過ぎとの見方を示した上で、現在の情勢は
、❷ 円安が「自国窮乏化」につながり、❸ 景気後退に至った2008年前半に似ていると警鐘を鳴らした。
岩田氏は19日のインタビューで、「日本経済の全体のバランスを見て、ファンダメンタルズに近いレートと言われれば、❹1ドル=90-100円ではないか」と指摘。現在の水準は「円安方向にやや行き過ぎになっているのではないか。経済全体に与える影響もプラスとばかりは言えず、むしろ❺ ネットでマイナスということもあり得る」と述べた。
19日の東京市場でドル円相場は109円台に乗せ、08年8月以来の水準までドル高円安が進んだ。日銀の黒田東彦総裁は同日、20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議に出席するため訪れたオーストラリアのケアンズで、❻「今の動き自体について何か大きな問題があるように思っていない」と述べた。
黒田総裁の円安容認論に対し、同じ元財務官の渡辺博史国際協力銀行(JBIC)総裁が同105円程度だった3日、「これ以上円安になること自体がどちらかというと
マイナスになる産業が増えてきている❼ 感じがする」と述べた。
自国窮乏化の先例
岩田氏は「 円安が進み、エネルギー価格も上昇ないし高止まりすると
、❽ 交易条件は大幅に悪化する。企業の仕入れ価格は大きく上がるが販売価格はあまり上がらず、利潤が圧縮され賃金も抑制される」と指摘。その上で「実質所得の国外流出が輸出や生産、所得の増加といった効果を上回ると、経済全体として消費者の効用の水準は低下する」という。
それが実際に起きたのが08年前半。円相場は現在とほぼ同じ100円台後半から110円程度で推移。円安と原油価格高騰で消費者物価(生鮮食品を除くコアCPI)は上昇を続け、同年夏に前年比2.4%上昇とピークを付けた。❾そうした状況下で景気は08年2月に後退局面に入った。
岩田氏は「相対的に拡張的な金融政策と原油高騰の組み合わせで、08年前半は言ってみれば自国窮乏化の状態にあった。交易条件の悪化は、消費者からすれば
❿ 産油国から増税されるのと同じだ。しかも、今年8月の景気動向指数の結果次第で、テクニカルな意味で景気後退と認定される可能性がある点も、08年前半との類似点の1つだ」という。
その上で、「今は幸い、地政学リスクがあるにもかかわらず、原油価格は落ち着いているので多少は救いだが、水準としては高いので、自国窮乏化のリスクが徐々に表れている」という。
⓫ 消費増税はやるしかない
安倍首相は年内に来年10月の消費再増税の是非を決めるが、景気の低迷から延期論も浮上している。しかし、岩田氏は「今の税・社会保障制度を維持すると、政府債務のGDP比率はどうしても発散する。そういうことを考えると、やるしかないというのが私の見解だ」と語る。
岩田氏は日本経済は3つのリスクを抱えているという。1つはフィスカル・ドミナンス(財政支配)。「民間部門が国債をこれ以上買いたくないと思った時、それが始まる。それまでは中央銀行が長期金利をある程度コントロールできるが、それが外れてしまうと、⓬デットのダイナミクスが金利を決めていくようになってしまう」という。
次が長期停滞。経済成長は労働投入、資本投入、全要素生産性の3つで成り立っているが、労働投入は中長期的にマイナス。「資本投入も良くてせいぜいゼロ。全要素生産性が現在の0.7%程度のままだと、われわれの標準予測では今後50年、平均してゼロ成長が続く」という。
。
財政破綻
3つ目のリスクは、⓯消費増税を見送った場合、まずフィスカル・ドミナンスが起き、それが財政破綻につながることだ。「いつ民間が国債を持ちたくないと思うか、1つのめどはネットの貯蓄だ。まだ国債の吸収余力は残っているが、あと10年か、最悪だと5年以内か」という。
さらに、⓰「悪いショックを与えると、市場は期待で動くので、
悪い方に流れると誰も止められない。
消費増税は短期的に見れば明らかに景気にマイナスの影響があるが、財政破綻は欧州で現実に起こっており、日本も潜在的にそういうリスクを抱えている」という。
こうした状況を打破するのは財政政策でも金融政策でもないと岩田氏はいう。「長期的に実質消費水準が下がっていく事態をブレークスルーするのは⓱成長戦略しかない。生産性を上げる一番大きな要因は開放経済だ。その点、⓲TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)が重要だし、投資で言えば⓳法人税率引き下げだ」と強調。「ハードルは高いが、もしここでもたつけば、長期停滞の道を結果的に選択してしまう」と語った。
金融政策はほぼ限界
金融政策については⓴「
マネタリーベースを倍増する政策は技術的な意味で限界まで打ち出されたと思う」としながらも、需給ギャップの改善の遅れに加え、
これまでの円安効果の剥落により、コアCPIは今後「1%を切る可能性がある。日銀は2%を物価の安定と位置付けているので●㉑ そういうリスクがあれば追加緩和をやるしかない」とみている。
岩田氏は、日銀が物価目標を達成するには「2年という期間は短すぎ、少なくとも5年はかかる」と指摘。「中央銀行が2%を目標にすると宣言したら、その途端に人々の期待が2%までジャンプするかというと、そうではない」とした上で、日銀は2年で達成するという目標を撤回し、●㉒
5年程度の中期的な目標に修正すべきだとの見解を示した。
記事に関する記者への問い合わせ先:東京 日高正裕 mhidaka@bloomberg.net;東京 藤岡 徹 tfujioka1@bloomberg.net
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
● ㉒ またまた蠢き始めた、
白川残党。デフレ派がいつの間にか、5年後の2%インフレターゲット派に変身。
数字の小細工で、本質議論を避けて相手を非難する、いつもの手口である。
●
デフレ派なのに、⓴コアーCPIは1%切る可能性があるので、追加緩和をやるしかないという。論理の混乱のみ
ならず矛盾があちこちに見られます。
マネタリーベースは限界まで打ち出されていると言った矢先に追加緩和
をすべきという、驚くべき矛盾である。自分の信念と相手の政策が入り乱れて、結局何が言いたいのか
ハッキリしない。右が正しいと思うが左に行くときはこうすべき”と言っているようなものである。
● 成長戦略は⓳TPPと言っているが、その根拠を示すべきである。又⓳法人税は引き下げるべきと言いながら、
消費税は絶対10%に上げるべきと言っている。その整合性をデータで示すべきである。
●
⓰悪いショックで悪方向に向けばだれも止められない、消費税は短期的には悪い影響を齎すと言いながら
やはり10%に上げるべきという。
● 「社会保障制度を改革しなければ、少子高齢化により、⓭ 働く世代の税と社会保障の負担が増えていく。
働く世代の貯蓄率は下がり、可処分所得は減る。そうすると⓮ 1人当たりの実質消費水準も
下がっていくが、それでもいいのか」、と言いながら
消費税で国民の可処分所得を減らせ
と言う。論理の著しい矛盾である。
● ➊❷❸2007年までは、円は120円台であり、経済にはそれほど大きな影響は有りませんでした。
2008年になり、
日銀が緩和政策を止めてから、円高に進行したのです。リーマショックで
世界の株が大暴落する過程の一時期の現象を、意図的に曲解している。
●
その時は今と逆に、円高になる過程であり、今の円安になる過程とは全くの真逆です。
山を下りる人が、途中で山を登ってくる人に遭って、我々は同じ境遇だと言っている
ようなものです。
山登りが終わりあとは鼻歌で帰る人と今からリスクを冒して
危険な山に登る人とが、何故同じ境遇なのです?
● 上り坂下り坂を同じと言っているのです。
同じかどうかは自転車を漕いでみれば分かります。
この人は本当に愚かではないのだろうか? もしくは確信犯?。
● ❼これ以上円安になると、マイナスになる企業が増えるような
気・が・す・ると言っていますが、
アンケートやデータや資料などを示さずに、気がするでお茶を濁している。これは知恵者の
する事ではありません。又は悪知恵を働かしているつもりでしょうが、単なるアホである。
● ❿原油高になれば、産油諸国から増税されるようなもので、交易条件が悪化して、日本経済は
景気が悪くなると言う。
自国の税金は景気に影響ないとデモ言うのでしょうか?
原油高は我々の影響下にはないのです。すべての国がこうむる影響であり、
その意味では
産業国家はすべて、交易条件が悪化するものです。
● この原油高は、
日本政府の方針とは全く別次元で動いているのです。政府とは関係ありません。
日本は過去二回の原油ショックを乗り越えてきた稀有な国です。日本の省資源の技術は
世界一なのです。2度あることは三度ある。今回も他国に比してより乗り越えられる
ことは想定内です。この時=
原油高で世界が苦しんでいる時こそ日本の出番なのです。
● この時は世界の資源のない産業国家、
特に中韓は苦しみます。そして自国の貨幣を切り下げて
乗り越えようとします。その時こそすかさず、もっと金融緩和をして円安に持って行き、
中韓の企業を抑えてこそ、日本の企業の復活があるのです。
● 分かりやすく言えば、
皆が大変な時の我慢比べです。試練=原油高は誰にも来るのです。
その試練で生き残った国⁼企業が明日を制するのです。中韓に負けては駄目です。
中韓に負ければ、アジアで日本は悲惨な事になります。
これは生き残り競争なのです。
● この様な世界的な俯瞰能力がないので、自国内の問題で全てが解決するという、愚かな日本の
教科書しか知らない、教科書秀才の最大の問題点です。
● だから東大は解体の必要があるのです。
問題解決能力=応用問題を解く能力がないのです。
答えのない現実の問題や未来の問題を解くには、彼らは国家にとって邪魔な存在です。
● 初回の追加緩和は、バズーカ砲でしたが、今回はブクミサイルが必要なのです。
初回の❹倍(つまり今の更に2倍の)緩和が必要なのです。残念ながら
バズーカ如きでは世界を生き残る事は出来ないのです。