今日10月4日は、「里親デー」なんですね。 戦後早い時期に制定されたと
ありますが、あまり知られていないのではないでしょうか? そういう私もあまり
関心がなかったのか知りませんでした。 カレンダーなどには、「十三夜」や「ハロ
ウイン」の記述はありますが、「里親デー」は書かれていませんでした。
この記念日は、1948年(昭和23年)に施行された「里親等家庭養育の運営に関
する厚生事務次官通告」にちなみ、里親制度が正式にスタートし、戦災孤児をはじ
めとする多くの子どもたちが家庭での養育を受ける機会を得ることとなりました。
そして、1950年(昭和25年)に厚生省によって「里親デー」が制定され、戦後の
混乱期に社会的養護の必要性に応え、里親制度の普及と理解促進が求められました・・
とあります。
 (厚労省より)
(厚労省より)
なるほど、戦後の混乱期に多くの戦災孤児たちに対して家庭の愛と支えを与える
べく、大きな社会メッセージとして制定されているのですね。しかし、現代社会に
おいてもその意義は失っているどころか、多くの生みの親と暮らすことが難しい
子どもたちに対して、児童福祉法に基づいて、家庭環境で愛情をもって育てられる
ことの大切さは、何も変わることなく続いているのです。
日本に、生みの親と離れて暮らす子どもが現在4万2000人いてそのうち8割以上が、
乳児院や児童養護施設で生活を送っているとあります。これは、先進諸国と比べて
も圧倒的に多いそうで、里親だけで言えば、オーストラリアは93%、アメリカは
77%であるのに対し、日本が18%にとどまっているとあります。
日本財団(*脚注)の調査によると潜在的な里親候補者は100万世帯いるのに、
実際に里親家庭で生活する子どもは約7,500人(2019年度、ファミリーホーム含む)
とあります。
 (読売オンラインより)
(読売オンラインより)
どうしてこのように、里親制度や特別養子縁組制度が普及せずに大きなギャップが
生じているかといえば、圧倒的な情報不足が一つの原因であると分析されています。
たしかに、ネットで本件を検索しても、的確なページが見当たらず、しかも、統計
的なデータ(難しいのかもしれませんが)が殆ど見当たらない状況でした。
(個人的に思うのは、日本の住環境によるところも大きいのではないかと・・。)
里親には経済的な支援(月々9万円+養育費5〜6万円の補助、そのほか教育費、
医療費など)があり短期委託も可能であるそうで、制度への理解が進めば、多くの
子どもが家庭を得られる可能性があるとも述べられています。
(日本財団、高橋恵里子さん)
*日本財団は、地方自治体が主催するボートレースの売上金をもとに、国内外の社会課題
解決に取り組むNPOの事業への資金助成をする民間の団体。 活動資金の助成をするだけ
でなく、新たな社会課題を見つけ、解決のためのモデルを作る、調査と実践の機能を持つ
世界でもユニークな財団です。「いいことは、みんなでやろう」を合言葉に、寄付や
ボランティア文化の醸成も進めています。
このような歴史を有する「里親制度」に対して国はどのような施策を取っている
のか? まことに遅ればせながら、ネットを繰ってみました。
里親には、さまざまな迎え入れ方があり、4つの種類があります。
- 養育里親:原則18歳未満のこどもを、家庭に戻るまでの間や自立するまでの間、
養育します。期間は1年以内の短期それ以上の長期の場合もあります。 - 専門里親:養育里親のうち、虐待、非行、障害などの理由により専門的な援助を
必要とする子供を養育する里親です。 - 養子縁組里親:養子縁組を結ぶことが前提です。養子縁組が成立するまでの間、
里親として一緒に生活します。 - 親族里親:実親が死亡、行方不明などにより養育できない場合に、祖父母など
の親族がこどもを養育する里親です。
その他にも、自治体独自の取り組みとして、季節里親、週末里親があります。
これは、週末やお正月・夏休みなどの長期休暇に、数日から1週間ほど、施設で
暮らすこどもを家庭に迎えるというものです。 平日はこどもとの時間が取れない
人や、最初から長期で養育するのが不安な人などに向けて設定されています。
自治体独自の取り組みなので、名称や事前研修の有無等、自治体によって運用が
異なるそうです(例:東京都「フレンドホーム」、横須賀市「ボランティアファミリー」)。

従来、子どもに関する所管が文部科学省、厚生労働省、内閣府、警察庁など様々な
省庁に分かれ、縦割り行政になっていると指摘されてきましたが、ここ数年をかけ
て、内閣府の外局として「こども家庭庁」が 昨年(2023年)4月1日に発足しました。
この間の経緯について、ウイキペディアに詳しく述べられていますが割愛しました。
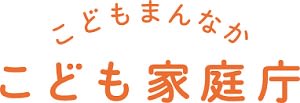 (同庁より)
(同庁より)
で、この「こども家庭庁」を検索してみました。
内閣府特命担当大臣 三原じゅん子(この10月1日に就任)、こども家庭庁長官 渡辺
由美子(初代)で、組織区分は、大きく「企画立案・総合調整部門」、「成育部門」、
「支援部門」の三部門から構成され合計定員は430名とあります。来年度予算案の
概算要求は6兆4600億円(今年度の2400億円増)とあります。
こども家庭庁は、子育てや少子化、児童虐待、いじめなど子どもを取り巻く社会
問題に対して本質的な対策を進め解決するために内閣府に設置された組織ですから
しっかりと活動してもらいたいところです。

虐待などを含めて家庭で暮らせずにいる子どもがたくさんいる現状において
「里親デー」は、里親制度や児童養護の重要性について考えるだけでなく、子ども
たちが幸せに育つために、社会全体で子どもたちを支える意識を高め、彼らが健やか
に成長できる環境を整えることが、私たちの大きな使命であると、社会に対して
大切なメッセージを発信しているのですね。

里親制度について「こども家庭庁」ホームページ(下記)を観ましたが、お役所
風のページで、誰もが引き寄せられて気軽に閲覧できる構成とは思えなかったですね。
(https://www.cfa.go.jp/policies/shakaiteki-yougo/satooya-seido)

私の住む市では、月一の広報誌に、A4半ページに『10月は「里親月刊です。」』
の見出しで、里親制度の概要、里親の種類、里親になるには・・の解説が掲載され
ていました。
「Ya Ya(あの時代(とき)を忘れない)」 サザンオールスターズ

















