毎度、だんだん年がおし詰まってくると思い浮かべるのが、愛すべき20世紀のカルチャーで活躍した偉人の死去の名前。
特に60年代から70年代に活躍したミュージシャンはみんないい年なんで、次々と天国の扉をノックする。
チャックベリーに
トム・ペティ
そういえば、リンゴも亡くなった、、、
沖縄こどもの国で飼育されていたライオンだけど。
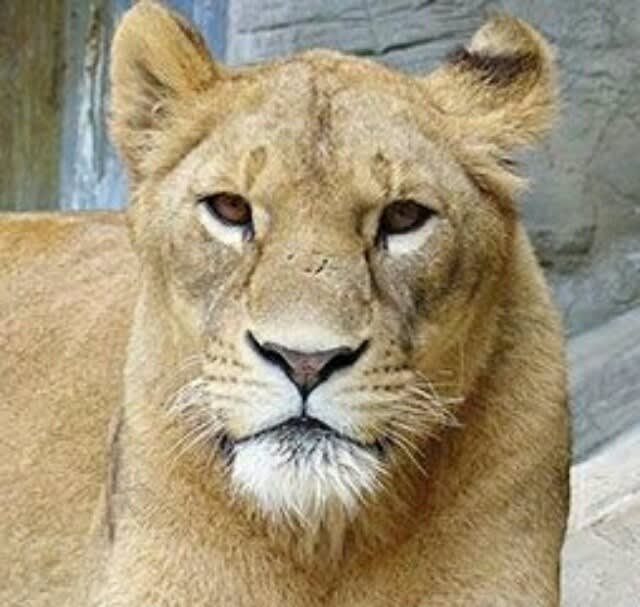
一番ショックだったのは、やはり遠藤賢司。
年をとっても衰えず進化し続ける音楽家の死はなんというか、もったいないというか、もう一度見ておけば良かったと悔やまれる。
あとは、ホルガーチューカイ。
昔、サントリーのCMで採用されていたり、ピーターバラカンのラジオ番組の頭に流れていたりして、日本でもそこそこ知名度あるけど、
何といっても彼を中心に60年代後半に結成されたジャーマンロックのバンド、
『CAN』
現代音楽、民族音楽、実験音楽、フリージャズなどからヴェルヴェットアンダーグラウンドなどのロック、果てには雅楽までも取り込んだサウンドは、未だに旧さを感じさせない。
常々バントの中では、自発(spontaneous)が合言葉のように言われていたそうだ。
最近たまたま、川上未映子による村上春樹へのインタビュー「みみずくは黄昏に飛び立つ」
を読んだ。
その第一章「優れたパーカッショニストは一番大事な音を叩かない」で、小説の書き方について、
リズム、ボイス、フリーインプロビゼーションの感覚にプラスして、大事なのは
「自発性」だと。
それだけは。テクニックでは補えないと。
あと、あっち側に行っちゃう感覚、一種の天国的な領域に足を踏み入れることが感動的な小説や音楽にも不可欠だという。
先ずは書き上げてから、書き直す。その書き直しのすごさは、自慢らしい。
ホルガーチューカイも録音したテープを手作業で切って編集するという実験を繰返し、サンブリングの先駆者と呼ばれるようになった。
CANのアルバムの楽曲も長尺なインプロsessionの録音を、後でじっくり編集し直して作品に仕上げるという方法が多くとられている(と思う)
別に、二方の共通点がどうこうではないんだけど、自分の好きな作品には、似たような方法で出来上がったものが多いような気がしたんだな。
初めから全てを設定してしまうんではなく、大事なものを失わないように流れに身を任せて、、、
以前は、ペーバーハウス位しか映像がなかったけど、全盛期のライブ映像などが沢山フリーで見られるのはありがたい時代になったのか、
そうでもないのか、
特に60年代から70年代に活躍したミュージシャンはみんないい年なんで、次々と天国の扉をノックする。
チャックベリーに
トム・ペティ
そういえば、リンゴも亡くなった、、、
沖縄こどもの国で飼育されていたライオンだけど。
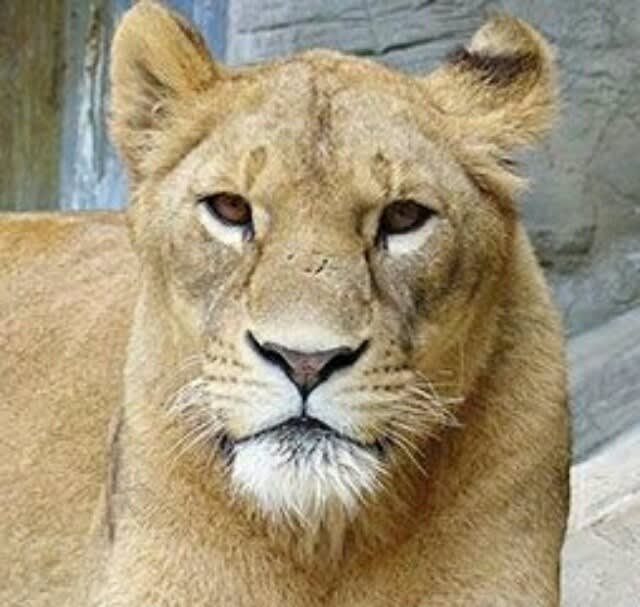
一番ショックだったのは、やはり遠藤賢司。
年をとっても衰えず進化し続ける音楽家の死はなんというか、もったいないというか、もう一度見ておけば良かったと悔やまれる。
あとは、ホルガーチューカイ。
昔、サントリーのCMで採用されていたり、ピーターバラカンのラジオ番組の頭に流れていたりして、日本でもそこそこ知名度あるけど、
何といっても彼を中心に60年代後半に結成されたジャーマンロックのバンド、
『CAN』
現代音楽、民族音楽、実験音楽、フリージャズなどからヴェルヴェットアンダーグラウンドなどのロック、果てには雅楽までも取り込んだサウンドは、未だに旧さを感じさせない。
常々バントの中では、自発(spontaneous)が合言葉のように言われていたそうだ。
最近たまたま、川上未映子による村上春樹へのインタビュー「みみずくは黄昏に飛び立つ」
を読んだ。
その第一章「優れたパーカッショニストは一番大事な音を叩かない」で、小説の書き方について、
リズム、ボイス、フリーインプロビゼーションの感覚にプラスして、大事なのは
「自発性」だと。
それだけは。テクニックでは補えないと。
あと、あっち側に行っちゃう感覚、一種の天国的な領域に足を踏み入れることが感動的な小説や音楽にも不可欠だという。
先ずは書き上げてから、書き直す。その書き直しのすごさは、自慢らしい。
ホルガーチューカイも録音したテープを手作業で切って編集するという実験を繰返し、サンブリングの先駆者と呼ばれるようになった。
CANのアルバムの楽曲も長尺なインプロsessionの録音を、後でじっくり編集し直して作品に仕上げるという方法が多くとられている(と思う)
別に、二方の共通点がどうこうではないんだけど、自分の好きな作品には、似たような方法で出来上がったものが多いような気がしたんだな。
初めから全てを設定してしまうんではなく、大事なものを失わないように流れに身を任せて、、、
以前は、ペーバーハウス位しか映像がなかったけど、全盛期のライブ映像などが沢山フリーで見られるのはありがたい時代になったのか、
そうでもないのか、
"Can - Mother Sky" を YouTube で見る




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます