先日の新聞記事。
所有者不明の土地が現在九州の面積より広く存在しており、これ以上増やさないための法案が国会で審議されている。この要因については所有者死亡時の相続のあり方との指摘している。

仕事柄相続についてはよく耳にする。価値のある土地であれば別だが、バブルの頃に購入した行ったことも見たことも無い「負動産」と呼ばれる土地については相続人も積極的にはならずそのまま放置され、また代が代わり相続人が増加し、そのまま「塩漬け」になってしまう悪循環。その面積が2040年には720万ヘクタールに達する可能性があり、実に北海道本島に迫るとのこと。

改めて日本地図で北海道の広さを確認する。この広さの土地が塩漬けされているなんて非常に勿体ない。記事には国道新設のため土地所有者を確認したところ、明治生まれの故人のままで、法定相続人は判明しただけで148名にもなり、特定に至らない例も相次いだ結果、約3年を要したと書かれている。現在住所変更時や相続時の登記を義務化や違反過料をする不動産登記法の改正案が衆院を通過し、参院で審議されている。
ただ相続には法定相続人間での分け方を決め、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印捺印して法務局へ提出する必要があり、全員分の印鑑証明書や住民票、故人の所有者の戸籍謄本を揃える労力が必要となり、さらに疎遠や犬猿になっている親族とのやり取りもあり、なかなか進まないのも頷ける。
相続した土地を手放せる制度「相続土地国庫帰属法」の新法についても併せて審議中で、建物や土壌汚染がなく、担保が設定されていない等の一定の要件を満たせば、用途や面積、周辺環境に応じて定める10年分の管理費相当額を納付し、所有権を国庫に帰属させられるようにする。ちなみに標準的な10年分の管理費は原野で約20万、宅地(200平方)で約80万とのこと。う~んただでさえ大変な相続の上、所有している土地を手放すにも関わらずさらに管理費を支払う相続人がどれぐらいいるのだろうか?
大幅な相続についての改正がない限り、財産は残すのではなく、下手な土地は所有しないこと・亡くなる前に処分するなど根本的な対応が残された相続人のためには必要なのだろう。
そして昨日の参院本会議で全会一致により可決成立した。
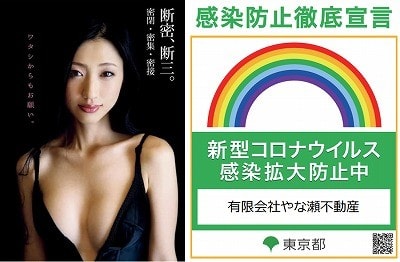
 【総武線・新小岩駅 賃貸専門店】有限会社やな瀬不動産
【総武線・新小岩駅 賃貸専門店】有限会社やな瀬不動産

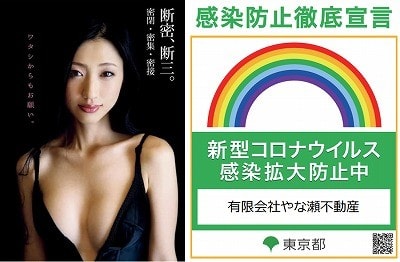













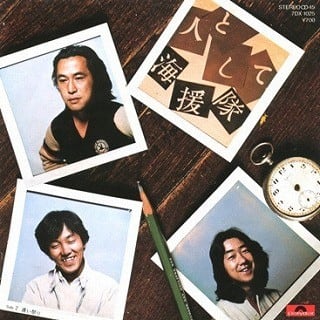

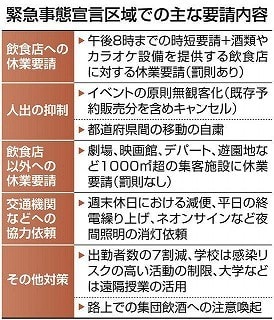










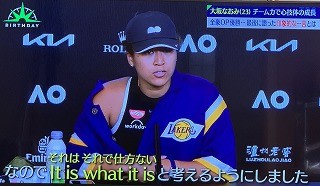

 これもまた人生やね
これもまた人生やね 】
】















