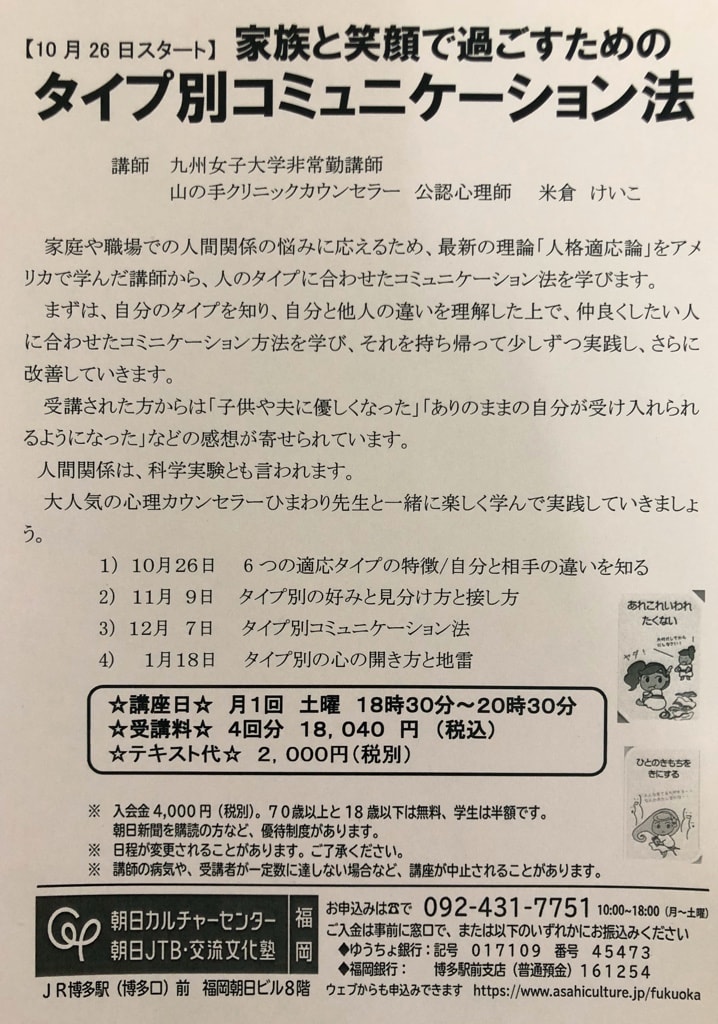写真は、福岡市博多区博多消防署に咲く大輪のひまわり。
写真は、福岡市博多区博多消防署に咲く大輪のひまわり。
先週10月というのに、ひまわりがノビノビと太陽に向かって咲いていました。
さて、私はカウンセリングの技法を学び
相談を受けるようになって18年目になりました。
大学院も卒業して
公認心理師という国家資格も取得しました。
そんな私は、面談している10代、20代のクライアントさんからも
沢山のことを教えてもらいます。
特に、
「純粋性」
「率直さ」
違った視点からの意見、見方も新鮮です。
その度に、傲慢にならないように自分を戒めます。
「素人と玄人」というタイトルの夏目漱石のエッセイにも、
その様な記述があります。
1914年(大正13年)東京朝日新聞に掲載された夏目漱石のエッセイを引用します。
以下、引用
***
まず第一にわが眼に入るのはその輪郭である。次にはその局部である。
次には局部の又また局部である。
観察や研究の時間が長ければ長いほど、段々細かい所が眼に入って来る、ますます小さい点に気が付いて来る。
これはすべての物に対する我々の態度であって、ほとんど例外を許さないほど応用の広い自然の順序と見ても差支さしつかえない。
だから芸術の研究も亦またこの階段を追って進んで行くに違いない。
いわゆる黒人というものはこの道を素人より先へ通り越したものである。
そうしてそこに彼等の自負が潜んでいるらしい。
彼等の素人に対する軽蔑の念も亦そこから湧わいて出るらしい。
けれどもそれは彼等が彼等の径路を誤解して評価づけた結果に過ぎないと、自分は断言してはばからない。
彼等の径路は単に大から小に移りつつ進んだのである。
浅い所から深い所に達しつつあるのでもなければ、上部から内部に立体的に突き込んで行きつつあるのでもない。
大通りを見つくしたから裏通りを見る、裏通りを歩き終ったから、横丁や露地を一つ一つ覗のぞいているという順序なら、たとい泥板どろいたの上を一軒一軒数えて廻っても、研究の性質に変化の来る筈はずがない。
それを低い平面から高い平面に移された様に思うのは、いわゆる黒人のイリュージョンで、平凡な黒人は皆このイリュージョンに酔わされているのである。
単にこれだけなら彼等の芸術に及ぼす害毒はさほど大したものでないかも知れない。
けれども彼等はこの甘いイリュージョンに欺あざむかれて、大事なものは何処どこかへ振り落して気が付かずにいるのである。
観察が輪郭に始まって漸々ぜんぜん局部に移っていくという意味を別の言葉で現すと、観察が輪郭を離れてしまうという事に帰着する。
離れるのは忘れる方面へ一歩近寄るのと同然である。
しかもその局部に注ぐ熱心が強ければ強いほど輪郭の観念は頭を去る訳である。
だから黒人は局部に明るい癖に大体を眼中に置かない変人に化けて来る。
そうして彼等の得意にやってのける改良とか工夫というものはことごとく部分的である。
そうしてその部分的の改良なり工夫なりが毫ごうも全体に響いて居ない場合が多い。
大きな眼で見ると何の為にあんな所に苦心して喜んでいるのか気が知れない小刀細工をするのである。
素人は馬鹿馬鹿しいと思っても、先が黒人だと遠慮して何もいわない。
すると黒人はますます増長してただ細かく細かくと切り込んで行く。
それで自分は立派に進歩したものと考えるらしい。
高い立場から見下すとこれは進歩でなくって、堕落である。
根本義を棚へ上げて置いて、末節にばかり齷齪あくせくする自分の態度に気がついたら黒人自身もしか認めなければなるまい。
素人はもとより部分的の研究なり観察に欠けている。
その代り大きな輪郭に対しての第一印象は、この輪郭のなかで金魚のようにあぶあぶ浮いている黒人よりは鮮やかに把捉はそく出来る。
黒人のように細かい鋭さは得られないかも知れないが、ある芸術全体を一眼に握る力に於おいて、糜爛びらんした黒人の眸ひとみよりもたしかに溌剌としている。
富士山の全体は富士を離れた時にのみ判然と眺められるのである。
ある芸術の門を潜もぐる刹那に、この危険は既にその芸術家の頭に落ちかかっている。
虚心に門を潜ってさえそうである。
与えられた輪郭を是認して、これは破れないものだと観念した以上、彼の仕事の自由は到底毫釐ごうりの間をうろついているにすぎない。
だから在来の型や法則を土台にして成立している保守的の芸術になると、個人の自由はほとんど殺されている。
その覚悟でなければ這入はいる訳に行かない。
能でも踊おどりでも守旧派の絵画でもみんなそうである。
こういう芸術になると、当初から輪郭は神聖にして犯すべからずという約束の下に成立するのだから、その中に活動する芸術家は、たとえ輪郭を忘れないでも、忘れたと同じ結果に陥って、ただ五十歩百歩の間で己の自由をみせようと苦心するだけである。
素人の眼は、この方面においても、一目の下に芸術の全景を受け入れるという意味から見て、黒人に優っている。