小関智弘さんの『働きながら書く人の文章教室』 にこんな言葉がある。
にこんな言葉がある。
《…ノンフィクションだから、事実をありのままに羅列すればいい、というものではない。事実を、イメージ豊かに読者に伝えるには、事実を肉付けする豊富なエピソードが必要である。》
《民衆のなかには無数の事実が散乱しているが、それらの事実、民衆あるいは庶民と呼ばれる人びとが経験したものの蓄積は、そのままでは墓場に埋もれてしまう運命にある。それをどう掬い上げ表現するかが、書き手の役割である。》
《数字や資料は、文章の骨格をつくる。エピソードがそれに肉付けをし、血を通わせる。そういう意味でわたしは、とりわけノンフィクションを書く場合にエピソードを大切にしている。》
どれも我が意を得たりの思いがする。
追記
《エピソードは、その文章の肉付けをし血を通わせるだけではない。エピソードは、書いた本人がそれと気づかない力を、その内側に秘めているものなのだ。(略)読者の想像力を引き出し、その想像力によって育つことができる生命力をその内側に秘めている。(略)その期待や予測を超えるものを書くのが書き手の力量ではないか、と肝に銘じつつ書いた。》
《他人を語ることは、自分を語ることである。自分というフィルターを通してしか、他人を語ることはできないのだから。》
《それはともかく、掴みボクロの体験でわたしは、聞き手のプロというのは話を脱線させる名手なのにちがいないと確信した。意識して脱線させようとしてできることではないが、》
《わたしのフィルターは、旋盤工そのものであった。(略)フィルターを通して、そこで濾過して不要なものは捨て、必要なものだけを使う。それをしなかったら、たとえば一人の人生を語ってもらって、それをわずか十五枚や二十枚の原稿に凝縮して書くなんてことはできはしない。》
《他人を語ることはおのれを語ることであるが、なにかを語らないことがおのれを語っている、ということだってあり得るはずである。取材ノートにびっしり書き込まれた話題のあれこれ、二時間三時間に及ぶ録音テープに吹き込まれた豊富なエピソードや脱線ばなしの数々、そこから何を取り捨てるかは、書き手の選択にまかされているのだから。》
《町工場ではかつて”一人残業”はさせないという不文律があった。不測の事故に備えてのことである。》
これはわたしも経験したこと。三年間の町工場勤めで、何度も危険な場面に遭遇した。機械は無情なのである。
《わたしはかつて一度も、どこかの出版社や雑誌の編集部というようなところに自分の原稿を”売り込み”に行ったことがない。すべては依頼されて書いた。(略)安月給とはいえ、最低の生活は旋盤工で稼げる。原稿料や印税だけで食べていく身だったらそうはいかないだろうなと、そんなときはほっとしたものである。》
《わたしは、工場と書いて「こうば」と読んでいる。「こうじょう」だと、建物と機械がクローズアップされてしまって、そこで働く人たちが点景になってしまうというイメージが強い。「こうば」だと、働いている人間がクローズアップされて、建物や機械はその背景に後退する。(略)主人公は人間だという思いを込めている。》
このことについては、20年以上も前に拙詩集『工場風景』をお送りした際、「わたしは『こうばふうけい』と読みます」と評して下さったことを思い出した。
《工場の人たちは口が重いとか、職人はなかなか話をしてくれないなんて言う人がいるが、それはその人の器が貧弱だからにすぎない。人格や教養のことではない。相手の話を受け入れる、容器としての器である。(略)口が重いと思うのは、彼らの心を開かせる手段を知らないにすぎない。》
《…わたしはそういう人たちの実体験を聞いた。しかしその実体験をそのまま書けばルポルタージュになるのか、といえばそうではない。そのまま書くだけなら、メモやテープを起こして、体験記とすればいい。(略)文章を書くというのは、聞いた話のテープを起こすことではない。実際にその人たちの人生に触れた直接の印象から出発して、さらにもう一歩も二歩も深い現実に踏み込んでいくのが、ルポルタージュやノンフィクションを書く者の役割である。》
《書き手は常に軟らかな感性を磨き、他人の話を謙虚にそして真摯に受け入れる器となることが必要なのであろう。そうやって書いた文章を、語ってくれた人にお返しする、それが書き手の役割というものであろう。(略)そこに書かれた自分の姿から、何か一つでも新しい自分を発見して頂くことができたなら、それこそ書き手冥利に尽きるというものではあるまいか。》
ここまでお読みくださいましてありがとうございます。
小関さんにご興味を持っていただけた方には、もう少しお付き合いください。
小関さん原作のテレビドラマの話です。
緒形拳さんとのエピソード。感動的です。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。
 ←クリック。
←クリック。
 ←クリック。
←クリック。
どうでしょうか。小関さんのお人柄があふれ出たような文章ではありませんか。
 にこんな言葉がある。
にこんな言葉がある。《…ノンフィクションだから、事実をありのままに羅列すればいい、というものではない。事実を、イメージ豊かに読者に伝えるには、事実を肉付けする豊富なエピソードが必要である。》
《民衆のなかには無数の事実が散乱しているが、それらの事実、民衆あるいは庶民と呼ばれる人びとが経験したものの蓄積は、そのままでは墓場に埋もれてしまう運命にある。それをどう掬い上げ表現するかが、書き手の役割である。》
《数字や資料は、文章の骨格をつくる。エピソードがそれに肉付けをし、血を通わせる。そういう意味でわたしは、とりわけノンフィクションを書く場合にエピソードを大切にしている。》
どれも我が意を得たりの思いがする。
追記
《エピソードは、その文章の肉付けをし血を通わせるだけではない。エピソードは、書いた本人がそれと気づかない力を、その内側に秘めているものなのだ。(略)読者の想像力を引き出し、その想像力によって育つことができる生命力をその内側に秘めている。(略)その期待や予測を超えるものを書くのが書き手の力量ではないか、と肝に銘じつつ書いた。》
《他人を語ることは、自分を語ることである。自分というフィルターを通してしか、他人を語ることはできないのだから。》
《それはともかく、掴みボクロの体験でわたしは、聞き手のプロというのは話を脱線させる名手なのにちがいないと確信した。意識して脱線させようとしてできることではないが、》
《わたしのフィルターは、旋盤工そのものであった。(略)フィルターを通して、そこで濾過して不要なものは捨て、必要なものだけを使う。それをしなかったら、たとえば一人の人生を語ってもらって、それをわずか十五枚や二十枚の原稿に凝縮して書くなんてことはできはしない。》
《他人を語ることはおのれを語ることであるが、なにかを語らないことがおのれを語っている、ということだってあり得るはずである。取材ノートにびっしり書き込まれた話題のあれこれ、二時間三時間に及ぶ録音テープに吹き込まれた豊富なエピソードや脱線ばなしの数々、そこから何を取り捨てるかは、書き手の選択にまかされているのだから。》
《町工場ではかつて”一人残業”はさせないという不文律があった。不測の事故に備えてのことである。》
これはわたしも経験したこと。三年間の町工場勤めで、何度も危険な場面に遭遇した。機械は無情なのである。
《わたしはかつて一度も、どこかの出版社や雑誌の編集部というようなところに自分の原稿を”売り込み”に行ったことがない。すべては依頼されて書いた。(略)安月給とはいえ、最低の生活は旋盤工で稼げる。原稿料や印税だけで食べていく身だったらそうはいかないだろうなと、そんなときはほっとしたものである。》
《わたしは、工場と書いて「こうば」と読んでいる。「こうじょう」だと、建物と機械がクローズアップされてしまって、そこで働く人たちが点景になってしまうというイメージが強い。「こうば」だと、働いている人間がクローズアップされて、建物や機械はその背景に後退する。(略)主人公は人間だという思いを込めている。》
このことについては、20年以上も前に拙詩集『工場風景』をお送りした際、「わたしは『こうばふうけい』と読みます」と評して下さったことを思い出した。
《工場の人たちは口が重いとか、職人はなかなか話をしてくれないなんて言う人がいるが、それはその人の器が貧弱だからにすぎない。人格や教養のことではない。相手の話を受け入れる、容器としての器である。(略)口が重いと思うのは、彼らの心を開かせる手段を知らないにすぎない。》
《…わたしはそういう人たちの実体験を聞いた。しかしその実体験をそのまま書けばルポルタージュになるのか、といえばそうではない。そのまま書くだけなら、メモやテープを起こして、体験記とすればいい。(略)文章を書くというのは、聞いた話のテープを起こすことではない。実際にその人たちの人生に触れた直接の印象から出発して、さらにもう一歩も二歩も深い現実に踏み込んでいくのが、ルポルタージュやノンフィクションを書く者の役割である。》
《書き手は常に軟らかな感性を磨き、他人の話を謙虚にそして真摯に受け入れる器となることが必要なのであろう。そうやって書いた文章を、語ってくれた人にお返しする、それが書き手の役割というものであろう。(略)そこに書かれた自分の姿から、何か一つでも新しい自分を発見して頂くことができたなら、それこそ書き手冥利に尽きるというものではあるまいか。》
ここまでお読みくださいましてありがとうございます。
小関さんにご興味を持っていただけた方には、もう少しお付き合いください。
小関さん原作のテレビドラマの話です。
緒形拳さんとのエピソード。感動的です。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。 ←クリック。
←クリック。 ←クリック。
←クリック。どうでしょうか。小関さんのお人柄があふれ出たような文章ではありませんか。
今朝の神戸新聞「正平調」です。
神戸新聞さん、拝借お許しを。
 ←クリック。
←クリック。
今、読書週間なんですねえ。知りませんでした。わたしは毎日、一年中が読書週間みたいなものですので。
この正平調の終わりの方にある言葉。
《ページをめくるのも惜しい、そんな本に出会うときがある。》
これ、どこかで聞いたことがあるぞ、と思ったのです。
そうでした。画家で著述家、装幀家、そしてわたしは書評家でもあると思っている林哲夫さんの言葉でした。
拙著『完本コーヒーカップの耳』を評して下さっての言葉。
《読み終わるのがもったいない読書というのはそうあるものではない。そんな一冊。》と。
氏のブログ、「daily-sumus2」です。
うれしい言葉をいただいたのでした。我田引水、お許しを。
そうだ。林さんにはこんな本があります。
『喫茶店の時代』(ちくま文庫)。
残念ながら「喫茶・輪」は出て来ませんが、このブログと縁があるというわけで。
神戸新聞さん、拝借お許しを。
 ←クリック。
←クリック。今、読書週間なんですねえ。知りませんでした。わたしは毎日、一年中が読書週間みたいなものですので。
この正平調の終わりの方にある言葉。
《ページをめくるのも惜しい、そんな本に出会うときがある。》
これ、どこかで聞いたことがあるぞ、と思ったのです。
そうでした。画家で著述家、装幀家、そしてわたしは書評家でもあると思っている林哲夫さんの言葉でした。
拙著『完本コーヒーカップの耳』を評して下さっての言葉。
《読み終わるのがもったいない読書というのはそうあるものではない。そんな一冊。》と。
氏のブログ、「daily-sumus2」です。
うれしい言葉をいただいたのでした。我田引水、お許しを。
そうだ。林さんにはこんな本があります。
『喫茶店の時代』(ちくま文庫)。
残念ながら「喫茶・輪」は出て来ませんが、このブログと縁があるというわけで。
この前読んだ葉室麟さんの『霖雨』という歴史小説はモデルがあったが、今読み終えた時代小説『峠しぐれ』(双葉文庫)はモデルはなく架空の人物が描かれている。フィクションだ。

面白かった。
380ページほどあるが、息つく間もないほどの場面転回があって、しかも、こうなってほしいと思う方に話が流れて行って楽しませてもらった。

面白かった。
380ページほどあるが、息つく間もないほどの場面転回があって、しかも、こうなってほしいと思う方に話が流れて行って楽しませてもらった。
毎朝、NHKの朝ドラ「エール」を見ている。
今日は「栄冠は君に輝く」の話。
作詞者が男性になっていたが、この時点では女性が作詞者とされていたはず。
実際の作詞者、加賀大介が婚約者の名前で応募し、それが採用されたのだった。
その事実が明かされたのは20年後のこと。
これの補作を富田砕花師がされている。
そのこと「神戸っ子」昨年3月号に書きました。
今日は「栄冠は君に輝く」の話。
作詞者が男性になっていたが、この時点では女性が作詞者とされていたはず。
実際の作詞者、加賀大介が婚約者の名前で応募し、それが採用されたのだった。
その事実が明かされたのは20年後のこと。
これの補作を富田砕花師がされている。
そのこと「神戸っ子」昨年3月号に書きました。
入院中に、東京の小関智弘さんから分厚い封書が届いた。
小関さんは、芥川賞直木賞の候補に何度もなった作家さん。
家内が病院に届けてくれて、「なんだろう?」と思ったのだが、開けてびっくり。
《たまたま知り合いの方から送られた「別嬢」を読んでいたところ、貴君のお名前を知りました。》とある。
加古川の詩誌「別嬢」112号を読まれてのことだった。

その号には編集者の高橋夏男氏のお誘いでわたしも駄文を書かせていただいている。
それを読まれたのだ。
まず、小関さんのことだが、氏と知り合ったのはもう20年以上も昔のこと。
わたしが初めてともいえる詩集『工場風景』を30部ほど私家版で出した時、
詩人杉山平一先生がそれを絶賛して下さり、そして、小関さんにもお送りするようにと紹介して下さったのだった。
以後、ずっと交流が続いていて、西宮に講演に来られた時、一度だけお会いしている。
なぜ小関さんの所に「別嬢」が行ったかというと、中に猪狩洋という人の文章が5ページにわたって載っている。
そこに小関さんが登場しているのだ。
猪狩洋さんは、農民詩人猪狩満直のご子息。
満直は高橋夏男さんが、坂本遼、木山捷平と並んでその事跡を追いかけている農民詩人である。
その過程で夏男さんは洋さんを取材し、交流が生まれていたというわけ。
そして、小関さんと洋さんも旧知だった。
小関さんと洋さんの関係もドラマチックで面白いのだが、それは『働きながら…』をお読みいただきたい。
小関さんが送って下さった資料に、ご自身の著書『働きながら書く人の文章教室』(岩波新書)からのコピーがあった。
そこに、猪狩満直と洋さんが登場している。
この本、わたしも以前読んでいるはずだったが、内容は忘れていた。

一部紹介します。
 ←クリック。
←クリック。
前後なんページかに、満直さんと洋さんのことが小関さんの温かい筆致で感動的に書かれている。
そして、洋さんが「別嬢」に書かれた一部。
 ←クリック。
←クリック。
左側ページに小関さんのことが書かれている。
ということで、小関さんの便りにあった「知り合いの方」というのは洋さんだったというわけ。
ホントに世間は広いようで狭いもの。人の世、面白いものです。
人の世の本。『完本コーヒーカップの耳』
小関さんは、芥川賞直木賞の候補に何度もなった作家さん。
家内が病院に届けてくれて、「なんだろう?」と思ったのだが、開けてびっくり。
《たまたま知り合いの方から送られた「別嬢」を読んでいたところ、貴君のお名前を知りました。》とある。
加古川の詩誌「別嬢」112号を読まれてのことだった。

その号には編集者の高橋夏男氏のお誘いでわたしも駄文を書かせていただいている。
それを読まれたのだ。
まず、小関さんのことだが、氏と知り合ったのはもう20年以上も昔のこと。
わたしが初めてともいえる詩集『工場風景』を30部ほど私家版で出した時、
詩人杉山平一先生がそれを絶賛して下さり、そして、小関さんにもお送りするようにと紹介して下さったのだった。
以後、ずっと交流が続いていて、西宮に講演に来られた時、一度だけお会いしている。
なぜ小関さんの所に「別嬢」が行ったかというと、中に猪狩洋という人の文章が5ページにわたって載っている。
そこに小関さんが登場しているのだ。
猪狩洋さんは、農民詩人猪狩満直のご子息。
満直は高橋夏男さんが、坂本遼、木山捷平と並んでその事跡を追いかけている農民詩人である。
その過程で夏男さんは洋さんを取材し、交流が生まれていたというわけ。
そして、小関さんと洋さんも旧知だった。
小関さんと洋さんの関係もドラマチックで面白いのだが、それは『働きながら…』をお読みいただきたい。
小関さんが送って下さった資料に、ご自身の著書『働きながら書く人の文章教室』(岩波新書)からのコピーがあった。
そこに、猪狩満直と洋さんが登場している。
この本、わたしも以前読んでいるはずだったが、内容は忘れていた。

一部紹介します。
 ←クリック。
←クリック。前後なんページかに、満直さんと洋さんのことが小関さんの温かい筆致で感動的に書かれている。
そして、洋さんが「別嬢」に書かれた一部。
 ←クリック。
←クリック。左側ページに小関さんのことが書かれている。
ということで、小関さんの便りにあった「知り合いの方」というのは洋さんだったというわけ。
ホントに世間は広いようで狭いもの。人の世、面白いものです。
人の世の本。『完本コーヒーカップの耳』
入院中に届いていました。
詩集『そこはまだ第四紀砂岩層』(服部誕著・書肆山田)。

14行詩が26篇、70ページの瀟洒な詩集。
この服部さんからは、先に小説集『もう一つの夏 もう一つの夢』をお贈りいただいている。
この小説集が素晴らしかったので、この人は散文系の人だと勝手に思っていた。
しかしやっぱり詩人なんですね。
語彙が豊富。
そしてスマートな飛躍。
一篇わたしが好きなのを紹介しましょう。
「屋根を超えて」です。
 ←二段階クリックで。
←二段階クリックで。
もしもわたしがこのモチーフで書いたなら、俗っぽいものになるのでしょうね。
泥臭いものに仕上げてしまいそうな気がします。
それはそれでいいのかも知れません、と自己弁護しておきましょうか。
そして、印象的だったのが「あとがき」でした。
 ←クリック。
←クリック。
 ←クリック。
←クリック。
味わい深い「あとがき」ではありませんか。
そしてわたしがことのほか驚いたのは、禅の公案「隻手音声」という言葉が出てきたこと。
実はわたし、若き日に禅寺の門を叩いたことがあり、師家、大井裁断老師から最初に戴いた公案が、この「隻手音声」でした。
たしか一年以上悩まされたかと思います。
そんなこともあって、この『そこはまだ第四紀砂岩層』は印象深い詩集でした。
禅の世界とは正反対?の世界を描いた本『完本コーヒーカップの耳』。
面白うてやがてかなしき人の世かな。
詩集『そこはまだ第四紀砂岩層』(服部誕著・書肆山田)。

14行詩が26篇、70ページの瀟洒な詩集。
この服部さんからは、先に小説集『もう一つの夏 もう一つの夢』をお贈りいただいている。
この小説集が素晴らしかったので、この人は散文系の人だと勝手に思っていた。
しかしやっぱり詩人なんですね。
語彙が豊富。
そしてスマートな飛躍。
一篇わたしが好きなのを紹介しましょう。
「屋根を超えて」です。
 ←二段階クリックで。
←二段階クリックで。もしもわたしがこのモチーフで書いたなら、俗っぽいものになるのでしょうね。
泥臭いものに仕上げてしまいそうな気がします。
それはそれでいいのかも知れません、と自己弁護しておきましょうか。
そして、印象的だったのが「あとがき」でした。
 ←クリック。
←クリック。 ←クリック。
←クリック。味わい深い「あとがき」ではありませんか。
そしてわたしがことのほか驚いたのは、禅の公案「隻手音声」という言葉が出てきたこと。
実はわたし、若き日に禅寺の門を叩いたことがあり、師家、大井裁断老師から最初に戴いた公案が、この「隻手音声」でした。
たしか一年以上悩まされたかと思います。
そんなこともあって、この『そこはまだ第四紀砂岩層』は印象深い詩集でした。
禅の世界とは正反対?の世界を描いた本『完本コーヒーカップの耳』。
面白うてやがてかなしき人の世かな。
入院前に途中まで読んでいた本、『霖雨』(葉室麟・PHP文芸文庫)です。
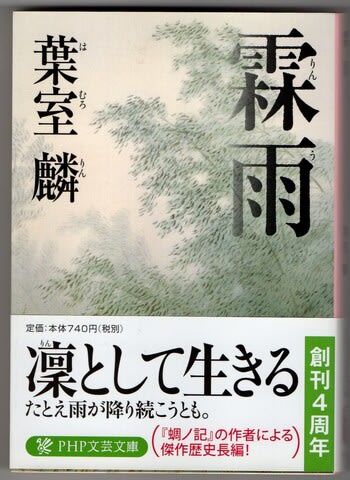
400ページ近い本格的長編時代小説。
病院へは持って行きませんでした。
この小説の続きは家でじっくりと読みたかったのです。
読みごたえがありました。骨太でありながら繊細な小説でした。
時代小説なのですが、主人公は武士ではありません。
「咸宜園」という私塾を主宰する学者広瀬淡窓と商家を継いだ弟の久兵衛を中心とした物語。
今の大分県、日田が舞台。
今の世に生きるものにも心の支えになりそうな話。
読み終えて、「解説」をと思ったら、解説はなく対談録が載っていた。
今回はなぜか解説を先には読みませんでした。
著者の葉室麟さんと大分県知事の広瀬勝貞さんによるもの。
なぜ?と思ったら、広瀬勝貞氏は、この本の主人公のご子孫だという。
広瀬さん、こんなことをおっしゃってる。
《実を言いますと私、淡窓のことがあまり好きではなかったんです(笑)。小さい頃、悪さをしますと母に淡窓先生の教えを繙きながら説教されたものですから。》
広瀬淡窓、魅力的な人だ。弟の久兵衛も。
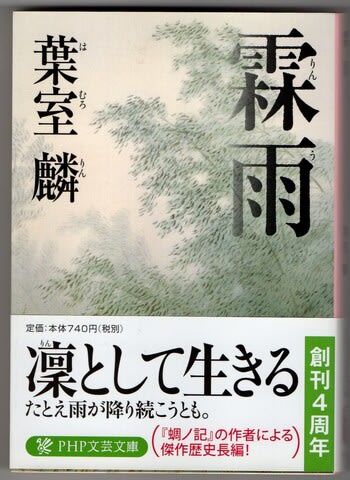
400ページ近い本格的長編時代小説。
病院へは持って行きませんでした。
この小説の続きは家でじっくりと読みたかったのです。
読みごたえがありました。骨太でありながら繊細な小説でした。
時代小説なのですが、主人公は武士ではありません。
「咸宜園」という私塾を主宰する学者広瀬淡窓と商家を継いだ弟の久兵衛を中心とした物語。
今の大分県、日田が舞台。
今の世に生きるものにも心の支えになりそうな話。
読み終えて、「解説」をと思ったら、解説はなく対談録が載っていた。
今回はなぜか解説を先には読みませんでした。
著者の葉室麟さんと大分県知事の広瀬勝貞さんによるもの。
なぜ?と思ったら、広瀬勝貞氏は、この本の主人公のご子孫だという。
広瀬さん、こんなことをおっしゃってる。
《実を言いますと私、淡窓のことがあまり好きではなかったんです(笑)。小さい頃、悪さをしますと母に淡窓先生の教えを繙きながら説教されたものですから。》
広瀬淡窓、魅力的な人だ。弟の久兵衛も。
入院に携えて行った本は『山田稔自選集』Ⅰ~Ⅲの三冊と桂文珍さんの『落語的笑いのすすめ』、そして、詩の同人誌などでした。
入院中に全部読み切れると思ってたのですが、それは甘い考えで、術後二日間はしんどくて読書どころではなかったです。
なので、退院してから『山田稔自選集』の読み残しを読み終え、今、文珍さんの本を読んでます。
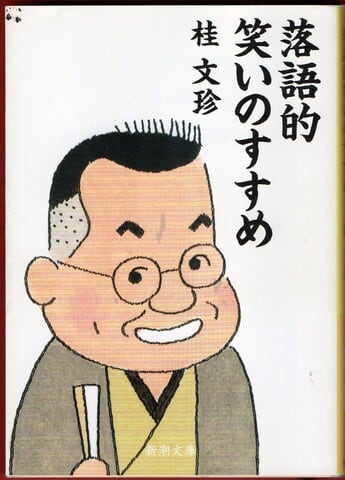
ほぼ終わりの方にこんなことが。
《私は「笑腺」という言葉を作りましたんですが、涙腺があるのと同じように、笑いの腺、笑腺というのがあるんではなかろうかと思います。》
人によってそのツボが違うからと。その人の持っている知識、経験、育った環境、体調、などにより、と。
そのうえで、こんなことを言っておられる。
《笑腺の同じ人と結婚すれば、幸せになれます。安くつきます。》と。
なるほどと思いました。
入院中に全部読み切れると思ってたのですが、それは甘い考えで、術後二日間はしんどくて読書どころではなかったです。
なので、退院してから『山田稔自選集』の読み残しを読み終え、今、文珍さんの本を読んでます。
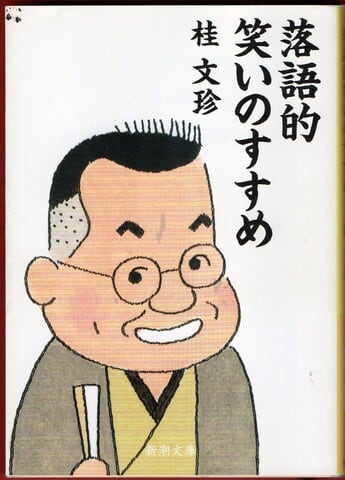
ほぼ終わりの方にこんなことが。
《私は「笑腺」という言葉を作りましたんですが、涙腺があるのと同じように、笑いの腺、笑腺というのがあるんではなかろうかと思います。》
人によってそのツボが違うからと。その人の持っている知識、経験、育った環境、体調、などにより、と。
そのうえで、こんなことを言っておられる。
《笑腺の同じ人と結婚すれば、幸せになれます。安くつきます。》と。
なるほどと思いました。
今日の神戸新聞朝刊「科学」欄に「がん光免疫療法」のことが掲載されていました。

《この治療法は、米国立衛生研究所の小林久隆研究員が開発し「がん光免疫療法」と呼ばれています。》
こうして徐々に世間に認識が広まってゆくのでしょうか。

《この治療法は、米国立衛生研究所の小林久隆研究員が開発し「がん光免疫療法」と呼ばれています。》
こうして徐々に世間に認識が広まってゆくのでしょうか。
10月14日に手術(カテーテルによる)を受けたので、今日で丁度10日。
病院でノートに記していた日誌、『313にて』の編集をぼちぼち始めました。


乱雑な字で書いてますので我ながら読み取るのに苦労する場面も。
冊子に仕上げたいと思ってますが、限定一部発行の非公開です。
病院でノートに記していた日誌、『313にて』の編集をぼちぼち始めました。


乱雑な字で書いてますので我ながら読み取るのに苦労する場面も。
冊子に仕上げたいと思ってますが、限定一部発行の非公開です。
鳥取の詩人手皮小四郎さんからお贈り頂きました。

創刊が1968年となっていますので、半世紀以上の歴史を持つ詩誌。
これがまた、わたしの肌によく合った詩誌なのです。
じっくり、しっとりと読めます。
滝本勤さんの「若きはカメラマン」という詩。
”カメラを買ったばかりの頃” の書き出しで始まるその詩、
百歳の祖母を撮ったが手振れになってしまっていた。
”あの時のカメラもネガも もう手許にはない 手振れの映像を思い出すだけだ”
そして、今、鏡の中の自分の皺の深い顔を見て、
”だが祖母のように 慈愛に満ちてはいない あと三十年も生きられれば
皺はあんなにもふくよかになるだろうか たぶんその前に 私は死ぬであろう
遠い目に見つめられるなら それは祖母であってほしいのだが”
と続く。
そして手皮さんの詩、「草に臥す」がいいです。
 ←クリック。
←クリック。
なにも言わないでおきましょう。じっくりと読んでみてください。
今号は「西崎昌追悼号」となっています。
西崎昌(まさる)=1937年(昭和12)兵庫県美方郡西浜村(現・新温泉町)居組に生まれる。
わたしは知らない人ですが、その追悼文の中にこんなのが出て来ました。
ちょっと余談になりますがお付き合いのほど。
井上嘉明さんの「西崎昌の文芸的な足跡」という文章の中。
《『菱』はひところ、<文学散歩>と称し、年一回は県東部を中心に散策を試みていたが、1999年と2000年の12月、西崎の案内により、”県境”を越えて但馬に小旅行したことがある。初めは但馬浜坂で、加藤文太郎記念図書館や(略)…》
ここまで読んできてわたしは「おっ!」と。
これまでならなんとも思わずに読み過ぎるところ。しかし「加藤文太郎記念図書館」に反応しました。
実は拙著『完本コーヒーカップの耳』がこの図書館に架蔵されているのです。
そして、次々と借り出されているのです。
返却されたら次にまた借り出されてと。
新温泉町という都会からは遠く離れた地の「加藤文太郎記念図書館」という所で。
但馬地方では唯一、この図書館に入っているのです。
なんとも不思議な気がしてわたし、「なんで?」と問合せてみました。すると、
「リクエストがあったのです」とのこと。
奇特な方がいてくださったものです。そして、
「この本、返ってきてもすぐにまた借り出されます」と。
ということは、口コミでつながっているのでしょうね。
ありがたいことですが、ちょっと不思議な気がしてます。
㊟あとで手皮さん編集の西崎氏の年譜を詳しく見ていたら、《1998年四月 加藤文太郎記念図書館館長就任。2000年迄》とあった。びっくり。
『完本コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版刊)は、兵庫県の多くの図書館で置いて下さってますが、
残念ながらわたしと縁の深い豊岡や朝来の図書館にはまだ入ってないのです。
前の詩集『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア刊)は豊岡には収蔵されているのですがね。
話がとんだ方向へ飛びました。我田引水、申し訳ありません。
『菱』、いい詩誌です。
手皮さん、ありがとうございます。
『完本コーヒーカップの耳』泣かずに読めるか。笑わずに読めるか。

創刊が1968年となっていますので、半世紀以上の歴史を持つ詩誌。
これがまた、わたしの肌によく合った詩誌なのです。
じっくり、しっとりと読めます。
滝本勤さんの「若きはカメラマン」という詩。
”カメラを買ったばかりの頃” の書き出しで始まるその詩、
百歳の祖母を撮ったが手振れになってしまっていた。
”あの時のカメラもネガも もう手許にはない 手振れの映像を思い出すだけだ”
そして、今、鏡の中の自分の皺の深い顔を見て、
”だが祖母のように 慈愛に満ちてはいない あと三十年も生きられれば
皺はあんなにもふくよかになるだろうか たぶんその前に 私は死ぬであろう
遠い目に見つめられるなら それは祖母であってほしいのだが”
と続く。
そして手皮さんの詩、「草に臥す」がいいです。
 ←クリック。
←クリック。なにも言わないでおきましょう。じっくりと読んでみてください。
今号は「西崎昌追悼号」となっています。
西崎昌(まさる)=1937年(昭和12)兵庫県美方郡西浜村(現・新温泉町)居組に生まれる。
わたしは知らない人ですが、その追悼文の中にこんなのが出て来ました。
ちょっと余談になりますがお付き合いのほど。
井上嘉明さんの「西崎昌の文芸的な足跡」という文章の中。
《『菱』はひところ、<文学散歩>と称し、年一回は県東部を中心に散策を試みていたが、1999年と2000年の12月、西崎の案内により、”県境”を越えて但馬に小旅行したことがある。初めは但馬浜坂で、加藤文太郎記念図書館や(略)…》
ここまで読んできてわたしは「おっ!」と。
これまでならなんとも思わずに読み過ぎるところ。しかし「加藤文太郎記念図書館」に反応しました。
実は拙著『完本コーヒーカップの耳』がこの図書館に架蔵されているのです。
そして、次々と借り出されているのです。
返却されたら次にまた借り出されてと。
新温泉町という都会からは遠く離れた地の「加藤文太郎記念図書館」という所で。
但馬地方では唯一、この図書館に入っているのです。
なんとも不思議な気がしてわたし、「なんで?」と問合せてみました。すると、
「リクエストがあったのです」とのこと。
奇特な方がいてくださったものです。そして、
「この本、返ってきてもすぐにまた借り出されます」と。
ということは、口コミでつながっているのでしょうね。
ありがたいことですが、ちょっと不思議な気がしてます。
㊟あとで手皮さん編集の西崎氏の年譜を詳しく見ていたら、《1998年四月 加藤文太郎記念図書館館長就任。2000年迄》とあった。びっくり。
『完本コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版刊)は、兵庫県の多くの図書館で置いて下さってますが、
残念ながらわたしと縁の深い豊岡や朝来の図書館にはまだ入ってないのです。
前の詩集『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア刊)は豊岡には収蔵されているのですがね。
話がとんだ方向へ飛びました。我田引水、申し訳ありません。
『菱』、いい詩誌です。
手皮さん、ありがとうございます。
『完本コーヒーカップの耳』泣かずに読めるか。笑わずに読めるか。
来年のカレンダー、第一号が届きました。
雲海の城「竹田城」です。

そんな季節になったのですねえ。これは忙しないことになってきました。
贈ってくれたのは、竹田城でボランティアガイドをしている従姉。
今年は例のコロナでガイドの機会がほぼなくなってしまっていたようですが、最近ボツボツと復活のようです。
『完本コーヒーカップの耳』 笑わずに読めるか。泣かずに読めるか。
雲海の城「竹田城」です。

そんな季節になったのですねえ。これは忙しないことになってきました。
贈ってくれたのは、竹田城でボランティアガイドをしている従姉。
今年は例のコロナでガイドの機会がほぼなくなってしまっていたようですが、最近ボツボツと復活のようです。
『完本コーヒーカップの耳』 笑わずに読めるか。泣かずに読めるか。
入院直前に『別嬢』112号をお送り頂いていた。

表紙絵はいつも通り大川和宏さん。
病院へ持って行って読ませていただいた。
巻頭詩は西川保市さんの「駆逐艦桑の軍医長」。
これが凄い。
西川さんの作風がこの前からガラリと変わった。
ご高齢(1923年生まれ)にもかかわらず、思い切った方向転換。
わたしはこれまでの一種飄々とした氏の作風が大好きだった。
いつも楽しみにしていて、時に欠稿があると淋しかったものである。
ファンは多かったのではないか。
ところが前回からの、ご自身の戦時体験を描いた作品には、また違った力がこもっている。
使命感のようなものを感じる。「今書いておかなくては」といったような。
そしてそれは成功していると思う。
ご高齢にもかかわらず頭脳明晰だ。
これまで培ってこられた詩の技術が生かされて、読む者に感動を与えながら、実に貴重な記録になっている。
机に向かわれる凛とした姿勢のようなものさえ感じられる。
その詩、お読みください。
 ←クリック。
←クリック。
 ←クリック。
←クリック。
どうか西川さん、お身体を大切に書き続けてください。

表紙絵はいつも通り大川和宏さん。
病院へ持って行って読ませていただいた。
巻頭詩は西川保市さんの「駆逐艦桑の軍医長」。
これが凄い。
西川さんの作風がこの前からガラリと変わった。
ご高齢(1923年生まれ)にもかかわらず、思い切った方向転換。
わたしはこれまでの一種飄々とした氏の作風が大好きだった。
いつも楽しみにしていて、時に欠稿があると淋しかったものである。
ファンは多かったのではないか。
ところが前回からの、ご自身の戦時体験を描いた作品には、また違った力がこもっている。
使命感のようなものを感じる。「今書いておかなくては」といったような。
そしてそれは成功していると思う。
ご高齢にもかかわらず頭脳明晰だ。
これまで培ってこられた詩の技術が生かされて、読む者に感動を与えながら、実に貴重な記録になっている。
机に向かわれる凛とした姿勢のようなものさえ感じられる。
その詩、お読みください。
 ←クリック。
←クリック。 ←クリック。
←クリック。どうか西川さん、お身体を大切に書き続けてください。





















