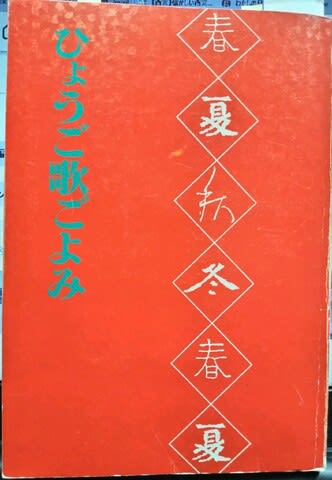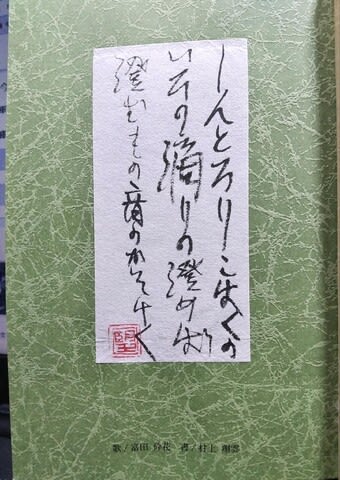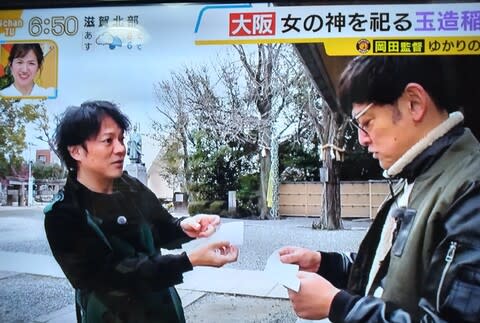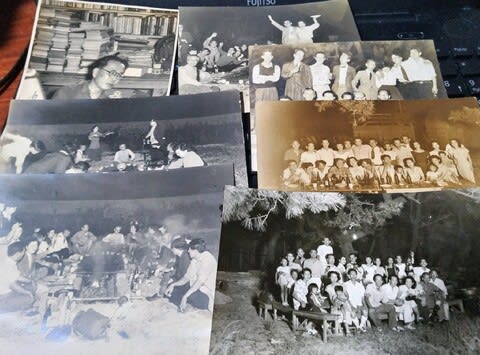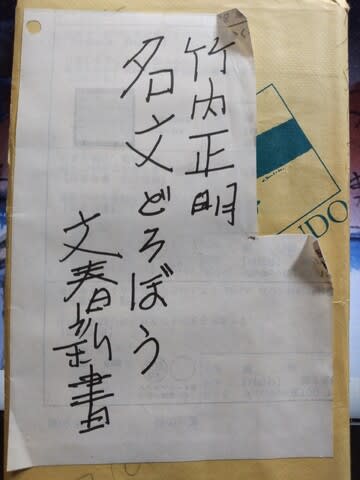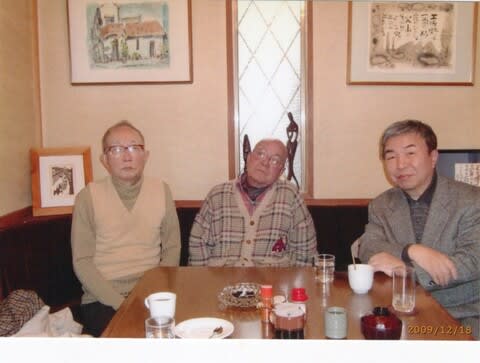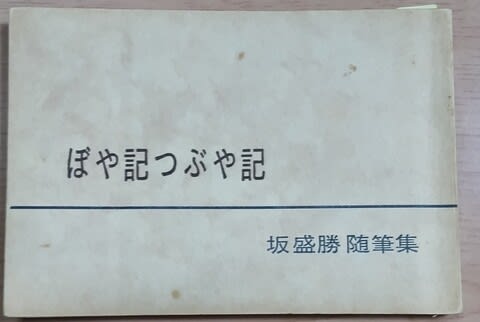「先山鐘銘」のページです。
この村上翔雲さんの文章を読むと、拓本取りの苦労が解るというものです。
そしてこの本の値打ちも。
村上翔雲師と宮崎修二朗翁のお二人は、二年間かけて兵庫県を駆けずり回ってこの本を成されたのでした。
今なら作ることは誰も不可能でしょう。
村上翔雲師による「あとがき」の中に、宮崎翁の言葉が引用されています。
「君たち書家が、今やらなくて、一体だれがやるのか。開発という名の暴力と、人間モドキどもの心ない仕わざによって、道しるべも地蔵さんも、みんな姿を消していってるではないか。今こそ……」
ということでこの貴重な本は成ったのでした。
どの拓本も宮崎修二朗翁が翔雲師と共に採拓しておられますが、苦労が忍ばれます。
わたしも一度、翁の採拓するところを見せてもらったことがありますが、根気のいる仕事でした。
因みにその拓本は、足立巻一先生を語る講演で使われた後にわたしに授けられ、今も書斎に飾っています。
播磨中央公園に建つ足立巻一先生の文学碑からのもの。