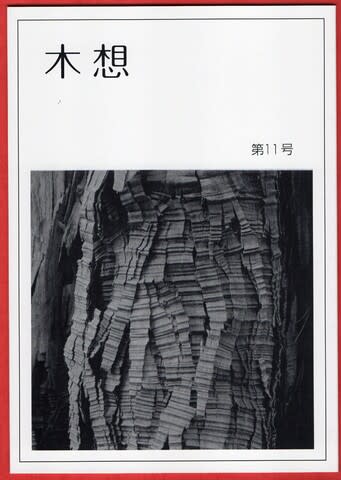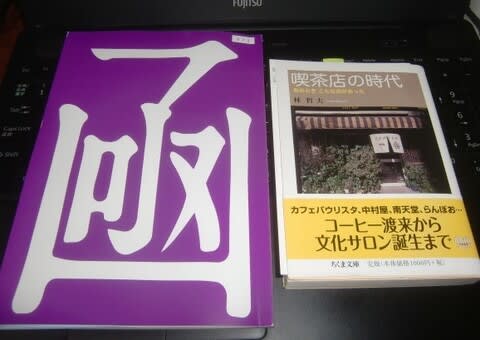今年最後に読んでいる本はこれです。

『書物』(森銑三・柴田宵曲著 岩波文庫・1997年刊)。
初めの方にこんな言葉があります。
「良書とは何ぞや」の項。
《文は人なりという。然らば書もまた人なりといってよい。書物は著者の分身に外ならぬ。いやしくも人たる以上は、その品性の高下を問わず、これを待つに人格者を以てすべきである。書物もまた私等は、これを著者の生命の宿れるものとして対したい。ここにおいてまた書物尊重論を蒸返すこととなるが、私等はいかようなる凡書にも、書物としての敬意を払いたい。
いかなる凡書にも、何かしら得るところがあるといった。手にする者の心構え一つで、いかなる書物からも、何らかの養分を摂取することが出来るはずである。しかしながら人生には限りがある。短い人生において、殆ど無数に近い書物を片端から読破することは、もとより不可能事に属する。ここにおいていかなる書を読むべきかの問題が起こる。》
そこから読み進んで、今、半分近くを読んだ所。
今年はこの本が読み納めになりそう。

『書物』(森銑三・柴田宵曲著 岩波文庫・1997年刊)。
初めの方にこんな言葉があります。
「良書とは何ぞや」の項。
《文は人なりという。然らば書もまた人なりといってよい。書物は著者の分身に外ならぬ。いやしくも人たる以上は、その品性の高下を問わず、これを待つに人格者を以てすべきである。書物もまた私等は、これを著者の生命の宿れるものとして対したい。ここにおいてまた書物尊重論を蒸返すこととなるが、私等はいかようなる凡書にも、書物としての敬意を払いたい。
いかなる凡書にも、何かしら得るところがあるといった。手にする者の心構え一つで、いかなる書物からも、何らかの養分を摂取することが出来るはずである。しかしながら人生には限りがある。短い人生において、殆ど無数に近い書物を片端から読破することは、もとより不可能事に属する。ここにおいていかなる書を読むべきかの問題が起こる。》
そこから読み進んで、今、半分近くを読んだ所。
今年はこの本が読み納めになりそう。