
「喫茶・輪」の常連で人気者だったU山さんが体調不良とのことで、先日見舞い状を娘さん宛に出していた。
その返事が今日来て、辛かった。
どうやらもう、お顔を見せて下さることはなさそう。
わたしは淋しくて淋しくてしかたない。
ブログを開いてから10年以上になるが、ずっと彼のことを書いてきた。
それを抽出してまとめた。

小さな文字で行数も多く取り二段組にして22ページ。
ざっと読んでみたが、彼の個性が横溢していて、笑いと共に泣けてくる。
『完本・コーヒーカップの耳』にも数多く登場しているのだが。



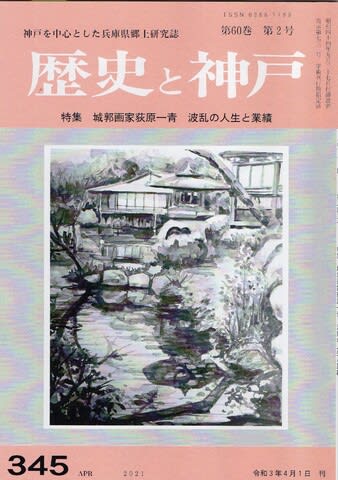


 ←二段階クリック。
←二段階クリック。 



 ←二段階クリック。
←二段階クリック。

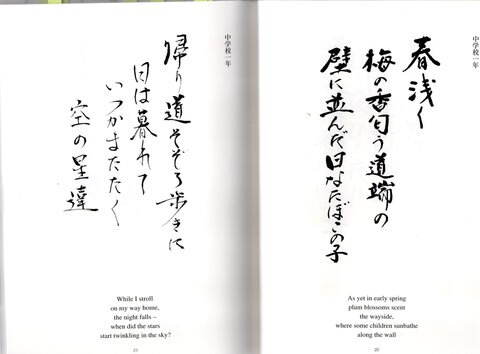




 ←クリック。
←クリック。 ←クリック。
←クリック。