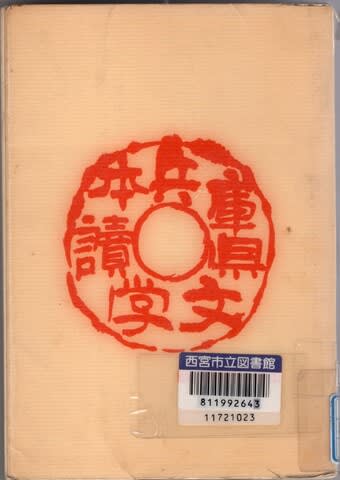またまた編集工房ノアさんから詩集をお贈りいただきました。

『スケッチ』です。
著者は橋田繁文さん。わたしには未知の人です。
表紙がユニーク。
帯がありません。邪魔なのでしょうね。
表紙絵については「あとがき」に書かれています。

←クリック。
「計画していた山小屋のスケッチ」とのこと。
そしてそして、わたしが注目したのは、著者の出身地。
奈良県天川村洞川とあります。
なんと懐かしい!
初めて行ったのは小学校4年生の秋。
父親に連れられての大峰登山。山上参りともいいます。
その山のふもとにあるのが洞川(どろがわ)。龍泉寺を中心とした旅館街でした。
その時、なんと台風に遭遇したのでした。
北海道で青函連絡船洞爺丸を沈め、多くの人が亡くなった台風でした。
この話は以前にも書きましたので省略しますが、後々までの語り草になったものです。
以来わたしは、大峰登山を続け、後には「一心講」という講の役員を長年にわたってやったのでした。
「正大先達」という免状をお寺(龍泉寺)からいただきました。
当時の定宿は「さら徳」という旅館でした。会計をしてましたので宿の人とは仲良くさせて頂いていました。
洞川の思い出を語るととどまるところがありません。
詩集のことでした。
というわけで、この詩集の背景に大峰の自然を感じながら読ませていただきました。
美しい風景の中に細やかな心のありようが描かれていて、著者の純粋性が見えるようです。
これは「星屑」という詩。

←クリック。
自然を写しながら、心の奥底を垣間見せて。
あるいは時を操るような、あっちへ押しやりこっちへ手繰り寄せるような。
具体的な場所が示されているわけではないですが、大峰の自然を感じさせてもらいました。
「茫々」という作品の後半などにそれを感じました。
全体を通して、比喩の巧みさにおどろきました。
作意なく自然な比喩です。「六月は」の中にこんなのがあります。
《日傘をさした ゆかた姿の舞子は モネの絵の陽光を 艶やかにまとい 古い時間の 残る通りに …》
上手いものですね。
これは比喩ではないですが、感心した言葉。
「星があった」の終わりの方。
《 訪ねてみよう 過ぎた日が 閉じて しまわない うちに 》
わたしが最も良かったと思う詩です。これはドラマ性があって秀逸だと思います。
「わたし」

←クリック。


ああ、それにしても洞川は懐かしいです。
念のために申し添えますが、著者の橋田さんは現在、洞川にお住まいではありません。
『コーヒーカップの耳』究極の喫茶店物語。
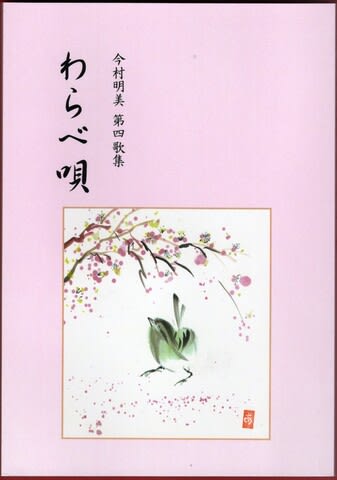
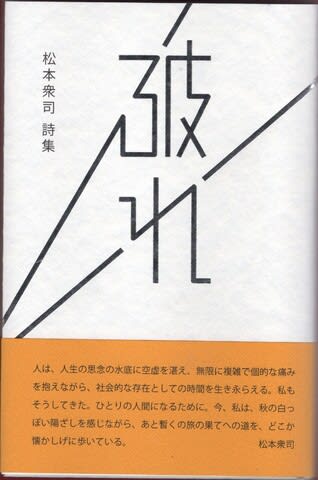
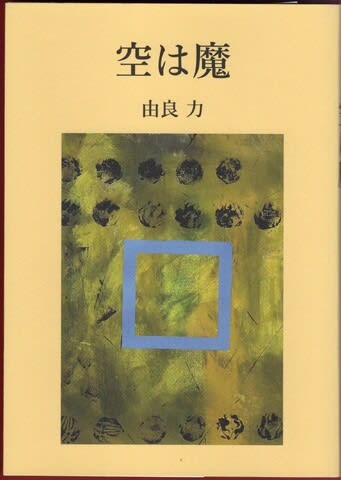

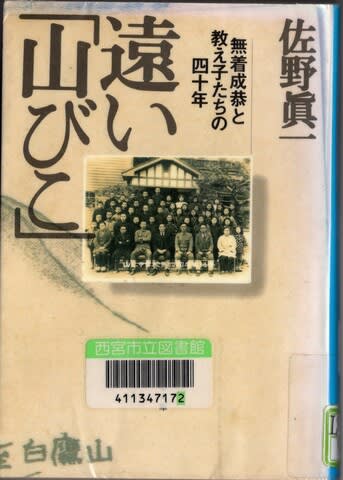

 ←二段階クリック。
←二段階クリック。
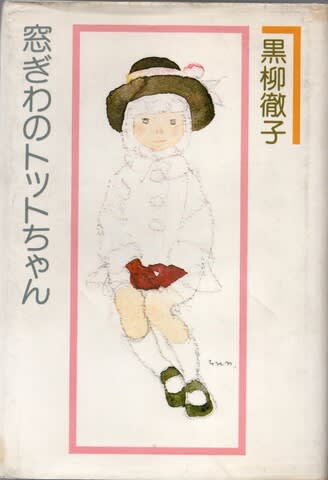
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。 ←二段階クリック。
←二段階クリック。 ←二段階クリック。
←二段階クリック。


 ←クリック。
←クリック。 ←クリック。
←クリック。 ←クリック。
←クリック。