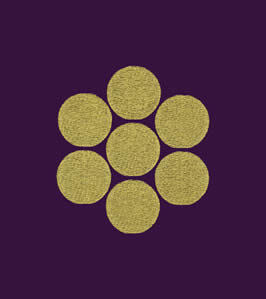◎腑抜けども、悲しみの愛を見せろ(2007年 日本 112分)
staff 原作/本谷有希子『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』
監督・脚本/吉田大八
撮影/阿藤正一 尾澤篤史 美術/原田恭明
ヘアメイク/佐藤光栄 スタイリスト/藤井牧子 大西博之 呪みちる 赤塚明
音楽/鈴木惣一朗 主題歌/チャットモンチー『世界が終わる夜に』
cast 佐藤江梨子 佐津川愛美 永作博美 永瀬正敏 山本浩司 土佐信道 上田耕一
◎トラウマからの脱皮
ありきたりでない題名の爆裂度が、
果たして内容にそぐわしいものかどうかは観る人が判断することだけど、
なんとも凶暴に崩壊してゆく家族のおりなす物語が、
隠々滅々とした結末に落ち込んでゆきかねない以上、
こうした過剰な題名によって、吹き飛ばされる痛快さが孕んでいる、
ような、気がする。
ま、それは、ぼくの単なる印象なんだけどね。
主題をなんとか受けとめようとおもいつつも、
原作者の本谷有希子が怨念を籠めて綴っているのかどうかで違うし、
監督の吉田大八がどんなふうに自分なりの主題を見出したかによっても違うから、
なんともいいにくいものの、
トラウマからの脱皮をめざそうとする連中が、
本来、癒しの空間であるはずの家庭という名の共同体を潰滅させてゆく中で、
夫は斃れ、妻は残り、妹は旅立ち、姉は変わらないという、
それぞれの結果に至るんだけど、
妹のモデルが原作者であるとしたら、
普遍的な主題である旅立ちを、
なんとも歪な形で描いたものと受け止めるのがいいのかもしれない。
だから、本来、語り部となるのは妹で、
すべては妹の視点から描かれているはずなんだけど、
姉の暴走ぶりが強烈なため、ついつい、姉の物語のように勘違いしてしまう。
このあたりは難しいよね。
でも、こういう世界は決して特異な世界ではなくて、
この国の田舎に行けば、こういわれちゃうかもしれない。
「そんなもん、大なり小なり、そこらじゅうにあるがや」
ただ、ここまで大仰な設定と展開はないにせよ、
カリカチュアされている分を差し引けば、たしかに「あるある」と頷ける。
田舎の抱えているのは、都会に対する引け目と僻みで、
そういう自虐的な感情がはらわたの中でとぐろを巻いているもんだから、
この姉の場合、
女優になりたいけど、なれるような才能なんか本当はないんだと自覚している分、
その真実に負けちゃったら自分の居場所がなくなっちゃうという崖っぷちに立ち、
必死にもがけばもがくほど、それは家族に対する、
中でもいちばん弱い者であり、
かつ、ただひとり、自分と血の繋がっている者、
つまり妹に対する罵倒とイジメに繋がっていく。
これは誰もが持っている不安感で、もちろん、ぼくにもある。
だから、観ていて、痛々しくもなる。
夫の場合、
都会に対する憧れみたいなものはないかわりに、
因習に囚われた田舎で生きていかなくちゃいけないっていう、
どうしようもない束縛感だけは抱えてて、
そこへもって、たまさか家族という名の共同体に紛れ込んできた、
スタイル抜群で、なんとも男好きのする顔をした、
自分のことが大好きで、自分の武器は肉体しかないってことを、
本能的に承知している勘違い高慢ふとどきアホたれ女の処女を奪ってしまったために、
田舎の束縛に加えて、義理の妹にして愛人の呪縛によって、
がんじがらめになってしまってるんだけど、
これが本来あたりまえの妻とセックスするという行為によって破綻をきたし、
さらには唯一、自分のことを尊敬してくれている妹に目撃されていたと知った瞬間、
なにもかもを放り出そうとはせず、なにもかもを抱えて死を選ぶまでに追い込まれる。
でも、こういう原罪みたいなものは多かれ少なかれ、誰もが抱えている。
だから、観ていて、身につまされる。
妻の場合、
一般的にとある家に嫁いでくれば、自分以外は当然他人しかいないわけで、
そこで孤独に苛まれて、その孤独をまぎらわすためには、
さらには、家族の一員となるためには、
終始笑顔でいなくちゃいけないのは当たり前ながら、彼女はちょっと違ってて、
新橋のコインロッカーの中から拾われ、孤児院で育ち、缶詰工場に就職し、
結婚相談所によってようやく人と人とが対話できる家庭という絆を見つけたんだけど、
でも、そこにいたるまでにあまりにも孤独な箱の中にいたため、
本人でも気づかない仮面を被るしかない生活に追い込まれ、
さらに、
夫という存在は得たものの、いつまでも処女のまま過ごさなければならないっていう、
なんとも悲惨な境遇に据えられてもなお、
自分が生きてゆくためには、健気さだけを頼りにしなくちゃいけないものだから、
当然、その発露になるものが必要になるわけで、
それが自分のほんとうの顔だってことを気づかず、
無意識のまま、愛らしい化け物の人形を作ってる。
こういう彼女の爆発点が夫をなかばレイプするように初体験に至るのは、
いやまあ、よくわかるとはいえないけど、そうなんだろな~とおもえちゃう。
妹の場合、
もともとまともな思考の持ち主だったはずが、
暴走トラックによって両親が轢殺されてばらばらになるのを目撃したとき、
こんなおもしろい映像があるんだろうかっていう思考もまた持っていたことを自覚し、
かつて、
その片鱗だった姉の同級生への売春行為をおもしろいと漫画化したことは、
将来、自分の才能を活かせる唯一の道だと悟ったことから、
姉と兄と義姉の生活を取材し始めてしまうという歪な性格に変わり、
やがて、自分を徹底的に虐めていた姉と映画監督との文通を、
郵便局でバイトすることによって阻害して叩き潰すという復讐を演じた上で、
ようやく巡ってきた機会に縋るようにして、家族を捨てて上京するんだけど、
誇張された表現を削り落としてしまえば、
田舎を捨てて上京した者の心の底に共通する何かが感じられる。
それは、そう、傑作『祭りの準備』を観ているような錯覚すら覚える。
いや、そもそも、
タイトルバックの陽炎にゆれる鉄道はまさに『祭りの準備』だった。
ただ、監督の手紙を妹が代筆して、
姉の喜ぶさまを観て嘲笑っていたかどうかは、わからない。
監督の顔がぱっくりと割れて妹の顔が登場するのは、
化けの皮が剥がれたということの暗示なのかどうか、
これは吉田大八に訊いてみたいものだけど、考え過ぎだと嗤われちゃうかしら?
まあ、そんなこんな、いろいろと考えさせられる映画だったことは間違いなくて、
これが長編の処女作だとはおもえないほど、
淡白な映像でさらりと物語を展開させていく演出は、
いや、ほんとにたいしたもんだな~と。