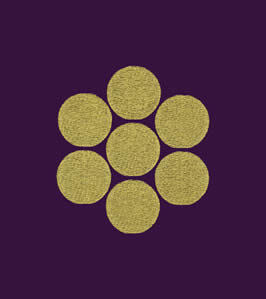◎十一人の侍(1967年 日本 100分)
英題 Eleven Samurai
staff 企画/岡田茂、天尾完次 監督/工藤栄一 脚本/田坂啓、国弘威雄、鈴木則文 撮影/吉田貞次 美術/塚本隆治 音楽/伊福部昭
cast 夏八木勲 宮園純子 里見浩太朗 大川栄子 西村晃 近藤正臣 大友柳太朗
◎集団時代劇の骨頂
つくづくおもうんだけど、工藤栄一には最後の作品として時代劇を撮らせてあげたかった。
工藤さんには少なくとも5本の時代劇の傑作がある。『十三人の刺客』はいうにおよばず『大殺陣』『八荒流騎隊』『忍者秘帖 梟の城』そしてこの『十一人の侍』だ。年を食ってから現代劇ばかりになり、人殺しの話を撮ってきて、途中で服部半蔵を演出してヒットは飛ばしたものの、堂々とした大作時代劇は撮れず仕舞いだった。
おそらく、寂しかったろう。
だって、それだけの腕前はあったんだから。
工藤さんは役者からもスタッフからも信頼される人だった。なんとなく薄汚くて、それでいてかっこよくて、どことなくフクロウに似てた。まったく気取りのないように見えるんだけど、実はとっても気障な性格だった。楽しいことが好きで、お酒とタバコもまた好きで、濡らしの演出も、逆光のアングルも、時代劇で鍛えられたものだ。だから撮らせてあげたかった。
この作品の凄さは雨にある。街道を封鎖して小さな宿場に追い込むのは工藤さんの得意な展開で、なにもこの作品だけのものじゃないし、もしもこの作品にいかにも工藤さんらしい点があるとすれば、それは雨の宿場とその郊外での戦闘だろう。研ぎ澄まされたモノクロームの世界で、人間が吠え狂いながら戦う図は実に見事だ。
この時代、東映の時代劇はきわめて特色があった。集団戦という独自の戦闘を創り上げたわけだけど、それはなんだか侠客の抗争にも似ているし、戦争における歩兵戦にも似ている。むろん、戦国時代の合戦絵巻はそれこそ集団戦の最たるものだけど、どちらかといえば清水の次郎長に近い。それは、企画を担当してた岡田茂と天尾完次の指向によるものかもしれないんだけど、たしかなことはわからない。
ただ、そうしたプロデューサーたちと志が合っちゃったんだね、工藤さんは。
だから、この傑作が生まれたんだろな~と、ぼくはおもってるんだけどね。