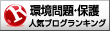太宰府から再び西鉄で大牟田まで向かい、そこからJRに乗り換えて熊本へ。実に8年振りに熊本城を訪れました。ところが、いざ到着してみると熊本城は12月29日から年末年始のお休みのため閉園。ぶらっと思いつきで立ち寄ったので事前に調べていなかったのですから自業自得ですが、わざわざ熊本まで来てお城の中に入ることができませんでした。したがって上の天守閣の写真は8年前撮影したものです。最近本丸御殿が再建されたと聞いていたので中に入れなかったのは大変残念でした。

現在の熊本城はご存知加藤清正が1591年から築城を開始し、関が原の合戦のあった1600年頃大天守が完成しました。徳川家康も南の島津氏の台頭を抑えるため清正に大規模な築城を許したと言われています。
勇猛さで知られる加藤清正ですが、土木や農業政策に優れ、また築城の名人でもありました。前回ご紹介した名護屋城も清正の設計によるものです。熊本城はその美しさで姫路城、松本城と並び「日本三大名城」に数えられますが、熊本城は上の写真にあるように大天守・小天守・宇土櫓の3つの天守を始め、

敵の攻撃にさらされることなく櫓間を移動できる渡り櫓や、

俗に「武者返し」とも「扇の勾配」とも呼ばれる他に類を見ない反りの大きい石垣など要塞として城が本来持つ実用性にも優れていました。国内の戦いだけでなく朝鮮出兵で異国での戦いの経験も豊富な清正は篭城戦に備え、実の食べられる銀杏を城内に多く植え(このことから熊本城は「銀杏城」とも呼ばれています)、井戸を数多く掘りました。この点は水の確保に致命的な欠陥を抱えていた名護屋城とは対照的です。
しかも熊本城の実戦性は築城から270年も過ぎた明治10年の西南戦争によって証明されることになりました。谷干城指揮する新政府軍4,000人は熊本城に立て籠もり西郷軍14,000人の攻撃に良く耐え、ついに陥落することはありませんでした。士族の反乱とはいえ、この戦いは近代戦であったのですから熊本城の要塞としての実用性がいかに優れていたかが分かると言うものです。
因みに大天守・小天守は西郷軍の総攻撃が始まる2日前、原因不明の出火により惜しくも焼失しています。しかし上の写真にある宇土櫓を始め、多くの建物が現存しています。

さて今回2日間で名護屋城、熊本城と同じ1591年に加藤清正によって設計されたとされる2つの城を訪れ気づいたことがあります。それは上の二つの石垣の写真(上は熊本城、下は名護屋城)を見比べて分かるように、同時期、同じ人物によって設計された城であるにもかかわらず、石垣の技術が自然石を積み上げた「野面積」と呼ばれる安土城に代表されるような従来の方式から、石の角を整形した「打込ハギ」と呼ばれる方式に進歩していることです。そうするとこの時期、日本の築城技術に何らかの大きな変革がもたらされたということになります。
変革をもたらした要因を考えてみると、あくまで僕の推測に過ぎませんが、やはり1592年から98年にかけての文禄・慶長の役だったのではないかと思います。

上の写真は10年前に沖縄を訪れ今帰仁、勝連、中城の3城を巡ったときの中城城の写真です。これら14世紀から15世紀の沖縄の城跡を見て、同時期の本土に比べ石垣の技術が格段に進んでいるなと思った記憶があります。

また上の写真は以前ご紹介した蘇州盤門の城壁で元代(14世紀)のものです。いずれも16世紀の日本の城に見られる石垣より優れているように思えます。つまり、朝鮮出兵によって朝鮮あるいは明の先進的な石垣の技術が日本にもたらされた影響により名護屋城と熊本城の間に築城技術の変化が見られたのではないかということです。加藤清正は朝鮮にも出兵していますので、土木や築城に明るかった清正が現地の優れた技術士を連れ帰り熊本城の築城に先進技術を反映させたとしてもおかしくありませんし、むしろその方が自然だと思います。
なお熊本城に見られる「扇の勾配」は加藤清正が現在の韓国蔚山に縄張りし、浅野幸長、毛利秀元らによって築城された蔚山倭城(鳥山城)の影響とする説もあるそうですが、この城の築城は1597年であり3年後の1600年には熊本城大天守の完成をみていますので、蔚山での経験を活かしてというよりはほとんど同時進行で技術の伝播があったのであろうと思います。

因みに名護屋城の本丸西側と南側からは現在の石垣の内側に古い石垣が埋められているのが発見されています。名護屋城の記事でもご紹介した上の写真はちょうど天守台から見た本丸西側の石垣です。四隅が壊されているので何とも言えませんが、明らかな野面積である大手口の石垣と比べると、やはり石垣が進歩しているような気がしないでもありません。何故名護屋城が大規模に改修されたのかは謎とされていますが、秀吉が長期戦を想定し先ほどの蔚山倭城など朝鮮半島にいくつも大規模な城を築かせていたことを考えれば、海側から見た正面にあたる本丸の西側と南側の防御を増強させたと考えてもおかしくありません。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした
 よろしければクリックおねがいします!
よろしければクリックおねがいします!
↓