都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「田中一村 新たなる全貌」 千葉市美術館
千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)
「田中一村 新たなる全貌」
8/21-9/26
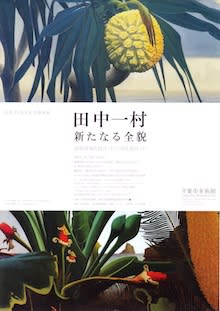
「伝説を捨象し、作品と資料に沿って、田中一村の画家としての実像を明らかにします。」(キャプションより一部引用)千葉市美術館で開催中の「田中一村 新たなる全貌」へ行って来ました。
作品よりも何かと人となりの語られる機会の多い一村の「実像」を知るにはこれ以上ない展覧会かもしれません。一村が約20年間生活したここ千葉の地に集まったのは、過去最大規模の名に恥じない新出作を含む、全250点もの絵画や資料でした。(出品リスト)
構成は以下の通りです。
1 東京時代 :田中米邨と名乗った時代。文人画、中国絵画の影響。初期作。
2 千葉時代 :一村への改号。30歳から50歳の千葉在住時代。
3 奄美時代 :昭和33年の奄美移住。没するまでの19年間。画業の集大成。
居住地毎のシンプルな三章立てにて画業を年代別に辿っていました。

「蘇鉄図」大正14年 紙本墨画着色 掛軸
栃木に生まれ、幼少の頃に東京へ出た一村は、僅か一年間で退学した東京美術学校時代を含め、南画や漢詩などに関心を寄せていきますが、初期の水墨は確かに中国絵画の様式に近いものがあるかもしれません。趙宗謙に倣い、画面いっぱいにソテツを描いた「蘇鉄図」(大正14年)は幹の陰影に筋目の技法が用いられたせいか、どこか若冲を彷彿させる面があります。

「藤花図」(一部)大正15年 紙本墨画着色 掛軸
また一村最大の掛軸画の「藤花図」も、「海上派」と呼ばれる上海画壇に近い作品でした。それにしてもこの龍が昇るように藤が群れる様子は何と力強いことでしょうか。花がのたうち回っていました。

「富貴図衝立」昭和4年 絹本金地墨画着色 衝立
この他でも、例えば金地に原色の艶やかな青い太湖を描く「富貴図衝立」(昭和4年)や、一村カラーとも言える黄金色と朱色の草花のコントラストが眩しい「秋色」など、晩期の作品にも連なるような色の熱気に溢れた作品が目立っています。
実のところ私が今回、最も感銘を受けたのはこれらの初期(東京時代)の作品でした。一村は学校退学後も絵画を描き、様々な注文を受けるなど充実した画業を展開していましたが、作品からもそうした若き一村の活力が感じられました。
さて一村は昭和13年、千葉市美術館にも程近い同市内の千葉寺町に転居し、20年間ほど農作業の傍ら絵画を描き続けます。この千葉時代の作品としてまず重要なのは、同地の田園を描いた風景画と彼が愛していたという鳥や植物のスケッチです。ともかく細かな素描類がこれでもかと言うほど多く展示されていますが、風景画にもエキゾチックな奄美時代のそれとは異なる素朴な自然讃歌の精神に満ち溢れていました。

「千葉寺 麦秋」 絹本墨画着色 額装 田中一村記念美術館蔵
とりわけこの展覧会における調査で60年ぶりに所在が確認された「千葉寺風景荷車と農夫」(昭和21年頃)のパステルカラーに染まる野山の景色は、まさに晴耕雨読と言えるのではないでしょうか。野山で悠々自適に生活する一村の姿がなんとなく浮かび上がってきました。

「薬草図天井画」昭和29年 やわらぎの郷聖徳太子殿
とは言え一村は決して外界と関係を断って独自の境地を開いていたわけではありません。この時代の二つ目のポイントとして挙げられるのは、彼が公募展に挑戦するために様々なスタイルの絵画を描いていたことと、各地から依頼されて描いた大作の襖絵や天井画の仕事でした。

「白い花」昭和22年 紙本着色 屏風
一部入選したとはいえ、公募展そのもの成果は芳しいものとは言えませんが、時に西洋画風の絵画を描くなどの実験的な制作をしていたことには注意しなくてはいけません。一本の杉を濃い色彩で表した「秋杉図」の点描的表現をはじめ、一転して二曲一隻の銀屏風を背景に強い緑と白い花を踊らせた「白い花」(昭和22年)などからは、水墨や奄美時代の絵画とも異なる独特な画風を見ることが出来ます。
千葉時代の作品は一見地味かもしれませんが、それを単に一村の奄美へ至る過渡期と捉えてしまうのはあまりにも勿体ないことでした。

「花と軍鶏」(一部) 紙本着色 襖8面 田中一村記念美術館蔵
そうした意味でも襖や天井画はやはり見逃せません。特に軍鶏師の元まで出向いてその姿を捉えた襖8面の「花と軍鶏」には目を奪われます。この凛としかも力強い眼差しで起立する軍鶏に、一村の自我の投影を見るのは私だけでしょうか。その多様な画風を見ていくと、彼が千葉で見つけ、また得たたものはきっとどの時代よりも多かったのではないかと思いました。
昭和30年に九州や四国などへ旅をした一村は昭和33年末、いよいよ単身で奄美大島へと渡ります。そこで彼は染色工として働きながら、これまでと同様に絵画の制作に取り組み始めました。そしてもちろんここで見るべきはチラシの図版にも多数使われた、言わば一村を一村たらしめた奄美の風景画に他なりません。

「奄美の海に蘇鉄とアダン」昭和36年 絹本墨画着色 額装 田中一村記念美術館蔵
前景と後景の明快な対比、細部の精緻な描写、そして空間を埋め尽くしつつも図像的な植物のモチーフ、さらには日本画らしからぬ鮮烈な色彩は、この時代の作品に一定の様式と強い個性を与えています。初期作でも登場したそてつが南国の海と神の世界を描いた「奄美の海に蘇鉄とアダン」に織り込まれた時、変わらない面と変わった両面のある一村の画業の到達点を見ているような気がしました。

「不喰芋と蘇鉄」 絹本著色 額装
率直なところ、これらの作品から不思議と苦手なルソーを連想してしまってなかなか馴染めませんが、奄美の大作の風景画が並ぶ最後の展示室はやはりハイライトになりそうです。 まさに唯一無比の世界でした。
全250点を追うとそれこそ2時間コースですが、私自身、一村を殆ど見たことがなかったので、終始新鮮な気持ちで楽しめました。ちなみに今回の出品作は全て千葉市美術館以外の作品です。新発見などの作品調査を含め、展示の開催に尽力された同美術館の方々には頭が下がりました。 大掛かりな屏風再現展示も見応え十分でした。
千葉市美術館「田中一村 新たなる全貌」展 会場風景@千葉市美術館YouTubeチャンネル(動画)
展示も重量級ですが図録も負けてはいません。図版と解説をあわせて永久保存版になりうる一冊でした。(2500円)
明後日(9/12)の朝、日曜美術館の本編で一村の特集があります。
「田中一村 奄美の陰影」@日曜美術館 9月12日朝9時放送予定(再放送:9月19日夜8時)
現段階で会場内が混雑しているわけではありませんが、入場者の実数自体はかなりハイペースで推移しているそうです。放送後、さらに人出が増すこと間違いありません。
 「もっと知りたい田中一村/大矢鞆音/東京美術」
「もっと知りたい田中一村/大矢鞆音/東京美術」
9月26日までの開催です。当然ながらおすすめします。 *千葉展終了後、鹿児島市立美術館(10/5~11/7)と田中一村記念美術館(11/14~12/14)へ巡回。
「田中一村 新たなる全貌」
8/21-9/26
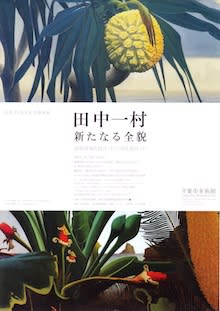
「伝説を捨象し、作品と資料に沿って、田中一村の画家としての実像を明らかにします。」(キャプションより一部引用)千葉市美術館で開催中の「田中一村 新たなる全貌」へ行って来ました。
作品よりも何かと人となりの語られる機会の多い一村の「実像」を知るにはこれ以上ない展覧会かもしれません。一村が約20年間生活したここ千葉の地に集まったのは、過去最大規模の名に恥じない新出作を含む、全250点もの絵画や資料でした。(出品リスト)
構成は以下の通りです。
1 東京時代 :田中米邨と名乗った時代。文人画、中国絵画の影響。初期作。
2 千葉時代 :一村への改号。30歳から50歳の千葉在住時代。
3 奄美時代 :昭和33年の奄美移住。没するまでの19年間。画業の集大成。
居住地毎のシンプルな三章立てにて画業を年代別に辿っていました。

「蘇鉄図」大正14年 紙本墨画着色 掛軸
栃木に生まれ、幼少の頃に東京へ出た一村は、僅か一年間で退学した東京美術学校時代を含め、南画や漢詩などに関心を寄せていきますが、初期の水墨は確かに中国絵画の様式に近いものがあるかもしれません。趙宗謙に倣い、画面いっぱいにソテツを描いた「蘇鉄図」(大正14年)は幹の陰影に筋目の技法が用いられたせいか、どこか若冲を彷彿させる面があります。

「藤花図」(一部)大正15年 紙本墨画着色 掛軸
また一村最大の掛軸画の「藤花図」も、「海上派」と呼ばれる上海画壇に近い作品でした。それにしてもこの龍が昇るように藤が群れる様子は何と力強いことでしょうか。花がのたうち回っていました。

「富貴図衝立」昭和4年 絹本金地墨画着色 衝立
この他でも、例えば金地に原色の艶やかな青い太湖を描く「富貴図衝立」(昭和4年)や、一村カラーとも言える黄金色と朱色の草花のコントラストが眩しい「秋色」など、晩期の作品にも連なるような色の熱気に溢れた作品が目立っています。
実のところ私が今回、最も感銘を受けたのはこれらの初期(東京時代)の作品でした。一村は学校退学後も絵画を描き、様々な注文を受けるなど充実した画業を展開していましたが、作品からもそうした若き一村の活力が感じられました。
さて一村は昭和13年、千葉市美術館にも程近い同市内の千葉寺町に転居し、20年間ほど農作業の傍ら絵画を描き続けます。この千葉時代の作品としてまず重要なのは、同地の田園を描いた風景画と彼が愛していたという鳥や植物のスケッチです。ともかく細かな素描類がこれでもかと言うほど多く展示されていますが、風景画にもエキゾチックな奄美時代のそれとは異なる素朴な自然讃歌の精神に満ち溢れていました。

「千葉寺 麦秋」 絹本墨画着色 額装 田中一村記念美術館蔵
とりわけこの展覧会における調査で60年ぶりに所在が確認された「千葉寺風景荷車と農夫」(昭和21年頃)のパステルカラーに染まる野山の景色は、まさに晴耕雨読と言えるのではないでしょうか。野山で悠々自適に生活する一村の姿がなんとなく浮かび上がってきました。

「薬草図天井画」昭和29年 やわらぎの郷聖徳太子殿
とは言え一村は決して外界と関係を断って独自の境地を開いていたわけではありません。この時代の二つ目のポイントとして挙げられるのは、彼が公募展に挑戦するために様々なスタイルの絵画を描いていたことと、各地から依頼されて描いた大作の襖絵や天井画の仕事でした。

「白い花」昭和22年 紙本着色 屏風
一部入選したとはいえ、公募展そのもの成果は芳しいものとは言えませんが、時に西洋画風の絵画を描くなどの実験的な制作をしていたことには注意しなくてはいけません。一本の杉を濃い色彩で表した「秋杉図」の点描的表現をはじめ、一転して二曲一隻の銀屏風を背景に強い緑と白い花を踊らせた「白い花」(昭和22年)などからは、水墨や奄美時代の絵画とも異なる独特な画風を見ることが出来ます。
千葉時代の作品は一見地味かもしれませんが、それを単に一村の奄美へ至る過渡期と捉えてしまうのはあまりにも勿体ないことでした。

「花と軍鶏」(一部) 紙本着色 襖8面 田中一村記念美術館蔵
そうした意味でも襖や天井画はやはり見逃せません。特に軍鶏師の元まで出向いてその姿を捉えた襖8面の「花と軍鶏」には目を奪われます。この凛としかも力強い眼差しで起立する軍鶏に、一村の自我の投影を見るのは私だけでしょうか。その多様な画風を見ていくと、彼が千葉で見つけ、また得たたものはきっとどの時代よりも多かったのではないかと思いました。
昭和30年に九州や四国などへ旅をした一村は昭和33年末、いよいよ単身で奄美大島へと渡ります。そこで彼は染色工として働きながら、これまでと同様に絵画の制作に取り組み始めました。そしてもちろんここで見るべきはチラシの図版にも多数使われた、言わば一村を一村たらしめた奄美の風景画に他なりません。

「奄美の海に蘇鉄とアダン」昭和36年 絹本墨画着色 額装 田中一村記念美術館蔵
前景と後景の明快な対比、細部の精緻な描写、そして空間を埋め尽くしつつも図像的な植物のモチーフ、さらには日本画らしからぬ鮮烈な色彩は、この時代の作品に一定の様式と強い個性を与えています。初期作でも登場したそてつが南国の海と神の世界を描いた「奄美の海に蘇鉄とアダン」に織り込まれた時、変わらない面と変わった両面のある一村の画業の到達点を見ているような気がしました。

「不喰芋と蘇鉄」 絹本著色 額装
率直なところ、これらの作品から不思議と苦手なルソーを連想してしまってなかなか馴染めませんが、奄美の大作の風景画が並ぶ最後の展示室はやはりハイライトになりそうです。 まさに唯一無比の世界でした。
全250点を追うとそれこそ2時間コースですが、私自身、一村を殆ど見たことがなかったので、終始新鮮な気持ちで楽しめました。ちなみに今回の出品作は全て千葉市美術館以外の作品です。新発見などの作品調査を含め、展示の開催に尽力された同美術館の方々には頭が下がりました。 大掛かりな屏風再現展示も見応え十分でした。
千葉市美術館「田中一村 新たなる全貌」展 会場風景@千葉市美術館YouTubeチャンネル(動画)
展示も重量級ですが図録も負けてはいません。図版と解説をあわせて永久保存版になりうる一冊でした。(2500円)
明後日(9/12)の朝、日曜美術館の本編で一村の特集があります。
「田中一村 奄美の陰影」@日曜美術館 9月12日朝9時放送予定(再放送:9月19日夜8時)
現段階で会場内が混雑しているわけではありませんが、入場者の実数自体はかなりハイペースで推移しているそうです。放送後、さらに人出が増すこと間違いありません。
 「もっと知りたい田中一村/大矢鞆音/東京美術」
「もっと知りたい田中一村/大矢鞆音/東京美術」9月26日までの開催です。当然ながらおすすめします。 *千葉展終了後、鹿児島市立美術館(10/5~11/7)と田中一村記念美術館(11/14~12/14)へ巡回。
コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )









