都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「グエルチーノ展」 国立西洋美術館
国立西洋美術館
「グエルチーノ展 よみがえるバロックの画家」
3/3~5/31
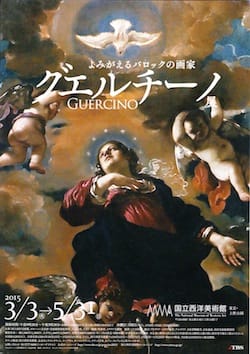
国立西洋美術館で開催中の「グエルチーノ展 よみがえるバロックの画家」のプレスプレビューに参加してきました。
17世紀イタリア美術、バロック絵画を代表する画家の一人であるグエルチーノ(1591-1666)。若くして名声を轟かせ、画風を変化させながら、故郷チェントをはじめ、ローマやボローニャでも活動。死後はゲーテやスタンダールが賞賛しました。またボローニャ派の礎を築くなど、後の西洋絵画にも影響を及ぼしたとも言われています。
ただ19世紀半ばには一度、「否定され」(チラシより)てしまったそうです。それゆえか特に日本での知名度は決して高いとは言えません。

グエルチーノ「ゴリアテの首を持つダヴィデ」 1650年頃 国立西洋美術館
実は私もグエルチーノの名を聞いてすぐに画家のイメージが浮かびませんでした。ただどうでしょうか、上の一枚、「ゴリアテの首を持つダヴィデ」は見覚えのある方も多いかもしれません。ずばり、今回の会場でもある国立西洋美術館のコレクション。常設展でよく見かけます。神に感謝を捧げるダヴィデ、その姿はどこか感傷的です。画家晩年の優れた作品の一つでもあります。
日本初の回顧展です。出品は全44点。チェント市立絵画館をはじめ、ボローニャ国立絵画館ほか、ボルゲーゼ美術館など、主にイタリア各地の美術館などから作品がやって来ました。
さて若くして才能を開花させたグエルチーノ、まず圧巻なのは、1618年前後、まだ20代の頃に描いた一連の宗教画、中でも「キリストから鍵を受け取る聖ペテロ」です。

グエルチーノ「キリストから鍵を受け取る聖ペテロ」1618年 油彩、カンヴァス チェント市立絵画館
高さ4メートル弱、幅2メートル超の大作、跪くペテロにキリストが金と銀の鍵を渡す。マタイ書の一節に基づく作品です。
二つの鍵は天国と地上の権力を示します。右の大きな椅子は教皇のためのもの、キリストが左手で指しています。つまりペテロがこれから座ろうとするための椅子です。

グエルチーノ展 「2.才能の開花」 会場風景
それにしてもこの大きさ、写真ではなかなか伝わらないかもしれません。まさしく畏怖の念すら覚えますが、実はこの作品のあるセクション、「トラパニの聖アルベルトにスカプラリオを与えるカルミネの聖母」や「幼児キリストを崇める聖母と悔悛の聖ペテロ、聖カルロ・ボッロメーオ、天使と寄進者」など、いずれも大きく、またダイナミックな作品が多い。それこそ祭壇を仰ぐかの如く、否応無しに下から見上げざるを得ません。思わず空間にのまれます。展覧会の一種のハイライトと化していました。

グエルチーノ「マルシュアスの皮をはぐアポロ」 1618年 フィレンツィエ、パラティーナ美術館
「マルシュアスの皮をはぐアポロ」はどうでしょうか。画面中央に立つのがアポロ、右手には鋭いナイフを持っています。手を木に縛り付けられ、背を向けて転がるのが半身半獣のマルシュアスです。笛と竪琴の対決に勝利したアポロが罰としてマルシュアスの皮をそぐ。左手で脚を持ち上げ、先ほどのナイフを使って皮をまさに引き裂いています。痛々しい光景、だからこそマルシュアスも口を少し開けてもがき苦しんでいるのでしょう。右からあたる強い光はアポロの背中を白く照らします。実にドラマテックでした。
展示は基本的に時系列です。グエルチーノの制作を時代で追うように構成されています。
そしてここで興味深いのは、年代によって作風に変化が見られることです。とするのも前期は、動的でかつ鮮やかな明暗を特徴としているのに対し、後期、晩年の作品はどこか静的でかつ、良く言えば優美でもある。いわゆる古典主義的な画風です。全体を通して構図は基本的にシンプルですが、後期はさらに単純化します。半ば様式化しているとも言えるかもしれません。

グエルチーノ「説教する洗礼者聖ヨハネ」 1650年 チェント市立絵画館
後期の作品については今も評価が分かれているそうです。たたその中でも、はじめに挙げた「ゴリアテの首を持つダヴィデ」や「説教する洗礼者聖ヨハネ」は力作と言っても良いのではないでしょうか。とりわけ後者です。故郷チェントの礼拝堂に飾られた一枚ですが、ヨハネが説教する様子は、威圧的というよりも、どこか静謐で美しくもあります。

右:グエルチーノ「洗礼者聖ヨハネ」 1644年 ボローニャ国立絵画館
また優美といえば「洗礼者聖ヨハネ」も忘れられません。「見よ、紙の子羊」という言葉を記して紙を手にして立つヨハネ。温和な表情が目を引きました。
約15年ほど時代を遡りましょう。かのゲーテが賞したのが、「聖母のもとに現れる復活したキリスト」です。

グエルチーノ「聖母のもとに現れる復活したキリスト」 1628-30年 チェント市立絵画館
非常に明快な構図、左がキリストで右が聖母です。聖母はどこか恍惚した様子でキリストを見上げ、逆にキリストは泰然、ないしはやや慈愛に満ちた表情で母を見つめています。風に靡く旗をはじめ、キリストや聖母の纏う衣の襞のボリューム感も素晴らしいもの。画面は静的ではありますが、復活したキリストに驚いて母が寄り添った一瞬を切り取ったようにも見えなくない。中期作までに見られる躍動感を秘めた作品でもあります。
チラシ表紙を飾る「聖母被昇天」は、そのさらに5年以上前の作品です。絵が飾られていたのはチェントの礼拝堂、高さを意識してのことでしょう。会場でもかなり高い位置に展示されていました。

グエルチーノ「聖母被昇天」 1622年 チェント、サンティッシモ・ロザリオ聖堂
ちなみにグエルチーノの作風が変化したのは、1年間半あまりローマに滞在したことが契機だそうです。まさに「聖母飛昇天」はローマで制作された作品。故郷チェントからローマ、そして再びチェント、さらに晩年のボローニャ。画家の滞在した地と画風との相互に影響が見られます。その辺を追うのも面白いかもしれません。
最後に一枚、私が惹かれた作品を挙げておきます。それがまだ若きグエルチーノの一枚、初期チェント時代の「聖母子と雀」です。

右:グエルチーノ「聖母子と雀」 1615-16年頃 ボローニャ国立絵画館
おそらくは室内空間の聖母子の姿、目を引くのは聖母の人差し指の先にのる雀。イエスもやや驚いた様で雀を見やっています。
この雀はキリストの受難を象徴するごしきひわと同じ意味をなしているそうです。そして写真ではまるで分かりませんが、雀、聖母の指の下から白い糸が垂れている。その糸のもう一方の端をイエスが右手で握っています。
聖母子の密着した姿、ただしここには神々しさよりも、より家庭的な母子の日常の姿が強調されているようにも見えます。そっと子を支える母の左手、さらにはあくまでも仄かで穏やかな微笑み。非常に情感溢れた作品だとは言えないでしょうか。

グエルチーノ展 「1.名声を求めて」 会場風景
点数は西美にしては少なめかもしれませんが、一点一点の作品が大きく、また力作揃いのため、全くもって不足感はありませんでした。さも空間を圧倒せんとばかりに立ち並ぶ宗教画群、これほど西美の展示室が神々しく感じられたこともなかったかもしれません。
なおチェントは2012年5月に地震に襲われ、今回の展示作を多く出品しているチェント市立絵画館のほか、グエルチーノ作品が多く飾られている教会なども大きな被害を受けました。
うち絵画館は現在も休館中です。よって本展の収益の一部が絵画館の再建に当てられます。言わばチェントの復興支援の展覧会でもあります。
音声ガイドの原稿をバロック美術が専門で神戸大学の宮下規久朗先生が担当されています。
 「芸術新潮2015年3月号/新潮社」
「芸術新潮2015年3月号/新潮社」
また芸術新潮3月号の特集、「グエルチーノ 再び脚光を浴びる イタリア・バロック絵画の立役者」のテキストも同じく宮下先生です。グエルチーノの来歴を含め、作品をどう評価していくのか。専門的でかつ非常に分かりやすい内容です。あわせて参照されることをおすすめします。
実は内覧では時間の都合で見きれなかったため、再度もう一回、会期1週目の日曜日に観覧してきました。

グエルチーノ展 「3.芸術の都ローマとの出会い」 会場風景
まだ始まったばかりだからか、館内にはかなり余裕がありました。桜の時期に入ると多少混み合うかもしれませんが、早い段階であればスムーズに楽しそうです。
3月17日(火)より常設展でヨハネス・フェルメールに帰属すると言われる「聖プラクセディス」が公開されます。
「常設展新規展示作品のお知らせ」@国立西洋美術館
西洋美術館の告知は至ってもの静かですが、こちらもまた話題となるのではないでしょうか。
巡回はありません。5月31日までの開催です。おすすめします。
「グエルチーノ展 よみがえるバロックの画家」(@guercino2015) 国立西洋美術館
会期:3月3日(火)~5月31日(日)
休館:月曜日。但し3月30日、5月4日、5月18日は開館。
時間:9:30~17:30 (毎週金曜日は20時まで開館)
*入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1500(1300)円、大学生1300(1100)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
住所:台東区上野公園7-7
交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
「グエルチーノ展 よみがえるバロックの画家」
3/3~5/31
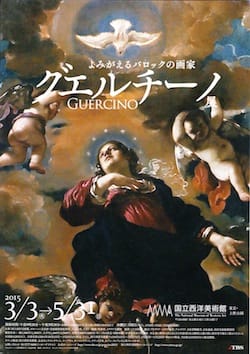
国立西洋美術館で開催中の「グエルチーノ展 よみがえるバロックの画家」のプレスプレビューに参加してきました。
17世紀イタリア美術、バロック絵画を代表する画家の一人であるグエルチーノ(1591-1666)。若くして名声を轟かせ、画風を変化させながら、故郷チェントをはじめ、ローマやボローニャでも活動。死後はゲーテやスタンダールが賞賛しました。またボローニャ派の礎を築くなど、後の西洋絵画にも影響を及ぼしたとも言われています。
ただ19世紀半ばには一度、「否定され」(チラシより)てしまったそうです。それゆえか特に日本での知名度は決して高いとは言えません。

グエルチーノ「ゴリアテの首を持つダヴィデ」 1650年頃 国立西洋美術館
実は私もグエルチーノの名を聞いてすぐに画家のイメージが浮かびませんでした。ただどうでしょうか、上の一枚、「ゴリアテの首を持つダヴィデ」は見覚えのある方も多いかもしれません。ずばり、今回の会場でもある国立西洋美術館のコレクション。常設展でよく見かけます。神に感謝を捧げるダヴィデ、その姿はどこか感傷的です。画家晩年の優れた作品の一つでもあります。
日本初の回顧展です。出品は全44点。チェント市立絵画館をはじめ、ボローニャ国立絵画館ほか、ボルゲーゼ美術館など、主にイタリア各地の美術館などから作品がやって来ました。
さて若くして才能を開花させたグエルチーノ、まず圧巻なのは、1618年前後、まだ20代の頃に描いた一連の宗教画、中でも「キリストから鍵を受け取る聖ペテロ」です。

グエルチーノ「キリストから鍵を受け取る聖ペテロ」1618年 油彩、カンヴァス チェント市立絵画館
高さ4メートル弱、幅2メートル超の大作、跪くペテロにキリストが金と銀の鍵を渡す。マタイ書の一節に基づく作品です。
二つの鍵は天国と地上の権力を示します。右の大きな椅子は教皇のためのもの、キリストが左手で指しています。つまりペテロがこれから座ろうとするための椅子です。

グエルチーノ展 「2.才能の開花」 会場風景
それにしてもこの大きさ、写真ではなかなか伝わらないかもしれません。まさしく畏怖の念すら覚えますが、実はこの作品のあるセクション、「トラパニの聖アルベルトにスカプラリオを与えるカルミネの聖母」や「幼児キリストを崇める聖母と悔悛の聖ペテロ、聖カルロ・ボッロメーオ、天使と寄進者」など、いずれも大きく、またダイナミックな作品が多い。それこそ祭壇を仰ぐかの如く、否応無しに下から見上げざるを得ません。思わず空間にのまれます。展覧会の一種のハイライトと化していました。

グエルチーノ「マルシュアスの皮をはぐアポロ」 1618年 フィレンツィエ、パラティーナ美術館
「マルシュアスの皮をはぐアポロ」はどうでしょうか。画面中央に立つのがアポロ、右手には鋭いナイフを持っています。手を木に縛り付けられ、背を向けて転がるのが半身半獣のマルシュアスです。笛と竪琴の対決に勝利したアポロが罰としてマルシュアスの皮をそぐ。左手で脚を持ち上げ、先ほどのナイフを使って皮をまさに引き裂いています。痛々しい光景、だからこそマルシュアスも口を少し開けてもがき苦しんでいるのでしょう。右からあたる強い光はアポロの背中を白く照らします。実にドラマテックでした。
展示は基本的に時系列です。グエルチーノの制作を時代で追うように構成されています。
そしてここで興味深いのは、年代によって作風に変化が見られることです。とするのも前期は、動的でかつ鮮やかな明暗を特徴としているのに対し、後期、晩年の作品はどこか静的でかつ、良く言えば優美でもある。いわゆる古典主義的な画風です。全体を通して構図は基本的にシンプルですが、後期はさらに単純化します。半ば様式化しているとも言えるかもしれません。

グエルチーノ「説教する洗礼者聖ヨハネ」 1650年 チェント市立絵画館
後期の作品については今も評価が分かれているそうです。たたその中でも、はじめに挙げた「ゴリアテの首を持つダヴィデ」や「説教する洗礼者聖ヨハネ」は力作と言っても良いのではないでしょうか。とりわけ後者です。故郷チェントの礼拝堂に飾られた一枚ですが、ヨハネが説教する様子は、威圧的というよりも、どこか静謐で美しくもあります。

右:グエルチーノ「洗礼者聖ヨハネ」 1644年 ボローニャ国立絵画館
また優美といえば「洗礼者聖ヨハネ」も忘れられません。「見よ、紙の子羊」という言葉を記して紙を手にして立つヨハネ。温和な表情が目を引きました。
約15年ほど時代を遡りましょう。かのゲーテが賞したのが、「聖母のもとに現れる復活したキリスト」です。

グエルチーノ「聖母のもとに現れる復活したキリスト」 1628-30年 チェント市立絵画館
非常に明快な構図、左がキリストで右が聖母です。聖母はどこか恍惚した様子でキリストを見上げ、逆にキリストは泰然、ないしはやや慈愛に満ちた表情で母を見つめています。風に靡く旗をはじめ、キリストや聖母の纏う衣の襞のボリューム感も素晴らしいもの。画面は静的ではありますが、復活したキリストに驚いて母が寄り添った一瞬を切り取ったようにも見えなくない。中期作までに見られる躍動感を秘めた作品でもあります。
チラシ表紙を飾る「聖母被昇天」は、そのさらに5年以上前の作品です。絵が飾られていたのはチェントの礼拝堂、高さを意識してのことでしょう。会場でもかなり高い位置に展示されていました。

グエルチーノ「聖母被昇天」 1622年 チェント、サンティッシモ・ロザリオ聖堂
ちなみにグエルチーノの作風が変化したのは、1年間半あまりローマに滞在したことが契機だそうです。まさに「聖母飛昇天」はローマで制作された作品。故郷チェントからローマ、そして再びチェント、さらに晩年のボローニャ。画家の滞在した地と画風との相互に影響が見られます。その辺を追うのも面白いかもしれません。
最後に一枚、私が惹かれた作品を挙げておきます。それがまだ若きグエルチーノの一枚、初期チェント時代の「聖母子と雀」です。

右:グエルチーノ「聖母子と雀」 1615-16年頃 ボローニャ国立絵画館
おそらくは室内空間の聖母子の姿、目を引くのは聖母の人差し指の先にのる雀。イエスもやや驚いた様で雀を見やっています。
この雀はキリストの受難を象徴するごしきひわと同じ意味をなしているそうです。そして写真ではまるで分かりませんが、雀、聖母の指の下から白い糸が垂れている。その糸のもう一方の端をイエスが右手で握っています。
聖母子の密着した姿、ただしここには神々しさよりも、より家庭的な母子の日常の姿が強調されているようにも見えます。そっと子を支える母の左手、さらにはあくまでも仄かで穏やかな微笑み。非常に情感溢れた作品だとは言えないでしょうか。

グエルチーノ展 「1.名声を求めて」 会場風景
点数は西美にしては少なめかもしれませんが、一点一点の作品が大きく、また力作揃いのため、全くもって不足感はありませんでした。さも空間を圧倒せんとばかりに立ち並ぶ宗教画群、これほど西美の展示室が神々しく感じられたこともなかったかもしれません。
なおチェントは2012年5月に地震に襲われ、今回の展示作を多く出品しているチェント市立絵画館のほか、グエルチーノ作品が多く飾られている教会なども大きな被害を受けました。
うち絵画館は現在も休館中です。よって本展の収益の一部が絵画館の再建に当てられます。言わばチェントの復興支援の展覧会でもあります。
音声ガイドの原稿をバロック美術が専門で神戸大学の宮下規久朗先生が担当されています。
 「芸術新潮2015年3月号/新潮社」
「芸術新潮2015年3月号/新潮社」また芸術新潮3月号の特集、「グエルチーノ 再び脚光を浴びる イタリア・バロック絵画の立役者」のテキストも同じく宮下先生です。グエルチーノの来歴を含め、作品をどう評価していくのか。専門的でかつ非常に分かりやすい内容です。あわせて参照されることをおすすめします。
実は内覧では時間の都合で見きれなかったため、再度もう一回、会期1週目の日曜日に観覧してきました。

グエルチーノ展 「3.芸術の都ローマとの出会い」 会場風景
まだ始まったばかりだからか、館内にはかなり余裕がありました。桜の時期に入ると多少混み合うかもしれませんが、早い段階であればスムーズに楽しそうです。
3月17日(火)より常設展でヨハネス・フェルメールに帰属すると言われる「聖プラクセディス」が公開されます。
「常設展新規展示作品のお知らせ」@国立西洋美術館
西洋美術館の告知は至ってもの静かですが、こちらもまた話題となるのではないでしょうか。
巡回はありません。5月31日までの開催です。おすすめします。
「グエルチーノ展 よみがえるバロックの画家」(@guercino2015) 国立西洋美術館
会期:3月3日(火)~5月31日(日)
休館:月曜日。但し3月30日、5月4日、5月18日は開館。
時間:9:30~17:30 (毎週金曜日は20時まで開館)
*入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1500(1300)円、大学生1300(1100)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
住所:台東区上野公園7-7
交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










