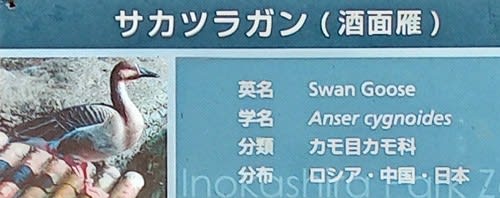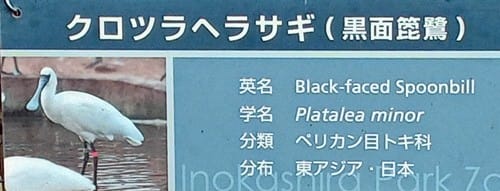3月30日(日)10時過ぎ、時間が早いので空いていると思ったが、どうしてどうして。
井の頭公園でもっとも早く咲く桜のある井の頭池東端の「ひょうたん橋」の桜。当然、満開。

花が重なって見える。

北側から見る。写真左端に群がって桜を撮影する人たち。

「七井橋」の北端から見た、公園で一番遅く咲く桜。まだ蕾が見える。7分咲きと言ったところか。

「七井橋」から井の頭池の東側を眺めると、池の上に枝を伸ばす桜は満開だ。

スワンボートが一杯。

スワンボートは出払って、足漕ぎボートが次々に出ていく。

池の端で眺める人の中に、ハンモックで楽しむ人がいた。

写真左端の人は、エアークッションのベット?を持ち込んでいる。

「野外ステージ」前に陣取った若者が早くも奇声を上げていた。

3月30日、日曜とはいえ、まだ10時10分なのに、池の南側には、こんなにシートが敷き詰められていた。
それにしても、井の頭公園の桜も老木となって、切られてしまい、花が少なくなってしまったと先日嘆いたが、失礼しました。

桜って、枝の周りを花で覆いつくすのだなと改めて思う。

見上げると、空が桜で覆われる

桜の花も満開だが、それを眺め、撮る人も溢れている。

まわりが桜ばかりだと、山吹色が映える

西から「ひょうたん橋」を眺めると、左の若葉が、桜を引き立てて見える。

池の東端から、遠く七井橋越しにマンションを眺める。それにしてもスワンボートがこんなにあるのか!

お腹いっぱい桜を楽しみました。












 。
。