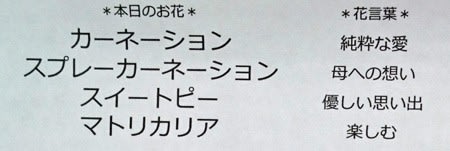志水辰夫著『きのうの空』(2001年4月20日新潮社発行)を読んだ。
宣伝文句は以下。
見上げた空は果てしなく高かった。都会での華やかな暮らし、想い続けている人の横顔が、ふわり浮かんだ。だが、この地にしがみつき、一日一日をひたすらに積み重ねなければ、生きてゆけなかった。わたしの帰りを家族が待っていた。親やきょうだいは、ときに疎ましくときには重く、ただ間違いなく、私をささえていた。名匠が自らを注ぎこみ、磨き続けた十色の珠玉。柴田錬三郎賞受賞作。
最初に蕪村の句「凧(いかのぼり) きのふの空の 有り所」とある。
凧は、いかのぼりと読む。「たこ」は江戸時代までは「イカ」「いかのぼり」と言われていて、関西に対抗して江戸でイカでなくタコだと言って凧という漢字を作ったらしい。
『旅立ち』
茂は、一番のちびでひねくれものだった。転校生で体の大きな清司が茂を助けたことから唯一の友人となった。二人は共に母子家庭だった。茂は廃船を修理し、はるかなるアメリカを目指す船旅の準備を始める。
『短夜(みじかよ)』
厳しい姑がいる格上の家へ嫁ぐ姉・智美を思いやって弟・信夫は機嫌が悪い。嫁入り行列の姉の背中に弟は「ばかやろーっ!」と叫ぶ。姉は……。
『イーッ!』
高校生ながら成熟した体を持つ榊原加奈子。啓介とは高校一年のとき演劇祭で共演することになり、城山でふたりだけで何回も練習した。啓介の父は事業に失敗し借金取りが押しかけてきて、受験勉強に熱が入らなかった。加奈子の母は小さな飲み屋をやっていて、いろいろ噂があった。加奈子も英語教師の殿村と噂があった。城山で会った彼女は街に向かって朗々と腹式呼吸で呼び掛けた。
「わたしたちは知り合ってもう八年になるんですよ。それなのにこうして、ふたりで向かい合って真面目にお話しするのは、きょうがはじめてだということにお気づきなりませんの?」
『家族』
畑中光彦は進学を断念し材木会社の事務員になり、公務員試験中級の勉強中。父は戦死し、一家の大黒柱だ。母・満子は行商、弟・昇は新聞配達、忠は東京で学校に通いながら働いている。妹・智子は家事。高校でクラスメートだった福田由美子は福田家の長女で将来は決められていた。
『かげろう』
桑原敬之(のりゆき)は、母と、高三の美代、中三妹・佳代の4人暮らし。敬之は肺結核の治療中だが、蚕業試験場の臨時職員に採用されていた。同じアパートの美人の田端芙美子が気になっていた。しかし、彼女の家にヤクザ風の茂夫がやって来た。夫だという。茂夫はなにかと敬之に頼み事をし、とまどいながらも巻き込まれてしまい、ヤクザの親分のところへ使いに行かされてしまう。
『息子』
康治の妻は男の子を出産し、病院にいる。母は康治に対してなんでも決めつけるように言い、妻とうまくいっていなかった。康治の会社に田舎饅頭を持って母・佐和子の姉、70歳過ぎの伯母が訪ねてくる。翌日伯母が亡くなったと電話を受ける。伯母は母と妻と康治を訪ねて仲を持とうとしたらしい。そんな状況なのに母はいきなり病院へ行ったらびっくりするが「喜ぶじゃろう」という。康治の「佐和子に謝ってくれよな」に対して、「どうして? 謝るようなことはなにもしとらんが」という。
『高い高い』
惣一は妻・喜美子と歩き始めたばかりの正を連れて久しぶりに帰省した。父は惣一が15歳のとき家族を捨て出て行って、惣一が母と妹・宏美を支えた。喜美子は惣一に城山の桜祭りに行って父と会うよう勧めるが彼は頑として俺は行かないと拒否する。翌日父が入院する病院へ惣一の運転で行き、宏美と喜美子だけが病室へ行く。惣一は口をへの字にすると父が窓に映る病室へ背を向け、抱いていた正を頭上に高く差し上げた。
『夜汽車』
幸一は息子・大介との約束を破っておじの葉山行夫を訪ねた。行夫は一応退院したがもうこの夏を超すことはできないだろうという状態だった。結局泊まることになったおじの家で、行夫を夜中起きると、おじが納屋で座っていた。おじは「汽車は来んのか」「なんにも聞こえん」と言った。行夫はおじは自分の寿命を‥‥。
『男親』
佐倉敬三には妻・芳子との間に一人娘で30歳になる道代がいる。道代は東京で外資系保険会社で働いている。親は付き合っている人がいるか、どんな人か気になってしかたない。ためらいながら聞いてみると、春川というその男の歳は……。
店の前で寝そべっていた犬が、ふたりの近づいて来るのを見ると居住まいを正した。
「今晩は」
と道代が犬に向かって言った。わん、と敬三が言った。犬はなんにも言わなかった。
『里の秋』
遠藤秀宏が昔住んでいて思い出多い家を壊し更地にする。仕事を頼んだ峯岸は遠慮なくさばさばと仕事を進める。秀宏と中学で同級だった砂原暁子は美人の母と二人暮らしで、鉱山の所長と噂があったその母が亡くなり、旅立つ汽車の窓の暁子に、秀宏は「負けるなよ」と声をかけた。
初出:「小説新潮」1997年1月号~2000年8月号
私の評価としては、★★★★☆(四つ星:お勧め)(最大は五つ星)
『旅立ち』:孤立した中での唯一の親友の交流。
『短夜(みじかよ)』:家族の犠牲になろうとする姉への弟のいらだちと想い。
『イーッ!』:共に経済的破綻環境にあるが、心も体も先に行っている同級生の彼女ともどかしい彼
『息子』:他人への思いなしに突き進む母をもてあます息子
『高い高い』:家族を捨てて家出し明日をも知れぬ体となった父に、苦労させられ許せない息子の精一杯のふるまい
とくに活躍しているわけではないが、貧しい環境の中で地道に努力してきた男の切なさとやさしさ。しみじみとした想いが詰まり、心を打つ短編集だ。
現在ではちょっと古めかしいが、たまにはこんな話に浸るのもいいものだ。
志水辰夫の略歴と既読本リスト
燠:おき。熾火(おきび)に同じ。消し炭。
忸怩とした思い:じくじ