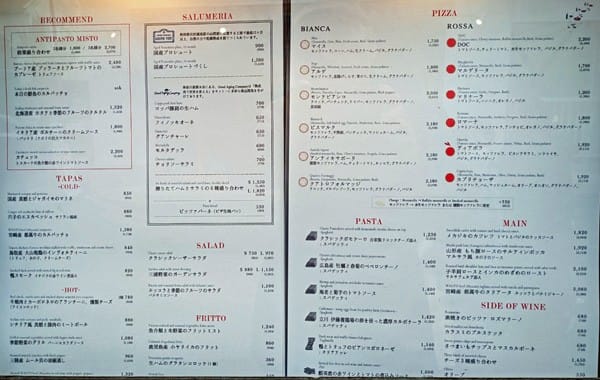南杏子著『いのちの波止場』(2024年11月20日幻冬舎発行)を読んだ。
吉永小百合さん主演映画『いのちの停車場』シリーズ最終話。主人公は映画で広瀬すずさんが演じた看護師・麻世。
これで安心して死ねるよ。
ありがとう、ありがとう。
余命わずかな人たちの役に立ちたい――“熱血看護師”麻世が「緩和ケア科」で学び、最後に受け取ったものは。
震災前の能登半島の美しい風景と共に、様々な旅立ちを綴る感動長編。
患者さんの苦痛を取り、嫌だと思うだろうことをしない。
それが最後にできる最高の仕事。
まほろば診療所の看護師・麻世は、能登半島の穴水にある病院の看護実習で「ターミナルケア」について学ぶ。激しい痛みがあるのに、どうしてもモルヒネを使いたくないという老婦人。認知症と癌を患い余命少ない父に無理やり胃ろうつけさせようする息子。そして麻世が研修の最後に涙と感謝と共に送るのは、恩師・仙川先生だった――。
シリーズの登場人物は共通だが、主人公は異なる。
『いのちの停車場』は62歳の医師・白石咲和子。
『いのちの十字路』は、新人医師・野呂聖二。
本書『いのちの波止場』は、若手看護師・麻世。
プロローグ
金沢のまほろば診療所の院長・仙川徹は突然、「70歳になるから、リタイアするね」と宣言。院長は白石咲和子、訪問診療は野呂聖二となる。そして、看護師・麻世は、能登半島・穴水町にある能登さとうみ病院・緩和ケア科の院長・北島の元で6カ月の看護実習を受けることになる。(これにはもう一つの隠された目的があった。)
第一章 キリシマツツジの赤
麻世の直接指導者は一回り上の45歳の妹尾理央子。仙川も病院顧問で週1日働いている。
この病院の、緩和病床は8床。死亡退院率は83%。入院期間は長くても30日くらい。
麻世の担当患者は久保田ルミ子。ルミ子は痛みが強くなっているのに、麻世が勧めてもどうしてもモルヒネをなぜか強固に拒否する。……
第二章 海女のお日様
中村照枝さんは83歳の現役を引退したばかりの海女さんだが、子宮体癌のステージⅣ。致死性の不整脈のためにICD(植え込み型除細動器)を胸に入れる手術を受けていた。ICDは小型のAEDで突然の不整脈に襲われたときに自動的に電気ショックを起こし正常な心拍に戻す機能がある。
問題は、死の淵にあるがん患者のICDを停止させないままでいると、体は静かに死に向かっているのに、ICDが作動して心臓と周辺筋肉はピクンとし、除細動が起きて苦痛をもたらす、これが繰り返される。
やがて、照枝さんにも死が訪れようとして、……。
ICDを止めるのは簡単だ、プログラミングをするか、体の上に磁石を当てるだけでよい。問題はいつ止めるかだ。
第三章 親父のつゆ
元そば店主で77歳の大山寛介さんが前立腺がんで入院した。63歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断されすでに14が経過し、重度認知症にもなっている。
認知症も最終的には死に至る病だ。一般的には発症から10年から15年くらいで亡くなるケースが多い。最終的には「食べる」「飲み込む」といった生命を維持する機能までもが障害され、やがて目覚めた状態を保つのも難しくなる。
第四章 キリコの別れ
48歳の古屋茂さんが、進行が早くて治癒しにくい小細胞肺がんで入院してきた。両親の面会をあくまで拒絶している。
数基の高さ6mもある直方体の燈籠(キリコ)が神輿(みこし)を照らす「キリコ祭り」は、夏から秋にかけて能登半島の百か所以上あるどこかの地域で毎日行われる。茂さんは介護タクシーと車椅子で祭を見学した。
第五章 内浦の凪
新しい入院患者は、年齢70歳、男性、名前は仙川徹さん。……
エピローグ
2024年1月1日の起きた能登半島地震から8カ月目、麻世は野呂と共に穴水の町を訪れた。……
本書は書下ろし。原稿用紙488枚。
私の評価としては、★★★★☆(四つ星:お勧め、 最大は五つ星)
少しずつ衰えていき、死に進んでいくことに、本人、家族、場合によっては看護側も戸惑いながらも、徐々に受け入れていく過程が丁寧に描かれている。
患者側から見ると、医療について種々思うところがあるだろうが、臨床医が描く小説では、医者側からの、場合によりまったく異なる見方が示されるので、いろいろ思わされる。
本書は、主人公が医療側ではあるが、患者に近い所にいる看護師であるから、とくに患者側の意見が主張され、徐々に医師側の意見との整合が図られるという流れになっていて、我々の思考パターンに沿っているので分かりやすかった。
緩和ケアとは、心身ともに苦痛を最小限に抑えつつ、最後まで「生ききる』ことだと思うようになった。
しかし、苦痛(肉体的・精神的)を取り除き、患者ファーストで、嫌なことはせず、最後の希望を叶えることが望ましいのだが、現実にはこの小説ほどうまくいく場合は少ないのだろう。
事故などで急に亡くなるより、ガンの方が死ぬまで時間があるので、本人、家族にとって、もちろん辛いのだが、対処する多少の余地があるとも言える。
疼痛(とうつう):癌の浸潤などでおきるズキズキとうずくような強い痛み
病棟入院料:定額で一日、1割負担なら5千円、3割負担で15千円だが高額療養費制度を使うと70歳以上は1カ月で計5万円前後。
緩和ケアの名言:「治すことー時々、和らげることーしばしば、慰めることーいつも」“To cure somethings, to relieve often, to comfort always…”
ICD(植え込み型除細動器)の設置件数:年間6千件以上、累計2万人。AEDは全国で推計67万台以上。
花の終わり:昔から、サクラは「散る」、ウメは「こぼれる」、ツバキは「落ちる」、ボタンは「くずれる」、アジサイは「しがみつく」と言い表す。
膀胱の容量:一般的に最大容量は400㎖程度。我慢して1ℓ。
麻薬の使用:仮に緩和治療の副作用によって呼吸停止が起き、死期が早まる可能性があっても、苦痛緩和を目的とするなら麻薬の使用は間違っていない。
「生き物は必ず死を迎えるの。そして、死ぬ前には少しずつ体の働きを止めていくのよ」(白石咲和子)
つまり、死ぬ前に消化吸収機能が落ち、尿を作る力も落ちる。免疫の力や血液を作り出す能力も下がり、心臓や脳さえも機能しなくなる。