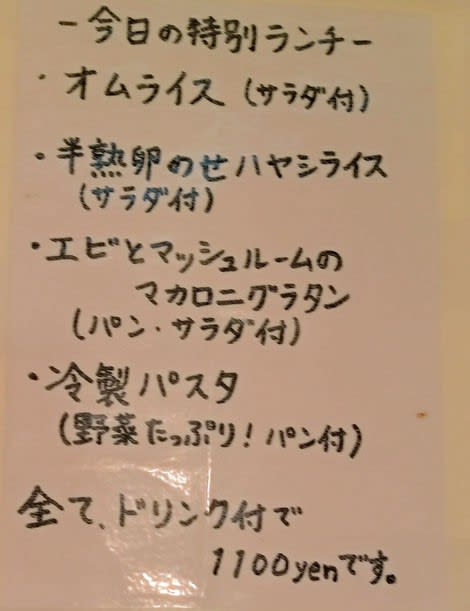深緑野分著『スタッフロール』(2022年4月14日文藝春秋発行、p468)を読んだ。
文藝春秋BOOKSの作品紹介
戦後ハリウッドの映画界でもがき、爪痕を残そうと奮闘した特殊造形師・マチルダ。
脚光を浴びながら、自身の才能を信じ切れず葛藤する、現代ロンドンのCGクリエイター・ヴィヴィアン。
CGの嵐が吹き荒れるなか、映画に魅せられた2人の魂が、時を越えて共鳴する。
特殊効果の“魔法”によって、“夢”を生み出すことに人生を賭した2人の女性クリエイター。その愛と真実の物語。
かつて映画で衝撃的だったことの一つは、人の顔を猿に変えるなどの特殊メイク(特殊造形)だった。しかし、2000年以前から少しずつCG(コンピュータグラフィック)がその座を奪い始めていた。
この物語は、映画に限りない情熱を燃やす、戦後ハリウッドの特殊造形師・マチルダと、現代ロンドンのCGクリエイター・ヴィヴィアン、2人の女性クリエイターの苦闘と葛藤を描く長編小説だ。
Part of Matilda
映画好きのマチルダ(マティ)は米国東部の有名大学に入ったが、ハリウッドで働く夢をあきらめきれない。20歳のとき親に知らせずに偏屈な老人の特殊造形師・ヴェンゴスの弟子になり、苦労を重ねようやく一人前になってハリウッドで特殊造形師として働くようになる。
ユタ大学院生のモーリーンから、制約も多く、手間がかかる特殊造形より、コンピュータグラフィックス・CGの方が将来有望だと吹聴されたが、コンピュータに懐疑的なマチルダには受け入れがたかった。
ところが、ベトナム戦争で負傷して絶望していた同居人リーヴはモーリーンに従ってマチルダから去った。さらにかつて映画の魅力を教えてくれた、父の友人ロニーの死を知りショックを受ける。
マチルダは、子供の頃から温め育てた犬のイメージ・怪物像Xを憑かれたように完成し、忽然と姿を消す。後にXは映画『レジェンド・オブ・ストレンジャー』に使われ、名作と絶賛され彼女は伝説の造形師となるが、彼女自身はスタッフロールに一度たりともクレジットされたことのないままだった。
Part of Vivienne
30年後のロンドン。有名なポサダ監督が『レジェンド・オブ・ストレンジャー』のXをCGでリメイクするためにリンクス社にCG化を発注した。
24歳のアニメーター・ヴィヴィアン(ヴィヴ)もその一員となる。尊敬するXの生みの親・マチルダがCGを嫌っていたという話を聞いてヴィヴの心は乱れる。
行方を誰も知らないマチルダは今?
初出:「別冊文藝春秋」2016年9月号~2019年3月号
私の評価としては、★★★★★(五つ星:読むべき、 最大は五つ星)
人の顔の石膏型をとり、シリコン鋳型を元に油性粘土で彫刻をするなど数々の手順を踏む特殊造形の工程が詳しく説明される。
コンピュータ利用のCGについても、話の筋道の中で詳しい説明がある。そんな話が好きな私には五つ星だが、粘着質の話ぶりに普通の人はいやになるのではないだろうか。
著者の勉強ぶりには驚かされるが、リアル感を醸しだす以上の詳しい記述は、小説としての出来にはマイナスになっているような気がする。
日本人の著者が、舞台が米国や英国で、日本人がほとんど出てこない小説を書いているのだが、私は抵抗感を感じなかった。著者はいくら勉強してもハンデを抱えることになるが、映画を作る話を書きたいので、どうしても舞台はハリウッドということになるのだろう。欧米の人が読んでも違和感がないかどうかはわからない。
深緑 野分(ふかみどり・のわき)
1983年厚木市生れ。海老名高校卒業。パート書店員から作家に。
2010年短編「オーブランの少女」でミステリーズ!新人賞の佳作入選で作家デビュー。
2013年『オーブランの少女』刊行。
2016年『戦場のコックたち』で直木賞・本屋大賞ノミネート。
2019年『ベルリンは晴れているか』で直木賞・大藪春彦賞候補、本屋大賞第3位
2020年『この本を盗む者は』で本屋大賞ノミネート。
その他、『分かれ道ノストラダムス』
「スタッフロール」は、映画などの終わりに流れる、制作にかかわった者を記載した字幕のことで、これに出演者の「キャストロール」、更に協力や配給といったそれ以外も加わわたものが「エンドロール」。
リンクス社のCGのお仕事
「モデリング」:人・動物・小道具を多角形の面を張り付けた形の三次元像としてコンピュータ上で作る。
「リギング」:人・動物が関節の周りで動けるように設計する。
「レンダリング」: 3D(3次元)シーンを2Dのイメージ画像に変換する。
「シミュレーション」:キャラクターの動きに合わせて、毛や服などを本物のように動かす。
「アニメーション」:キャラクターに動きをつけて、演技させる。