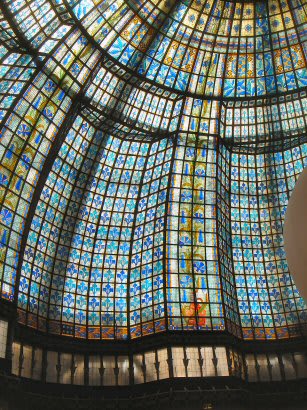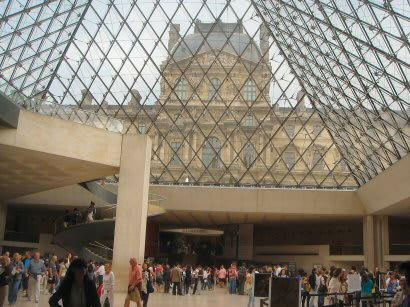奥様がインターネットで参観者募集を見つけて、往復はがきで申込み、抽選で当たったものだ。
迎賓館・赤坂離宮は、東宮御所として1909年(明治42年)に建設され、1974年(昭和49年)3月に国賓などの迎賓施設として改修された。
四ッ谷駅赤坂口から四谷見附交差点方向に出て、外堀通りを南に行くと、正面外柵が見えてくる。正門の上部には16弁の菊花の御紋章があり、柵内外の左右には衛兵の小屋がある。道路の際のガードレールは抜けるようになっていて、賓客はこの正門から入る。

6月末に行ったヴェルサイユ宮殿などを模したというだけあって、外柵も似ている。ただし、ヴェルサイユは金ぴかだった。

柵のすきまからのぞくと、144本のクロマツを左右に配した道が本館北面正面の正式の玄関に続いている。

西門で受付と手荷物検査を受けて、入場する。建物はネオ・バロック様式で、4kmに渡る鉄道のレールを基礎に用いた鉄骨補強レンガ作りで、関東大震災にも耐えた。

左右の屋根の上には、「鸞」(らん)と呼ばれる架空の霊鳥、天穹(天球)と桐紋が見える。なお、桐紋(五七桐)は天皇家の副紋だが、菊の御紋のように天皇家専用ではないため、徳川家など広く用いられている。

正面左右の屋根の上には甲冑がある。

本館の西入口から入る。フランスで見たような?アールヌーボー風のひさし?がある。


本館入口を入り、円弧状の廊下を進み、2階へ階段を登る。廊下は真紅の絨毯が敷き詰められ、壁や天井は白一色だ。
館内は写真撮影ができないので、映像は、政府インターネットテレビの動画で紹介されている「迎賓館赤坂離宮 本館」をご覧あれ。
2階に上がると、まず彩鸞(さいらん)の間 だ。
白い天井と壁は、金箔が施された石膏の浮彫りで装飾され、10枚の鏡が並ぶ。それはそれは豪華。
花鳥(かちょう)の間
天井に描かれた36枚の鳥の絵、花や鳥が描かれている30枚の楕円形の七宝、欄間に張られたゴブラン織風綴織が見事で、良い仕事をしている。茶褐色のシオジ材で板張りした腰壁が落着いた雰囲気を出している。
朝日の間
壁の京都西陣の金華山織には見とれてしまった。床に敷かれた段通も淡い色合いで恐れ多いほどだ。
羽衣(はごろも)の間
正面の中2階には、オーケストラボックスがあり、舞踏会の光景が目に浮かぶ。異常なほど大きいシャンデリアは重さ800kgだ。
最後に、2階大ホールから中央階段をのぞき、いつの日にか招待され、この階段を静かに登ってくる自分を想像しつつ、本館の東側出口に出る。
出たところに、アカマツの園芸品種タギョウショウがあり、建物に沿う銅の雨どいが輝く。

やけに銅が輝いているので今回の改修で新設したのかと思い、近づいてみると、裏側まで輝いている。しかし、良く見ると、わずかに汚れが残るところがあり、古いものを磨いたのだった。

噴水や、手入れの行き届いた花壇のある主庭を回り、


再び、北側正面に回る。

正面の入口の菊花御紋章のあるドアから中央階段をのぞいたが、良く見えない。

入ってきた西門に戻り、参観を終えた。
フランスのヴェルサイユまで行かなくとも、日本にもこんなすばらしい西欧式宮殿があったのだ。もっと宣伝した方が良いし、一度は見ておくべきと思った。
沿革
迎賓館の建物は、東宮御所として元紀州藩の屋敷跡に1909年(明治42年)に建設された。戦後、皇室から国に移管され、国立国会図書館や、東京オリンピック組織委員会などに使用された。
その後、外国の賓客を迎えることが多くなり、旧赤坂離宮を改修し、これを迎賓施設とすることが1967年に決定された。5年の期間と108億円(工事費101億円、家具等製作費7億円)の費用をかけて、本館は村野藤吾、和風別館は谷口吉郎の設計協力により1974年(昭和49年)3月に迎賓施設として改修された。
また、2006年から2008年にかけて、大規模な改修工事が行われた。
本館
構造:鉄骨補強煉瓦石造、地上2階(地下1階) 延床面積:1万5000m?
庭園
主庭は全面砂利敷きであり、中央には噴水池や花壇が設けられている。フォード大統領(1974年、ハナミズキ)、エリザベス女王(1975年、ブラウン・オーク)、ゴルバチョフ大統領(1991年、フユ・ボダイジュ)の記念樹がある。