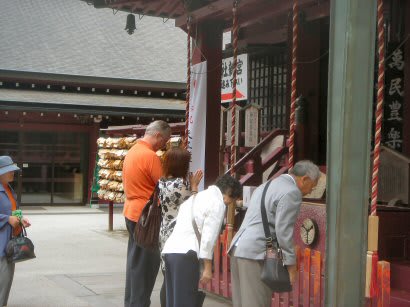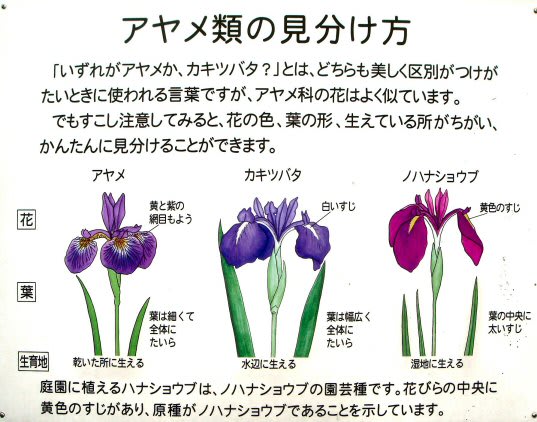美術館の入口を入ると、そこはメディチ家の邸宅風(多分)。通路の壁にはモザイク画。

柔らかな顔を拡大してもやはりモザイク。でも本当に細かいところは筆で書いてあるような?

ふたつきゴブレット:数少ない16世紀のヴェネチアン・グラスの名品は、イタリア国外持出し禁止だが、大富豪のロスチャイルド家に長く伝えられてきたものだったため、日本に渡来してきた。

通路を出ると、天井画が描かれたホールに出る。


ここに数多く展示されているガラス作品の多くが、レース・グラスだ。16世紀、ヴェネチアの貴族の間では、レース編みがもてはやされた。そのレースをガラス作品に持ち込んだのがヴェネチアン・グラスで、その技法は長い間、門外不出の秘法だった。
レース・グラス大皿:最も難しい格子模様技法で、中心から時計回りと、反時計回りに渦を巻いた2枚のガラスを重ね合わせて作る。網目を均一に作るのは、いかにも難しそうだ。

これも作ることを考えると、気の遠くなるような美しさだ。

レース・グラス玉脚コンポート:乳白色のガラス棒と格子模様の入ったレース・ガラス棒を組み合わせたコンポート。

レース・グラスの作り方の説明図があったので、ちょっと見にくいが、ご紹介。
(1)溝のついた型の中に白色ガラス棒を立てる。
(2)溶けたカラスの塊を型の中に入れ、白色ガラス棒に熔着する。
(3)型から抜き出し、ならし台の上で転がして形を整える。
(4)反対側にも竿をつけ、ねじりながら引っ張り、1本のレースガラス棒が完成する。
(5)複数のレースガラス棒の数や位置をいろいろ変えて文様を工夫する。
(6)レース・ガラス棒を並べ、炉で加熱し、棒同士を熔着する。
(7)ガラスの塊をつけた吹き竿で、板状になったレース・ガラスを巻き取り、円筒にする。(8)西洋箸で先をすぼめる。
(9)宙吹きで形を作る。
(10)器の底をならし、脚部・底部を熔着する。
(11)底部にポンテ竿を熔着し、口縁部の吹き竿を外して広げ、形を整える。
(12)レースグラスの完成

花装飾脚オパールセント・グラス・コブレット:新しい華やかな装飾を取り入れた19世紀後半の作品。
風にそよぐグラス:3階の展望室にあるアール・ヌーボ様式のベェネチアン・グラスで、細くて今にも折れそうな脚の上に大きな杯が乗って、ゆれている。

地震で折れないかなと思ったら、後ろに支えがあった。

この後、箱根湿生花園、強羅公園などの写真があるが、どうしよう。10日も前では忘却のかなただ。