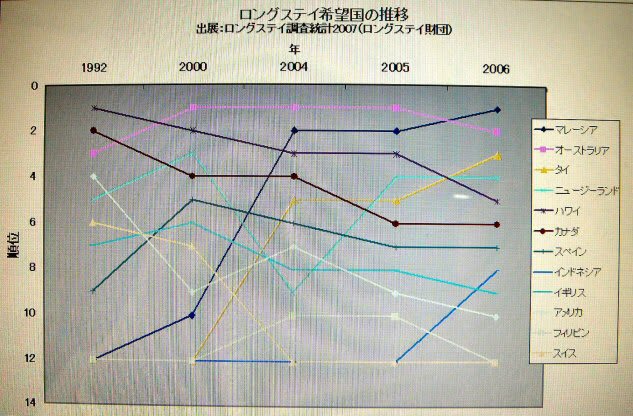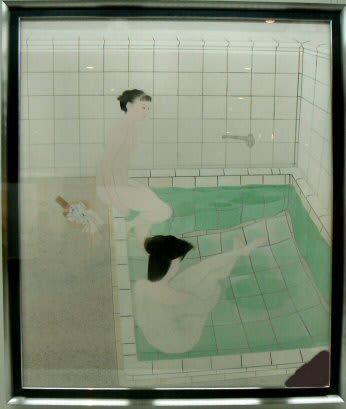孫悟空のモデルとも言われたキンシコウが12月末に中国へ返還されると聞いて、よこはま動物園ズーラシアへ行った。
ズーラシアとは、ZOO(ズー 動物園)とユーラシア大陸(広いという意味)にちなんでつけられた(市民公募)。まだまだ拡大中で全面開園すると、日本最大級の動物園となるらしい。
展示動物は、約70種400点で、キリンの仲間オカピ、インドのごく限られた地域にしか生息していないインドライオンなど珍しい動物がいる。ズーラシアに希少動物が多いのは、種の保存を行っていくことを目的の1つとしているためだ。
気になった動物と植物をご紹介。
キンシコウ 金絲猴
中国では国家第一級保護動物に指定された絶滅危機にある動物で、12年の横浜での保護、繁殖を終え、今年12月に中国に返還される。標高1,800~3,300mの高山に住み、サル類の中で最も寒い地域に分布している。
やさしそうなお母さんにしっかり抱きついている赤ん坊と離れて見つめるお父さん。逆光で長い毛並みがよけいに輝いていた。

オカピ 偶蹄目 キリン科
コンゴの東部の熱帯雨林に多雨林地帯で主に単独で生活している。キリンのように長い舌で若い木や低木の葉や新芽をたぐり寄せて食べる。シマウマの仲間ではなく、キリン科。草原に出て、首が長く進化したのが、キリンになった。1901年に発見され、ジャイアントパンダ、コビトカバとともに世界三大珍獣の一つ。
きれいな色をしている。

インドゾウ
長い鼻で器用に、地面に散らばった細かい餌を集めて小さな山にして、吸い上げて食べていた。

シロフクロウ
北極海やツンドラ地帯で繁殖し、冬にはステップ地帯にまで南下して越冬する。フクロウ類としては珍しく、明るい時間帯に活動する。雄はほとんど真っ白で、雌は黒い斑がある。ときどき、首だけ回すので、細い目と鼻だけクルリと回ったように見え、女性たちにウケテいた。

フンボルトペンギン
アンチョビのような魚やイカなどが豊富な、ペルーとチリの沿岸のフンボルト海流に沿って分布している。

メガネグマ
南米に生息する唯一のクマで、アンデス山脈の標高1,800~2,700mの湿潤な森林に分布する。名前の由来となった鼻から目の周りや胸にかけて白くなっているのが特徴で、冬ごもりはしない。背中がかゆいのだろうか、何回も立ち上がり、背中をコンクリートにこすり付けていた。

アカカワイノシシ
中部アフリカの森林や深いやぶなどに棲息する。石の下や落ち葉にかくれた昆虫、落ちた果実などを探し、強力な鼻先をスコップのように使って地中の根茎、トカゲやミミズなども食べる。

オカピ、キンシコウといい、なぜこんなに動物は美しいのか。長い耳は生き抜くのに必要とは思えない。進化は美も要求するのだろうか。
ズーラシアには、自然体験林もあり、各種植物も植えられていて動物以外の見所も多い。

ところどころに真っ赤に紅葉した木があった。多分、ニシキギだろう。

鮮やかな赤は、イロハモミジ(カエデ科、カエデ属)だ。名前は7つに分かれた葉をイロハニホヘトと数えたことからついたそうだ。

花や幹がどう見ても桜だと思う。カンザクラだろうか。

草丈が3mはあろうかという皇帝ダリア(キク科、ダリア属)が大きな花を咲かせていた。木立ダリアとも呼ばれらしい。

出口付近で、お母さんに遅れてヨチヨチと歩いて来た子どもが、道端の網の破れ目が気になるらしく、つまみながら、我々にさかんに、「コワレテル。コワレテル」と訴えてきた。お相手していると、お母さんが戻ってきて、「そお、こわれてるわね。教えてあげたのね」「どうもすいません」「さあ、バイバイしましょうね」と言った。未練を残しながら、子どもも手を振った。
そういえば、子どもはちょっと変になっているところを見つけると、とても気になるようだったと、思い出した。奥様が言った。「いちばん良いときかもね」